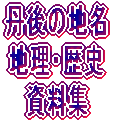 |
白柏(しらかせ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白柏の概要《白柏の概要》 市街地の西部で、元の国道176号・312号(重複)沿いの南北に長く延びた商店街の両側町で、北は川向、南は魚屋に連なる。如願寺川下流右岸に位置する。 白柏町は江戸期の広域町名で、宮津城下6町粗の1組。町組の構成は寛文初年白柏町を触頭として、その下に河原町・吹屋谷・池ノ谷・葛屋町・山王下・如願寺下が見える。のち住吉町・万年新地が参加。 家数は寛文6年288軒、元禄16年302軒、寛保4年278軒(1、646人)、宝暦年間360軒余、明治維新以前583軒余。 安政3年、葛屋町を蛭子町に、文久2年、山王下およぴ如願寺下を合併して宮町に、慶応2年に吹屋谷を万年町に改称し、同時に万年町の田畑を開いて万年新地を設けて遊女町としている。 当町域の海岸部は江戸期を通じて宮津城下では最も盛んに埋め立てが実施されたという。京極高国時代の城下絵図には白柏町の東には河原町などの町名が見えずわずかな浜通りが新町と記されている、下に引用の元禄16年の御城下絵図には河原町などが記されている。 寛延2年・天明6年にわたって如願寺川が氾濫し当町は大被害を受けたという。明治29年8月にも大水があり、同40年8月の洪水は宮町・蛭子・白柏・川向・河原などが泥海と化した。 白柏町は、江戸期〜明治22年の町名。宮津城下白柏町組の1町。触下に河原町・吹屋谷・池ノ谷がある。河原町に東接、葛屋町(安政3年以後蛭子町と改称した)に西接して南北に長く続く町筋。 家数は、寛文6年138軒、元禄16年139軒(以上河原町・住吉町を含む)、宝暦年間150軒(住吉町を含む)、明治維新以前132軒、明治21年109戸。 天明3年2月12日当町晒屋治郎兵衛家より出火して、猟師町・川向町を包む竃数378棟数1、000余が焼失した。 嘉永6年3月から当町の白柏砂山の取払い普請が実施された、町中男子は総出で波止場へ砂を運んだという。文久2年この砂山は亀山と改称された。明治22年宮津町の大字となった。 白柏は、明治22年〜現在の大字名。はじめ宮津町、昭和29年からは宮津市の大字。 《白柏の人口・世帯数》124・57 《主な社寺など》 《交通》 《産業》 白柏の主な歴史記録《丹後宮津志》(地図も)
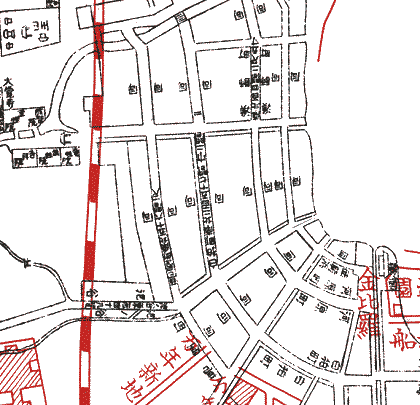 関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『宮津市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2009 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||