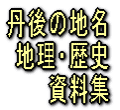 |
旧・余内村(あまうち)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧・余内の地誌《旧・余内村の概要》余内は現在は倉谷の余内小学校に名を残している。現在普通には余内といえば、この小学校区の範囲で、伊佐津川から東側の両トンネル(五老・白鳥)までをいい、この地名は今も使われているのだが、最初は北部の余部地域も含めての地域であった。 余内にしろ上安や上安久・下安久は読みにくい地名のようで、他所から来た人でまともに読める人はまずない。ヨナイ、ウワヤス、カミヤスヒサなどと読んでいる。市全体としては過疎化の進む舞鶴市ではあるが、この辺りは例外でむしろ過密化が進む地域である。 明治22年〜昭和11年の加佐郡内の自治体名。円満寺・上安久・下安久・福来・倉谷・清道・天台・上安・和田・長浜・余部上・余部下の12ヵ村が合併して成立した。 古代の加佐郡余戸郷と大内郷に当たるため二つの地名を合わせた新地名である。 明治35年和田・長浜・余部上・余部下の4大字は舞鶴海軍鎮守府設置の中心地となったため、余部町として独立した。 同42年余内尋常高等小学校が開校した。昭和11年舞鶴町に合併。村制時の8大字は舞鶴町の大字に継承された。 《人口》8665《世帯数》3330(現在の余内地区の合計) 旧・余内の主な歴史記録《加佐郡誌》 〈 餘内村 (一)戸数 五七三戸 (二)住民 男 一五二五名 女一五七五名 計三一〇〇名 (三)生業の状況 本村には二百餘町歩の耕地と百二十二町歩餘の山林とがあるが、新中両舞鶴町の中間に位するので、生業の状態は極めて複雑である。即ち之を大別すると、普通農業、養蚕、水産、商工業、労働等である。各其業に励みつゝあるけれども、近来農村の不振と財界の変動とによって、一般に生活の不安を感じつゝあるので、愈々自覚ある改良発展を期さなければならぬ状態にある。 (四) 主要物産 略 (五) 人情一般 舞鶴町と相接する所及び中舞鶴に至る沿道と、村の東南部即ち山の手方面と稍々趣を異にする如くなるも、村民一般に質資温健で、克く公共のことに竭し、義理を弁へ、未だ曾て訴願訴訟等のあったことはない。特に近来各種の税金一人の滞納者を出したことがないので、皆納の故を以て其筋から二回表彰を受けた。 余内の字円満寺・上安久・下安久・福来・倉谷・清道・天台・上安・和田・長浜・余部上・余部下関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||