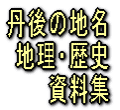 |
北有路(きたありじ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北有路の概要 《北有路の概要》 北有路は由良川流域の左岸に位置し、福知山市大江町の中央部。河守町方面より東流してきた由良川が、北方に流路を変える蛇行部一帯に発達した集落で河道に沿って湾曲する河守街道(国道175)に沿う。矢部山(309m)東南麓で西は上野村、東は三河村に接し、南は川を隔てて南有路村に対する。自治会は1〜4区に分かれる。 由良川と国道は当地で大きく湾曲、その湾曲部に由良川流域最大の大雲橋が架かり、対岸の南有路とを結んでいる。 また元田池・五ケ市池・尾後池・井ノ奥池・太良池・深田池などの中小湖沼が多い。 古代の この付近の由良川ではかつて鮭漁が盛んで、江戸時代北有路・南有路・二箇の三村はその中心であったという。藩の許可を得た三村は一年交代で鮭漁を行い、運上として毎年六〇〇匹(のちに金納)を藩へ納めたという(旧語集)。漁獲の方法は川の流れを簗でさえぎり、八つ縄とよばれる網で鮭を受ける。簗の途中に番小屋を二ヵ所つくり、八つ縄番人が四−六人ぐらいずつ昼夜交代で勤めたという(「有路船役文書」平野家文書)。 その後漁獲量が減少し運上金に困るようになると、三村は航行する船に課税するようになった(旧語集)。当時河口の由良と福知山城下との間を石・塩・米などを積んだ船が頻繁に往来したため簗の開き料として積荷の二、三パーセントを品物で取り立てた(同文書)。由良神埼の塩船は一艘につき塩四斗ずつで(丹後藩語記)、多数の塩船が上る時には村中の家が一軒あたり塩二、三俵の分け前にあずかったという(有路船役文書)。 由良川は舟運による物資輸送の便をもたらし、村民にも10数艘の高瀬舟を操って水運業に従事する者もいた。有路舟戸は舟継場としてにぎわっている。また一方由良川はたび重なる氾濫により住民生活の脅威となった。 北有路村は江戸期〜明治22年の村名。北有路は明治22年〜現在の大字名。はじめ有路上村、昭和26年からは加佐郡大江町の大字、平成18年からは福知山市大江町の大字。 《北有路の人口・世帯数》333・108 《主な社寺など》 鎮守は阿良須神社(式内社) 十倉五社神社 権現宮 地蔵堂 観音堂 鎮守の七面明神 明暦2年創建の曹洞宗恵日山光明寺(久昌寺末)(上野・千原・三河・高津江4か村の檀那寺でもある) 古墳2基 中世の山城跡 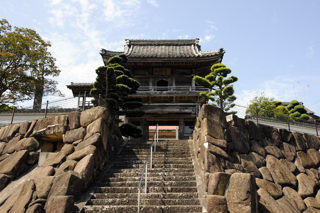 → あまりにこの地にピッタリの寺号なので古いのかと思っていたが以下のようなことという。 『加佐郡誌』は、 「恵日山光明寺、曹洞宗、明暦二年創立国宝として晁殿司筆羅漢書像あり、有路上。」 、 『大江町誌』は、 「絹本著色羅漢像 一幅 縦一○六・五センチメートに 横三一・七センチメートル これと図柄の一致する羅漢図が滋賀・宝厳寺蔵十六羅漢像や、神奈川・光明寺蔵十八羅漢像の一幅にみられる。これらはいずれも宋元画を手本とした漢画系の羅漢図であるが、この羅漢像には上部に色紙形があることや、彩色の調子に柔らか味があるところから、古く唐画に起源をもつ大和絵系羅漢像との折衷が考えられる。一部の描線や彩色に後補が認められるが、南北朝時代ころの制作らしく、大江町屈指の古画といえる。先々住の代に寄進されたと伝える。(中野)」 《交通》 国道175号 《産業》 北有路の主な歴史記録《丹後国加佐郡寺社町在旧起》〈 昔薬湯出類由、赤尾薬師温泉の鎮守なり。十倉五社大明神二社あり、権現堂、地蔵堂、観音堂あり菩提寺は恵日山光明寺と号す、倉橋弥三ともあり山名与九郎山城の跡あり。 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 北有路村 高七百四拾六石五斗八升 内四拾石九斗四升六合七勺 万定引 六拾石御用捨高 十倉五社明神 氏神 鍵取 玄入 十倉五社明神 権現宮 地蔵堂 観音堂 赤穂薬師 七面明神 鎮守 光明寺 恵日山 丹波福知山 久昌寺末 高津江 三河 上野 千原 北有路五ヶ村ノ寺 当村平野吉左衛門ト云テ富成者住リ 酒ヲ作り毎年新米納次第百俵宛拝借仕代銀極且上納ス 平日刀脇差ノ目利ヲ好ミ腰物多所ス隠居之時刀ヲ献ス御家老中江モ一腰宛致進上候由目利違多有之由沙汰有之枠ヲ立玄ト云法師也吉左衛門ハ京都ニ隠居家督立玄へ銀三拾貫目渡シ候由後立玄身上段々衰病死 河守ヨリ聟ヲ取立玄子幼稚ノ内夫婦引越来相続成長ノ後譲リ河守へ帰ル 《丹哥府志》 〈 【十倉大明神】 【恵日山光明寺】(臨済宗) 【山名与九郎城墟】 【付録】(一ノ宮、八幡宮、愛宕社、辻堂) 北有路の小字北有路 阿良須 堂本 三ケ村 五ケ市 関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『大江町誌』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||