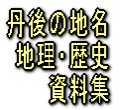 |
金剛院
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛院(慈恩寺)の案内《金剛院の概要》 鹿原川に架かる湯船橋を越えると、↓右手に奉行杉がある、平忠盛手植と書かれている、この奥である。大きな駐車場がある。  真言宗東寺派の寺院で、「鹿原(かわら)の金剛院(こんごういん)」といえばわかるが、正式には鹿原山金剛院(慈恩寺)という。   本尊はもと阿弥陀如来であったが、白河天皇勅願の永保2年(1082)以後波切不動尊となったという(海難、水難などすべての災害を除くとされることから海軍の信仰も篤かったというが秘仏で、節分の日だけの開帳されるという)。     ちょっと遅かったか、という頃でも、逆光にして見ると案外に見られる。    ↑↓ここはカメラマンの腕の見せ所。いっぱいいっぱいおられた。写し方も機材も全員の格が上の様子であった。  高岳親王は貞観3年に入唐し、その後は寺は荒廃したが、永保2年に白河天皇が再建し、不動堂以下の諸堂や一二坊を造立して  「禁制 丹後国志楽庄内鹿原山 金剛院 美福門院御願所 (勅判) 右至于当庄内地頭下司以下人々等任自由彼寺山木切取輩背 勅制歟然者可処重科之状如件 元弘三年六月日」  三重塔から本堂道へ登る石段↑↓ 数えた人によれば106段とか。足腰弱い人にはキツイ。    慶長7年の寺領検地帳(金剛院文書)には福聚院・橋本坊・宝蔵坊・東ノ坊・中之坊・多門坊・桜谷坊・南ノ坊などの坊名がみられる。 「丹哥府志」によれば、山椒太夫物語の厨子王丸身代りの地蔵があったと記す。 国重文の所蔵物には、絵画の絹本著色薬師十二神像、仏像の木造阿弥陀如来坐像・木造増長天立像・木造多聞天立像(平安後期)、木造執金剛神立像、木造深沙大将立像・木造金剛力士立像(鎌倉初期)がある。 寺領関係の寄進状・田地売券など(南北朝期から戦国期)金剛院文書といわれる古文書類も所蔵されている。 市天然記念物のカヤの木(千年榧)がある。   《簡単な境内案内》 紅葉の様子はその年の季候や、訪れる時期などによりビミョーに異なります、最美の紅葉に恵まれますよう、幸運を祈ります。 ↓動画(2010)いきなり大きな音がするかも、少し音量を絞っておいて下さい。  駐車場がある(無料)。自家用車はもちろん、観光バスも入って来るが途中の道幅が狭いので注意を。「まあ綺麗、京都みたいやね」などと申されながらゾロゾロと降りて来られる。 紅葉の名所がこの周辺には少なく、この時期は人出が多いが、京都の有名所みたいに歩けないほどではなく、ちょうどいいくらいのものになる。 約三千本とも言われる紅葉などのほかにも、境内は桜や松なども中途半端に植えてあって、どちらかといえば紅葉の邪魔になるのが難点。ドングリ、シイノミも落ち葉にまじってコロコロしている。無住のために荒れやすいのか、紅葉の色がも一つにも感じられる。狭い谷間なので、すぐに太陽が山影に隠れてしまう。正午前後の3時間ばかりがよいようである。  紅葉の期間中は「ぜんざい」「抹茶」とか「大根だき」とかもある。 高岳親王の墓  金剛院の向かいの山腹に開山の高岳親王の墓がある、という、行ってみたがよくわからなかった。 『舞鶴市史』 〈 親王の足跡は大略このように伝えられているが内地での巡錫とその地域についての記録は乏しく、その実状は不明な点が多い。金剛院への親王の留錫についても縁記に記されている以外に徴証する文献はないが、しかし推測して注目されるのは「三代実録」の陽成天皇元慶五年(八八一)十月十三日条に見える真如の次の上表文である。 貞観三年、上表して曰ひけらく、「真如出家以降四十余年、三菩提を企て、一道場在り。竊に以へらく、菩薩の道必ずしも一致せず、或は戒行に住して乃ち禅乃ち学と。而して一事も未だ遂げざるに、余算稍く頽る。願ふ所は諸国の山林を跋渉して、斗薮の勝跡を渇仰せむ」と。(原漢文。訓読は「訓読日本三代実録」による。) この上奏は真如が回国修業するために行なったものでこれに対しての大政官符は貞観三年(八六一) 三月二十九日に出され、これは「東寺要集」(巻三)に所収されている。 真如の留錫によって金剛院が開創されたと伝える縁記はその時期を天長六年としているが、これは上表文のなかの「真如出家以降四十余年」の期間に相当し、金剛院の地が一時「或は戒行に住し」た霊地となったことを類推させる。金剛院と真如との何等かの由縁はこれらからも否定し去ることはできず、その関係は常に真如研究に一石を投じていることになっている。 縁記はこのあと、さらに白河天皇が高岳親王の旧跡として、この寺院を再興し永保二年(一○八二)九月二十八日本尊として比叡山無動寺の相応和尚が彫刻した三体仏の随一である不動明王を若州から移し安置したことを述べ、この時の祈祷効験によって勅命で寺構が整備されたと伝え、ついで久安二年(一一四六)鳥羽天皇の皇后美福門院(藤原得子)が金剛院の開創ならびに中興は、ともに所由あるものとして、新たに阿弥陀如来像を安置し、国家鎮護の道場としたことを記している。 金剛院にはこうした縁記体ではないが今尚一本の寺史を語る木札が襲蔵されている。これは開基の高岳親王についてはふれていないが現在安置されている周丈六の阿弥陀如来坐像の造像を示唆する中世の本尊開帳にかかわる重要な史料となっている。 木尊御帳事 右彼不動者相応和尚御作日本三躰中是也 然自若州当山影向給事白河御宇永保弐年壬戌歳也 其後近衛御宇久安弐年丙?美福門院成御願所阿弥陀奉安置者也 御帳奉開始事応永九年壬午八月廿日奉治事応永拾壱年甲申八月九日也 この銘文は棟札様式の木札に墨書されたもので、白河天皇の永保二年に若州がら当寺に移した不動明王は相応和尚の三体の一であること、また其後近衛天皇の久安二年に美福門院の御願所となって新たに阿弥陀像が奉安されたことなどを記し、本尊不動明王の開帳を応永九年(一四○二)八月二十日の寅の刻に行ない、これを同十一年(一四○四)八月十九日寅の刻に奉治したことを書留めている。この内容は前記二本の縁記と略似通っているものの年代的には遡及しているので寺伝としては、かなり信憑性も高いとされるが、しかしこのなかに記されている永保二年の再興にかかわる本尊の不動明王が、もし現在奉安されている不動明王立像であるとするなれば、この作像の時代はそこにまで至らない中世のものとされている。これに対して現存する周丈六の阿弥陀如来坐像は縁記と木札銘文に伝える美福門院の御願所として新たに安置された阿弥陀像の可能性が強く、その製作の時代も丁度そのころに当る定朝様の尊像であることが既にいわれて久しい。  インドは仏教本貫地、僧侶のあこがれの聖地、何としても行きたいが、インドまでたどり着けた日本人僧は一人もいない、ごく最近にいたるまではない。 近くの僧では、古くは西遊記の中国の三蔵法師などや新羅にもいる。 お寺と関係ある家の子なのかワタシの知り合いはインドへ一度はいきたい、死ぬまでには行きたいと、よく言っていたのを思い出すが、交通が難しく、あるいはそんなヤッカイなことまでせいでもなのか、せいぜい中国で、それでもエライエライお坊さんとされる。 彼はそんなことでは満足しなかったスゴイ名僧としてよく知られている、当時の日本仏教にはたいへんに不満だったのだろう。舞鶴が誇るべき人物だが、さすがにバンザイバンザイのどこかのマチのことで、ほったらかしであまり取り上げられることはない、パンフにもない。インドまで行かねば本物の仏教がわかるかと、インド目指して広州を発ったときは66才くらいか。 インドというか、目指すはあるいは北部のガンダーラ(パキスタン、アフガニスタン)であろうか。実際はこの時代になれば、インド仏教もすでに衰頽している。ガンダーラは大乗仏教発祥の地とされる、仏教が世界に広まる転換を遂げた地で、仏像とか国家権力との結びつき、だいたい今の日本仏教の原点の場所であるが、あるいは古い仏典を持ち帰えられるかも、そこへ行くんだ… ♪だれもみな行きたがる 遙かな世界 … どうしたら行けるのだろう 教えてほしい In Gandhara、Gandhara They say it was in India 愛の国 ガンダーラ 当寺のテーマ曲にしたいようなものである。 しかしその後の消息は不明で、10数年を経て元慶5年に留学僧中取が親王は流砂を渡らんとして、羅越国で薨じたことを奏上してきた。また或る人は獅子国に至って群虎に遭い薨じたとも、瘴癘の悪気に冒されて薨じたとも伝えた。 日本から行った僧はいないが、インドからやってきた僧はある。峰山町橋木の縁城寺は、養老元年(717)インドの僧、善無畏三蔵の創建と伝えられている。東大寺の大仏開眼に立ち会ったのも確かインドの僧。 行くのならこの時代に行かねばならない、行って行けなくもなくはなかったが、高岳親王の熱意と較べるなら、皆ちと甘く、ハンパであったのかったかも知れない。聖地巡礼へ行ったこともない、行こうともしなかったという、エライお坊さんばかりのスンバラシイ国であった。 紅葉もいいが、せっかく金剛院を訪れるのなら、開山のこの熱い思いもまた忘れることなく、よく引き継がねばなるまい。 ガンダーラ仏教は古代の騎馬民族クシャン人だが、その後裔が今はウズベキスタンとなっている。  金剛院の主な歴史記録↓鹿原川。今はこの位置を流れるが昔はもっと山寄り(写真の右手側)を流れていた(旧河道のヘコミが残る)。こんな川だがなかなかの暴れ川で、金剛院橋の近くにあった山門を押し流し、中に納めてあった重文の仁王像を泉源寺まで流した、また本堂へ登る108段の下3段を埋めたり削ったのであった。  護岸工事がなされていて浅く、この季節は周囲の紅葉色を写して赤い流れに見える。 《丹哥府志》 〈 鹿原山慈恩寺金剛心院は真如親王の開基なり(真如親王は平城帝の皇子なり、始め高岡親王と称す、嵯峨帝の位に即くに及び立ちて太子となる、平城帝既に位を譲りて後奈良の故宮を修理して妃薬子と居焉、薬子の人となり恣にして奸なり、其兄仲成勢を恃みて頗る暴戻なり、遂に薬子と重祚を謀る、事露はれて皆誅に伏す、此時太子も亦廃せられて僧となり名を真如と改む(日本後記三代実録)後に入唐して遂に返らず)、天長二年真如親王諸国巡遊して志楽の庄に来り(在昔高岳親王京にあるの日鳳凰来り鳴く其肇善哉善哉と呼ぶ、高岳親王之を追ふて丹後に来り其鳥鹿原山に来り七日七夜鳴く、於是高岳親王其地を卜して伽藍を建立すといま人語り伝ふ、奇怪の説なれども、仲成の事露るるに及びて、高岳親王鳥に托して丹後に遁るにも斗りがたし)堂宇を建立す、號して金剛院といふ。後二百余年を経て白川帝の御宇に至る永保二年夏四月より雨ふらず七月に至る、於是新たに不動明王を勧請して請雨経法を修す、蓋勅に応ずるなり(日本史請雨経法を神泉苑に修する事を挙げて他の寺院を挙げず)、其請雨の験ありて慈雨の澤天下に及ぶ、よって慈恩寺の勅號を賜はる、是年重修の勅ありて伽藍を再建す、後六十年を経て近衛帝の御宇に至る、久安二年美福門院大伽藍を増立して三重の塔を造る(日本史曰后嘗金剛勝)是時平忠盛普請奉行となる。先是永保年中以来永く勅願所となりぬ、勅書勅願今に存す、皆以て徴とするに足る、後世に至りては元弘三年の制札、其文に云、 丹後国志楽庄内鹿原金剛院 美福門院御願所 判 右至于当庄内地領下司以上人々等任自由彼等山木切取輩背勅制顕然者可處重科之状如件 元弘三年六月 日 愚按ずるに、丹後より御願所に至る凡廿字是を本文とす、勅封の處は今冨御紋の在る處なり、右至て以下月日に至る四十六字は即ち宮司の付録なり、元弘年中既に一色氏丹後の国司なり、恐らくは一色氏前司に継ぎて月日を改め故の如く建る所ならん、此後細川氏二代の制札あり今此を用ゆ。辛丑夏余其寺に遊びて堂宇及仏像尽く是を観るに昔の如く壮なる事なしといへども、本堂の傍に鎮守社ありて天照、熊野権現を合せ祭る、其社の前に拝殿あり、所謂かけ作りなり、懸崖の下に柱を建つ凡二丈余り、本堂の前に護摩堂あり、護摩堂の前より石階六、七十段を下りて右の方に三重の塔あり、塔の前に大日堂地蔵堂あり、又楼門の内に十二坊今左右に連り、鐘楼塔堂悉く備はる、其門の前に下乗の札あり。本堂に安置し奉る不動明王は相応和尚の作なり、本堂の脇士多門天持国天は運慶の作なり、阿弥陀如来は行基菩薩の作なり、永保以前は是を以て本尊とすといふ、六臂如意輪観音は安阿弥の作なり、愛染明王は弘法大師の作なり、金胎大日如来は仁和寺智証大師の御作なり、弘法大師の木像は真雅の作なり、護摩堂に安置する不動明王は智証大師の作なり、塔の内にある大日如来は安阿弥の作なり、地蔵堂の地蔵は津志王丸の身代り地蔵なりと称す。 蔵宝目録 一、眞如親王肯像(御自製) 一、種字曼荼羅(仝上) 一、五色佛舎利(開山貫如親王手附の存する所) 一、鬼形仮面 (仝上) 一、五種鈴杵(仝上) 一、弘法大師袈裟 (仝土) 一、弘法大師肖像(仝上) 一、勅札(美福門院より賜る) 一、普賢菩薩(弘法大師) 一、星曼荼羅 (仝上) 一、不動明王(仝) 一、不動明王 (妙沢) 一、青面金剛(唐絵) 一、虚室蔵 (仝上) 一、薬師十二神(宅摩法師) 一、雨宝童子(仝上) 一、賀利帝母(互勢金岡) 一、不動明王(鳥羽僧正) 一、薬師十二神(唐顔輝) 一、十六善神 (恵心僧都) 一、愛染明王(伝教大師) 一、八組各図 (古図) 一、五大尊 (古図) 一、倶楽像 (宋人絵) 一、金迦羅制多迦(浮絵又兵衝) 一、卅三所観音 (僧慈覚) 一、列僧(古図凡卅五軸) 一、十二天 (古図) 一、三千仏(古図) 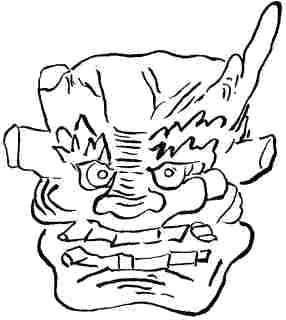 【にしきの里】 鹿原山に楓樹多かりしかばにしきの里といふ。藻塩草ににしきの里は春部の次にありといふ、丹後とも備中ともあり、備中名勝考に備中の国に探り求めるは誤りといふ。 【犬の馬場】(鹿原山境内城の尾といふ所) 平重盛の五男平忠房丹後の守に任ぜられ丹後侍従といふ、其住国の頃此處に於て犬逐物をなせりといふ、今に其馬場の所あり犬の馬場といふ、古き絵巻物あり。  《丹後旧事記》 〈 寺領弐拾弐石八斗七升八合 境内千八百弐拾五坪 其外山林 縁起紙面 人王五十一代平城天皇王子高岡親王、法名真如法師、出家廻国此山ニ至草創也。于時淳和天皇御宇天長六己酉年建立号金剛院九百六十年ニ及 寺之境ママ節云 高岡親王京都ニ御座時鳳凰鳴其声善哉々々ト鳴飛行跡ヲ慕ヒ給ふニ丹後国鹿原山ニ至山ニ宿ス。七日七夜鳴昼ハ善哉夜ハ怪云々々ト鳴依是相応之勝地トテ開給フ鳴声薫甚敷由 弁財天、高野山ヨリ勧請開基相継之所山上ニ有リ 此外中興建立 当時ニ楓多シ色ハ不勝黄葉多シ 大日堂 三間四面 地蔵堂 高岡親王戒名真如法師初ハ東大寺ニ居給ヒ後高野山ニ住シ給ヒ其後入唐 人王七十二代白河院永保二壬戌年高岡親王創建ノ跡ヲ尋神社仏閣荒タルヲ修補シ給フ是中興開山也 此年大旱也。四月ヨリ七月迄雨不降諸事雨ヲ祈レトモ不降。当寺ニ詔シ給ヒ雨ヲ祈ル七日間祈結願ノ日大雨天下ヲ潤ス。亦同年御悩有諸寺諸山丹誠ヲ尽して験ナシ亦当寺ニテ祈之其験無ニヨリ衆僧相議シ若州辺ニ有不動明王勧請シ祈祷ス。于時永保二壬戌年九月廿八日明王ヲ鹿原ニ移ス。此作無動寺ノ相応和尚彫刻三体ノ内也。悪魔退治ノ法ヲ祈ル御悩忽平癒シ給フ依而新ニ不動ヲ安置ス 本堂 本尊阿弥陀 安阿弥ノ作 不動明王 相応和尚作 五間四面 往古阿弥陀ヲ本尊トス 白河天皇勅願以後不動ヲ本尊トス 護麻堂 三間四面 二階鐘楼 二間四方 鐘ハ金崎ノ海ヨリ上リタリシ由金崎ノ銘有り 金崎ノ海底ニ今モ鐘有由地ニ耳ヲ当テ聞ケハ鐘ノ響有由。長浜ノ沖ニモ鐘有テ夜更ケテ海上ニ灯火見ユル村ノ者是ヲ灯明ト云 拝殿 掛作 鎮守拝殿也 三間四方 回廊 五間ニ一間 会堂 廃ス 浴堂 廃ス 荒神社 時代不知 三尺ニ一尺 熊野権現 同 三間ニ二間 伊勢大神宮 同 五尺ニ三尺 三重素塔 同 三間四面 二王門 三間ニ二間 二王門ヨリ本堂迄 二丁半 二王ハ安阿弥作 方丈 九間ニ六間 今七間半ニ五間 庫裏 七間ニ五間 今六間四方 塔頭 今無之 十二坊舎 此時寺号ヲ慈恩寺ト名付慈悲ノ恩沢故亦諸堂修理衆僧供領ハ志楽ノ荘ニ於被為寄付御祈願ノ勅書勅願明白也。是中興開山也。亦次ニ近衛院御宇久安二丙寅年、五百八十九年ニ及、美福門院霊仏奇瑞ノ事被及聞召高岡親王ノ草創白河帝ノ中興有由所トテ新ニ弥陀ノ像ヲ安鎮シ造営有シ。平忠盛奉行タリ。今本堂也 考巌院御宇 制札 禁 制 丹後国志楽庄内鹿原山 金剛院 美福門院御願所 右至于当庄内地頭下司以下人々等 任自由彼寺山木切取輩背勅制 然者可処重科之状如件 元弘三年六月 日 昔境内湯舟山城ケ尾山ヲ限ル近年細川家山門切ニ仕給。城ケ尾古城小松殿嫡子三位中将惟盛爰ニ居給ふ 細川家之時下馬札給ル于今在之 宝 物 一 五色仏舎利 三粒 一 五葦不動専 一軸 一 鳥羽僧正不動専 一 氏信筆薬師十二神 一 大師御袈裟 一 後鳥羽院勅額 建久戊午年被為掛 五百四十九年ニ及 一光厳院御于 元弘年中山林制札 四百四年 此年正慶 改元 一 唐筆数多有之 一 藤孝卿 忠興卿御自筆制札 寺中 福寺院 周快 藤ノ坊 橋本坊 医王山 多祢寺 西蔵院 末寺由良山 如意寺 油良ケ嶽 虚空蔵別 当虚空蔵嶽トモ云昔長福寺ト云 笠松山 泉源寺 智性院 愛宕山 松尾村ヨリ市場迄志楽荘ト云 元来日下部村卜云 古来奈良西大寺領地也 収納物相滞ニ付一色左京 太夫ヲ頼田中ノ大島但馬ヲ頓テ納米取立奈良ニ送ル 然所労而無功故後ハ但馬押領ス 其後大島御家人卜 成故領地替ル 一 高岡親王貞観三年上表奏事渡海入唐羅越国逆旅遷化 高野山宿坊 西谷院 報恩寺 荒神社 山神社  《大日本地名辞書》 〈  《加佐郡誌》 〈 《舞鶴》(大正12年) 〈 新舞鶴町の東一里ばかり志楽村字鹿原にある眞言宗の古刹で平城天皇の皇子高岡親王が出塵の念を抱かれ佛門に入らせられ受戒して眞如法印と御改名先づ東大寺に三輪を修し後高野山に上って密教を受けられ空海の入唐後天長六年の夏回国して此の地に??風物の佳勝なのを愛し高野山の弁財天女を勧請して天女社壇を建立し大日堂、薬師堂、地蔵堂をも設けて金剛院と號せられたに始まるのである、然るに一時頗る頽廃したが後白河院の永保二年再興せられた、霊塔は後白河院の勅建で久安三年に補修せられたもの加佐郡では最も古い建築物で浪切不動明王をまつり大正六年四月特別保護建造物として指定せられた、 もみぢ葉の色をしかへて流るれば 浅くも見えず谷川の水 と細川幽斎の詠じたのはこの山中の大瀧である、本山の所蔵にかゝる阿弥陀如来像(彫刻)薬師十二神通像(絵画)=顔輝筆、執金剛神立像(彫刻)=安阿無作等は何れも国宝として珍重せられこの他平城天皇から眞如法親王へ御下賜になって親王が本山開基の時これを被って邪鬼猛獣を攘ひ給ふたといふ鬼形面及び勅使参向の節饗膳に供へたといふ勅使椀等の宝物が多く藏せられて居る。  《舞鶴史話》(昭和29年発行) 〈 慈恩寺というのが寺号で、金剛院はもと塔中の主坊の称であったのです。真言宗の古刹で、平城天皇の皇子高丘親王が天長六年この地に来られ、その景勝幽邃の地を賞でてこゝに堂宇を創建せしめられました。祭檀には高野山の弁勝天女を勧請し、天女社檀を建立して大日堂、薬師堂、地蔵堂などをも設けられました。後親王は入唐せられたので寺は大へん荒廃しましたが白河院の永保二年に勅命によって再建せられ三重の塔なども建ちました。 又近衛天皇の久安三年には勅願寺として補修せられ、平忠盛が造営奉行になったことなどは有名な話であります。前記の三重の塔は特別保護建造物に指定せられています。境内にある御奉行杉は周囲十三尺余あって、平忠盛の手植になるものであります。 なお高丘親王手植と称する周囲十五尺に余る柏の木もあります。 同寺の国宝には 阿密陀如来(木像)安阿密作 深砂大王(木像)同 執金剛神(木像)同 薬師神(画帖)唐顔輝筆 金剛院禁制木札 (元弘三年六月日)一枚 等があり、又親王が本院開山の時被って邪鬼猛獣をはらい給うたという鬼形面、弘法太師より親王におくられたという蓮糸の袈裟、親王念持仏舎利塔、後醍醐天皇の山林禁制札(銅札)等いろいろな珍宝を蔵しています。 もみじ葉の色をし 替へて流るれば 浅くる見えず 谷川の水 幽斎が詠じたこの谷川はこの寺の下を流れている清流であります。…  《舞鶴文化懇話会会報》 〈 金剛院は戦後一時期、凄む人とて無く、檀家の人にも、なかなか人手が廻りかね、荒廃が酷く床下には狐狸の類が巣くい、萱葺の屋根の処々は崩れ落ちんとし、緑ごけの群生が見られ、・ペン・ペン草も繁茂し、おちこちには宵待草が黄色の花をしぼませて、時時興る風に、吹かるるままに、東に西にと揺れておりました。 その中を、善知鳥にはあらずして、二羽の鶺鴒がけたたましく、かん高い声をはり上げて鳴きながら、長い尾羽を上下させて飛びかっておりました。檀家の人が見廻りには来るのでしょうが。… 金剛院にまつわる話。 金剛院関係者、舞鶴の人には心地の良い響として耳に入り難いと想い、水らく胸底に潜めて秘めておりましたが、私もようやく馬齢を重ね、鬢も髪も青葉山の頂に降り積る雪よりも白くなり、来迎の近きを考え、禿筆を咬み、手に息を吹きかけながら、筆を走らせる次第。不快の響と聞こえましたら、耳を洗われたし。 昭和三十五年頃、友人某、我が陋屋に来りて告げるには、若狭の佐分利村の山奥に川上と称する部落在り。その在所の一番奥の農家のF家に、平安・鎌倉期の仏像が多数存するとのこと故、一度拝見に出むかんとのこと。日を定めて訪問することと決し、某日出かけました。 F家に至り、門を叩く。 九○才程の年で腰が弓の如き老躯と、七○歳程の老婦の二人が在宅されており、我達二人遠方より来り、貴家に伝わる仏像を拝見致したき旨申しますと、遠き処からようこそと、家へ招じ入れられる。 一歩屋内に入り廻りを見ますれど、昔の山奥の農家のこと故、昼でも屋内は暗い。ようやく暗さに目がなれたころ、縁側の雨戸を一枚くる、さっと射込む陽光で屋内の仏像が浮かび上がる。 淡いあかりを受け、あまり大きくもない古い仏像が一○体程、薄明の針光の中でかすかに微笑むが如くにして鎮座なされてましまする。正しく平安・鎌倉仏、室町仏もまじってござる。 私は凝然として佇立するのみ。 今もこの文を書いておりますと、あの時の戦慄が蘇ります。礼を失した云い方ですが、山奥の農家にこの様なものが存在するとは夢想だにしませんでした。 拝し終り、囲炉り端で山茶を喫しながら、この家に伝わる謂われと申しますか、故事来歴と申すものを、九○才の嫗が、歯の抜けおちた口で赤い歯茎をもぐもぐとさせながら、七○歳の老婦の助けをかりて、訛の強い若狭弁で訥々として語る話を拝聴させて戴きました。 三○年後の今、我が耳底に残るその時の言葉を多少標準語に置き替へまして誌しておきます。 嫗の話 「うらが(九○嫗が)子供の頃より、お爺さんから時々聞かされた話では、この山の奥の方に谷が開けて平になった処が在ります。そこには千年の昔から寺が在りました。七堂伽藍が並び建ち真中には高い高い天までとどく七重の塔が聳へておりました。 私達の家はその寺の前に住んでおり、代々寺に壮へておりました。途中の頃から(室町時代か)寺がだんだんと衰微いたしました。江戸時代の末頃になって寺は荒廃し、維持が困難になりました。 私達の先祖も寺が無くなれば身過ぎ世過ぎが出来なくなりますので、山を降りることとなり、明治の始め頃に山麓に土地を求めて家を建て、そこで暮らしをする様になりました。……が、 寺に在る仏さんと、仏具・寺道具・寺の書き付けを、そのままにしておいては罰が当ると云うので、何体かの仏さんと諸道具・諸教典は本家が預ることとなり、分家の我が家には小さな仏さんを何体か預ることとなりました。そして、寺の大きな仏さんは在家に置くものでは無いと云うことで、皆の衆は協議の上で、鹿原に在る金剛院さんへ納めることと相なりました。 農閑期の暇が出来ました時に、うらの(九○嫗の)爺さんが連尺に背たら負うて、山を越へて金剛院さんへ納めましたと、聞いております…。 本家に預りました仏像・仏具・書き付けその他一切のものは、その後家中のものが山仕事に出ている間に、家から火が出て家が丸焼となり、一物も残さず灰となりました。 分家の我が家に預かった小さな仏さんの内のわずかばかりが、今、家に伝わっておりますこの仏さんです…。」と 長い話を聞き終り、一息ついて、ふと縁側を見上げますと、一枚くった雨戸の向うに、木の皮の様なものが軒先に簾の如く多数干してあるのが目に入る。 聞けば藤の皮とのこと。このあたりでは、これにて一布を織り野良着や、カルサンを作ると云う。珍しきもの故織り上げし節一反割愛下さるべく申してその家を辞す。 三年後の昭和三十八年、再訪し約束の藤布一反戴く。 明治の初め、村人達に抱かれて山麓へ降りた仏像の一部は農家の家奥に、今もひそと残り、古代の藤布は我が掌中に存り。 嫗の父親に連尺で背負われ、村人達に見おくられて鹿原の金剛院へ旅立った仏像、深州大将と執金剛像は、今も金剛院に鎮座して衆生に慈悲を施す。二仏共にアン阿禰陀の墨書銘在り。鎌倉時代快慶の初期作として国の重要文化財に措置されております。 江戸末期の『丹後国伽佐郡志楽庄鹿原山金剛院霊宝記』には、深州、執金剛二仏の記載を見ず。然し、明治以後の金剛院宝物帳には二仏が揚げられております。このこと、何と解釈致しましたら良いのでしょうか。 あなたの考えをお聞きしたい。 平成二年一月十四日 寒けれど雪なし 註 若狭の農家では自分のつれあい(主人)を呼ぶ場合、中年ならば「お父さん」と呼び、老年ならば「お爺さん」と呼ぶ。嫗の話の「お爺さん」は祖父でもなくつれ合でもなし。この場合は自分の父親のこと。嫗は明治三、四年の生れ、父親は当時三十才前後か。二嫗共に旅立つ。 関連項目 ものすごく個性的な文化財をもつお寺でもある。 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008-2017 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
