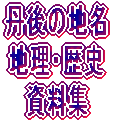 |
古殿(ふるどの)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古殿の概要《古殿の概要》 府立峰山高校がある一帯で、古名を丸山町と称した。藩主京極家の茶園「茶園場」や旧吉原山城の出城丸山があり、北西の山稜づたいに善明通があって吉原山城内へ続いている。かつて茶園場は現在はグラウンドとなっている。丸山横穴1基があった。同校敷地に弥生時代~平安期の古殿遺跡がある。 古殿町は、江戸期~明治22年の町名。江戸期は城下町峰山町の1町。家中町。もとは丸山町。慶長6年宮津藩領となって以来20年間は同藩役人衆が丸山町に出張して近郷を治め、元和8年峰山藩に引継がれるに際しても、まず家臣が丸山町に仮居住した。そのためやがて古殿町と称されるようになったという。 明治17年からは峰山15か町の1町となり、峰山を冠称。同22年峰山町の大字となる。 古殿は、明治22年からの峰山町の大字名。平成16年から京丹後市の大字。 《古殿の人口・世帯数》 112・47 《主な社寺など》 《小字》 古殿 サエンバ 咲谷奥 丸山 元薬師 《交通》 《産業》 古殿の主な歴史記録『中郡誌稿』 〈 古殿遺跡 『京丹後市の考古資料』 〈 所在地:峰山町古殿小字丸山 立 地:竹野川中流域、支流小西川左岸扇状地 時 代:弥生時代後期~古墳時代前期、中世 調査年次:1977年(府教委) 1982、86、89年(府センター) 現 状:調査部分は消滅(峰山高校) 遺物保管:丹後郷土資料館、府センター 文 献:C044、C069、C077 遺構 古殿遺跡は、北西側より伸びる3本の細尾根丘陵の裾を中心とした扇状地に立地する。過去、4次にわたる発掘調査が実施され、弥生時代後期~古墳時代前期、平安時代末葉~鎌倉時代初頭の2時期の遺跡であることが判明した。 主な遺構は、弥生時代後期~古墳時代前期にかけての住居跡3、溝および溝状遺構20以上、土器溜り、土壙などが検出されている。 住居跡のうちSB05は、幅0.3mの溝により区画された4.5×4.2mの方形建物遺構である。棟を支える柱穴が検出され、平地式の壁構造を持つ竪穴住居跡と考えられている。溝および溝状遺構は、東西方向もしくは北東から南西方向に伸びている。 弥生時代後期にあたるものは、溝SD12がある。集落内を流れる溝と判断されている。後期末になると、溝SD04に並行する住居跡SB05、07が形成されるなど一定のブロックごとに平坦面を形成していた可能性がある。土器溜りSX11では、完形の土器が並べ置かれた状態で土製模造品(杓、手づくね土器)とセットで出士し、井戸SE03では桶を転用した井戸枠が検出され、完形の壺が出土している。共に祭祀的性格を持くつものと判断されている。 古墳時代前期にあたるものには、構SD302、303などがある。流路を木材により護岸したもので、堰および付属施設の構築が確認されており、大規模な施設の拡充が想像される。多量の土器に加え、柱材や板材などの土木建材、農機具、紡織具など生活用品、古代の机である案や盤、箱など木製品が多数出土した。また、木器溜りSX301では布留式土器を供伴した建築材などが集積した状態で検出された。集落内の流路が埋没し機能しなくなると集落の造営も停止されたようである。 遺物 古殿遺跡では、土器、土製品、木製品、石器、植物遺体などが出上している。もっとも特筆されることは2、000点を越える木製品の出土である。 木製品は工具、農具、容器、案、祭祀具、発火具、組具、機織具、棒状木製品ほか、多数の建築、土木部材がある。案は組物と刳物の2種類出土し、四脚のものと二脚のものがある。材の木取りは横木取りによる。また、祭祀具としては鏃の模造品、舟形木製品が出土している。ほかに、用途不明の梯子状木製品が包含土層中から出土している。 土器は弥生土器、土師器があり、壷、甕、鉢、高杯、器台が出土している。 壷は、擬凹線文を持つものと二重口縁を持つものがあり、貼付突帯を施した装飾壺、小型丸底壺の出土も見られる。甕は擬凹線文のもの、いわゆる「山陰甕」と呼ばれる二重口縁を持つもの、「く」の字形の口縁を持つもの、布留式甕が出土している。このほか装飾器台、ミニチュア土器、注口土器の出土もみられる。 土製品には、鐸形土製品、勾玉形土製品、動物形土製品、土錘、土玉などがある。鐸形土製品は鈕部分が有礼莟鈕の形をとり、断面が正円形をとる。そのほか、モモ、トチの種子、桜樹皮などが山土している。 意義 古殿遺跡は、主に弥生時代後期から古墳時代前期にかけて営まれた集落遺跡である。流路が多数確認されていることから、この場には、常時、水の流れ込みがあったものと思われ、そのため「木製品の宝庫」と呼ばれるほど数多く木製品が残されたのであろう。共伴土器の状況などから、古墳時代前期に水路の再整備を行い、集落の最盛期を迎えていたと考えられる。 木製品については、建築、土木材が半数を占め、比率的に農工具が少ない。また祭祀具や容器には精巧な作りの物が多く、加工水準の高さをうかがわせる。また、1次調査出土の木製品158点を顕微鏡観察により樹種識別すると、スギが全体の84.8%を占め、すべての器種でスギが多く用いられていることが判明した。 古墳時代前期初頭の土器については、注口土器、山陰系の二重口縁を持つ壺、甕など山陰地方との土器交流がうかがえるものが多く出土している。 『日本の古代遺跡・京都Ⅰ』(写真も) 〈 古墳時代前期の竪穴住居跡三軒以外は、溝や土壙、井戸などの遺構であるため、集落遺跡としての実体は明確でないが、出土した遣物は、当時の丹波国の中心であったことを実見させる資料となっている。 とくに弥生時代後期から古墳時代前期にかけての溝から出土した木製品には、農具、機織具、食膳具などがあり、なかでも「案(あん)」とよばれる四脚机は、当時の最高水準の技術で製作されたとおもわれる逸品である。 白川静氏の『常用字解』に、 「案(解説)。音符は安。木を偏(きへん)にしないで下部におく形の漢字は、栄(榮)・架・某など、例が多い。案はものをおく台、「つくえ」をいう。はじめは、食事用のもので脚のあるものを案、ないものを槃(たらい)といった。のち書物をおいて考案する(工夫して考え出す)こと、考察することに使うので、「かんがえる」ことを案という。」 とあって、こんな図がついている→ これは今も案と呼ばれている。 神道ではよく見受けられる。机というのか白木の台で、神事に関係した重要な物が上に置かれる細長い目の脚の長いものである。 『京都新聞』(日付が不明になってしまった) 「続・京・近江の古代朝鮮を歩く〈44〉*アメノヒボコ伝説を訪ねて」のシリーズに、「 生活感漂う木製遺物*古殿遺跡*」 〈 出土した木製品は千三百点を越える数。柱、板などの土木建築材、杓(しゃく)子などの食事具、祭祀(さいし)の時に食べ物などを乗せて使用したとされる案、盤や槽、箱などの容器、糸車などの紡織具、鍬(くわ)、鋤(すき)の柄などの農具、木の釘(くぎ)などの工具などだ。案は膳(ぜん)、卓、テーブルのことで、盤は供膳に使った盆のこと。槽は水、その他の物を入れるために使われた。 案は台が長方形の四脚と二脚のほかに、台が円形の三脚もあったらしく、古墳時代前期の遺物とされる。案は静岡県、奈良市、滋賀ノ湖西地方の遺跡でも出土しているが、古殿遺跡の案は台の縁の側を反らせ、脚の中央を細くし、全体を曲線にしてあるなど、他の遺跡と異なっていた。 どこから伝えられたのだろうか。京都府埋蔵文化財調査研究センター主任調査員の戸原和人さんは「案の系譜」の論文で次のように書いている。 「中国大陸や朝鮮半島の漢代の墓から出土する案にその類例を求めることができる。中国及び朝鮮半島における漢代の墓から出土した案は、前漢から後漢までの約200年にわたるものである。今回出土の案については、概ね朝鮮半島を経て中国漢代の影響を受け製作された製品と考えて大過ないものと考えられる」 前漢は紀元前二〇二年から八年、後漢は二五年から二二〇年まで続いている。漢は朝鮮半島に「楽浪郡」という植民地を持っていたが、戸原さんは二世紀後半に後漢の統制力が衰え、朝鮮半島の住民の逃亡があったとされるとしたあとに、「朝鮮半島の東岸から船出すると、日本海流に流され能登半島以東に漂着するという。また朝鮮半島の南岸から船出すると、島根や丹後半島の浜に漂着するといい、現在でもよく韓国からの漂着物がある。人々の中から日本に向け出港し、丹後の地に文化をもたらしたものがいても不思議ではないと考えられる」と縮めくくっている。 戸原さんが言うように、人々が移動する時、それと同時に衣食住のあり方、こまごまとした生活習慣などの文化も持ち込まれる。峰山高校の地下で暮らしていた人々も例外ではなかったろう。 古殿の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『峰山郷土志』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2013 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||