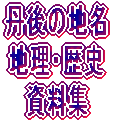 |
井辺(いのべ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥栄村井辺 |
井辺の概要《井辺の概要》 竹野川西岸の山麓、鳥取の北にある小さな集落。 近世の井辺村は、江戸期~明治22年の村名。宮津藩領。 明治4年宮津県、豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年深田村の大字となる。 井辺は、明治22年~現在の大字名。はじめ深田村、昭和8年弥栄村、同30年からは弥栄町の大字。平成16年から京丹後市の大字。  タンボの中にあって全長30メートルくらいか、集落を走る府道からよく見えて、ここを通るたびに、これは前方後円墳でないかと、もう何十年と思っているのだが、手持ちの遺跡地図などには何も記載されててはいない。専門家ならそう考えるに違いない姿をしているので、調査は当然なされていると思うが、古墳状の自然地形なのだろうか。対岸には黒部銚子山古墳がある。 もう一度調べてみると、やはり前方後円墳で、桑田2号墳、全長21.5m、後円部高0.7mとある、完存しているが、未調査でこれ以上はわからない。まあ考古学会からすら完全に無視されているようなことだが、小さいが古いかも知れず丹後王家のものだろうから少しは注意してもらいたい。 《井辺の人口・世帯数》 177・43 《主な社寺など》 境内に円墳を中心とした古墳群が完存。  『丹後国竹野郡誌』 〈 (神社明細帳) 祭神 須佐之男命 元八大荒神と称せしが明治二年十一月神社改称の際社のある所の地名穂曾長を以て神社の號とし明治四年先月村社に列す、享保二年十二月、安政六年十月再建 社 殿 梁行 一間四尺七寸 桁行 二間四寸 境内坪数 千七百六十二坪 (丹哥府志) 八大荒神 祭九月十六日 『弥栄町史』 〈 祭神 須佐之男命 元村社 由緒 創祀の年代は不詳であるが享保二乙卯年十二月(二百五十年前)安政六己未年(百十年前)等の再建記録がある。 元社名は八大荒神といったが、明治二年十一月神社調書作成の際当社鎮守森は穂曽長といったので、穂曽長神社と改称し、さらに明治四年五月村社に列せられた。その他の由緒も不詳であるが、当社地穂曽長の森は古墳であるらしく、境内に円墳らしい小高い所が三ケあり、その中央の小高い所に社殿があって、人里に近いが、老樹巨木鬱蒼として生い繁り、境内の清掃整備よく行き届いて幽邃の感一入のものがある。 社殿 梁行 一メートル三十センチ 桁行 一メートル六十三センチ 上家 梁行 三メートル六十三センチ 桁行六メートル三十六センチ 境内坪数 千七百六十二坪 ホソナガとかヘビではなかろうか。  『丹後国竹野郡誌』 〈 (丹哥府志) 天王山長福寺 曹洞宗 (村誌) 福昌寺末派なり往古は眞言宗なりしが、万治年間転宗し、開山を長伝和尚とす、 (福昌寺文書) 福昌寺第二世密菴長伝大和尚隠居して長福寺を建て開山となれり 『弥栄町史』 〈 本尊 大日如来 曹洞宗 丹哥府志によれば、 「往古は真言宗なりしが万治年間転宗し、開山を長伝和尚とす。 とあり、福昌寺交書によれば、 「福昌寺第二世密華長伝大和尚隠居して長福寺を建て開山となれり」 とある。 『弥栄町史』 〈 現在城山という地名の岡あり、城のあったことはうかがわれるが、城主名等丹後旧事記等の古文書にも見られない。 《交通》 《産業》 小田の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 【八大荒神】(祭九月十六日) 【天王山長福寺】(曹洞宗) 『京丹後市の考古資料』 〈 所在地:弥栄町井辺小字普甲 立地:竹野川中流域左岸丘陵上 時代:古墳時代中期 調査年次:1987年(府センター) 現状:全壊(国営農地) 遺物保管:市教委 文献:C068 遺構 普甲古墳群は、竹野川が形成する沖積平野に向かって延びる二つの低丘陵の尾根線上に築かれた13基からなる古墳群である。それぞれの古墳が裾を接するように連接して築造されており、このち北側の尾根にある1~7号墳の調査が行われている。 いずれの古墳も盛土は見られない。標高の高い方から順に築かれた1~3号墳は、尾根筋に直交する溝によって区画されている。4~7号墳は、墓域を確保するために、傾斜の急な尾根稜部を削り台形の平坦面を作り出すが、それ以外の斜面部分は自然地形のままである。 埋葬施設は全部で16基あり、すべて木棺を直葬したものである。複数の埋葬施設を持つ1~3号墳と1墳丘1埋葬施設の4~7号墳に分けられる。特徴的なものとして4号墳の埋葬施設があり、長さ約6m墓壙内に仕切り板で棺内を区画した箱形木棺をもち、玉類どが副葬されていた。また6、7号墳では、規模、構造の類似した割竹形木棺が採用されていた。 遺物 土器は、4号墳から3個の土師器が出土しているのみである。鉄製品としては鉄鏃11、鉄剣2、ヤリガンナ1針状鉄製品1があり、玉類としては滑石製の勾玉6、棗玉47、臼玉6、管玉3、小玉1のほか、碧玉製管玉8と緑色凝灰岩製管玉、硬玉製勾玉、ガラス小玉各1などがある。また竪櫛2も出土している。 意義 普甲古墳群は、丹後地域の特徴的墓制である弥生時代後期に盛行する方形台状墓の系譜を受け継ぐものである。1~7号墳の形成過程は尾根上部から先端に向かって順次築造されたもので、その時期は5世紀前半から中葉にかけてと考えられている。 小田の小字一覧井辺(いのべ) イケジリ イシフロ ウチツボ オクダニ カワクボ クワダ コブコウ コミヤダニ ゴセモノ サカノシタ シモジ ノノウ フコウ ミヤノマエ モリヤマ ヲテジ 関連情報 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『弥栄町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2013 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||