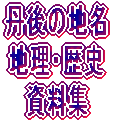 |
久僧(きゅうそ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下宇川村久僧 |
久僧の概要《久僧の概要》  久僧の海岸を見るなら「宇川温泉・吉野の里」の浴槽からの眺望である、そんな所へはカメラ持って行くわけにもいかないので、これはそこへ可能な限り近づいて写したもの。↑もう少し左へ寄りたいが浴場があるためできない。 海岸は超美しい。水美しい。ポコっと高い島が高島。  吉野川河口の東方、日本海に北面する海岸沿いの集落。 久僧村は、江戸期~明治22年の村名。はじめ宮津藩領、享保2年より幕府領。当初宇川村のうち、のち分村独立。 明治元年に久美浜県、同4年豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年下宇川村の大字となる。 久僧は、明治22年~現在の大字名。はじめ下宇川村、昭和30年からは丹後町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 伝承によれば、久僧村は貞治年間(1362-68)までは現在地より300メートルほど南方の小字池田およぴ池上の山間に、100余戸散在して農業を営んでいたという。永禄年間(1558-70)大暴風雨に遭い、付近の山谷が崩れ、部落の過半は土砂に埋没したので小字小谷の地にしだいに移転し、農業の傍ら海藻を採って生活した。その後漁業のためには海辺のほうが便利なので現在地へ移ったという。 漁師町といってもこれくらい漁船しかないよう。↓  キュウソと呼んでいるが、「クソですわ、クソ、糞ですわ」と地元の人も言っているが、おそらく本来の発音はそうではなかろうか、意味は糞ではなかろうと思う。「九艘」とか書くところもあるが、全国的に見られる地名である、意味不明とされる、宇川の川上にも竹久僧(たけきゅうそ)という集落があったが、ここが本村かも知れない。クシフルのクシではなかろうか。大(ク)ソフルのフル(村)がついてないものか。母音変化してカサとなっても同じ、丹後の加佐人のはしくれには何か親しみが湧いてくる。弥生か古墳の頃は聖地だったと思われる。 吉野川の河口の何かワレラのルーツを示していそうな地名になる。 《久僧の人口・世帯数》 222・78 《主な社寺など》  『丹後国竹野郡誌』 〈 (神社明細帳) 祭神 天御中主神 創立年月不詳、寛永五年、寛政九年に建替たり、明治四年村社に列す境内百二十四坪、上屋桁行二間半梁行一間半、氏子六十戸なり 『丹後町史』 〈 天御中主神を祭る。 寛永五年、寛政九年再建を行い明治四年村社になった。  『丹後国竹野郡誌』 〈 (同寺調文書)智源寺末にして潮音山と號す 本 尊 観世昔 坐 像 由緒、往昔は岩野山隣海庵と唱へ同村同字脇地と申處に創立す、天和年中の頃より常徳寺末寺なりしが元禄九丙子年宮津智源寺末寺と相成而して享保年中頃同村同字中地移転し創立す、安政七戌年字池田へ移転す此時山號改て潮音山と號す、寛政甲寅年に本秀代に伽藍再興享和三癸亥年五月法地の許可を受候、文久二壬戌年秀芳代に伽藍再興す、明治九丙子年寺號の許可を受け隣海寺と改之 堂宇桁行六間梁行四間半、位牌堂桁行一間半梁行二間半、庫裡桁行七間半梁行五間、土蔵桁行三間梁行二間、 境内佛堂 薬師堂 本 尊 薬師如来 由緒不詳、 建物梁行三間桁行四間半 財産田一反一畝十二歩、畑一町三畝廿四歩、宅地一反七畝廿八歩、境内坪数五百三十八坪 (丹哥府志) 潮音山隣海寺 曹洞宗 『丹後町史』 〈 本尊、観世音菩薩坐像 昔は岩野山隣海庵といい同字脇地に創立天和元年(一六八一)常徳寺の末寺であったが、元禄九丙子年(一六九六)宮津智源寺の末寺となった。享保元年(一七一六)同字中地に移転した。安政七戌年(一八六〇)字池田へ移転、此の時山号を潮音山と号した。寛政申寅年(一七八九)、本秀代に伽藍再建、享和三癸亥年(一八〇三)五月法地の許可を受け、文久二壬戌年(一八六二)秀芳代に伽藍再興、以来十八世小谷弘道師に至る。 境内仏堂 薬師堂 本尊(薬師如来) 檀家約七〇戸。   わずかな距離だが、凝灰岩の奇岩がゴロゴロ。何か海の側から押してきたような感じである、あちら側に火山があったものか。大島というのだが、どの岩が大島なのかはわからない。どれくらいの岩なら島と呼ぶのだろう。 《交通》 国道178号が東西に貫通し、府道久僧伊根線が南へ分岐。 《産業》 吉野川河口付近の高島から中浜の西に突出する大島の間は、白砂の遠浅海岸で、町内屈指の海水浴場である。 ♨ 天然温泉「宇川温泉・よし野の里」。「日本海の青さや水平線に沈む夕日に息をのむ海の温泉、竹林に囲まれた山の温泉、二つの浴場は男女日替わりになっています。レストランや宿泊施設があり、湯治を兼ねた長期滞在もできます」とある。  久僧の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 【鈴岡明神】(祭九月朔日) 【潮音山隣海寺】(曹洞宗) 【付録】(三宝荒神) 『丹後国竹野郡誌』 (京都府漁業誌) 〈 『丹後町史』 〈 久僧の小字一覧久僧(きゅうそ) 才尻(さいじり) 下高田(しもたかだ) 砂田(すなだ) 黒岩(くろいわ) 片山(かたやま) 菖蒲谷(しょうぶだに) 菅ケ谷(すがたに) 外若(そちわか) 白幾地(しろいくじ) 宮ノ尾(みやのお) 堀友谷(ほりともだに) 細畑(ほそばた) 休場(やすみば) 小豆谷(あずきだに) 金クソ(かなくそ) 徳上(とくじょう) 徳上坂(とくじょうざか) 山ノ谷坂(やまのたにさか) 山ノ谷(やまのたに) 向菖蒲谷(むかいしょうぶだに) 吉ノ(よしの) 黒崎(くろさき) 三十八(みそはち) 源ケ谷(げんがたに) 春日(かすが) 白ケ鼻(しらがはな) 上ノ(うえの) 車ノ(くるまの) 千ケ野(せんじょうがの) 三平田(さんべいだ) 夜長(よなが) 高田(たかだ) 浜尻(はまじり) 池田(いけだ) 上地(かみぢ) 中地(なかぢ) 脇地(わきぢ) 小屋(こや) 松サキ(まつさき) クゴ ヨマイ坂 上ノ山(うえのやま) 中道(なかみち) イサキ 池ノ上(いけのうえ) 中間(なかま) クゴ 宮ノ後(みやのおて) 東浜ノ上(ひがしはまのうえ) 東浜(ひがしはま) 水ケ本(みずがもと) 渡ケサキ(わたりがさき) 石ケ谷(いしがたに) 小坂(こさか) 宮ノ前(みやのまえ) ハザコ 家ノ上(いえのうえ) コシマ 向クゴ(むかいくご) 岡角(おかのかど) 西ノ下 林竹(はやしたけ) 大谷(おおたに) 丸山(まるやま) 両欠(りょうがけ) 大清水(おおしみず) 小谷(こたに) 西小谷(にしこたに) 小谷坂(こたにざか) デンゴ 左山(さやま) 後ケ谷(おてがたに) 栗ケコ(くりけこ) 家ノ口(いえのくち) 横尾(よこお) ワラビガナル スエ谷(すえだに) 間谷(マダニ) 中尾(なかお) 東ダケ(ひがしだけ) 関連情報 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『丹後町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||