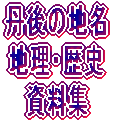 |
旧・野間村(のま)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧・野間村の概要《旧・野間村の概要》 東の太鼓山(683m)、西の小金山(416m)・金剛童子山(613m)、南に高尾山(620m)等より数条の支流が流れ出て、北流する宇川に合流する。その谷間に幾つかの集落が散在する。ここへ入るにはいずれかの山系の高い尾根を越さなければならない。宇川下流から入るのも大変で大きな山を越えなければならないが、それらの道々はたいていは廃道に近い状態で、冬期は通行止めになる。今は弥栄町黒部から入るのが一番楽である。  近代の野間村は、明治22年~昭和30年の自治体名。はじめ与謝郡、昭和23年からは竹野郡のうち。須川・野中の2か村が再び合併して成立。旧村名を継承した2大字を編成した。 江戸期以来この地の経済を支えてきた薪炭・養蚕・棉作・林産の需要低下や多雪の影響により人口が減少した。 一戸から数戸であったもと須川村の出合・黒川・尾崎・茶園(ちゃえん)・熊谷(くまがや)・小杉・平家(へいけ)などの小集落は、昭和38年の豪雪がおもな原因で住民は移転し、現在人家はない。 昭和30年弥栄町の一部となる。村制時の2大字は弥栄町の大字に継承された。平成16年から京丹後市の大字。 地名から考えれば、野間は野間神、すなわち娘媽神を祀る地と思われる。中国南部の航海安全の神として知られるが、片目とする伝承もあり、鍜冶神でもある。東隣に連なる世屋もタタラの地であろうし、内陸に入った南方海人系の人々の産鉄の地であったのではなかろうか。 伝承では平家落武者伝説があり、平家という所もある、平家はタタラ家のことかも、矢野弾左衛門伝説もある、江戸期には江戸の穢多頭として知られるが、この一族も長い歴史があって鎌倉権五郎景政の一門に加えてもらったりするが、元々は摂津国能勢郡の野間の隣の多田庄の人のようで、景正は桓武平氏である。あるいはその野間や世屋が当地へ移動してきたものかも知れない。 《交通》 《産業》 旧・野間村の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 ◎味土野村(木子村駒倉村の西、中郡延利村又男山村へ道あり) 【蔵王権現】 【御 殿】 細川忠興の妻は明智光秀の女なり、天正十年夏六月三日明智光秀京都本能寺に於て将軍信長公を弑す、細川忠興共不義を悪み遂に其妻を上戸に禁錮す(上戸は今の味土野なり明智軍記に丹波三戸野に作るは非なり)共後太閤秀吉の命めるを以てこれを免ず、事は太閤記明智軍記武林伝に詳なり。 天正小鏡 身を隠す 里は吉野の奥ながら 花なき峯に 呼子鳥鳴く 忠興妻 【茶摺鉢】 味土野村の端郷に小杉、三舟の二村あり.昔より木地師あり相伝へて今に至る、是を以て昔の茶摺鉢といふもの往々残れり。 ◎大谷村(味土野村の下) 【大将軍社】(祭九月廿八日) 平家物語三草合戦に曰。平家方の大将には小松新三位中将祐盛、同少将有盛、同丹後侍従忠房、又藤戸合戦に、平家の大将には小松新三位中将祐盛、同少将有盛、同丹後侍従忠房とあり。軍破れて後中将祐盛は少将有盛と共に水に入りて蹤を晦ます、維盛は一の谷に於て討死す、獨丹後侍従忠房は主馬判官盛久、越中治郎兵衛盛次、上総五郎兵衛忠元と丹後與謝に帰りて平家のなり行を見、後に自害せりと丹後の口碑に残る。大将軍は大将の社といひしが近世大将軍社といふ、定て忠房を祭るなるべし。 ◎霰村(大谷村の下) 【山神社】 【金剛童子】(霰村の西) 往昔役小角丹後に於て業を勤められし跡と申伝へて、大和の業場と略相似たる所あれども、慥に記したる記録もなければ、後の世に擬して拵へたるものかも斗り難し、されども上山寺の開基より率合すれば殆ど千年余りにもなるなり、且記して後の考證に備ふ(宇川の庄上山寺条下を参考すべし。) 金剛童子道筋 上山(宇川の次、久僧村より南の方山に登る凡一塁余吉野山上山寺といふ寺あり、上山寺条下に詳なり)吉野(紅葉のよし野といふ、上山寺より一里斗もあり)霰村(吉野村より霞村へ下る)。 宮川(霰村の西南、是より又山に登る)。 休堂(宮川の上、此處に古代五輪石灯籠かと覚敷もの数多残る)。 かねかけの業場(休堂より五十丁斗登りて此業場に至る、此上にかねかけ松あり)。 御手洗の池(かねかけより五十丁斗登りて池に至る、池の広サ五、六間四面もあり、諺に此池を汲めば必ず雨ふるよって旱する時は村人此池に来りて雨乞をなす)。 行者堂(三間四面、昔の本尊洞養寺に納む)。 西の業場(堂の西南にあり、懸崖数十丈の上に突出したる大なる岩あり、岩の端へ出て数千丈の下を覗く、心不正の人は必ず責を蒙る、是を以て業とす)。 【附録】(八大荒神) ◎須川村(霰村の東)…略… ◎住山村(太鼓ケ嶽の西殆ど絶頂にあり、此下に熊谷村あり、是より須川村へ出る) 【丸山権現】 【露なしヶ嶽】(太鼓ヶ獄のつゞき、太鼓ヶ嶽より高きこと又一層) ◎来見谷村(霰村の西、是より竹野郡外村へ出る) 【八大荒神】 ◎野中村(来見谷村の下)…略… ◎横住村(野中村の上より東北へ入る) ◎吉野村(横住村より北に入る) 竹野郡宇川の庄上山村に在る上山寺の山号を吉野山といふ、紅葉の名所なり。吉野村は與謝郡野間の庄にありて、上山寺と腹脊の處なり。 ◎中津村(野中村の下) 【三森荒神】(祭九月廿三日) ◎中山村(中津村の西、山を越て竹野郡黒部村の奥にあり) 【三宝荒神】(祭九月十八日) ◎田中村(中津村の下) 【八大荒神】(祭九月廿三日) ◎永谷村(田中村の下) 【三宝荒神】(祭九月八日) ◎川久保村(永谷村の下、是より竹野郡宇川の庄小脇村へ出る。) 【八大荒神】(祭九月廿三日) 『丹後旧事記』 〈 小松大臣殿の公達は嫡男三位中将惟盛は軍破れて後出家してみつの御山の権現へ詣て後入水有けるとなり新三位中将祐盛少将有盛共に入水あり、備中守諸盛は一の谷にて討死有丹後守忠房は悪七兵衛景清越中の次郎兵衛と共に世を忍び後次郎兵衛盛次を具して丹後但馬に身を隠し給ふと伝ふ。当国府中中村といふ処に忠房建立の神社有里俗左大将の宮ともつとふ、是は父重盛公を崇め奉りし社也といふ。又九世戸文珠の浜に泪ケ磯といふ有り此所に身投岩といふ大岩有是は忠盛卿に宮仕へせし花松といふ白拍子平家の運のかたふくかなしみ三草藤戸の戦の後忠房卿行方知れず成給ふときこえければ御忘れがたみを御子立をめのと矢野長左衛門頼重主馬判官盛久にたのみ置く所詮永らへべき命ならずと夜ふけて泪ケ磯に出て丈余の岩の上より落て海にしづみけると也、是を丹後物狂といふ謡物の曲に花松といふ狂女と記せり。主馬判官盛久矢野長左衛門頼重は忠房の忘れがたみの公達を守り奉り小松の館にありけるを源氏さがし来りて盛久頼重と戦ふ、破軍の後矢野は野間の庄に身を隠し公達を守護す盛久成相寺一辻堂のほとりにて搦めとられ鎌倉へ渡る、是を謡物の曲に盛久成相寺に隠れ居たるをさがし出して搦め捕りしといふは非也。今も野間の庄に平家の旗さし物楯板弓矢鎧等持伝へて一族也といふもの多し、又府中小松村忠房の苗裔ありと今も小松を名のる。 〈 『京都の伝説・丹後を歩く』 〈 3 伝承地 竹野郡弥栄町平家 平重盛の子忠房は、丹後守に任ぜられたので、平氏壇浦に敗れた後は、残党が丹後の奥に逃れる者が多かった。 木子・駒倉は、矢野弾左衛門の隠れ場所であったが、この地方は人跡稀なる所であったので、はじめはだれにも知られなかった。ある日、平氏の落人たちが市場に塩を買いに出たが、その身なりがただの人でないと怪しまれ、その後を付けられ、その栖み家を見つけられてしまった。ただちに追手の小軍が差し向けられたので、残党はさらに野間の荘の奥まで落ち延びたという。須川の奥にある鎧ヶ淵・降参ヶ谷は、その戦跡と伝える。鎧ヶ淵は残党の敗北の証として、武器・具足を投げ棄てた淵だという。降参ヶ谷は、俗にコーサガ谷と称し、残党が身の置き所を失い、源氏に降参した所という。 また平家の落人はついに山奥に籠居して、平家聚落の先祖となったが、その子孫は身体健康ならず、誠意を神仏に書願するに、神仏の占いで宝剣の祟りと知り、秘蔵の宝剣一振を氏神の祠に奉納し子孫の安全をはかったという。その宝剣は、なに者かに盗み取られたか、その後、平家聚落の真東にある高さ三十尺・幅十二、三尺の旗岩と称された巨岩の上に、節分の夜、燈明の火をみる翌朝旗を見ることがあったと伝える。(『野間郷土誌』) 4 伝承地 竹野郡弥栄町大谷 字大谷の細田神社は、中古は大将軍と称し、土地の人はダイシャウゴサンと伝えている。平重盛の子・丹後侍従小松忠房は、主馬判官盛久・越中治郎兵衛盛次・上総国部兵衛忠元と丹後与謝郡に留まり、平家の成り行きを見た後に自刃したという。この大将軍社は、原大将の社と称し、小松忠房を祀るものと伝える。 (『野間郷土誌』) 5 伝承地 竹野郡弥栄町小杉 小杉というところ(今の八丁)に平坦な土地がある。戦いに破れた侍が一人そこに落ち延びて来て、草庵を建て、毎晩泊って暮らしていたそうだ。 ある晩のこと、「親父どの、親父どの」と、小屋の周りをぐるぐる回りながら言う人間の声がした。そこで、これはきっと、狐か狸の仕業だなと思って、傍らの槍を取って声のする方を目印にしてズブーンと突いた。すると、大きな悲鳴が聞こえて、人の倒れる手ごたえもあった。「まあ、これで何者であろうと退治ができた。死骸を見るのは、朝にしよう」。そして、朝になって見ると、九曜星の紋を付けた、羽二重の着物を着た自分の長男が、そこに死んでいたという。 このことが動機となって、妻や子どもを呼び寄せ、ここではどうも都会に不便だから、もう少し住み心地のよいところがないだろうかと思って、下の方に降りた。そのころから小杉にはおうぎやけがあったが、その一の枝に登って、ずっと見渡し、このあたりなら、いちばん水利もいいし、ゆきずりも出ないだろうということで そこに初めて家ーー家といっても草庵であるがー三軒を建てた。次男とその次の末子との三軒が小杉の元祖らしい。その後、九軒まで増えたそうだが、このごろは離村で、みな散り散りになっている。 先祖さまの命日は長男の亡くなった八月一日で、この日は小杉全体の者が集い、ご先祖さまの供養を申し上げて、お祭りとした。 (『弥栄町昔話集」) 『丹後の民話』(萬年社・関西電力) 〈 野間の味土野に利エ門いう旦那さんがあって、藤兵衛いう人を人足につれて、宮津へ行きなった。 ある日、宮津の殿さんの所で用をすまして、犬の堂まできて、えらい旦那さんださけあ舟はあるだし、舟が待っとったで、「まあ侍っとってくれたか。さあ帰んでくれ」言うてしたら、どこの人だかわからん元気盛りの者が「この舟、どこい行く舟ですい」言うで、「岩滝の方へ帰る舟だ」「そんなええ都合ならわしも乗せてもらえんだろうか」言うて。「これあわしの舟ださけあわしら三人ほか乗れへんださけあ、乗るのが都合よかったら乗んなれな」言うたら、それに乗って、海の上を、帰りもってなあその若い者が「あんたらあ何処の人たちだ」「わしや野間の味土野の者だ」「へえ、野間の味土野の人ですかあ。野間の方は寒の内でも、夜着(ようき)だふとんだいうようなものは無い。寒かったら、とうがらしを体の上にのせてねんならん所だそうななあ」「うーんそうだ。ふとんだ夜着だいうもんはあるような所じゃにやあ。寒かったら、とうがらしを体に乗せてねる」「そんなことは、なんぼなんでも寒てれられまいなあ」「ねられてもねられんでも、それより無やださけあ仕様がにやあわなあ」言うと、「はなしにや聞いておったけど、やっぱりそうですか」「そうだ。そんなふとんだ夜着だいうもんは無や。野間ちゅうとこは」言うとった。 その旦那は仁体のどえらいええ人だったそうで宮津さんから名字帯刀を許されとって、ぶつさき羽織と腰差しと御免下駄とを、宮津へ行く時は、行李に入れといて、それを背負って行ったそうな。それから舟がだいぶ、岩滝の方に行った。旦那は、岩滝の千賀さん(大庄屋で回船問屋)に用事があったで、千賀の浜へ舟を近よせて、もう上るいうあたりで、「藤兵衛。荷物を出やてくれ」いうて、ぶっさき羽織や腰差しや御免下駄を出やて、大きな昔の鏡を、金の柄の着いた金の鏡をそれを、でーんと置いて、旦那が、鏡見て、髪をといておんなった。それを見て、「な-んとこの人はちょっとちがう人だなあ」おもって、加悦谷(野田川町・加悦町)の人だったそうなが、それを見とって、「これあまあ途中で、ひやかし半分でとうがらしの話や夜着のはなしをしたが、これあ悪いこっちゃった。悪いこと言うたけぞ、言うてしまったでしょうがにやあ」おもって、浜へ船頭が、舟を引き揚げたら、「さよなら」とも言わず「ごめん」とも言わず、舟から、ポーンと飛んで、わらじ下げて、はきもせんと、さあっと、走って岩滝の町の奥へにげてしもうた。ほしたら、旦那さんが、〝藤兵衛。へ知らんとこで言いうな、いうが、今日の若い衆は、だいぶ、足らん者じゃったなあ。わしが、「ふんふん」、 言うて、「そうだ、そうだ」」言うとれあ、調子に乗って、ほうけたような話しとった。何処の国い行ったって、寒いときに、とうがらしで夜を明かすもんがあるもんか。昔から、野間の夜着、だいうけど、とうがらしをなあ。食うと汗をかくだ。それでいうたもんだ。今日は勉強しただろう。知らんとこで、うかうか物をいうと、『よう乗せてくれた』とも、言えんと、飛んでにげた。あんなことは、人間のするようなことぢやにやあ。今日は勉強しただろうが〝言うて、まあ干賀さんの家い行きなった。そういう話、聞きました。 (味土野・江宮豊蔵様より) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『弥栄町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2013 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||