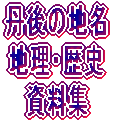 |
魚屋(うおや)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚屋の概要《魚屋の概要》 市街地の中央部で、本町通りの一本海側の東西400mばかり長細い商店街。北は新浜、南は本町に隣接する。東部に消防署がある。 魚屋町は、江戸期〜明治22年の町名。六幹町の一つで、幹町としての魚屋町分には小川町の44軒、東堀川通北部の追掛町を含んだ。 魚屋町は、城下魚屋町組の1町。慶長7年「宮津下村検地帳」に当地名が見える。魚屋町組の町年寄が設置されていた。元禄16年の町筋は、東西187間余、道幅は2間余であった。家数は寛文6年141軒、元禄16年143軒、宝暦年間80軒余、明治維新以前192軒、明治19年177軒、同21年159軒。 文化8年に宮津に初めて遊女屋が許可された。「宮津事跡記」は「田町八番組岡田屋弥吉、万町細間泉屋与市、魚屋町綿屋栄治右三人願主…皆々五人許りつつ召抱候処、追々繁昌いたし老若男女夜々格子よりのぞきに罷越候」と伝える。 一本浜側の新町通りあたりまで海であったが、少しずつ砂浜が突き出てきたので文化14年に須津村浅七を頭取にして、町中の男子全員が毎日出役、大手川川尻出州の砂を持ち運んで新地築出普請を始めた。この地を魚屋町新道(東新浜・新浜)と名付け、次第に町屋が移転したという。また元文5年に魚屋町小川町110人等の伊勢抜参りがあった。明治22年宮津町の大字となった。 魚屋は、明治22年〜現在の大字名。はじめ宮津町、昭和29年からは宮津市の大字。 《魚屋町の人口・世帯数》 238・94 《主な社寺など》 《交通》 《産業》 魚屋の主な歴史記録《丹後宮津志》(地図も)
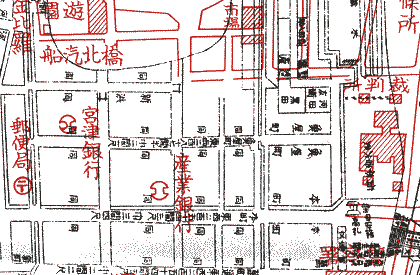 関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『宮津市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2009 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||