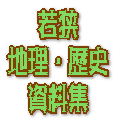 |
若宮(わかみや)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若宮の概要《若宮の概要》 西からなら旧国道(今は県道)へ入って立石の次の集落、民家は道縁に途切れなく続いていて、どこが境かはわからない。東西に細長い町で江戸期は岸名町といったそうである。このあたりは昔とあまりかわらない景観をとどめている。 神社と寺院が南北に5つ並んでいるが、この辺りが特徴か。北は海に接していて海水浴場になる。  若宮町は、明治14~22年の町名。高浜村を構成する5町の1つ。もとは高浜村の町方小名岸名町。明治22年高浜村の大字となる。 若宮は、明治22年~現在の大字名。はじめ高浜村、明治45年からは高浜町の大字。明治24年の幅員は東西3町余・南北1町。 《若宮の人口・世帯数》 305・146 《若宮の主な社寺など》  町名の由来となる「若宮八幡」だが、何も資料がない。長福寺の山門の脇、県道に一番近い位置に鎮座している。  『高浜町誌』 臨済宗相国寺派 慶雲山長福寺 一 所在地 高浜町若宮(岸名町) 一 開 創 永享年月日(一四二九~) 一 開 基 性天景繕和尚 一 本 尊 釈迦牟尼仏 一 檀家数 一五〇戸 一 由緒沿革 当寺は人皇五十六代清和天皇七代の後胤新羅三郎義光の後裔治部小輔武田信栄、将軍義教の命を受け大和の陣中において一色義貫を誅し、その功によって若狭の国守護職に任ぜられ、永享年間当寺を開創した。法名を「長福寺殿天遊光芸大居士」と号し、永享一二年七月二三日に逝去した。 なお開山性天景繕和尚は、大本山相国寺再住第四十七世である。創建の当初は当町海岸城山字藪之内に在って、相応の堂宇伽藍を完備し、その結構を誇っていたが、永享年間逸見昌経が今の城山に築城の際現在の地に移した。その後享保年間火災に遭い、諸堂宇尽く焼失して、古文書、什宝等悉く烏有に帰して現在みるべきものはないが、武田氏年譜の写本を蔵している。 なお(東寺古文書)八穴山長福寺文安六年云々によれば、後年八穴山久昌寺と分離長福寺を創立したともいわれる。 明治・大正年間の傑僧、釈宗演禅師は、当寺檀家一瀬五右衛門家の出である。 (大飯郡誌) (東寺古文書)八穴山長福寺文安六年云々(後八穴山久昌寺と分れ両寺となりしか) (元禄五年改帳)慶雲山長福寺 大檀那新羅三郎義光朝臣後裔脱長福寺殿前禮部侍郎天遊芸信栄大居士御建立来歴失念中興開山前住相国後住南禅性天和尚享徳三甲戌十月十二日遷化). 『大飯郡誌』 長福寺 臨済宗相國寺派 若宮字東若宮に在り 寺地四百〇五坪 境外所有地四畝壹歩 檀徒百七戸 建物本堂〔〕庫裡〔〕土蔵〔〕廊下〔〕門〔〕本尊釋迦如来 由緒〔明細帳〕永享年間創立開祖 性天景禪師 開基若狭守治部少輔武田信榮印長福寺殿天遊光芸大居士 〔東寺古文書〕 八穴山長福寺 文安六年云々(後八穴山久昌寺と分れ兩寺となりしか) 〔元禄五年改帳〕 慶雲山長福寺 大檀那新羅三耶義光朝臣後裔脱長福寺殿前禮部侍郎天遊藝信榮大居士御建立 來歴失念 中興開山前住相 國後住南禅性天和尚享徳三甲戌十月十二日遷化 寄八斗四升九合年貢地也。 舊城山附近に在りしを、逸見昌經築城の際、現地に移せりと傳ふ。同宗内の互刹にして、現に地方宗務院たり。  一番手前から寿福寺、養江寺、長養寺、長福寺。大きな山門の寺院だが、寺号がない。 『高浜町誌』 臨済宗相国寺派 青井山長養寺 一 所在地 高浜町若宮(岸名町) 一 開 創 天正年月日(一五七三~) 一 開 基 基俊源公首座(文禄年中示寂) 一 本 尊 聖観世音菩薩 一 檀家数 三〇戸 一 由緒沿革 創建当寺は茅葺きの堂宇であったが、第九世方室丈和尚寛政年間に瓦葺きに再建したが、昭和五一年大改修を施した。 当寺檀越〝しまや〟一瀬仲右衛門家より明治の傑僧越渓和尚が出ている。当寺は現在は無住で長福寺住職が兼務している。 [大飯郡誌] 本尊正観音 堂宇〔三間六間〕 由緒(明細帳) 文禄年中基俊和尚開基 (元禄五年改帳) 開基基俊源公首座文禄年中示寂 建立者諸檀那中 名寄 三斗八升年貢地也。 〔若州管内社寺由緒記〕 禅宗京相国寺末 長養庵 開基基俊源公首座天正年中開闢也 住持 周徳 『大飯郡誌』 長養庵 臨濟宗相國寺派 若宮字東若宮に在り 寺地七十一坪 境外所有地五畝四歩 檀徒三十戸 本尊正観音 堂宇〔〕 由緒〔明細帳〕文祿年中基俊和尚開基 (元禄五年心改帳) 開基基俊源公首座文祿年中示寂 建立者諸檀那中 名寄三斗八升年貢地也。  『高浜町誌』 臨済宗相国寺派 慈雲山養江寺 一 所在地 高浜町若宮(岸名町) 一 開 創 文禄年月日(一五九二~) 一 開 基 繁寂茂公和尚禅師 一 本 尊 聖観世音菩薩 一 檀家数 五〇戸 一 由緒沿革 平朝臣吉田左衛門尉光茂の裔、畑村吉田新右衛門が文禄年間に、繁寂茂公和尚を請じて開山と仰ぎ建立したものと伝える。 その後火の災厄を蒙り、天保一〇年九月恵寛和尚が現在の堂宇を再建した。 当寺内には当町出身臨済宗第三十五世南禅寺第一座鼈山和尚(当町塩土出身)の墓があり、同禅師は当寺において出家得度した。〔大飯郡誌〕 本尊正観世音 堂宇〔三間半七間半〕 由緒(明細帳)天正十年繁寂和尚創立 [同前]開基繁叔茂公文禄年中示寂 建立者諸檀那中 名寄七斗二升九合年貢地也 〔若州管内社寺由緒記〕 禅宗京相国寺末養江庵 天正年中開闢也 開基繁叔茂公首座 住持 梵長 『大飯郡誌』 養江庵 臨済宗相國寺派 若宮字東若宮に在り 寺地六十六坪 境外所有地一反四畝五歩 檀徒三十九人 本尊正観世音 堂宇〔〕 由緒〔明細書〕天正十年繁寂和尚創立 〔同前〕 開基繁叔茂公文祿年中示寂 建立者諸檀那中 名寄七斗二升九合年貢地也  『高浜町誌』 臨済宗相国寺派 無量山寿福寺 一 所在地 高浜町若宮(岸名町) 一 開 創 天正年月日(一五七三~) 一 開 基 章国王公座元 一 本 尊 地蔵菩薩 一 檀家数 二三戸 一 由緒沿革 久しく無住で、元興寺代々の住職が本寺を兼務する例となっている。 〔大飯郡誌〕 由緒(明細帳)天正年間章岩創立 (同前)開基章嵌玉公座元天正年中示寂 建立諸檀那中 名寄一石三斗六升二合年貢地也。 〔若州管内社寺由緒記〕 右同断寿福庵 建立天正年中 開基章国玉公座元 住持 宗春 『大飯郡誌』 壽福庵 同 同所に在り 寺地百拾坪 境外所有地二反七畝十六歩 檀徒二十四戸 本尊地蔵薩 堂宇〔〕 由緒〔明細帳〕天正年間章岩創立 〔同前〕開基章厳玉公座元天正年中示寂 建立諸檀那中 名寄一石三斗六升二合年貢地也。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 若宮の主な歴史記録若宮の伝説『大飯郡誌』 海底の神木 千年の昔・若宮の海浜 或云一軒堂の庵底 に一老榎あり、其陰翳朝には青葉山 中山寺 を覆ひ夕には遠く和田山を掩ひしに、一朝震災に遭ひ海中に仆ると、今尚天朗に波静なる時其躯幹を認むるを得、明治二十三年頃時の郡長之を曳揚げむとして果さず、大正四年御大典に区の青年等一片枝を採り、其倶楽部に紀念として保存せり。 『森の神々と民俗』 福井県の巨樹伝承としては杉原丈夫編『越前若狭の伝説』のなかに、高浜町若宮の「神代木」の伝説がある。 「むかし若宮の海岸に一本の巨大なえのき(榎)があった。その木の影は、朝は太陽光を受けて、青葉山のふもとの中山の里にその影を映し、夕暮れには犬見山をその木の影がおおった。ある時地震にあい、海中へ倒れてしまった。今なお天気のよい波静かな日には、海中に木の幹をみることができる。 明治二十三年に郡長が、この木を海中から引きあげようとして、村中の者が綱で引いたが、どうしても引きあげることができなかった」。 『若狭高浜むかしばなし』 榎の大木 塩土の沖の海中に、これまでに見たこともないような榎の大木が横だわっていると伝えられている。 この榎の大木は今から千年ほど前までは、岸名町の海辺にうっそうと茂っていた。この榎がどれほど大きかったかというと、朝日が地平線に上ると、木の影が青葉山のふもとの里に伸び、また夕日が落ちるときは犬見山にその影がかぶさったといわれるくらい、大きな大きな木であった。 ある年のこと、大地震が起こった。そのとき、榎の大木は天地を揺るがせて、どうっとばかりに海中の方へと倒れてしまった。やがて、その大きな姿は海底に沈んで見えなくなった。しかし、海流の加減で天気のよい波静かな日には、海中に横たわっている榎の大木の幹を見ることができるという。 明治二十二年、大飯郡の郡長をしていた遠藤正敏さんは、日頃からこの大木にたいへん興味をもっていたのだが、ついに決心した。 「そのように大きな木を見てみたいものだ。ぜひとも、榎を海底から引上げて見ようでないか。」 「それは、おもしろそうだ」 村の皆も興味津々だった。そこで、海底の榎の大木を引上げることになった。村中のものが懸命に綱で引いてみたが、大木は海の中から上かってこようとしなかったそうだ。 また、昔から伝わる榎の大木を一目見たいものだという思いにかられた若宮の青年団員は、大正四年ついに海底にもぐった。そこで海底に横たわる大木を見つけ、その一片を取ってきたそうである。それは、今も保存されているという。 若宮の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『大飯郡誌』 『高浜町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2020 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||