 京都府福知山市鋳物師 京都府福知山市鋳物師
 京都府天田郡福知山町鋳物師 京都府天田郡福知山町鋳物師
|
鋳物師の概要
《鋳物師の概要》
駅前の「けやき通り」を行って突き当たりに「厄除神社」がある、そのあたりから右側にある町家街である。市街地の北端になる。福知山城下15か町の1町に数えられた地で、地名どおりに鍋・釜・梵鐘などが製造され、近年まで鍋小・釜八・釜藤などの屋号が残っていたという。
鋳物師町は、江戸期~明治22年の町。明治初年~22年は福知山を冠称。江戸期は福知山城下15か町の1つ。城下を囲む総堀より外側、丹後口門外にあった。西側は曽我井橋によって和久市村につづいた。福知山町づくしに「たゝら踏み出す鋳物師町」と歌われ、鍋・釜・農工具・楚鐘・武器まで製造した。当町が総構外に設置されたのは防火上の配慮か。土地は低湿で洪水の時は最も早く浸水したという。
明治4年福知山県、豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年福知山町の大字となる。
鋳物師は、明治22年~現在の大字。はじめ福知山町、昭和12年からは福知山市の大字。昭和43年一部が昭和町となった。
《鋳物師の人口・世帯数》 235・117
《主な社寺など》
 高良厄除厄神社 高良厄除厄神社

鋳物師町の北端に鎮座。案内板がある。
高良厄除神社
鋳物師町は旧山陰街道筋にあり城下町北口の要路にあたるも底地のため雨風ひとたび狂えば由良川は氾濫し人家人命を吞みこまれた事がしばしばあった。水害の恐怖は安心立命の信仰を求め生活守護の大神高良玉垂命を勧請し文久二年堤防上大寛院の傍に創建し明治三十一年現在の地に還座奉祀した。
慶長五年福知山藩主となった有馬玄蕃頭豊氏侯は有馬検地を行い上下柳町京町寺町鋳物師町を新設した、後に久留米に移封したが、代々の藩主は九州北部五ケ国の総鎮守神である高良大社を尊崇し御社殿大鳥居等を寄進した。御祭神は高良玉垂命で御鎮座の年代は太古に属し皇室の尊崇篤く国幣大社です。筑後久留米藩主として明治維新に及ぶ歴代の有馬侯の縁故により当地に御分霊されたのです。
高良厄除神社は開運厄除無病息災延命長寿の神様として信仰極めて篤いお宮で二月と七月の十八日十九日に大祭が行われ厄年に当る方々が御祈願されると霊験灼であるといわれています。
…高良厄除神社奉讃会
 道標 道標
こんな物もある。当社の前を通る道がかつての国道9号線で、この道を右の方へ行けば、一方通行でそうしか行けないが「丹後口番所」があった。丹後から来ればここから城下町であった。


この道標は文化五年(一八〇八年)丹後口門の近辺に建てられた行先を示す道しるべである。
丹後国門(番所)とは現在の鋳物師町と寺町の境い辺りである。
道標の多くは巡礼や寺社参拝の旅人の道案内で、この道標は丹後の成相寺道を知らせると共に、京・大阪、丹後・但馬への道しるべである。
永年、鋳物師町の藤田吉兵衛宅に保存されていたが、平成一九年二月に、此所厄除神社に移された。
当地方には多くの道標があるが、福知山市では代表的な道標と言われている。
藤田吉兵衛氏は、第三代福知山藩主稲葉淡路守紀通の家臣、藤田庄兵衛の子孫で、この道標は藤田家の厚意により移設を行った。 平成十九年 二月吉日
 曽我井橋 曽我井橋
そが井橋について
福知山市の汚水を集めて流れる西川には、鋳物師町と和久市の境に曽我井橋がかゝっていました。
寛政六年(西暦一七九四)発行の「丹波志」という書物には、境界は丹後往来の土橋イモシ川の端、境 庵我郷 和久市に境 少の土居と境有りと書かれています。鋳物師町は明智光秀の福知山城改修以来城下町として栄え、その境は曽我井橋とされていました。
和久市はもと曽我井村といって、南岡、木村、堀、笹尾と共に大正七年四月に福知山市に合併されました。昭和三十八年に和久市ポンプ場が完成し同四十年の都市計画街路 鋳物師線築造工事のため、西川は地下に埋設されました。
度重なる出水にはこの川が逆流して、この地区の住民は幾度か水害になやまされて来ました。
このそが井橋の端銘柱は当時を知る数少ない貴重な文化財です。鋳物師区
《交通》
《産業》
《姓氏》
鋳物師の主な歴史記録
『天田郡志資料』
町村記
第四編 町
(緒言)今主として明治廿二年市町村制実施後の事を記するに先だち丹波志に見ええる郷村記を大体原書のまゝに本編に載せて、その変遷を知る一助とした。此丹波志は安永年間、我が福知山藩士古川茂正、篠山藩士永戸貞両氏の編纂に係り、神社、郷村、古城、姓氏、旧栖、産物、勝地、孝子、寺院、古墟、陵墓、雑記等に分類し、我が郷土唯一の資料にして総計二十一巻を二十五冊に訂正繕写せりといふ。蓋し丹波志といふと雖天田、氷止、多紀の三郡だけである。始め古川氏は氷上、天田、何鹿を永戸氏は多紀、桑田、船井を分担されたが、古川氏は氷上、天田の二郡、永戸氏は多紀一郡を起稿したばかりで不幸両氏とも歿した。依て古川氏の分十六巻、永戸氏の分五巻を、古川氏の息正路氏が寛政六年甲寅に校訂筆写された由、序文に見えて居る。予往年郷土を研究せる際、幸にしてこの内の数冊を得て直に採録した。(此数冊も火災のため焼失)即ち本編に載する所である。これは?に郷土の変遷を知るのみならず、又故人の功労を後世に伝へんとのゝゝであ。以下現今の町村名より前に記載せる所が即ちこれである。なるべく原文を存したれども多小私筆を加へたる所もある。
…
福知山町地諸役免許(明智時代)高七百三十四石九升。此地もと木村と南岡村との地なり。明智、城を改修せし後、福知山となる云々。 (附記)元亀、天正の間、此地屡戦乱の為、人民居たまらず、漸く離散する者多かりしが、福知山城改修の頃より、人民漸く帰来すら者多く、依て帰村(キムラ)と名づけしと故老はいへり。
城下町数十五町也 家数凡千軒 京町、呉服町、東西長町、上下新町、上下柳町、寺町、上下紺屋町、鍛冶町、菱屋町、鋳物師町、西町、
宗部の周囲は、東は土師郷土師村に堺し土師川の東屠者ある所より北へ見通す。愛宕道を越えて、少の畑地ある所は、土師村、猪崎村、堀村の境也、愛宕道(この道は蛇ヶ端の清水から薮の中を過ぎ土師川(出合の少し上)を渡り前田の愛宕山の南麓に出で愛宕神社に参詣する道なり、昔はこの道を前田の村なかを通って東林寺の南の綾部街道に合したものであるが今はなし)を西へ、蛇ケ端往来の下り口(即ち今いふ清水)にて猪崎村に堺す。蛇ヶ端三軒茶屋(今の目金橋の東つきあたりに三軒並んで茶店かあった、今は桑畑になって居る。藩時代には水防上此三軒より家屋を建てることは許されなかった。今のやうに敷軒出来たのは皆明治維新以後である。昔の三軒茶屋は町内に移住して居られる。呉服町の桑原活版所、内記三丁目桑原旅舘等が旧三軒茶屋とおもふ、そしてこの三軒で船を取締って居ったものとおもふ故に家号は三軒とも船屋といつたと記憶する)の後、薮を以て猪崎村に堺し、下は川堺なり、尚下にては丹後口(寺町金比羅神社の裏ノ辺)の土居外に境の木あり、北は鋳物師町端の往来なる土橋(今石橋)境。又庵我郷、和久市村の境に小き土居ありて境となれり。夫より南西の方大溝界。和久郷厚村に堺し、北溝曲り笹尾に界す。南は大橋(此橋今はなし、福知山駅の南西、機関車庫の南に溝あり、此の溝に架けたりし土橋である、明治廿年頃はあったと思ふが、笹尾より今の内記町筋へ出づる里道にあったのである。これを大橋と言ひしは、由良川はその昔今の駅の南方に通じて、そこから和久市の方へ北流して居った時代は駅裏あたりに可なり大きな橋があって、何筋が只今のやうに福知山の東方々流れるやうになっても、当時の名が伝って、かく大橋といったのである。予の知つて居る大橋は長さ二間位の土橋であった。かやうに昔の川筋が残って今なほ駅裏一帯水田である)の西に中道あり(此の中道とは先年来、土壌運びのためレールを敷設せる道を指したのである)南の谷へ見通し、羽合に会す。夫より室村の谷川と氷上郡一ノ貝村立合境となる荒木山は東南の方、一ノ貝分、西は室分、北は堀分也。一ノ貝峠の左右、山並尾筋を境とす。同郡西海瀬、才田の山限り長尾といふ所へ見通し、才田村に境す。又岩間村三軒茶屋、(塩津峠の口、往来に沿うてありし茶店、今は数戸あり)の下に堺あり。大川の向は堀村高畠なり、此所に境田といふ所あり、これ長田村との界也。夫より長田村山林にて高畠と境せる所あり。是より峯境、高畠の一本松にて長田村と境す。此一本松より川の北、堰下田地を見通し土師村と界す。
福知山
町裏惣構の土居は、即ち大川の堤也。此所へ丹後由良より通船あり、塩を積みて上る。福知山より上は通ずべからず。古例也その古は此川筋に通船なかりしが、中頃丹後加佐郡有路村に船持出来、福知山より積み下る荷物の継立をなすに至れり(有路は田辺領)又福知山のみは何鹿郡大島村堰の下まで通ずるを得べし。柏原領戸田村に農作のため船あり。然るに元文年印穀物を積み下りしかば、古例になきことゝて、福知山船持これを差止めたり。依て戸田村より京都へ訴へし所古例の趣相立ち、戸田村は荷船相成らざる旨公裁ありき。此の時船持十七人なりき。爾後、此者等船株なり。古は此所に船を使用し初めし者を小兵衛と云ふ。代々此者親方となりて、船株売買する時は、此親方に届くる古例なり。近来丹後国河守村、蓼原村に船を用ふれども古より船継の所にあらず。
さて下る船には茶、草綿、漆の実、古着、米穀、油実類、製紙原料、上り船には酒、油粕、干鰯、材木、薪、塩等なり。往古より津留の所にて、他の穀物を入るゝに制あり。
当所よりの道程
…
大川筋漁師御運上、 ○銀十三匁 大漁、年中鯉、鮭などの大網を用ふるもの、 ○銀六匁 中漁年中小魚を捕ふるもの
○銀三匁 小漁、鮎のみを捕ふるもの。
鍔物師は元来河内国狭山ノ庄へイキ村より始まる、それより全国四十八ヶ所に分れたり。 |
伝説
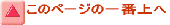
鋳物師の小字一覧
関連情報


|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|





