 京都府福知山市坂室 京都府福知山市坂室
 京都府天田郡上六人部村坂室 京都府天田郡上六人部村坂室
|
坂室の概要
《坂室の概要》
三俣の対岸になる、公民館などはここにあるが、本村はそこから山道を1㎞ばかり入った所にあるという。

ここはいわば「坂室口」。坂室川に沿って、この路を入るようであるが、狭いのでやめた。そこの案内板は「天突登山口・医王寺跡参道」となっている。本村を越えてさらに行けば中六人部の大内に出る。
坂室村は、江戸期~明治22年の村。はじめ福知山藩領、寛永10年綾部藩領、寛政12年からは幕府領京都代官小堀氏支配、さらに維新期篠山藩領。
明治4年篠山県、豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年上六人部村の大字となる。
坂室は、明治22年~現在の大字。はじめ上六人部村、昭和30年からは福知山市の大字。
《坂室の人口・世帯数》 18・8
《主な社寺など》
 真言宗坂室山医王寺跡 真言宗坂室山医王寺跡
中世代、坂室から大内村後正寺にかけての山の両斜面に真言宗の坂室山医王寺があり、坂室村分に3、後正寺分に5の塔頭があったと伝える。
仁王門は現存し2メートル余の仁王像も遺存する。像は室町時代の作という。仁王門を入ったところに供養塔・板碑が並ぶ。
古跡
今薬師堂 二間四方東向 立像一尺余 山門古跡有 仁王門ハ于今在之 仁王ハ運慶ノ作ナリト云 真言宗五山ノ内ト云 境内凡三十間四方 古ハ無本寺ナリト
坂室山医王寺加門院古跡
古へ塔頭三ケ寺有之 慶長中退転ス、委細ハ伊勢浅間山ニ有之 仁王門残テ于今有之、仁王像有之
古大内村ノ谷ト両谷ニ八ケ寺有ト云 尾崎坊ハ医師ト成
今境内ニ薬師堂アリ諸国ニ弥敷作仏ナリト云
(『丹波志』) |
《交通》
《産業》
《姓氏》
坂室の主な歴史記録
『丹波志』
坂室村 綾部領
高三拾石七斗六升 民家七戸
此地ハ山隅ニテ谷ニ入所小山アリテ包メリ他ヨリ不見所ナリ奥エ十町斗 |
伝説
『福知山の民話と昔ばなし』
天突(あまんづく)の雨ごい
毎日毎日ひどい日照りが続いて、谷川や池の水も枯れてしまいました。大切なお米や豆も干ばつで穫れなくなるのではないかと、村の人達は不安になり、氏神さまへ日参して「どうぞ七日間のうちに、きっと雨を降らせて下さい。お頗いします。」と願をかけました。
これを開いた金牛和尚は、常願の日に、村で一番高い山の天突で雨乞いをすることに決め、村人たちに、どこの家からも、まきを持って山上に集まるようにさせました。
その日になって、山の上には、みんながそれぞれ背負って来た割木が積み重ねられて、まきの小山が出来ました。そこで金牛和尚は、年よりや子どもは早く山から下りるように言いつけて、このまきの山に向って、一心に祈願をして氏神さまから、ともし火をつけて来た火なわをまきのたき口につけました。火はだんだん大きくなって、パチパチ音をたてて燃え、やがて天をもこがす勢になりました。
この火は、六人部の外、福知山の町なかや、竹田辺からも良く見えたといいます。和尚は火の燃え盛りを見て、ふところから書き物を出して、それを火にくべると、大きな書きつけは燃えながら天空高く舞い上りました。
ふと大空を見上げますと、黒雲が一面に広がって来て、あたりはうす暗くなって来ました。そのうちに大粒の雨が降り出して来たのです。
「雨が降りだした。雨が降り出した。」と村人たちは大よろこびです。
「和尚さんの雨乞いがすんだ。早く下山して下さい。」
というよりも早く、村人は山を下りかけましたが、雨はますます大雨になって、皆ぬれねずみのようになってしまいました。
村人たちは、雨乞いのおかげと喜び会い、その翌日は、村中雨喜びといって、一日中休みとなりました。その日は百姓仕事は一切せず、揃って氏神さんへお礼参りをしましたが、金牛和尚の神通力に恐れ入ったそうです。(文責 荒樋 重雄) |
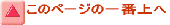
坂室の小字一覧
坂室(サカムロ)
井出 稲葉下 イヲウジ 大谷口 谷 宝堂谷 ヅヱノ下 寺坂 峠 西谷 林谷 ヒト谷 ビクニ川 水上 ムセノ前 薬師ノ下 谷口 峠 西谷 火シロ 火ナタ
関連情報


|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|

