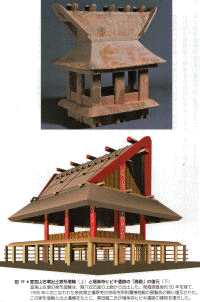京都府福知山市前田・土・石原・川北・戸田 京都府福知山市前田・土・石原・川北・戸田
 京都府天田郡福知山町田・土・石原・川北・戸田 京都府天田郡福知山町田・土・石原・川北・戸田
 京都府天田郡雀部村と西中筋村一部 京都府天田郡雀部村と西中筋村一部
|
雀部郷の概要
《雀部郷の概要》
 前田に雀部小学校↓がある、この校名は明治22年の雀部村の村名を冠したものだが、元々は丹波国天田郡十郷の1つ「雀部郷」によるものである(域とする範囲はことなる)。雀部は散々倍あるいは佐々伊倍と読まれたようである。 前田に雀部小学校↓がある、この校名は明治22年の雀部村の村名を冠したものだが、元々は丹波国天田郡十郷の1つ「雀部郷」によるものである(域とする範囲はことなる)。雀部は散々倍あるいは佐々伊倍と読まれたようである。

雀部は仁徳(大鷦鷯尊)のサザキを冠した御名代部とされる。『書紀』継体即位前記条によれば、丹波国桑田郡にいた仲哀五世孫の倭彦王を天皇にしようと迎えにきたのが物部麁鹿火大連と巨勢男人大臣であったという。その後の異議申し立てでは、「巨勢と雀部はもともと祖先が同じで、氏姓が分れた後で大臣に任じられました。その結果、雀部氏がかつて大臣に任じられたのに、今では、巨勢氏がかつて大臣に任じられたことにされている」と述べ、認められている(『続日本紀』)。巨勢男人大臣とは実は雀部男人大臣であった。
6世紀最初頃の継体即位前の王朝混乱期当時の大臣で、実力NO.1氏族であったよう、継体が即位できたのも今の天皇家があるのもあるいは彼のおかげなのかも知れないが、時の権威に都合悪い歴史は消されるので、この氏族も詳しくはわからない。彼は継体長子の安閑に二人の娘を嫁がせている。
神武記には子・神八井耳命は雀部臣、雀部造の祖。
また孝元記には、建内宿禰の子・許勢小柄宿禰は許勢臣、雀部臣、軽部臣の祖。とある。
「天孫本紀」では、天照国照彦火明櫛玉饒速日尊の八世孫が倭得玉彦命で、
九世孫が弟彦命。妹は日女命。
次に玉勝山代根古命(山代の水主の雀部連・軽部連・蘇宜部首等の祖。とある。
葛城氏系の巨勢氏系で西隣の宗部郷の蘇我氏などとは近い氏族と思われる。大和国高市郡巨勢郷(奈良県御所市古瀬)が巨勢氏の本貫のようで、御所市のゴセという市名もまた巨勢にちなむとか。
葛城氏といってもシラン人が多かろうが、天皇さんはシラン人はなかろう、その天皇さんと並んだ古代、5世紀頃までの大豪族、紀氏とも古くは同族、葛城氏・紀氏の大一族の一氏族が雀部氏である。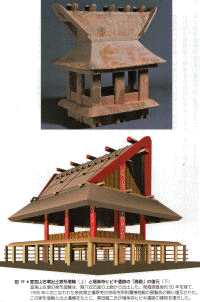
仁徳皇后(大后)の葛城襲津彦の娘・磐之媛が「葛城高宮、我家のあたり」と詠んでいるのでもわかる、葛城高宮は現在の御所市西佐味あたりになり、ここが襲津彦の根拠地だとわかるが、磐之媛は仁徳も蹴飛ばす、天皇とも対等の態度だが、それは実家の実力あってのことだろうか。
←高宮あたりの古墳出土の家型埴輪とそれのCG復原図(『葛城野王都』より)
これは神殿なのか王の住家だったのかはわからないが、磐之媛の「我家」もこうした様子だったかもわからない。
応神から武烈までの「河内王朝」「ワケ王朝」期の天皇の后はたいていが葛城氏で、なじみの市辺押磐皇子や弘計(顕宗)・億計(仁賢)・飯豊青皇女も葛城氏が母である。:
雀部氏の本貫ははっきりしたものがないが、だいたいこのあたりであろう。遺跡から見てもこのあたりの一帯が葛城氏の本拠地と見られ、雀部も葛城氏の本体部分の氏族かも知れない。
なお、六人部については尾張氏と同族。また和泉国諸蕃に「六人部連。百済公同祖。酒王之後也」、百済国酒王は河内国錦部郡あたりにいたようで、どちらにしても古くは大きくは葛城の一族ということになるかも知れない。律令時代の後の世では宗部とか笹部とか六人部などになっているが、それ以前は彼らの母体の葛城氏が押さえていた地であったと思われる。葛城氏は雄略時代に滅び、その後裔氏族、雀部氏などに引き継がれたのであろうか。
大和国葛上郡日置郷や朝妻や鴨も尾張(高尾張)も当地にあるので、こうしたなじみの氏族も当地あたりが本貫かも知れない。「高尾張邑に、土蜘蛛有り。其の人為り、身短くして手足長し。侏儒と相類たり。皇軍、葛の網を結きて、掩襲ひ殺しつ。因りて改めて其の邑を号けて葛城と曰ふ」と紀にある高尾張も当市内にある。本当かどうか知らぬが葛城の元の名が高尾張だという、「天孫本紀」には天照国照彦火明櫛玉饒速日尊の四世孫の瀛津世襲命は亦は云ふ葛木彦命、尾張連等の祖、とあり、どうも尾張氏は葛城とは関係が深そうに見える。用明紀に、葛城直磐村の娘の広子は一男一女を生んだ。男は麻呂子皇子という、当麻公の祖。とあり、鬼退治伝説の麻呂子親王もまたそうである。丹後の竹野神社の祭神の一人の建豊波豆羅和気命もまた葛城之垂水宿祢の娘と開化の子である。
コセは天津の是社神社のコソであろうと思われ、新羅の始祖王は赫居世(かくこせ)という、カクコセハンと正式には読むのかも知れないが、そのコセだから巨勢氏は渡来氏と思われる、その同族雀部氏もまた本来は渡来氏かと思われる。
紀には、彼ら氏族の祖・英雄葛城襲津彦が朝鮮で活躍し四邑(桑原・佐糜・高宮・忍海)の漢人の始祖らを連れ帰ったの伝が載せられているが、何のこともない彼ら自身もより古い渡来人であったからそうしたことができたものと思われる
各地に雀部が置かれたが、その一つに沙沙貴神社(近江八幡市安土町)があり、のちの佐々木源氏(近江源氏)の拠点となった、京極氏や朽木氏などなじみの江戸期の藩主家もこの一族になる。
天田郡雀部郷の郷域は土師郷の東側で何鹿郡堺まで、どこを流れていたか不明だが由良川を挟んで対岸もそうであったと思われる。だいたい土から石原、対岸の川北くらいまでであろう。
武内宿禰とかを祀る鎮守社としてあってもよさそうなものだが、当地には見当たらない。前田の明天社が安康の時代の創立と伝わる、安康とは何ともなじみのない天皇だが、安康は雄略の兄で一代前の天皇であり、葛城氏ありし頃になり、あるいはこの社がそうであるのかも知れないが、前田はフツーは土師郷とされる。それと気になるのは浦島社であるが、どなたかぜひにチャレンジを!
尚、三岳山西麓、古刹威光寺の向かいに佐々木神社があるし、上・中・下佐々木の集落がある。中世の佐々岐庄であるが、佐々木氏・雀部氏と関係があるのかは不明である、登り口の下小田に葛木神社があるのであるいは関係があるのかもわからない、丹後別路もあるいはここを通るのかもわからない。
舞鶴の笹部、朝来谷の一番奥の天空の村で今はゴルフ場があり、廃村になったが、名からはこうした氏族と関係ありそうだがも何も伝わらない。海路をねらったものなら東の若狭国大飯郡青郷日置に式内社青海神社があり、飯豊青皇女を祭神とするとも言う、何か葛城と関係がありそうな位置にありそうにも思えてくる。
葛城氏といえば、瀬戸内海航路で朝鮮と繋がることばかりが言われるが、意外にも日本海側にも拠点があったと思われる。但馬は天日槍でつながるし、丹後丹波もしっかり手配済み、大事な所を押さえているわい、なるほどの感心の大豪族の感がある。
 中世は雀部荘で、平安後期~戦国期の荘園。当荘は松尾大社領で松尾社の神菜を支えるため天田河(由良川)での魚釣の停止が命じられている。今も音無川と呼び、音無瀬橋があるのはこの慣例のためである。 中世は雀部荘で、平安後期~戦国期の荘園。当荘は松尾大社領で松尾社の神菜を支えるため天田河(由良川)での魚釣の停止が命じられている。今も音無川と呼び、音無瀬橋があるのはこの慣例のためである。
松尾社領というが、もとは丹波兼定の先祖相伝の私領で、ずいぶんと広い所だが、以前から在地では丹波氏の支配を受けているようである。
寛治5年(1091)11月15日付の丹波国天田郡前貫首丹波兼定寄進状(松尾大社東家文書)に、
丹波国天田郡前貫首丹波兼定謹辞
奉寄 松尾御社御領私領田畠等事
合壱処者
在丹波国天田郡管[
四至(割注・東限高津郷 南限□□□庄 西限土師郷并奄我 北限大山峯)
副進田畠坪付壱通
右、件田畠、兼定先祖相伝私領也、而寛治三年二
月五日受病悩沈寝席、前後不覚之刻、可寄進松尾
御社御領之由、令申祈□之処、以同八日夜、依有
夢想之告、任祈請之□、忽得平癒、随件私領永寄
進既畢、但於本公験者、以去応徳二年二月廿一日
夜、不慮之外、従国衙依被追捕失了、而向後件公
験等雖取出他人、敢不可有後日之沙汰、仍所寄進
如右、謹解、
寛治五年十一月十五日 前貫首丹波(花押)
(裏書)「兼定」
丹波氏は丹後国丹波郡丹波郷を本貫としたと考えらている、丹後王朝は葛城氏に対抗した三輪王朝系(のちの天皇氏系)氏族と同盟関係(開化妃の竹野媛・垂仁妃の日葉酢媛。天理市に丹波市という所があるが、こちら側に関係が深い)だが、但馬は葛城と結んで神功皇后を生んでいるし、葛城系の弘計・億計が丹後に逃れているからまったく葛城と関係がなかったわけでもない。
「続日本紀」延暦4年(785)正月17日条に天田郡大領丹波直広麻呂の名がみえ、天田郡でも支配的勢力となっていたと思われる。
南北朝以降は、秦(東)相憲-相衡-相季-相勝-相継-相言-相行-相郷と松尾社家東氏が代々伝領。
康安元年7月10日に荻野三河入道父子3人・杉本八郎父子5人などが荘内に乱入、当荘代官中務丞父子4人・上方公文父子4人・池辺四郎兵衛尉父子4人・林入道子3人・石原村孫三郎下人2人など41人が討たれるという事件が起こっている。
荘内の地名として「石原村」「富(戸カ)田村」「前田」「提村」「野中村」などが「松尾大社文書」「東家文書」に見える。
 近代は雀部村で、明治22年~昭和11年の自治体。土師・前田・川北の3か村が合併して成立し、旧村名を継承した3大字を編成。昭和11年福知山町の一部となり、村制時の3大字は福知山町の大字に継承された。 近代は雀部村で、明治22年~昭和11年の自治体。土師・前田・川北の3か村が合併して成立し、旧村名を継承した3大字を編成。昭和11年福知山町の一部となり、村制時の3大字は福知山町の大字に継承された。
《交通》
《産業》
《姓氏》
『丹波志』
雀部鍛冶 子孫 前田村 桜野ニ
雀部道明ト云鍛冶屋敷跡 今字ニ雀部屋教ト云 本ハ野道具ノ鍛冶也 天正年中明智光秀鎗矢ノ根ノ鍛タリ 細工ハ荒ケレトモ物ヲ能通ス故 雀部道明ト云四字ヲ付玉へリ 子孫ハ福智山下紺屋町鍛冶半兵衛ト云 前田村ニ雀部田地ト云所少有之トモ 今ハナシト云へり |
ここに言う「桜野」は、現在の前田の小字桜(さくら)だそうで、古来原野であったという。現在では誰も知る者もないが、「毛吹草」丹波の章に「雀部矢根、鑓」とあって、世に知られていたことがわかるという。福知山市字鍛冶に、先代まで屋号を鉄屋といい、もと下紺屋町に住み、刀鍛冶をしていたという家があるそう。また御霊神社の宝物に「丹波住雀部道明」の銘のある大きな鏃があるそう。
雀部郷の主な歴史記録
『福知山市史』
雀部郷
雀部郷は佐々伊倍とよみ、上野・三河にもある。「ささいべ」及び「ささべ」というのは佐々岐倍の転訛といわれる。近世雀部荘といいまた福知山市に合併するまで雀部村と称していた区域は、和名抄の雀部郷である。山口氏の天田郡志資料上巻々頭の中世十郷図は、和名抄の郷名を地図化したものと思われ、それには土師の北に雀部郷が広く占めている。
元来雀部というのは仁徳天皇の御名代である。御名代とは古代に天皇皇族その他貴人の名を後世に伝えるために、その名を冠した部民をおいたものである。そうして当時姓と称して家筋及び世襲の職名を分けた名称があり、臣・連・首・国造・県主があったのであるが、その類として雀部臣があり、雀部郷はその部民が住んだところかも知れない。ただし日本書紀や姓氏録を見るとこの姓に二流ある。姓氏録には「星川建彦宿祢、諡応神御世、代二皇太子大鷦鷯尊一繋二
木棉襷一掌二監御膳一因賜 名曰二大雀臣一」とある。星川建彦は武内宿祢の孫であって、応神帝の代に、皇太子大鷦鷯尊(後の仁徳天皇)に代って、天皇の御食事をつかさどったのでその名を賜ったというのである。また古事記には神八井耳命者、雀部臣等祖。また建内宿祢之子、許勢小柄宿祢者雀部臣之祖とある。そうして姓氏録左京の雀部の外に和泉・摂津にもこの姓がある。(吉田氏、地名辞書参照)
一方天孫本紀に「玉勝山代根古命雀部連は蘇宣部首等ノ祖なり、蘇宣部は即ち宗部なり、六人部氏と同系 であって、その族ここにいる。因って名づく」(日本地理志料)とあるところを見れば、玉勝山代根古命の子孫である宗部(蘇我部・曽我部)、六人部がこの地方に住み、先祖の名をとって地名としたことも考えられ、この点からすれば和名抄編さん当時、雀部郷が宗部郷の間におかれたわけがうなずかれるであろう。邨岡氏はまた、前記三宝院文書の外に、応仁別記にも丹波の国佐々岐荘が出ていると述べているが、佐々岐荘は雀部荘とは全然関係はなく、別の土地である。さらに源平盛衰記に「源頼朝丹波国新荘・本荘・雀部・宇津・縄野の諸荘をもって僧文覚に与う」という中の雀部もこの地であるとしているが、同書所載の荘名列挙の順序から考えると、これはむしろ桑田郡の雀部庄ではなかろうか、なおまた正中二年の文書には佐々木ノ保と作る。図を技ずるに、今上中下佐々木有り、一宮・常願寺・喜多・畑・宮垣・多和ノ諸邑に亘り金山郷と称す蓋其域也」と述べているのは大体妥当する。前記源頼朝が文覚に与えたものの中の雀部庄について、古川氏の丹波志には、
雀部郷六ヶ村 今雀部庄ト云 土村、川北村、戸田村、石原村、興村、観音寺村
興村観音寺村ハ何鹿郡高津村ノ地ニテ右下高津ト云所ナリ何ノ比天田郡i入タ哉謂不知興村ハ観音寺村ノ支ト云
また土師郷の条では
今雀部村ト称ス、大字土師存ス(中略)土師郷ハ今雀部庄トノミ呼ブ古名ヲ失フ
とあって、徳川時代には、土師郷の名は失われていたのであるが、古川氏はこれを丹波志で復活させたのであった。
著者自ら「今土師郷と云フヲ不知 古名亡失スルノミナラス雀部庄ト唱フ誤リ甚シ 和名抄ニ拠リテ土師郷ヲ出ス」と時人が古名を忘れその上誤った呼び方をしているから、和名抄の郷名を殊更に用いたのであると但書を入れているのである。そして土師郷の中には土師村及び前田村を挙げている。古川氏の努力にもかかわらず、その後、実際には土師郷の名は使用されず、土師は雀部庄内の一村として明治に至り、同二十二年の市町村制により雀部村が成立し、その管下に入ったものであった。
由良川右岸の川北は少なくとも徳川時代以前には古来の雀部庄に入っていたので、この機会に室町時代の川北について一言触れておきたい。川北の西部に小字多光というところと、その西部丘陵上に通称段ノ田と呼ぶところがある。丹波志古跡の部に、東禅寺古跡、薬師堂有、川北村、とあるのがこの地である。段ノ田は上って見るとかなり広く、数町歩の田畑が開かれている。昔七堂伽藍があったといわれているが、それにふさわしい面積はある。現在段ノ田から東に谷一つ隔てた丘陵の南の中腹、川北の集落に近いところに、三間に六間棟瓦藁葺の堂がある。この堂は現在地の西方約四百メートル程の前記段ノ田にあったもので、東禅寺の薬師如来を移したものである。
明治初年課税対称となるのをおそれて、川北頬光寺の一部として報告、現在地に移転して小字の集会所とした。この所にはもと洞流権現の祠が樫の大樹の下にあったが、これを鎮守の稲粒神社の境内に移した後をかきならして薬師堂を移築したものである。大正年間まで中老の尼僧が住し、近在からの参詣者も少なくなかったという。薬師如来は左右に日光・月光両菩薩を配し、薬師如来は美しく円満荘重の相を示し、刀法よりして室町を下らぬものといわれる。
昭和二十七年四月同地の塩見利夫氏、同頼男氏、芦田金次郎氏等が段ノ田の東禅寺跡を調査した時、貞治三年、大工彦四郎刻 という銘のある石仏や、前記の堂から東禅寺の寺額を発見した。貞治三年といえば西暦一三六四年で南北朝時代足利二代将軍義詮のころである。あたかも醍醐寺が足利草氏によって建立されて間もない時代であり、当時は醍醐寺の開山となった三光済国師が、同寺に入るまでに最初に開いた道場であった養泉寺も存在していたのであり、そこから北部及び東部にかけて、由良川右岸には一大仏域が連続していたこととなる。東禅寺跡の西南方に今数戸の集落があるが、それを小字門前といい、北方からそこへ流れ出る川を門前川、その川に架した福知山物部街道の橋を門前橋という。それから西方数百メートル由良川に沿うところを記録寺というが、東禅寺の記録所が門前にあったのであるという。こういうことを考え合わせるならば、東禅寺はかなり大規模な寺であったことが想像される。この寺には多くの仏像があったらしいが、寺の衰頽後は川北の各小字において、一体ずつ祠を建てて分祀したものだという。なお薬師堂の後の山頂から、今から約九十年程前と、約四十年ばかり以前に、高さ尺余の壷と金属製茶筒様のものが発掘されたという。それはおそらく経筒であって、東禅寺と関係があるものであろう。 |
『福知山・綾部の歴史』
雀部荘の成り立ち
雀部荘は、現在の雀部学区から土師を除き、戸田・石原・土を加えた地域である。平安後期から室町中期に至る間、京都の松尾大社の荘園であった。昔、雀部郷と呼ばれたこの地域は天田郡の豪族丹波氏の私領であったが、寛治五年(一〇九一)、丹波兼定が病気の快復を祈願して松尾大社に寄進したものである。
雀部荘の経営組織
松尾大社は雀部荘の領主となって後、荘内の名田を七反ずつに均等化して五か名(三五反)で一つの番を構成し、一二か番を編成した。番には番頭が置かれ、番頭の所有する名を番の名称とした。この他、これも七反均一の庄屋名と呼ばれる二四か名があり、有力名主が所有していた。
荘園の荘務は、下司と呼ばれる役人が公文・案主らの下級荘官を指揮して、年貢・公事・夫役などの徴収にあたった。案主は政所(役所)で文書記録の保管作成にあたり、公文は年貢などの徴収を分担した。
雀部荘のムラ
荘園時代の雀部郷には、富田(戸田)・石原・菅内・河与木・土・野中・堤の七か所の「ムラ」があり、このうち戸田・石原・土については現在の行政区に継承されている。菅内ムラは川北の東部から中央部にかけての地域、河与木ムラは川北の西部が、それぞれ想定される。また、野中ムラは名前が示すように、平地の広がる由良川左岸の、土ムラに接するあたりから愛宕神社に至る地域一帯が考えられる。堤ムラは石原ムラに隣接して由良川沿いにあったと推測される。前田地区については、荘園時代にムラがあったことを証する文書は残ってない。おそらくここは政所が置かれた雀部荘の中枢地域で荘園領主の直轄地であったのではないかと思われる。
雀部荘の人びと
松尾大社に所蔵される『松尾神社記録』によって、室町中期以降の名主の変遷を垣間見ることができる。池部・池田・前田・大西・中村・林などの姓は古くから登場しており、前田は「安宗番」を構成する名田のすべてを占め、由良川の上流に位置した五か番の総公文でもあった。長享二年(一四八八)以降の記録には内田が現れ、預所(高級荘官)の持分であった「為久番」の代官を勤めている。また大槻姓の名主が多く見られるようになるが、いずれも何鹿郡から勢力を広げてきた武士である。すでに戦国時代に入っており、堀・松山・玉井・山添など、近隣の地頭らしい名前も見え、地下の上層農民のなかにも、前田左京亮・中村備中などと、侍身分を思わせるものも現われるようになった。この頃になると生産力の向上によって農民の取分が増え、富裕化して、上層農民の地侍化が進んだ。一方、農耕に従事する作人たちにも農地に対する耕作権が生ずるようになり、しだいに自立するようになった。(笠原彰) |
伝説
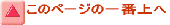
関連情報


|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|