 京都府福知山市下紺屋 京都府福知山市下紺屋
 京都府天田郡福知山町下紺屋 京都府天田郡福知山町下紺屋
|
下紺屋町の概要
《下紺屋町の概要》
堤防に沿う山陰道から法鷲寺の前から分かれて南ヘ入る道筋の両側町。福知山城下15か町の1つ。もともと紺屋(染物屋)が多かったのか、のちにはおいおい鍛冶屋・薬屋・糸屋など混住するようになったようで、「丹波志」には、「雀部鍛冶」の「子孫ハ福智山下紺屋町鍛冶半兵衛ト云」とあり、鍛冶の名家があったことを記す。

下紺屋町は、江戸期~明治22年の町名。明治初年~22年は福知山を冠称。
貞享3年250軒焼失・元禄7年62軒焼失・宝暦8年403軒焼失など当町を火元上する火災が多発したという(天田郡志資料)。由良川堤防にまで伸びる一帯は寺院が並ぶため寺町のうちに俗称されていた。
明治4年福知山県、豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年福知山町の大字となる。
下紺屋は、明治22年~現在の大字名。はじめ福知山町、昭和12年からは福知山市の大字。
《下紺屋町の人口・世帯数》 122・54
《主な社寺など》
 浄土宗霊光山法鷲寺 浄土宗霊光山法鷲寺
山陰道沿いの堤防下に京都知恩院末浄土宗法鷲寺。開山は実誉和尚、開基は喜屋清右衛門、創建年代は永禄11年、文化4年類焼ののち安政4年にも火災にあい再建。朽木氏の菩提寺の1つで、「丹波志」によれば領主仏殿があるという。なお境内石燈籠には寛政7年に信濃善光寺別当性谷大僧都による開帳が行われたことを刻む。

 案内板→ 案内板→
<浄土宗霊光山竹林院法鷲寺
浄土宗霊光山竹林院法鷲寺
開山 南蓮社実譽上人(豪放千葉氏の出)
創建 永禄十一年四月八日(1568)
開基 喜屋清右ヱ門
福知山藩主 朽木家帰依菩提寺
本尊 阿弥陀如来
宗祖 法然上人(円光大師)
称名 南無阿弥陀仏
教義 南無阿弥陀仏と称ることに依って、どんな不幸な者でも一切の苦しみか救われ、安らかな毎日を送り、明るい生活を迎えて、そのまゝの婆で人間えと向上し、浄土に生まれること出来るお教です
経典 無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経 その他
沿革 永禄十一年(1568)浄土宗は属し、呉服町(現明覚寺)に建立、天正十三年整備拡充、寛文十年(1670)現在に移る。寛政七年(1795)信州善光寺専念道場又時宗遊行上人の本陣となる。
文化四年(1807)安政四年(1857)再度類火罹災、明治二十九年(1896)大洪水のため本堂潰破、更に明治四十年、昭和廿八年再三の大水害に依り大破潰を受け其後修築を重ねて現状に復興す。
仏堂 弁才天社、笠森稲荷社、延命地蔵尊
弘法大師 両丹第四十九番 福天第一番霊場
浄土本山
京都智恩院、黒谷金戒光明寺、清浄華院、百万遍智恩寺
粟生光明寺、京極誓願寺、永観堂禅林寺 東京増上寺
鎌倉光明寺、信州善光寺 久留善尊寺
第三十六世 説譽代誌 |
霊光山竹林院 法鷲寺 (浄土宗智恩院末)同町字下紺屋
本尊 阿弥陀如来 脇立 観世音菩薩 大勢至菩薩
開山 南蓮社実譽霊尊大和尚 (姓は千葉氏、下総国の人、宗祖十六代の法孫 東京芝増上寺九代道譽上人の会下に於て附法)
開基 喜屋清石ェ門、霊鷲院念譽道光居士
創建 永緑十一年四月八日実譽大和筒、喜屋清右ェ門等の喜捨に依り堂宇創建。後、文化四年類火に逢ひ過去帳其他の記録悉く焼失、安政四年十月復た火災に罹り全部焼亡、当時の住職千葉諦巌和尚、檀信徒に浄財を乞ひ再建す。明治廿九年八月卅一日大洪水の爲め、本堂、庫裡等潰破、住職岩井智海上人(現智恩院管長)本堂再建、工事半途にして堺市旭蓮寺に転住、次に漆間徳定上人尽力せられしか是亦大和国如意輪寺に転住、次に現住徴典和尚に至り漸く再建復興す。然るに明治四十年八月又大洪水にて本堂、庫裡等半潰、什宝流失の惨害を被る、現住亦四方に奔走し檀徒の合力に依り境内地上げ現時の状態となれり。
寺宝 宗祖圓光照大師の名號。 仝大師所持の伏鐘。迎接曼荼羅、仏舎利。同塔等とす。
境内に鎮守道、弁才天、笠守稲荷神の祠あり。
…
(『天田郡志資料』) |
《交通》
《産業》
《姓氏》
下紺屋町の主な歴史記録
伝説
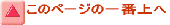
下紺屋町の小字一覧
関連情報


|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|


