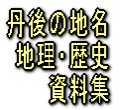 |
天藏神社(あまくらじんじゃ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天藏神社の概要《天藏神社の概要》天藏神社は舞鶴市の南部。東舞鶴市街地の東南部、  丹後風土記残欠にある古社である。それには、「高橋郷。本字高椅。高橋と号くる所以は天香語山命が倉部山の尾上に神庫をつくり、種々の神宝を収蔵し、長い梯を設けてその倉のしなと為したので、高橋と云う。今なお峰の頂に天蔵と称する神祠があり、天香語山命を祭る。」とある。現在の祖母谷から倉梯周辺の、従って東舞鶴地区の発祥と見られる神社であるが、今は忘れられたような小祠となっている。  この社は元々からここにあったとは考えられない。残欠は元々は倉部山の峰の頂にあったと書かれている。その  現在の天藏神社の北側に「 梯木といった古い地名で、この山が古い聖地であったろう事は間違いがないと思われるが、ここに元々からあったとは私は思えないのである。 なぜなら倉部山は、残欠にさらに 〈 倉梯川水源(以下虫食) とあるように 倉椅川は今は与保呂川の別名でもあるが、ここは祖母谷川のことと思われる。  庫梯山(倉梯山)は現在はそう呼ばれる山があり一般の地図にも載っているのである、与保呂小学校の真向かいの山、東舞鶴インターの北にある山であるが、しかしそこではどうもおかしい。クラハシ山と言えば現在のその山と考え、ツユ疑う人もないようであるが、現在人の倉椅山と古代人のいう庫梯山は同じとは限らない、これはちがうと思われるのである。  梯木林も現在の倉梯山も、これらを指して倉椅川の水源とは呼ばないと思われる。水源といえば川の一番奥にある大きな山であろう。 それは三国山(丹後・丹波・若狭国境616m)しかない。この山は祖母谷川と与保呂川の水源である。天藏神社は三国山の峰の頂にあった。そう思われる。 多門院の一番奥の、だから一番三国山寄りの集落は この黒部・黒符は倉部山のクラベが転訛したものではなかろうか。やはり三国山こそ倉部山(庫梯山)と思われるのである。倉部山の神はヘビであったと思われる。 福知山市に「 祭神の 『新撰姓氏録』を覗いてみれば、… 左京神別下。天孫。(第十三巻)。 尾張連。 尾張宿禰同祖。火明命之男 山城国神別。天孫。(第十六巻)。 尾張連。 火明命子 大和国神別。天孫。(第十七巻)。 尾張連。 天火明命子天香山命之後也。 大和国神別。天孫。(第十七巻)。 伊福部宿禰。 同上。 大和国神別。天孫。(第十七巻)。 伊福部連。 伊福部宿禰同祖。 河内国神別。天孫。(第十九巻)。 吹田連。 火明命児天香山命之後也。 和泉国神別。天孫。(第二十巻)。 丹比連。 同神男天香山命之後也。 和泉国神別。天孫。(第二十巻)。 石作連。 同上。 和泉国神別。天孫。(第二十巻)。 津守連。 同上。 和泉国神別。天孫。(第二十巻)。 同上。 和泉国神別。天孫。(第二十巻)。 同上。 和泉国神別。天孫。(第二十巻)。 津守連同祖。天香山命之後也。 …これらはごく一部のみ記録されたのであって、東舞鶴倉梯や西舞鶴田辺の氏族も彼らと同族と思われ、彼らというか我らというのか、我ら舞鶴人の祖先であるが、この一族は丹後海部氏へと編成されていったと思われる。 彼らにつきまとう、というのか、我らにつきまとうところのカゴとかタカ、クラといった名から考えれば、元々は渡来系、古くは天日槍系の金属精錬の集団と思わざるを得ない。 三国山の頂にあった天藏神社に、天香語山命によって収蔵された「種々の神宝」とは何か。これは米でなく、金属製の武器や農具類ではなかっただろうか。 天藏神社の主な歴史記録《丹後風土記残欠》〈 高橋郷。本字高椅。高橋と号くる所以は天香語山命が倉部山の尾上に神庫をつくり、種々の神宝を収蔵し、長い梯を設けてその倉のしなと為したので、高橋と云う。今なお峰の頂に天蔵と称する神祠があり、天香語山命を祭る。また、その山口(二字虫食)国に祠があって、祖母祠と称する。此国に天道日女命と称する者があって、歳老いて此地に来居まして、麻を績ぎ、蚕を養い、人民に衣を製る道を教えたので、山口坐御衣知祖母祠と云う。 田造郷。田造と号くる所以は、往昔、天孫の降臨の時に、豊宇気大神の教えに依って、天香語山命と天村雲命が伊去奈子嶽に天降った。天村雲命と天道姫命は共に豊宇気大神を祭り、新嘗しようとしたが、水がたちまち変わり神饌を炊ぐことができなかった。それで泥ヒチの真名井と云う。ここで天道姫命が葦を抜いて豊宇気大神の心を占ったので葦占山と云う。ここに於て天道姫命は天香語山命に弓矢を授けて、その矢を三たび発つべし、矢の留る処は必ず清き地である、と述べた。天香語山命が矢を発つと、矢原山ヤブに到り、根が生え枝葉青々となった。それで其地を矢原(矢原訓屋布)と云う。それで其地に神籬を建てて豊宇気大神を遷し、始めて墾田を定めた。巽の方向三里ばかりに霊泉が湧出ている、天香語山命がその泉を潅ぎ〔虫食で読めないところ意味不明のところを飛ばす〕その井を真名井と云う。亦その傍らに天吉葛が生え、その匏に真名井の水を盛り、神饌を調し、長く豊宇気大神を奉った。それで真名井原匏宮と称する。ここに於て、春秋、田を耕し、稲種を施し、四方に遍び、人々は豊になった。それで其地を田造と名づけた。(以下四行虫食) 《勘注系図》天香語山命の注文 〈 《室尾山観音寺神名帳》 〈 (京都府地誌) 〈 《倉梯村史》 〈 天藏神社 多門院材木鎮座 無格社 天香語山命を祀る。丹後風土記高橋郷の條下に曰く、 「天香語山命庫部山尾上に神庫を創営し給ひて云々……前述地名の起原の條参照……. と、 藤原光長在銘の神鏡あり、古老曰く「古くより伝はりし立派な新鏡ありしも何時の頃よりか現在のものと交れり」と。寛文…凡二七○年前…宝暦…一八○年前…等の修理棟札あり。其他不詳 新田氏 新田氏の支流来りて多門院に住み徳川氏を憚りて新谷と称せりと、今天藏神社の高麗犬に新田氏と刻せるを見るは其の消息をつたふるものにや。 関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||