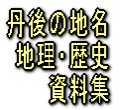 |
余部上(あまるべかみ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余部上の地誌《余部上の概要》余部上は舞鶴市の中央に位置し、国道27号線で言えば、五老岳下の榎トンネルから共楽公園下あたりまでの谷合にある。 和名抄の余戸郷、「丹後国田数帳」の余戸里と考えられる。 余部上村は江戸期〜明治22年の村名。 明治30年代に舞鶴鎮守府・舞鶴海軍工廠が近くにできたため、当村も大きく変貌した。舞鶴鎮守府のお膝元になる場所で、まっすぐな広い大通り(国道27号線)も整然とした区画もその遺産、大道路は鎮守府街道と呼ばれた。明治31年海軍用地として森ケ奥の柴草山5反余が海軍基地予定地として買上げ。 明治33年舞鶴憲兵分隊を上4丁目に設置(現在は駐在所がある)。 昭和20年建物強制疎開により6丁目道路沿いが撤去されている。 《人口》2132《世帯数》923 《主な社寺など》 『丹後国加佐郡旧語集』 〈 『加佐郡誌』 〈 …当字に神龍山雲門寺がある。天龍山鹿王院末で、昔境内に枯池があって此処に龍が棲んでいたから山号としたといふことである。新舞鶴湾内の蛇島に其霊魂が祭ってあるから此島にある二つの小池を龍眼水又は蛇ノ目池と呼ぶと古書に出ている。 『丹哥府志』 〈 神龍山雲門寺は応安二年春屋妙葩和尚の開基なり。妙葩和尚は南禅寺の卅代なり、故ありて余部村に来り雲門寺を建立す、後に南禅寺に帰る。或曰。応安二年夏四月叡山の僧徒南禅寺の僧徒と争論起る、是を六波羅に訴ふ、将軍是を決せず、於是叡山の僧徒怒りて日吉の神輿を奉じて京に入り将に禁門を焼かんとす、将軍の家人佐々木崇水之を討て悪僧等を退く事を得たり、帝賞するに御筆を以てす、妙葩和尚の来る蓋此時なり。足利氏の石碑あり。今宝物とて妙葩和尚より伝はるもの二品、懐釼一振、水の玉一ツ、蓋足利家より賜はるといふ、玉の大サ二寸余、玲々瓏々として名玉ともいふべきなり、但貌のうつる皆倒に見ゆ、目鏡などにも斯様のものありて珍しからぬ事とは云ひながら一寸笑しきものなり。 『舞鶴』 〈 中舞鶴町花木通りにある臨済宗天龍寺派の寺院で本尊は地蔵菩薩である、慶安三年普明国師の開基にかゝり以前は今の要港部の中に在ったのであるが明治二十二年現在の地に移されたので傳説に往昔此處に温泉湧出し「森の湯」と称せられたとある、寺宝に「龍珠」と称するものがあるがこれは普朋国師が大蛇を接得して蛇烏に移らしめたことがあって後にその大蛇が生天の恩を謝するために童子に化けて国師の室に現はれて献じたものといはれて居る。 『舞鶴史話』 〈 『舞鶴の民話2』 〈 中舞鶴の上三丁目花木通りを小学校の方へ向かう。右には花の名所の山がみえる。大きな屋根がみえる。山門があり、雲門寺という。この寺は有名な普明国師の創建になるものである。 京都の南禅寺から余部の里の鎮海軒という庵へやってきて、この寺をお造りになったのである。村人は国師のお話を聞くたびに何かさとりを開くようでありがたく、話をきいて各地からお参りにやってくる人がたえなかった。国師はどんな貧しい人でも、金持であっても話をきく人であった。 ある日のこと、ふさぎこんだ様に村人が国師のもとにかけこんできた。そして次のような話をした。村に帰る途中に菖蒲が池があり、あたりはこんもりとした森で、昼でも通るのにうす気味悪いところである。夜になると大蛇がでてきて、村人はおどろかされ、時によると大けがをする事があり、夜の用事にはいけなかった。そこで国師の御徳でこの村人の悩みを除いていただきたい。 国師はさっそく池のほとりに行き、毎日祈祷をくりかえした。そのあいだ池の方で何かざわざわするが大蛇の姿はみることが出来なかった。 それから数日後、朝早くからお堂で読経していると、人のけはいがした。尚も続けていると、国師のそばに黒髪をした美女がスーツと現われた。「そもさん」と国師が問うと、美女はすずをならすような清らかな声で、「私は菖蒲が池に住む大蛇です、私の願いを聞いてもらおうと村人に話しかけるが、みんな逃げていき、ある時は、大がまで私を殺そうとすることもありました。先日から国師の功徳によって、おかげで私も昇天の化を得ることができました。長らくこの池に住ませていただきましたお礼に、日ごろだいていた水珠を形見においておきます。」というが早いか大蛇に姿をかえ天へと昇っていった。 《交通》 国道27号線 《産業》 余部上の主な歴史記録《丹後風土記残欠》 〈 《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 神龍山雲門寺本寺京嵯峨鹿王院禅 余部上村、同下村、北吸、和田、長浜五ケ村の寺なり。開山普明国師、宝物国師の袈裟懐劒あり。昔高田平之丞山城に住居す。 「解説」山城は旧舞鶴鎮守府の跡地である。高田平之丞は中世の人であり近江へゆき布川姓となった、後に余部の布川氏先祖が庄屋で寺社町在旧起を書いたと云われている。 (「解説」は訳者の佐藤正夫氏による) 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 余部上村 高二百九拾四石七斗壱升 内六石四斗壱升弐合 万定引 四拾石御用捨高 若宮社 《丹哥府志》 〈 《地名辞書》 〈 《加佐郡誌》 〈 余部上の小字余部上 土井ノ内 余部上 森ケ奥 久田 前田 スゴ 奥母 北安 白戸 宇柳 小西 後山 谷口 下谷 才ケ谷 奥山 宇柳口 聟ケ坪 関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||