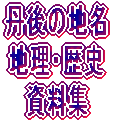 |
磯(いそ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯の概要《磯の概要》 浜詰から浅茂川へ府道665号線の一番浅茂川寄りの集落。日本海に面した海岸段丘上に立地。静御前ゆかりの地と伝えられ、静神社が鎮座している。 磯は、昭和25年から網野町の大字。もとは浜詰村の一部。平成16年から京丹後市の大字。  《磯の人口・世帯数》 112・35 《主な社寺など》  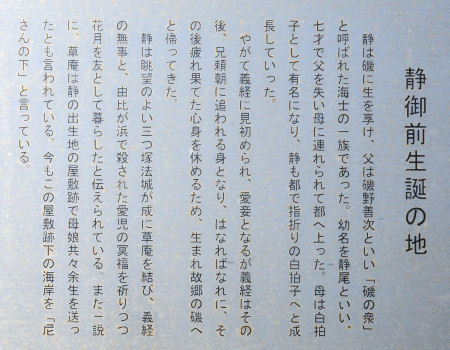 舞鶴にもシズカ神社がある、風土記残缺に志東社、これは志束社の誤記で、今の志楽二宮・鈴鹿神社だといわれる。 別に静御前の伝説はない、静御前の伝説のある地は彼女の親の磯禅師のイソという地名と結びつくことが多いようである。 イソ、ニソ、シズは繋がる名で、この地発祥の歴史を秘めていそうであるが、それとは別に静御前の村として知られ、「丹後七姫の一人」に数えられている。  静は磯村出身の磯の禅師の女で、源頼朝に許されたのち故郷へ帰り、死後この社に祀られたとの伝えがある。 『丹後国竹野郡誌』 〈 (神社明細帳) 祭神 静カ比女命 一、由雄 秋静カ比女は原と当所の産にして域時源義経の妻となりて静カ御前と云ふ其義経落舘の砌古郷磯に帰りて死す於之村人共同神社に列し祭り来ると古老の伝也 一、社殿 梁行一間 桁行一間 一、境内坪数並地種 二 十 坪 一、信徒人員 七十二人 (丹後旧事記) 竹野郡木津庄礒磯村 祭神 静女木像 元型二年丁巳夏五月京極高広順国の時、当社の神記有りけるに惣左衛門と云ふ海人一つの箱を持来り一書を取出し奉りけるに、源判官義経吉野山より贈り申されし消息なり、名当磯野惣太政源義経とあり、国主大いに感賞有りて再び此地を磯村と云ふ一村なるべき由仰有りけるなり、此頃漸に海士七軒有りと奥平家記に見えたり、相伝ふ源義経に仕へし静女は、当国塩江の海人の娘なり貧窮の餘り七歳にして都へ登せ遊里へ売りて白柏子となす、後義経の妾となると伝ふ (伝説浜詰村誌稿) 往昔当村には磯野氏なるもの僅に三戸許り在りて川東と云ひし所(今其の所を字して小屋谷と云ふ)に住みしも、生活上の便利によりて字大成と唱ふる僅東南方の地に移れり(比の時戸数一二を増す)と伝ふ、 其後磯野善次なる者復た字岡地に転居(年時不詳今の祠の在る所即ち井本浅右衛門の屋敷の傍なり)せしか不幸にして幾年ならす死亡せり故に寡婦(名不詳京都の産静の生母)幼女静尾(静の幼名)を携へて京都に帰り(静の六歳の時なりと)遂に祇園の某家に白拍子となす、後ち十八歳の時堺の住吉に於て舞会のありしとき初めて之に会す、偶々義経至り詣し静の舞を見て迎へられて妾となる 義経京都を去るに及ひ従ふて吉野に匿る、義経之を諭して別れ僕をして資を?し京都に送り帰らしむ、僕途に其資を奪ひて静を棄つ、静獨り風雨を冒して行き山僧に捕へらる、源頼朝鎌倉に招きて義経の所在を詰れども固く知らすと陳す、会々其の妊める有るを以て之を留む後頼朝の妻政子静の歌舞に達するを聞き之を見んと欲し、夫妻共に鶴カ岡八幡宮の社に詣し静を召して舞を命す、静固辞すること再三免されす、遂に起て離別の歌 吉野山峰の白雪ふみ分けて入りにし人の跡そ怪しき しつやしつしつのおたまきくりかへし昔を今になすよしもかな を作りて義理を慕ふの意を述へて舞ふ、衆哲涙を垂る、頼朝獨り色変して曰く賤婢我を領する事を肯せすして敢て乱入を恋ふ、之を誅せんとせしも政子諌めて止め纏頭を賜ひて罷む、工藤祐経梶原景茂等と倶に静の舎に飲し景茂酔て静を挑む、静怒り且つ泣て曰く公をして道を全くせしめは汝我面を識んと欲するも得んやと、此の時静年二十八なりと云ふ、後京都辺にて終ると伝ふれ共(義経困功記に見ゆ)又義経従僕二人を附して此の地に送り来らしめ海岸の岩上に休憩して弁当などを食ひしなり(ベットウ岩と云ふは弁当岩ならん)然して静は眺望の地を撰み法丈ケ成に草庵む結ひて花月を友とせらるゝを、義経蝦夷へ下向の後海路巡行にことよせ静の出生地なるを知り、寄港して入船の浜(今ニソの浜と云ふは入艘の転化ならん)より上陸し、訪ふて夫妻久々の対面ありしなり、然して離別の時影隠シ岩(コース岩といふ)に送られ船の遠く距れ行くを見て離別の情に堪へす腰屈ミ岩(泣き別れ岩の称あり)に泣き叫はれたりと云ふ (静は此時海に没して死せりとも云ひ伝ふれ共)又其後は尼となりて義経の菩提を弔ひたりと伝ふ、何れにしても何歳にて死せられしか詳かならす、死後静の愛具共を埋めしとも見ゆる塚三箇ありて近来磁器の類を出せし事あり、今其辺を三ヅ塚法丈ケ成と云へり、其後土人静の為めに木像を作り出生の地と伝ふる屋敷に形許りの祠む建て安置せり祠は今に存在せり 夫れより少しく彼の事ならんか義経の歯?と云ひ伝へて祭れる聖神と称するありて、年々祭日には非常に変風なる祭を行ひしも明治十六七年の頃より比の祭礼を廃し、今は一小社を建立して聖神社と称して祀り居れり、下りて慶長五年に旧領主京極孝広公領内巡見の際、社寺の神軆仏像等を改められ(静の祠に至り木像を認めて仔細を尋ねられし時漁師の総左衛門(時の庄屋か)と云ふ人答へて僅なる一個の箱を出しければ、京極公之を開き改められしに源判官義経より当村の住人磯野総太へ当て妾静な送るとの送り状なりけれは、八押戴き之は容易ならさる縁故あることなれは当村を以来磯村と称すへきことを下命せられたり、之れ今の磯村の起因なりと雖も今を去る百三十四年(大正四年)前即ち天明二年三月偶々其家に火を失し折柄大風ありで全村殆んと烏有に帰し其節右送状並に木像其の他多少の遺品文書の類ありしかとも悉皆焼失せしめ今は何の證査たるべきものなし、唯僅に或る一二の事項の口碑に伝ふ所を附記するのみ、 (伝説) 磯村静御前は昔当所に磯の善師と申者有骨之娘一人あり容貌美麗なり売人都へ連れ行く所に源義経公の御手に入り御寵愛に候へ共義経壇ノ浦へ御出被成候節此處に船御付被成静御寄揚被成候て御預け置かれ候と申事に候、即此の船付の處を御附濱と申候此浜の岡に大なる巌穴御座候此處に御忍び被成候と申伝へ候、遂に磯村にて絶命葬るに親子三人家来一人当山岡に塚御座候此の塚を今に四つ塚と申候とあり 『網野町誌』 〈 祭神 静比女命 由緒 静比女は原と当所の産にして或時源義経の妻となりて静御前と云ふ其義経落館の砌故郷磯に皈りて死す 於之村人共同 神社に列し祭り来ると古老の伝也(『竹野郡誌』)  集落の西側の浜で、写真でいえば、特に奥側をこう呼ぶという。特には何もないようである。イソ集落発祥の地ではなかろうか。ニソのNが落ちてイソとなったのかもわからない、あるいはニソと区別して東側集落をイソと呼んでいたのかも知れない。 『網野町誌』 〈 磯漁港西側の岬付近に「ニソ」という地名がある。ニソは民俗学でも注目される地名だが、福井県小浜湾西の大島半島にも「ニソの神」を祀る「ニソの杜」が三〇か所もある。杜全体は神聖な霊域とされている。「ニソ」という音の意味意義はいま不詳だとしても、全国的にも珍しいこの名が、磯と若狭湾岸に伝わる事実は何を語るのであろうか。(『ニソの杜民俗誌』〝柳田国男の手紙〟) 特に難しいことではないと思う、ニソという場所が集落発祥の地ということと思う。それは丹後も若狭も同じ事情であった。イソやシズカは同系の言葉でそうした集落発祥にさかのぼる古い由緒ある名だと思われる。 《交通》 《産業》 磯の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 【加茂大明神】 【静の社】 【ソブ】(以下六条皆奇観なり) 【銚子口】 【穴崎】 【かぶと岩】(出図) 【女滝】 【相似谷】丹後旧事記曰。昔保昌爰に狩して浅妻の狩場と相似てりといふ、よって名とす。 【男滝】女滝男滝相似谷を隔てて各数十丈の岩壁なり。男滝は岩壁の下に穴あり、穴の広サ四五尺、凡五、六間斗右に入りて洞然たる處あり、其處に滝あり、蓋女滝は水流あるにあらず岩壁数十丈の上より水滴りて雨の如し。 【章魚岩】(出図) 【五色浜】(章魚岩の次、塩江村に属す) 也足軒素然の配所日記に曰。上東門院の仰によりて赤染右衛門丹後に下りけるを誘ひ、国司保昌みづから浦々をめぐり、橘の志布比の浜にて光よき石を拾ひ朝廷に捧げれば、門院限りなく悦び給ひ式部が許へ送らるる御消息に長く此浜を御志記浜と名付べしとありける云。辛丑の夏余此浜に来りてこれを見るに、浜の広サ僅に四五間、其上に大なる岩ありて覆ふが如し、其下に李実程なる小石の浜あり、其石或は青、或は黄、或は白、或は赤、或は黒、或は一石に二色三色五色を帯たるものあり、俗に五色浜と云。玉葉和歌集に栄華物語りを引て曰。上東門院枇杷准后の為に仏を作らせける、保昌丹後守に侍ければ飾の玉を召れけるを 数ならぬ泪の露をかけてたに 玉の飾を添へんとそ思ふ (式部) 【志いら浜】 しいらは魚の名なり其大サ五六尺斗もあり、大魚なり、しいら漬とは塩に漬たるしいらをいふにあらず、しいらを捕るの名なり。凡四五間もある木を四、五十本斗くくり碇を付け沖に泛べ置く、此魚海に泛みたる物あれば会て其場所を去らずといふ、よって如此するものなり、是をしいら漬といふ。五六月頃より七八月迄の間夜々船を其傍に泛べ、松を焼てしいらをつる、魚の性も色々あるものなり、鯖なども火さへ焼けば其場所によるとかや。 【付録】(若神社) 『丹後旧事記』 〈 『丹哥府志』 〈 日本史云。静は磯禅師の女なり其人となり貞節にして又伎あり、撰れて源義経の室に入り殊に寵遇せらる義経既に跡を晦まして後、源頼朝鎌倉に捕へ義経の在所を尋問す、静これに答ふるに実を以てせず、先是頼朝静の舞を善くするを聞く、よつて之をして舞を舞はしむ、静敢て固辞すれども頼朝肯ぜず、於是静歌を作る、其辞に云「しづやしづのおだ巻くりかへし昔を今になすよしもがな」此歌を歌ふて立舞ふ、其心猶義経を哀慕せり、依て頼朝悦ばず、遂に其生む所の兒を殺す、静は幸に免れて一たび京都に帰ることを得たり、猶寝度を安んぜず亦跡を晦まして丹後竹野郡磯村に匿る。其鎌倉に在し時工藤祐経、梶原景茂千葉常秀等酒肴を携へて静の旅館に至る、景茂酔に乗じて静かに戯る、静涙をたれて大に怒る。曰。妾は予州の箕?をとるものなり、若し予州沈淪せずんば汝等我を見る事能はず、况や我に戯るをや。其勢当るべからず、景茂且は恐れ且は恥ぢ其面忸怩たるものありと云。或は云。頼朝静の舞を見る其歌を歌はざる以前、其心如何なるや計るべからず其歌を聞て悦ばざる處に就て見るべきなりと云。静の義を守ること斯の如し。 (丹後口碑云。静既に京に帰りて後猶寝度を安んぜず亦跡を晦まして丹後竹野郡磯村に匿るといふ。) 愚按ずるに、正史に静の丹後に来るを見ず。宮津府志云。義経動記といふ冊子に、丹後巡遊を引て、静の丹後に来るをのせたりといふ、然れ共これを以て証とするに足らず、今其地を踏みてこれを見るに、村の後山に室寺のなるといふ處あり昔室寺といふ寺ありとて今に礎石残る、其傍に四ツ塚といふ處あり、其西北に当りて石櫃あり(元二ツありといふ、今一ツ残れり)石櫃口の広サ一間斗に奥行二間斗もあり、又村の続きに尼僧ケ浜あり、其人の説に、皆静の由緒ある處なり、記録も慥に伝りしが六十年斗以前に一村焼失して宮も記録も皆烏有となり今審に知る事能はずといふ。其説によって考ふれば四ツ塚なり尼僧ケ浜なり又鄙僻の地に在りて右の如き石櫃なり、皆考証の一助とするに足る。又地理を以て考ふるに村の背に高山を負ひ村の前に大洋を受け村の左右は懸崖踰るべからず、誠に人跡不到の地なり、たとへ磯禅師の故郷にあらずとも恐らくは静の潜匿する處ならんと覚ゆ。又静の左右を考ふるに口碑にいふ如く静既に京に帰りて後いまだ心を安ずる處にあらず。是を以て之を見れば巡遊記に記す處未だ必ずしも據る所なくんばあらず。或し曰、磯禅師は讃岐国大内郡小磯村といふ處の人なり、又阿波国徳島の内にありといふ審ならず。 磯の小字一覧関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『丹後国竹野郡誌』 『網野町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||