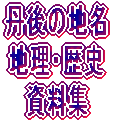 |
野中(のなか)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野中の概要《野中の概要》 佐濃谷流域と川上谷川流域を結ぶ国道312号線の石峠の登り口の集落。もと峰山街道の宿場であったという。 野中村は、江戸期~明治22年の村名。はじめ宮津藩領、寛文6年幕府領、同9年宮津藩領、延宝8年幕府領、天和元年宮津藩領、享保2年からは幕府領。明治元年久美浜県、同4年豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年上佐濃村の大字となる。 野中は、明治22年~現在の大字名。はじめ上佐濃村、昭和26年佐濃村、同33年からは久美浜町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 《野中の人口・世帯数》 125・39 《主な社寺など》  峠の登り口南側の丘の上に鎮座している。 『京都府熊野郡誌』 〈 祭神=菅原大神。 由緒=当社の創立年代等は徴証すべきものなけれど、古く奉祀せし事き明にして、幕政時代尊崇最も厚く、御朱印の交付ありし事は、徴証すべき文書存す。 崇敬者人数=四十五人。 境内神社。七社神社。祭神=須佐之男命、大山祗命、奥津彦命、奥津媛命、大宮媛命、若宮媛命、保食廼命。 愛宕神社。祭神=火産霊命。 明治四十三年十二月許可を得、天満神社境内に移転せり。 天満宮の反対側の山の上にあり、山上を城の尾とよび、また産屋敷(さんやしき)とよび、むかし産所であったという伝えがあるそう。 『久美浜町史・史料編』 〈 字野中小字豊谷に所在する。 遺跡は、野中集落から北西方向、佐濃谷川の西側丘陵上に展開する。本槨は、標高約九〇メートルの丘陵頂部に位置し、そこから北に向かって延びる支丘陵の先端部では堀切が確認されている。 発掘調査により、丘陵頂部から北方向へ急傾斜の尾根筋が延び、堀切部分を境にして、標高七〇メートル程度の比較的平坦な地形が約一〇〇メートル続くことが確認された。堀切はちょうど丘陵の傾斜変換点に位置する。 堀切は、幅約一〇メートル、最深部での深さは約三メートルを測り、断面形態はV字形を呈する。短期間に埋まったものと考えられ、埋土中から時期を示す遺物は出土しなかった。 《交通》 《産業》 野中の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 【天満宮社】(祭春秋彼岸日) 野中の小字一覧野中(のなか) 竹ノ下タ 古堂ノ下タ 川東 中ノ上ミ 石峠 中ノ下モ 六反坪 縄谷 大下モ 出合 畠田 中田 カナゲ 下モ川原 大柳 縄谷口 下末 下タ川原 大井禰 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『丹後町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||