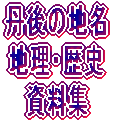 |
丹後国(たんごのくに)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹後国の概要《概要》  丹後はタンゴと普通は読むが、「和名抄」高山寺本に「太爾波乃美知乃之利」(タニハノミチノシリ)の訓注がある。正式には一応は丹波の古来からの地名を残すものなのかも知れない。 狭い意味(村程度)での丹波は全国的に有名な弥生環濠集落・扇谷遺蹟や途中ヶ丘遺蹟の地で、今は丹波小学校や「丹波」のバス停が古い地名を残している。『和名抄』風に言えば、丹波国丹波郡丹波郷は当地で、丹波の地名は元々はこの辺りを指したものであった。  【古代】(丹後国前史) 北は日本海で、大陸・半島と近いために早くから文化がひらけた。久美浜の函石浜遺跡からはの王莽(おうもう)の貨泉が出土しており、遅くともすでにこの時代には大陸文化を受けていた。 弥生時代になると峰山の赤坂今井、加悦の日吉ヶ丘、岩滝の大風呂南墳丘墓、扇谷・途中ヶケ丘の環濠集落遺跡、加悦谷・加佐郡の銅鐸などが全国的にも有名な先進的な遺蹟である。 古墳時代は、この時代全期間を通じての古墳の総数は丹後で約5000基、丹波で約2500基(府下のみ)、山城で約1500基。丹後と丹波はこの時代は同じ丹波国であったので、その数の多さ集中度は圧倒的で丹後王国論の論拠となっている。また加悦の蛭子山古墳、丹後町の神明山古墳、網野の銚子山古墳などの三巨大古墳は日本海側では最大、京都府下でも最大で、大和や河内などに匹敵する大古墳が営まれている。大陸との潟湖を通じての交易や、弥栄の奈具岡遺蹟、遠所遺跡などに見られる金属や玉などの最新技術の地であったのではないかと考えられている。 文献としては、大和権力側から都合よく記したようなものであるが、「古事記」には丹波大県主由碁理の娘・竹野比売が開化天皇に召されたこと、「日本書紀」には丹波道主王の5娘が垂仁天皇に召されたことを記している。また顕宗天皇即位前紀に、天皇の父が雄略天皇に殺された時、日下部連使主は天皇(弘計王)とその兄億計王を奉じて「余社郡」に逃げたと記している。この伝承は現在も丹後の各地に伝わっている。、「丹後国風土記」逸文は奈具社・天椅立・浦嶼子の伝説を載せている。当地の史料としては、丹後一宮の海部氏系図(国宝)は海部氏が応神天皇の時代に国造となり、その後籠神社の祝として仕えたことを伝えている。 丹後国が面白いのはこの時代か、渡来系住民の話や鉄や水銀のハナシなどは、丹後ばかりでなく日本史を考え直す上でも重要で、21世紀の日本のためにはぜひにも深めるべきものかとは考えるが、残念ながら今は一般的ではなく、祖先は天から降ってきた式の破綻済みの19世紀の皇国史観が支配するようなことなのでここでは触れない。歴史も社会科学であり、当然にも社会の制限を受ける、その時々の支配層にとって都合わるい歴史は消されたり、適当な別の話がデッチ上げられたりする。歴史は過去を写す鏡だけではなく、今の社会を映し出す鏡でもある。 後の時代はワタシは興味が薄い、チョー簡単に見てみると… 【古代】(丹後国時代)  丹後の国府は「和名抄」刊本に加佐郡に在りとして「上七日、下四日_」と記しているが、しかし地名にも残るように、国府・国分寺が与謝郡府中の地にあったことも否定できない。丹後国の中心は元々は丹波郡・竹野郡・熊野郡の主に西側にあったが、このころは与謝郡・加佐郡の東側に移動している。当初の国府は熊野郡にあったともされるが、すでに弘計・億計もこの地方に逃れているので丹後の重心はこちら側に移動していたのかも知れない。国府の遺蹟はまだ発見されていない。 5郡で構成された丹後国は、山陰道では隠岐国の4郡についで少ない。『和名抄』に記された田数も4700町余で、これも隠岐国についで少ない。元々の巨大丹波国の勢力を割くために小さく分割し、名も消したとする見方もある。丹後にはかろうじて海だけが残ったことになるが、メーン交易ロートは荒海の日本海から波穏やかな瀬戸内海へ移っていく。 『兵庫丹波の山』は、 「白鳳十二年(684)丹波の一部を割いて但馬と二国に分割、同十三年能勢郡を割いて摂津国に編入、更に和銅六年(713)五郡を割いて丹後国。…豊かな鉱物資源(武力にも財力にもなる)を背景にした強大な丹波国の一面を見る。実際に歩いてみても、いたる所で古代の鉄(金属)の影を残していた。丹波は朝廷をも脅かす程の資源大国だったと思われる。丹波の分割は異常といわれるが、和銅の分割は異常中の異常で丹波は完全に海を失った。」としている。 国府の地は後に日本三景の一とされる天橋立の付け根になり、すでに風土記にもみえて、名勝としても親しまれた。小式部内侍の「大江山生野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立」の歌は有名である。  荘園としては広隆寺縁起に薬師如来燃灯料として志高荘(舞鶴)、石清水別官として佐野荘(久美浜町)・板浪別宮(岩滝町)・黒戸荘(弥栄町)・平荘(丹後町)、宝荘厳院領志楽荘(舞鶴市)・八条院領大内郷吉囲荘(舞鶴市)などがある。 丹後国式内社は65座、うち大7・小58座である。 【中世】 丹後国衙は長徳元年(995)には丹後留守所になっていた。国分寺は鎌倉末期には存在していたことは丹後国分寺建武再興縁起や「丹後国田数帳」によってわかる。 中世の荘園としては西大寺領志楽荘、東寺領吉囲荘、久我家領椋橋荘、朽木家領与保呂村、長福寺領河上本荘、石清水八幡宮領鹿野荘等がある。このほか皇室領として吉田荘本家職が八条女院領、宮津荘・田村荘・久美荘等は長講堂領として見られる。  図の「田辺竹辺城」はこの位置でなく、建部山と思われるがそのままにする。(『舞鶴市史』より) ほかに有力城郭として加佐郡椋橋城、与謝郡亀山城、中郡吉原城、由良城、竹辺城、奥山城、八幡山城などがあった。各地の「市場」の成立もあるが、都市らしき機能はない。当国守護所も判明しないが、最末期は普甲山城、阿弥陀峰城、弓木城あたりかと推定されている。一色氏の末期には丹波から内藤氏、松永氏、赤井氏ら、海上から尼子氏、加悦谷方面から氷上郡の荻野直正らの軍事力が侵入した。 天正年代に織田信長の軍団が浸透し細川藤孝は八幡山城に入部し各地を平定し検地を実施、一色氏最後の当主を謀殺して丹後を制圧した(天正10年)。 鎌倉期に一遍が一時滞在して以降、時宗の隆盛が著しく、妙立寺を中心に教線を拡大し、日蓮宗・禅宗も民衆に浸透した。 【近世】 宮津藩領は京極氏以降藩主はめまぐるしく入れ替わり、天領―永井氏―天領―阿部氏―奥平氏―青山氏と支配が変遷し、宝暦9年(1759)遠江の浜松より本庄氏が入部し、以来7代ついで明治を迎えた。田辺藩は寛文8年(1668)京極高盛が但馬豊岡へ転封のあと、摂津より牧野親成が入封し10代を経て明治となった。峰山藩は京極氏(12代)で一貫した。 天領は但馬生野代官所、近江大津代官所、京都二条陣屋などに属したが、享保2年(1717)湊宮陣屋が設けられ、久美浜代官所となった。丹後にはそのほかに竹野郡・熊野郡の一部21ヵ村が但馬出石藩に編入されたことがあった。 産業としては、丹後ちりめんはその創業地は加悦谷地方と峰山町の2か所あり、いずれも享保初年に京都西陣から技術を修得したと伝えている。百姓の余業に始め機数は急速にのびた。しかし零細機屋で、糸問屋・親方機屋といわれる商業資本に依存していた。 沿岸漁業で、最も発展したのは伊禰浦3か村(日出・平田・亀嶋)や加佐郡田井村などの鰤漁場であった。伊禰浦では鰤網を中心に株組織がつくられ共同漁業の制がつくられた。 百姓一揆は宮津藩領が最も多く承応3年の算所村逃散をはじめ、天和元年の大飢饉に全領内の大庄屋が陳情訴願、正徳4年の大庄屋が団結して藩政改善訴願要求、文政5年の大一揆など゜がある。 田辺藩では享保年間の全藩一揆などがが発生している。 文化学術面では、医学者新宮凉庭、加佐郡由良村の出身で長崎で蘭学を学び天保10年京都東山に順正書院を開き多くの医学生を育てた。田辺藩の漢学者野田笛浦も文政に力を尽くした。宮津藩小林玄章は天野房成らと『宮津府志』を編纂、絵師佐藤正持を伴って丹後全体を踏査して『丹哥府志』を編纂した。与謝蕪村は宝暦頃母の郷里与謝郡宮津に寄寓した。 丹後国の主な歴史記録『丹後風土記残欠』 〈 丹波・旦波・但波、以上其文字皆、多爾波の訓である。 国の大体。首離尾坎東西壱百拾四里壱百参拾歩。南北七拾貮里壱百拾歩。東隣若狭国。西隣但馬国。南隣丹波国。北海に接す。 国中に所在の山川海野、其産する所の禽獣、草木、魚亀等は悉くこれを記すを得ず。但し其一二を郡毎の条の下に記す。(以下三行虫食) 郡合伍所 伽佐郡 本字笠 与謝郡 本字匏 丹波郡 本字田庭 竹野郡 今依前用 熊野郡 今依前用 郷合卅八 里九拾七 余戸 貮 神戸 四 神社合壹百卅伍座 六拾伍座在神祇官 七拾座不在神祇官 『丹後旧事記』 〈 此国分国なるが故に神社の郡違い多し国造以後の事を不知して撰集なしたる延喜式の誤なり或は大野の神社多久の神社揆枳の神社を竹野郡とし三重の神社を與謝郡に出せし也是皆丹波国の神なり。 和銅の国造は加佐郡より検地し竹野郡に終る依て竹野郡公庄邑に元明天皇(天智の女天武の母)を奉崇郡立大明神といわひ祭る。日本旧事記に曰く類聚抄に曰く当国の始め以て当国の造丹波に附す諾良の朝元明天皇の御宇類聚国史日本の朝歴史伝に曰く崇神天皇十年置四道将軍令治四方以谿羽道主命山陰置丹波国是四道将軍始也。 倭姫世紀に曰く大泊瀬桓武天皇廿一年丁巳冬十月(命夢教神社の部に出す依て中略す)丹波国余社の小見比治真名為ケ原に坐す道主の子八乙女奉斎御饌都の神(下略) 天正府志に曰く当国丹波郡は與謝、竹野の二郡を割て置し新郡なり今五ケの庄本箇の里に道主将軍の城跡有里民府の岡と云此里に御饌都の神天降る跡とて咋の岡といふ邑あり、又此所の西の山を咋石ケ嶽といふ、今是を久次か村久次ケ嶽と云は非なり咋の仮名也御饌都の神天降るの事日本紀神代の巻に宇気持神死る時の伝あり又崇神天皇の朝に豊宇賀咋の命天降有ける事は風土記元々集に委し延喜式に比治真名為の神社とあり神社啓蒙に比治比沼同事也とあり比治は土形の里の仮名書なり升富村の古名なり此里の西の峠を今に至り比治山峠といふ、又国名の事は風土記、類聚抄等の諸集に曰く当国篠村の東大江山の西の麓に大なる池有り一女此辺を過るに蛇有て是をのむ、夫此由を聞て其池の辺に行く再び大蛇出て夫ものむべくしけるを夫劒を以て蛇を斬る其血浪を染るを以て丹波の国と云也。源順曰く丹後といへる事は丹波の後と云心にて斯云也後の文字は北と云心なりとも聞ゆ国の字定らず。 古事記に丹波国と記す。倭姫世紀に但波と記す。本朝歴史伝に谿羽と記す。武備志二百卅巻目に丹哥国と記す国字諸集に不定、通俗用ゐ来るは丹波丹後なり。和名抄に曰く中管五郡国府加佐郡行程上七日下七日、源順和名抄に撰此加佐の国府ありけるが不知。》、4《延喜式に曰く丹後国年中元本の貢物廿四種(其品略之)。同書に曰く神社六十五座、内大社七座、小社五十八座。往昔丹後国は神田仏閣領多し丹波郡主基の里に正一位大宮売大明神従一位若宮売大明神と號る神社あり、此神は当天降の二神にして延喜式の大社也、崇神天皇治天下御世依勅諚田を定む。職員令に曰く正一位の神は地方八十町四方を給るの法例にして則二千石の領名なり従五位の下は八町四方の格にして二百五十石を給るの領名なり六位以下の神は切米なり王代の掟如斯なる丹波郡主基の里は四千石の神田あり。 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2015 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||