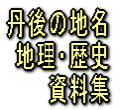 |
長谷(ながたに)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷の地誌《長谷の概要》 長谷は舞鶴市の西部。由良川左岸に位置する。由良川支流岡田川のそのまた支流長谷川の最上流域。上漆原の枝村であったが明治4年に分離した。宝永6年より上漆原村の枝郷。「享保郷村高附」に「上漆原村枝郷長谷」と見え村高記載なし。以後幕末まで書上げがなく、「旧高旧領」に至り、「長谷村 32石余」と見える。 「丹後国田数帳」には与佐郡宮津荘内に漆原名が見える。古くは与謝郡宮津庄に属したものと思われる。 長谷は車でなら上漆原から入ることもできるが、八戸地からも入れる。 長谷村は、江戸期〜明治22年の村名。長谷は明治22年〜現在の大字名。はじめは岡田中村、昭和30年加佐町、同32年からは舞鶴市の大字となる。 《人口》14《世帯数》9。 《主な社寺など》 日吉神社 岩鼻神社  集落北東約二キロの長谷川をさかのぼった谷間、小字大谷に長谷日限地蔵尊が祀られている。長谷公民館前から登れる。ここは宮津に通ずる巡礼路にあたり、田辺から中山村の渡船場に出、対岸和江村に渡り、国分寺谷に入り同地蔵尊の前を通り、上漆原村を経て宮津に出たという。地蔵尊(像高四〇センチ)は南北朝期の作と推定され、伝承によれば江戸時代百姓井平が耕作中発見し祀ったという。彼はたくさんの子供を抱えそのうえ妻がまたも身ごもったので、三日中に水子になることを祈願して願がかなえられたと伝える。それ以来日限の地蔵として崇められ、難病治癒・子宝・良縁その他の祈願で賑い、現在も参詣人が絶えない。  《交通》 《産業》 長谷の主な歴史記録《注進丹後国諸荘郷保惣田数帳目録》〈 一 宮津庄 百五十五町三百十二歩内 百七町九百八十歩 等持院 十三町四段二百四十一歩 栗田村御料所 此内一町一反三百六歩永不 十五町九段三百十五歩 壇林寺 七町五段二百八十九歩 同領公文分 七町五段二百八十九歩 公文分 延永左京亮 此内一町八段二百八十三歩 本不作 二町五段七十四歩 漆原名 同人 《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 長谷長野室鎌倉都而漆原と云う 地福山天然寺浄土宗、本寺田辺町浄土寺末寺なり。白髭大明神社二ケ所これ長野村(室)鎌倉の氏神なり、山王権現長谷の氏神なり。上漆原の郷民薪を採り同国宮津の城下に運び商なり。下漆原村山王権現社あり。 《丹哥府志》 〈 【山王権現】 【付録】(祇園社、薬師堂) 《加佐郡誌》 〈 =伝説など= 《ふるさと・岡田中》 〈 長谷日限地蔵尊は国道一七五号線岡田由里から十二キロ、八戸地入口より十キロの地点に長谷の里があり、更に約二キロ入った小字大谷にある。 平安中期に西国三十三か所霊場が選定されたころ、この山道が宮津への往還に使用されるようになり、旅人達の中には旅に病み、時には重病にかかって一命をも失った人もあったことであろう。 俳人高濱虚子の「道の辺に阿波の遍路の墓あはれ」の句の通り、長谷地蔵尊も或はこうした人の供養の石仏とも思われる。 この地蔵尊について口伝は二百余年前、長谷の住人井平某が田普請をした時、偶然にも堆積士の中から地蔵尊を発見し、早速近くの椿の根元に安置して供養した。その後、井平某は日頃の苦しみが安らぐよう一心に祈願したところ、満願の三日目に御利益があったという。 それから誰いうとなく日限り地蔵さんと崇めるようになり、方々で難病が治ったとか、子供を授かったとか、良縁を得たとか……。そして、第二次大戦のころは、愛児や夫の武運長久を祈る熱心な軍国の母や妻の姿、お詣する人がひきも切らぬ有様であった。最近では交通事故の補償問題が無事解決できたと、遠方より御礼詣りの人が見えるようになり、口から口へと伝っていった。 大戦末期には舞鶴海軍軍需部要員三、四十名が籠堂付近の田に宿舎として、簡易小屋を建て木炭生産のために駐屯し、また、由良か岳に航空監視哨を作るため、栗田海軍航空施設部兵員が、谷間に簡易兵舎を建てて駐留したことがあった。これら兵士は北は北海道から南は九州までの召集された兵隊であったので、終戦になって郷里に帰り、お蔭のあるあらたかな日限地蔵尊のことを言い伝えた。近年、北海道から郵送で願いごとをしてくる人々や、北九州、四国からはるばる家族でお詣りした人の名が参拝者名簿に記されている。こうして日限り地蔵尊の信者は全国に跨がり、更に広がりを見せている。 現在の地蔵堂は以前の本堂と籠堂に、昭和十年七月地元の人達の受託によって、舞鶴市の宮大工依田萬吉が建立に当たり、間口三一○センチ、奥行四五五センチ、お厨子は六七センチ従来の本堂がそのまま利用されている。籠堂は本堂より早く昭和八年七月、同字の大工泉某と村人達によって改築されたものである。 お祭りの当日七月二十四日には早朝からはるばる参詣する善男善女が列を作ってひきもきらず、お守りやお札の受け渡しの当番は休む間がないほどである。 信者の作といわれる 御詠歌 里も過ぎ山路を行きて長谷の 仏を頼む身こそ安けれ (地元参詣のしおりより) 《丹後路の史跡めぐり》 〈 大川橋から約十二キロ、大谷山の中腹に高さわずか三〇センチばかりのお地蔵さんがある。平安時代に道中の安全を願って建てられたと伝え、 かたわらに椿の木のあったところから椿地蔵ともよぶ。このお地蔵さんは日を限って願をかけておまいりすると必ず願い事をかなえてくれるというので「日限地蔵」とよばれるようになった。戦時中は「武運長久」を祈る人々が列をなしたほどで、出征兵士を出したことのある家族ならおまいりした経験が必ずあるはずである。当時の武運長久といえば公然とは口に出せなかった戦死や戦病死をせずに無事に帰ってきてくれということであった。いまは時代が変って安産、良縁、病気の平癒、交通安令、大学合格等を願かける人々でにぎわっている。また岡田上の頼光鬼退治ゆかりの大侯太妓と地頭太鼓は市の無形文化財に指定されている。 《舞鶴の民話1》 〈 大川橋から約十二キロ、緑につつまれた大谷山の中復に、高さ三十センチばかり、お地蔵さんがある。平安時代に道中、安全を願って建てられたと伝えられ、傍らに椿の木があったことから、椿地蔵ともいわれた。 このお地蔵さんは、日を限ってお参りすると、必ず願いごとがかなえられるというので、いつの間にか日限地蔵と呼ばれるようになった。 戦時中は「武運長久」を祈る人が列をなし、舞鶴の人で出征兵士を出した家なら、一度はお参りの経験があるだろう。 現在は安産、良縁、病気祈願、交通安全、受験合格などの願いをかける人々でにぎわいを見せている。 《舞鶴市民新聞》 〈 仏教の仏・菩薩のなかでもっともひろく親しまれているのは地蔵菩薩です。このような地蔵信仰の広がりのもととなったのは、平安時代末期の末法思想や、そこから発展した浄土信仰とされます。こうして生み出された地蔵信仰が、日本の津々浦々にひろがつたのは、念仏聖(ひじり)、高野聖、熊野聖などの遊行僧、なかでも山伏修験僧の動きによるとみられます。 天然寺の願かけ地蔵が、背中に負われるというかたちをのこしているのは、民俗学では、江戸時代にひろがったといわれる「廻り地蔵」のひとつと思われます。 それに対して長谷の地蔵は、中世の山岳信仰を背景にした「ヒジリ」系の地蔵であろうと思われます。現在は「長谷日限(ひぎり)地蔵尊」とよばれ、霊験あらたかな地蔵として、舞鶴市内外に名が高く、全国各地にも熱心な信者のひろがりをみせているとききます。 天然寺を出てすぐ下、道路わきの「長谷日限地蔵登口」の立て看板から左へ入る道は、長谷を通り、八戸地(はとち)に通じる旧道です。八戸地側にも同じ立て看板がたてられています。 この道の中間地点の長谷公民館前で車をおり、「是より2K先」の看板を左にみて歩きはじめます。 山道を登りはじめてすぐ薬師堂があり、参拝者のための杖や雨傘がおかれています。お堂のそばには、二十数基の石仏や板碑が集められています。ほとんどが中世のものと思われ、この道が古道であったことをしのばせます。ここから残りの道程を示す標識にはげまされて、緑におおわれた山道をたどります。 道ばたの岩のくぽみのそこここに、自然石に前だれをつけた「お地蔵さん」が祀られていて、心の痛みか信心の深さか、まつった人のひそやかでひたむきな祈りが、ひしひしと伝わってきます。 「あと三百米」。すすむにつれて谷川の瀬音が高くなり、地蔵堂へわたる橋がみえてきます。 地蔵堂は、深い谷を横に山を背に、こもり堂と並んで建っています。堂は、参詣の人びとの供献物であふれ、柱といわず天井といわず、堂内は地蔵にかけられた願い事と名まえで埋めつくされています。何冊もおかれたノートにも、無病息災や商売繁昌を圧倒して、合格祈願の文字があふれています。私は、きびしい競争社会の一面をみる思いがいたしました。 竹筒にあふれるばかりに生けられたコスモスの花。堂前の広場は手入れがゆきとどいていて、遠足をかねた人たちにも、格好な休けい場所を提供しています。長谷は、享保三年(一七一八)の領中郷村高付には、上漆原の枝村とあり、農林業のほか竹細工がさかんであったといわれ、長谷川にそって「宮津の道」があり、小字大谷の長谷日限地蔵は、この宮津に通ずる巡礼路でした。 また、田辺からは、中山村の渡船場に出て和江(わえ)にわたり、国分寺谷をさかのぼって、日限地蔵を通り、上漆原をへて宮津へ出たといわれます。 日限地蔵は、「江戸時代に、井平某という人が耕作中に土中から掘り出した。彼は子だくさんで、妻が身ごもったとき、三日のうちに水子にしてほしいと祈ったら願いがかなえられた。そのことから『日限り』の地蔵といわれるようになった」と伝えます。 中世、宮津道の峠に、ヒジリによってもたらされた地蔵が、江戸時代になって、水子という悲しい「現世利益」にもこたえる仏として、人びとの中に位置づいていったものと思われます。 長谷の小字長谷 森 大谷 滝 宮ノ谷 岩鼻 竹ノ下 上路 コガイナ 中ノ奥 ジャラ 和ケ内 大松 《ふるさと・岡田中》 〈 上漆原より長谷に向かい、家路に入ると立派な公民館がある。前に記念碑も建てられ村の中心地で中地と呼ばれ上地、下地、奥地等みな中心地を基にして名付けられた地名である。下地に当たる所は堂の下とも言う、公民館前より日限地蔵尊に至る大谷道または地蔵道の傍に古くから、お薬師様のお堂があり、その下に当たるので堂の下と言われるのであろう。 中心地から長谷滝に向って下がると、日吉神社の前に出る、宮の下・宮の前・宮の谷等の小字があり、いずれも日吉神社を中心につけられた小字の名称である。なお隣に岩ケ鼻があり、日吉神社は元岩鼻神社と呼ばれていたので、この神社と関係のある名称に違いない。 公民館の上手には栃谷・青杉・柳谷等あり長谷開作当時にその地に多かった樹種により命名し、ロクロは集材にロクロを使ったものと思われる。 長谷日限地蔵尊に向って大谷道をいくと、長迫・双迫があり、深い谷を長迫二つの谷が一つになった迫を双迫といい、山陰にかくれて見にくい谷をカクレ谷、地蔵尊の手前の谷がタカノ巣、鷹が巣を作っていたのであろう。地蔵さんから谷は二つに分かれて由良か岳に上ぼる。右が大谷左が大迫、大迫は真奥とも呼ばれ大谷とともに八戸池川の原流をなしている大きな谷である。 関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007-2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||