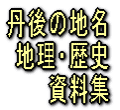 |
夏間(なつま)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏間の概要《夏間の概要》 由良川の右岸に位置して、加佐郡の一番天田郡より。 「なつまのむら」は鎌倉期に見える村名で、丹後国のうち。元亨元年(1321)9月3日付の尼きやうぐわん譲状に「たんこのくにかわもりのしやうかた、ならびに、なつまのむら一ふんはう」と見えて、尼より養子平賀三郎兼宗に譲られている(平賀家文書・大日古)。 夏間村は江戸期〜明治22年の村名。天正8年細川藤孝・忠興領、慶長6年より宮津藩領、元和8年一部が田辺藩領となった。享保2年宮津藩領は幕府領となった。 由良川に沿って在田村界に至る長さ52間の大雲川堤がある。 夏間は明治22年〜現在の大字名。はじめ河東村、昭和26年からは加佐郡大江町の大字、平成18年からは福知山市大江町の大字。  《夏間の人口・世帯数》287・86 《主な社寺など》 五宮神社(ごろみやともいう) 檀那寺は南山の真言宗観音寺。 《交通》 府道舞鶴福知山線 《産業》 夏間の主な歴史記録《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 これ領地の境なり宮津、田辺の知行を分け挿引をたまいたる所なり、五の宮は氏神毘沙門堂あり。 《丹後国加佐郡旧語集》  〈 夏間村 高六拾九石四斗五升 内壱石三斗壱升三合 万定引 八石御用捨高 五ノ宮 氏神 毘沙門堂 《丹哥府志》 〈 【五之宮明神】 【付録】(春日の社、三宝荒神、若宮、愛宕、毘沙門堂) 《大江のむかしばなし》 〈 一夜の宿をとるがために、ある農家へ、 「泊めてくれえ」ちゅうて言うちゃったんらしいですな。 ほいたら、 「泊まってもらおう」ちゅうて。 ほいてしとって泊めてはもろたんやけど、ほいたところが、こんだ朝出るときに、その時分やったら一文、二文言いよったんらしいが、その時代に、持っとる金が。出がけにこしらえして出ろうと思たら、「あ、金がない」ちゅうようなことで、おかしいなと思たけど、なにげのう旅に出ちゃったんそうですわ。 ほしたら、そのあとは、そのお家はどうやら栄えるなりしてからに、ほうして、その悪いことしたっていう供養のためにか、お地蔵さんを建てちゃったっちゅう話を聞いとりますわいな。自分とこの畑の地先にな、建てちゃったんですわ。 (注)この地蔵は四十年の大水で倒れたので、現在、府道の横に立っているという。 夏間の小字夏間(ナツマ) 中山 森 猪ノ奥 大久茂 大谷 昼ケ谷 宮ノ谷 上嶋 座入 平 深田 上路 丁田 安場 金剛院畑 雲部 麻町 瀬ノ爪 関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『大江町誌』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||