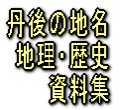 |
下福井(しもふくい)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下福井の地誌《下福井の概要》 下福井は西舞鶴の西部。西舞鶴港の西に位置する。北は舞鶴湾西港に面する。南部に山を負い、北部に臨海工業地帯と第4埠頭がある。東西に通る国道175号線(宮津街道)に沿って官公署・住宅・商店および農家が混在する。府道由良金ケ岬上福井線を北へ分岐する。 愛宕山の北麓はすぐ海が迫っていたという。海岸沿いに道が開かれるまでは、引土村から愛宕山の鞍郭を通って当地に出る山道が使われていた。という。 公設地方卸売市場(舞鶴合同青果)、舞鶴港湾合同庁舎、大阪検疫所・神戸植物防疫所・近畿海運局・大阪入国管理事務所・第8管区海上保安本部・舞鶴海上保安部・舞鶴海洋気象台・近畿農政局舞鶴統計情報出張所、舞鶴湾工事事務所などがある。 南部の山腹丘陵地には一般住宅・市営住宅・大野辺団地がある。大野辺地区の無常院跡には幕末の田辺藩家老で儒者の野田笛浦の墓がある。 西北の宮ノ上山地区に座尾(蔵王)峠があり、一色氏の臣福井藤吉郎が拠った福井城址がある。 昭和41年から舞鶴湾改修工事で地内の大野辺一帯が埋め立てられた。 下福井村は江戸期〜明治22年の村名。同22年四所村の大字。昭和11年舞鶴町、同13年からは舞鶴市の大字。明治27年四所村新宮の一部を編入。 《人口》509《世帯数》192 《神社など》 和泉神社(伊都美神社) 八幡神社 鎮守神社 八坂社 福井小学校 《交通》 下福井の主な歴史記録《丹後国加佐郡寺社町在旧起》〈 和泉大明神両福井村の氏神なり。 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 下福井村 高二百九拾三石八斗八升 内二拾石御用捨高 和泉明神 福井上下ノ氏神 当村土橋際二軒家中下福井分也 当所と喜多村の間に有る山を建部山といふ 是を田辺富士山と云ならハす 高山なり八分目に小池あり雨強き時は水谷江流れ滝を見るが如し 下福井ヨリ川口江越道難所蔵王峠と云 峠の上に到れハ建部山絶頂も近く見ゆる也 村ヨリ無常院迄を大野辺と云見渡す所を四所か浦と云又九景か浦ともいふ 此所愛宕江上る道もあり 無常院 見樹寺派下 延宝年中順昌卜云道心此所ニ草庵ヲ建元禄年中ニ 一寺建立常念仏ヲ筆ム是開山也 元禄七甲戌年二月 十五日導師見樹寺船誉上人 《丹哥府志》 〈 【和泉明神】 【建部山】(出図) 【足利泰氏の城墟】 日本史に東鑑を引て曰。足利義氏の子足利泰氏丹後守に任ぜられ宮内少輔に遷る、素より遁世の志あり建長三年剃髪して僧となる、文永七年卒す平石殿と称すると云々。是を一色氏の祖とす、加佐郡建部山に城郭を築き代々是に居る。祖父の義康は鎮守府の将軍源義家の孫式部大輔義国の長子なり。兄を新田義金といふ。泰氏に八男子あり、其四男一色宮内卿公深家を嗣ぐ初て一色氏を冒す、次を一色次郎範氏といふ、次を一色左馬の頭修理太夫範光といふ。建武三年正月足利尊氏兵を率ひて京師に入る、楠公の為に敗走して西国へ遁る、是時一色範光之に従ふて西国に下り菊池の兵と戦ひ之に克つ、遂に八代の城を落す、於是九州の兵皆尊氏に属す、此歳の五月足利尊氏西国の兵を率ひて再び京師に入らんとす、湊川に於て楠公と戦ひ楠公遂に討死す、一色範光尊氏の為に功ありといふ(丹後旧記に建武三年一色範光初めて丹後に封ぜらると云は誤なり)。次を一色兵部少輔詮範といふ、嘉慶三年山名氏清の為に押領せらる、よって姓名を吉原左京太夫詮範とあらため城を丹波郡吉原に築き山名の陣代となる、居焉四年其子一色修理太夫満範と同じく山名氏清を討てこれに克つ、明徳三年一色修理太夫満範再び丹後に封ぜらる、於是吉原城より又建部山の城に帰る。次を一色兵部少輔義範といふ、将軍義宜公に従ふ、永享元年伊勢の国司北畠氏と戦ひこれに克つ、嘉吉三年洪水陵に登る、国人殆ど餓ゆ、義範これが為に貢をゆるす、是時の觸書加佐郡志楽の庄の民家にありと順国志に記す。次を義直といふ、応仁年中山名宗全に属し御敵となる、永正五年七月九日卒す竜勝寺殿天?衍公大居士、加佐郡行永村竜勝寺に葬る、義直の長子義春応仁の乱に討死す、よって義直の弟義遠の子義季を以て嗣子とす、義季始め一色松丸といふ左京太夫といふ、永正四年若州の国司武田大膳太夫元信と成相山に戦ふ、是時小笠原澤蔵軒討死す(天橋記に永正年中に武田元信と成相山に戦ふを一色義有とす、然れども義有といふもの系譜に見えず、永正の頃は一色五郎義季の代なり、後に左京太夫といふ丹後の守松丸といふ、足利義昭公に従ふて若狭越前に赴く人なり)。丹後旧記に曰。義季より以下義俊に至る凡四代其間一百余年、是時に当りて八十五ケ處の城塁あり、皆一色氏に属すといへども或は従ひ従はざるものも亦あり、多くは足利の諸将遁れて丹後に来るものなり、是を以て義季より以下丹後の国主とせずと云。次を左京太夫義幸といふ、次を左京太夫義道といふ(義道一に義通に作る)天正五年冬十一月細川藤孝将軍信長の命を以て丹後に入る、一色義道是と戦ふ、一色の随将小倉播磨守、野村将監、河島備前、井上佐渡守、小倉筑前守、日置弾正、仝小次郎、千賀常陸介、仝山城守等追々馳集り細川藤孝殆ど危し、於是救を明智光秀に乞ふ、明智光秀使を日置の城主松井四郎左衛門及算所の城主有吉将監に嘱す、是より藤孝に属する者多しよって遂に克つ事を得たり、翌年の春正月廿日建部山城落城、一色義道中山村に走り其臣沼田幸兵衛の城に入る、仝廿四日中山村を出て討死す、其子五郎義俊中山より遁れて与謝郡弓木の城に篭る、細川藤孝数々是を攻めけれども克たず、仝十年義俊故ありて田辺の城に於て死す先是義道の弟吉原越前守義清吉原にあり、姪義俊の死するを聞て吉原より弓木の城に移り細川藤孝と戦ふ仝五月廿八日義清宮津に於て討死す、於是一色氏坊ぶ、足利泰氏より義俊に至る凡十三代、其年暦殆ど三百五十年。 或の説に、一色の本城は今の田辺なり、田辺の城細川藤孝の草創にあらず、といふ。然れども(一色の末葉といふ者の記録に建部山を以て一色の本城とす今之に従ふ抑も天保武鑑に一色の本城は宮津にありといふ蓋一色義俊建部山落城の後弓木の城によるこれを以てなり)吾丹後に城跡と称するもの凡八十五ケ處皆山城にて一も平城ある事なし是元亀天正以前は山城なりと見えたり、信長公起りてより城郭なり甲冑なり刀釼なり凡天下の武備一変せり、吾丹後も亦然り、細川藤孝の来りてより皆平城とぞなりぬ。 【付録】(八幡宮) 《加佐郡誌》 〈 下福井の小字下福井 黒崎 井根口 中田 家奥 平方 後反 見安 円満寺 座尾 後山座尾 大野辺 新宮 五斗 門畑 向山 後山 宮ノ谷 山ノ神 宅奥 関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||