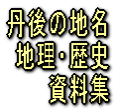 |
下見谷(しもみたに)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下見谷の地誌《下見谷の概要》 下見谷は舞鶴市の西部。由良川左岸に位置する。岡田川の支流下見谷川流域。「慶長郷村帳」「享保郷村高附」には河原村枝郷として見えるが村高記載なし。「旧高旧領」に至って、下見谷村と見え、村高は42石余。明治4年に1村として独立する 下見谷村は、江戸期〜明治22年の村名。下見谷は明治22年〜現在の大字名。はじめは岡田中村、昭和30年加佐町、同32年からは舞鶴市の大字となる。 《人口》53《世帯数》20。 《主な社寺など》 茶ノ木原地区に下見谷神社 寺尾地区に寺尾神社 《ふるさと・岡田中》  〈 当社は下見谷小字茶木原に鎮座する。 祭神 金山彦命 創立は非常に古く、天長六(829)年九月と伝えられる。かつては下見谷全域の氏神で、下見谷が香良と行政区を共にした当時は、これ等全域の氏神として尊崇を集め、古えは大峰八大金剛童子社として、丹後風土記等に紹介されている。 境内面積一千八十坪、氏子数十八戸、社殿は流造型で上屋・篭殿・鳥井・手水舎・狛犬等あり、岡田中一といわれる大石灯篭がある。 大峰八大金剛童子社は名前り通り、山嶽信仰が盛んであった時代は、大峰権現の流れを汲む回国の行者、役小角等の指導を受け天地の接点に、地域の高山である赤岩山に権現様を祀り赤岩権現と称し、頂上付近に規模は小さいが大峯山を真似た行場を作り、訪れる山伏の修行の場とし、女人禁制の霊場を築いた。当時が最も隆昌をきわめた時代で、今も大峯八代金剛童子社の幟が残っている。  例祭日は古来から旧暦九月八日を例祭日としていたが、太陽暦の採用後、十月八日に改めた。当番は例祭の前日与謝郡栗田村の七つの浜で日本海の荒波に向かって禊を執り、斉戒沐浴して神事を行った。これを七浜の清祓行事と云う。神饌田で収穫した新米で赤飯を炊き枡に盛り供えて神事に入る。今も古色豊かな神事が行われている。摂末社として北方の小字源蔵には地主荒神と称する不動明王、南方に大城宮と称する天神さん、東方の講田には才の神、西方に境内社として毘沙門天をそれぞれ祭り、下見谷神社の四方を守る末社としている。才の神は天然石を以って御神体とし、傍に藤の古木があり、幹が腐り皮許りを残した藤は才の神の神木として大切にされている。境内社の毘沙門像は高さ約一メートルの木造立像、いかめしい武人の姿に年代を感じる。 《交通》 《産業》 下見谷の主な歴史記録《丹哥府志》〈 【金剛童子】 【付録】(毘沙門堂、蛭子社、天王社、祇園社、地蔵堂) 《加佐郡誌》 〈 応徳元年久田美村の城主村上陸奥守岡田庄を配して、猪熊村、熊之美(見)村とし、猪熊村は又字由里、西方寺、富室、漆原の四字に分ち、熊之美村は地頭、大俣、高津江の三字に分った。所が寛治元年に改めて、由里村、富室村、西方河原村、下漆原村、上漆原村の五箇村を以て猪熊村を配する事とした。そして後更に仁治元年西方寺村の内字河原、下見谷、寺尾を以て河原村と称し、一村を配する様にしたのである。 伝説など 《ふるさと・岡田中》 〈 四道将軍日子座王に追われた、陸賀耳御笠(士蜘蛛童子)は、志託の戦で潰滅し、由良石浦の地に上陸して与謝郡と境の大山に逃げた。石浦、和江、八戸地の何れから逃げこんでも、漆原の地に辿りついたことであろう。 日子坐王は源蔵人を将として、四名の若武者を撰び追跡させた。選り抜きの屈強な若武者に追いたてられた土蜘蛛は、漆原の地に落ち着くことができず、下見谷に逃げ込んだが、追跡の手はいよいよ厳しく、童子は遂に赤岩越えを決意し再び山入りを試みた。追いつめられた土蜘蛛童子は、赤岩山のゴラ場に逃げこんだ。ゴラ場は家のような大石から小石まで、累々と積み重なっていて、樹木も育たぬ石ゴラの原で独特の奇観を呈しているところである。さすがの若武者も彼等の姿を見失い取り逃してしまった。岩場はもちろんのこと付近の山中もくまなく詮索したが、杳として足取りをつかむことができなかった。 源蔵人は疲労も加わり病のため整れてしまった。やがて、土地の人はこの地を源蔵と呼び、長く蔵人の武威を偲ぶことにした。他の四人の若武者は土蜘蛛を退治する目的は達したものの、その首級を取ることのできなかったことを面目なく思って、都に帰ることを断念し、野に下ることを決意した。四人は、姓に田の字を入れる約束をして土着したので、太田、河田、池田、藤田等の姓が当地に残っているのはこの勇士の末裔ではないかと言い伝えられている。 この事件が一段落すると、次の歌がどこからともなく伝わった。 往き帰り 三葉宇津木は 左り側 根元に眠る 黄金千両 この山のどこかに黄金が埋めてあるというのである。山仕事に出掛ける里人の夢はふくらんだ。黄金を埋めたのは土蜘蛛童子だろうか、源家の武士だろうか。まだ黄金は見付からないが、村人たちの働きによって立派な山があちらにもこちらにもできたという。 《舞鶴の民話5》 〈 若狭から丹後にかけて、住民を苦しめていた青葉山中に住む陸賀耳御笠(土蜘蛛童子)は、置将軍の日子座王の軍との志託の戦で、さんざん敗れ、散りじりになってしまった。残った童子と数名は由良石浦の地に上陸して、与謝との境の大山に逃げた。石浦、和江、八戸地のどこからか逃げこんで漆原の地にたどりついた。 日子座王は、残党が再び勢をもりかえすことを恐れ、源蔵人を将として、四名の若武者に追跡を命じた。選りぬかれた武芸達者な若武者に追われた土蜘殊は、漆原の地に落ちつくことは出来ず、下見谷へと逃げこんだが、ここでも追跡がきびしく、赤岩越えを決意した童子は山入りを試み、赤岩山のゴラ場へと逃げこんだ。ゴラ場は石の多いところで、五米もある大石や小石がつみかさなって、草木も育たぬ石ゴラの地で、かくれるのにはいい所であった。若武者たちは、童子の姿を見失い取り逃がしてしまった。あちこちと岩場や付近の山の中もくまなくさがしたが、足取りはつかむことができなかった。 源蔵人は、疲労が重なったため斃れてしまった。その地を村人たちのために戦い死んだ蔵人の武威を偲ぶために、源蔵と呼ぶことにした。四人の若武者は土蜘妹を退治する目的に達したものの、童子の首級を取ることができなかったことを面目なく思って、都へ帰ることを断念し、野に下ることを決意した。四人は、姓に田の字をいれることを約束をして土着した。太田、高田、池田、河田等の姓が当地に残っているのは、この勇士の末えいでないかと伝えられている。 又この地方に次の歌が伝わっている。 往き帰り、三葉宇津木は左側 根元に眠る 黄金千両 赤岩山のどこかに、黄金が埋めてあるのだろう。里人の山いきに夢がある。黄金は土蜘妹がうめたのだろうか、源蔵人一行がうめたのか、さがしてみるが未だ黄金はみつかっていないが、立派な樹木の山があちこちできた。 下見谷の小字下見谷 宮前 矢谷 矢谷口 石切 二ツ石 小滝谷 大滝谷 西谷 下栃 上栃 三本松 柴尾 別当 梅谷 大城宮 地主 講田 上ノ田 入道 長畑 源蔵 荒田 後ケ谷 木戸 寺尾 茶ノ木原 《ふるさと・岡田中》  〈 日子座王の伝記に依ると、陸賀耳御笠という土蜘妹、由良石浦の地から当地に逃げ込み、日子座王は蔵人と若武者に追跡させたが、赤宕山のゴラ場で見失った。年長の源家の蔵人も疲れて斃れ、この地を源蔵と呼称するようになったと伝えている。 下見谷は大別して、下見谷、中村、寺尾に分かれ、下見谷は後ろが大山であって、下の方だけが見える地勢なので下見谷と呼ばれ、寺尾は恵比須神社の古宮の跡地が恵比須堂という地名で残されている外、この古宮も当時は神仏混交の社で、寺院のようなたたずまいを持ち、この御堂のあった山麓が門前町のような形で発達し、寺尾の始まりと思われる、下見谷と寺尾の中間が中村である。寺尾の矢谷は狩猟に使う矢竹の生産地で、石切、二シ石等の地名は採石場の跡地であろう。 出合は下見谷道と西方寺平への道の交叉点を出合という。滝谷は下見谷の大滝がこの地にあるのでこの名称が生まれ、修験者みそぎの場といわれている。西谷、東谷は所在地により名付られ、大谷、大迫は大きな谷や迫と言う意味で土地の人には一番分かり易い名称である。木戸は昔木戸番所の置かれた処で、この地の裏側上漆原にも木戸の地名あり、界の峠道に木戸即ち番所があったものと思われる。寺尾に樋ノロと言われる所がある。寺尾の水田に用水を引いた処であろう。 関連項目 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007-2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||