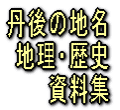 |
魚屋(うおや)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚屋の地誌《魚屋の概要》  西舞鶴市街地中央部の一番海寄り。東部を伊佐津川、西部を高野川が北流しその河口部である。静渓川も高野川に合流する。住宅・会社・工場・商店・旅館・医院などが混在の地域である。 明治41年から大正2年の伊佐津川尻付替、地先の埋立地を、その改修に功あった大森鐘一京都府知事にちなんで、大森町と命名した。現在も魚屋大森・大森海岸と称している。国鉄舞鶴港線が北部を東西に貫通していたが、今はその跡地に湾岸道路を建設中。国道27号が東から南へ走り、国道177号を北へ、国道175号を西へ分岐する。 田辺城下の魚屋町で、細川時代から地子銭免除の町屋であった。魚屋町は、江戸期〜明治22年の町名。田辺城下の1町。 田辺城の西北にあたった町屋で、北は中洲に囲まれた入海、東は外濠に面し、北部には広小路が東西に走る。広小路を東行、堀割に架かる伊織土橋(もと魚棚橋)を渡ると辻番所、米蔵があり、さらに船着門の前を過ぎると水門に架かる高橋(もと伊織橋)があって、馬場でもあったはりのき縄手に通じていた、という。 享保12年の丹後国田辺之図による町屋は、南北123間・幅2間、家数90軒。寛保3年には魚屋町70軒・魚屋町吉原31軒とあって(竹屋町文書)、当町支配の町屋が吉原にも存在していた、という。幕末に当町の東端、外濠沿いに職人町が移転した。 明治2年舞鶴町に所属。同22年舞鶴町の大字となる。昭和13年からは舞鶴市の大字。  ↑(『ふるさと今昔写真集』より) 広小路通りは今は広くなっているが、戦争中に北側が疎開され拡幅された。 《人口》238《世帯数》98 《主な社寺など》 住吉神社 《交通》 国道27号線・国道175号線・国道177号線 魚屋の主な歴史記録《舞鶴市史》〈 《まいづる田辺 道しるべ》 〈 田辺城籠城図(慶長五年・一六○○)によると、御小人町(足軽)の町名が見える。その後享保十二年の城下大火災迄は漁師町と呼ばれていたが、その後は魚屋町に改名されている。 寺社町在旧記によると、漁師町は、東西二町に分かれ、沖の猟、磯の猟数十艘の船網引の釣たれ、取揚る肴は魚の店、問屋、中買、立会い時節相応の値段を定め売買する。 家数 九十軒(享保十二年) 魚屋町吉原三十一軒(寛保三年) 町長 南北一二三間(二二三メートル) 道巾 二間(享保十二年)(三・六三メートル) 魚屋の小字築地 大森海岸 魚屋大森 魚屋住吉関連項目【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||