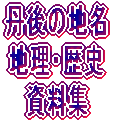 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与謝郡与謝野町・与謝郡伊根町 |
与謝郡の概要《与謝郡の概要》  「郡」という地方行政単位は、現在では死語になっていて、知らない人も多いと思われる。別に郡役所や郡会があるわけではなく、行政的は特には何も機能はない。 郡は古代律令国家の地方行政組織の一つで、国の下におかれた。古くはグンではなく「評」と書いてコオリと呼んだ。今でも「私はイカルガのコオリの者ですが、実はお宅の娘さんを…」等と正式に名乗りたい場合は使う人もあるとか。古代朝鮮語の大村すなわちクフルのことだろうと言われている。 もともとは中国の郡県制に淵源していて、日本での初見は『日本書紀』大化2年(646)正月条の「改新之詔」、いわゆる大化の改新だが、そのとき「凡そ郡は四十里をもって大郡とせよ。三十里以下、四里より以上を中郡とし、三里を小郡とせよ」とあり、このとき郡制が施行されたかのように記されている。 孝徳朝の649年(大化5)に評制が施行されて以来、金石文や木簡などの当時の史料から、7世紀の後半を通じて国の下の行政単位が一貫して評であったと確かめられている。評も郡もコオリと読まれたらしいが、郡は評を継承しつつ701年(大宝1)の大宝令の制定とともに始まり、「改新之詔」はそれにもとづいて後に作文されたものと考えられている。 「郡」と書くのは、正確には大宝令以後であり、それ以前は「評」と書いていた。聖典『日本書紀』に誤りありや否やと、有名な郡評論争のあったところで、この論争によって『日本書紀』の信憑性が大きく低下してしまった。舞鶴人の大好きな言葉でいえば、聖典から「偽書」に転げ落ちてしまった。藤原宮出土木簡には、与謝郡は「与射評」、加佐郡は「旦波国柯佐評」と書かれていた、このように藤原宮出土の木簡には「評」と書かれていて、『日本書紀』という超一級史料ですら、木簡という一次史料に比べれば二次史料に過ぎないことを改めて示した。権力が勝手にでっち上げた自主申告の「歴史書」をそのまま信じる学者などはもうない、ということになるのだが…。 令の規定では、50戸よりなる1里(のち郷と改称)で20里以下16里以上を大郡、12里以上を上郡、8里以上を中郡、4里以上を下郡、2里以上を小郡として、各郡ごとに郡家とよばれる役所を置き、、郡司(大領・少領・主政・主帳の四等官)が政務をとったという。 和銅6年5月に、『風土記』の斤進が命ぜられたのと同時に郡郷の名には好字が使われるようになった。 郡家には政務をとる庁屋のほかに、正税を収める正倉、厨房としての厨家、納屋などのほか、旅舎なども置かれて、律令国家の地方行政の基礎単位として政治的・経済的に重要な役割をになったという。 郡の総数は奈良時代の前半で555(『律書残篇』奈良時代)、平安前期では591(『延喜式』927年)であった。9世紀から10世紀にかけては郡の分割が行われて、10世紀以降はさらに進んで郡的な機能をもつ郷、保、別名なども出現し、郡司の四等官制も廃されて、地方行政単位の細分化と地方豪族によるその所領化が進行し、郡家も多くは廃絶していく。  古代の与謝郡 古代の与謝郡藤原宮出土木簡に「与射評」と見えるのが早く、『日本書紀』雄略天皇22年7月条に「餘社郡」、顕宗即位前紀、仁賢即位前紀に「余社郡」。『続日本紀』和銅6年(713)4月3日条に「與佐」郡、同書宝亀7年(774)閏8月28条に「与謝郡」。天平10年(738)但馬国正税帳(正倉院文書)に「與射郡」。『釈日本紀』に「丹後国風土記曰、與佐郡云々」、『三代実録』元慶2年(878)3月23日条に「與謝郡」、『延喜式』神名帳、『和名抄』高山寺本に「與謝郡」などともさまざまに表記された。訓は『和名抄』刊本は「与佐」と訓じている。 今は与謝郡と書き、ヨサと呼んでいるが、ヨザとも呼ばれている。地名の意味については古来不明とされることが多い、発祥地も明確にしまいままに、豊受大神の天吉葛や海人と関係深いヒョウタンだという説などなども見られるが大変に苦しい説明ばかりである、日本語では意味不明ということであろうか。丹後は古い地で、日本語では解けない郡名は与謝ばかりでない、日本古代の先進地とは実はこうした所が多い。 宮津は宮津川流域および栗田半島一帯、日置郷は現宮津市日置より与謝郡北部全体、拝師郷は阿蘇海沿岸、物部・山田・謁叡郷は現与謝野町の加悦谷(通称)域、がおよその見当として考えることができるとされ、拝師・神戸・駅家以外には遺称地がある。神戸は名神大社大虫・小虫の鎮座地あたりに、駅家は勾金駅のあたりではなかろうか。 国分寺も天橋立を望む景勝の地、今の宮津市国分に建てられた。丹後海部直が祀る籠神社は天橋立の傍らにある式内大社で、のちの丹後国一宮である。 小式部内侍の 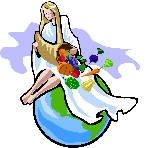 大江山いく野の道の遠ければまだふみもみずあまの橋立 内侍の今でいえば、小6くらいの時のものである、都の小学生でも知っていたことになる。 また「枕草子」は、「海はよさの海」と書いた。 平安時代の中葉を過ぎ、10世紀末〜11世紀前半のころには、郡が有した広範な権益は国衙に吸収され、国衙官人の統治が直接的に各郡内に及ぼされることになった。郡衙は広範な機能を失い、そして旧来の郡域そのものも、分裂・解体の過程をたどることとなった。 12世紀中葉を頂点とする荘園の設立・寄進の動向によって、新設の郡のうち、半数ほどは国衙の統治から離れて荘園として寄進・立券されていき、中央の貴族・寺社のもとに属することになった。 この結果、公領(国衙領)は大幅に減少して荘園は公領にほぼ匹敵する事態となった。その公領の部分にのみ郡が残存した。その公領でも別名など国衙直結の行政単位が郡から新たに分離・設定されるなどして郡の地位はさらに低下した。 鎌倉時代に入っても、国家の支配地としてはそうしたことであったが、地域社会においては「郡」の地位はそれなりの重みを失うことはなかったといわれる。 鎌倉御家人は郡を所領として給与され、その統治のために郡内に政所・公文所などの役所を設けた。地頭だけではなく守護も郡ごとに置かれることがあった。 守護大名・戦国大名は荘園制の枠組みをのり超えて領国の統一をはかるためにに、郡の行政機構を重視し郡代・郡使などの役人を置いた。 郡内の有力寺社は地域社会の中心として、人々の寄合いの場となった。南山城国一揆ように郡を拠り所とする人々の集団が中央の権力にたいして独立の勢いを示すこともあったという。 神戸・駅家郷は名も残さず、宮津郷は宮津荘となり他の郷は郷名こそ残しているがわずかで大部分は荘・保に移ったものと考えられる。 日置郷からは伊禰荘・筒川保、物部郷からは石川荘・大石荘、謁叡郷からは加悦荘などが分かれたと考えられる。 大きな荘は、「加悦庄 163町8段248歩 実相院殿」「石河庄134町5段330歩」。 与謝郡の末尾に「已上1190町5段29歩」とある、そのうち寺社支配地が、680町5段149歩と全体の半分以上を占める。その寺社のうち、等持院領「107町980歩」、常在光寺領106町8段74歩、実相院領163町8段248歩(以上三寺は山城国所在)、一宮領59町3段210歩、八幡領43町4段28歩、以上五寺社の合計が480町7段100歩となって寺社領全体のおよそ七割余を占めている。等持院は足利氏に関係の深い寺である。寺社領を除いた残りのおよそ半分が、幕府ないし守護一色氏料地・幕府奉行人・奉公衆およびこの地方国人層の所領、それに若干の国衙関係の土地である。 田数帳の時代には幕府権力ならびに中央諸社寺の荘園と武家方および国人層との抗争が中分・半済などのかたちで顕著にみられたのに対し、それより半世紀以上経過した御檀家帳の時代には、一色氏を中心として支配系統がずいぶん単純化されていることがわかる。荘園制が崩壊して新しい「むら」「垣」「段」という地縁結合体が生れ、「いちば」が広がりつつあるさまをうかがうことができる。しかしそのかたわらで、至る所に大城主・小城主がいて、一色氏との間に被宮関係を結び、地域支配権力として存在している。 天正13年(1585)に秀吉は古代以来の国家支配の枠組みを継承する路線をとって天下統一し、郡は支配・行政の基本単位とされるに至る。1591年の全国の御前帳(検地帳)と国絵図は国郡を単位としてつくられていて、豊臣政権の国郡制的国家支配の特質をよく示している。 江戸幕府もそのような古代以来の国郡制を幕末に至るまで継承し、郡は国とともに近世国家の行政・支配の根幹をなす単位であった。 元和8年(1622)高知死後はその子に丹後を三分し、与謝郡は宮津藩京極高広の領内に入っていた。 高知が慶長7年に実施した慶長検地によれば、与謝郡は52ヵ村、30462石余であった(慶長検地郷村帳)。 10%消費税となれば、それでは足りないとして20%までは最低もっていきたい政府与党野党どもだが、低所得者には実質27.6%以上の大増税となっておいかぶさり、選挙では隠して、日本の底辺は大破滅となるだろうかもの大増税であった。 加えて延宝8、9年は大飢饉で、延宝9年9月中旬、都合大数14086人の餓死人という有様であったという、総人口5万弱の中でであった、分母も分子も正確には明らかにならないが、総人口の30%程度の餓死者が出たことになろうか。(歴史が二度繰り返されねばよいが) そればかりでなく阿部時代になると領内は、政治的色彩の濃い組分けをされる。加悦谷を例にとると、ひとつの谷に連なっている加悦谷一七ヵ村は、田中組に四ヵ村、河守組に五ヵ村、温江組に八ヵ村と分断された。団結しないようにの分断策である。 『与謝郡誌』によれば、幕末期における宮津藩代官領含めて与謝郡の家数は百姓およそ7、900軒・城下町人1、180軒・武家830軒・ほか360軒・計1万270軒、人数は百姓およそ3万7、820人・城下町人6、230人・武家3、350人・ほか1、640人、計4万9、040人であったという。 明治4年(1871)の大区・小区制の下で旧来の郡は否定されたが、同11年の郡区町村編制法で行政区画として復活して郡役所と郡長がおかれた。 郡長は官選で府知事・県令の下にあって町村を監督し、もっぱら上命下達にたずさわった。当時郡長は警察とともに国家権力の象徴的存在とみなされていて、各府県会ではしばしば郡長公選が建議されている。 同23年の郡制公布によって郡会がおかれ初めて一応は地方自治体となったが課税権もなく、府県知事や内務大臣の強い監督権下におかれ自治体としては不完全であった。 郡会はその3分の2の議員を各町村会が選挙し、残り3分の1は地価1万円以上の土地を所有する大地主が互選でえらぶこととされていて地主層中心の議会となった。ヤシみたいな「議会」であった、こんなものに歳費を払う納税者はあほくさいの極限だが、しかし今もどの議会もこの推薦と互選の郡会議員と、実質的にはたいしては変わらぬ様子である、そうしたことではやがて死滅の運命か… その後、郡は若干の改良も試みられたが、自治体として不十分であったため地方制度合理化の見地から問題視されて日露戦争以後たびたび郡制廃止が議論の対象となっている。 大正12年(1923)4月1日郡制は廃止されて、郡は純然たる行政区画となった。さらに同15年7月に地方行政整備と地方財政緊縮の見地から郡長以下の官吏が廃止され、郡役所もそれに伴って姿を消して郡は単なる地理的名称となった。 郡は公職選挙法により衆議院議員選挙と都道府県議会議員選挙の選挙区編成単位となることもある。市町村行政の実態面からみると旧郡制時代の郡区画は依然として機能をある程度は残している。広域市町村圏などの市町村レベルにおける広域行政の圏域設定や府県庁の地方事務所の管轄区域など、おおむね郡制時代の区域に対応していることが多い。  与謝はフツー的にはヨサと読まれている、ヨザノブソンとかヨザノアキコとは言わない。しかし地元でこの地名はヨザと読まれることが多い。 与謝はフツー的にはヨサと読まれている、ヨザノブソンとかヨザノアキコとは言わない。しかし地元でこの地名はヨザと読まれることが多い。この車の所有会社も「よざ」としている。 与謝郡の主な歴史記録『大日本地名辞書』
『与謝郡誌』
『日鮮同祖論』
関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2012 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||