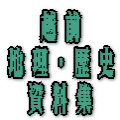 |
市野々(いちのの)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市野々の概要《市野々の概要》 国道27号(金山バイパス)の南側、粟野中学校や国名勝の柴田氏庭園があるあたり。 近世の市野々村は、江戸期~明治22年の村。市之野・市ノ野・市野などとも書いた。また、はじめは芝田村と呼ばれたこともあった(という柴田家文書)。当地はもとは金山村の田地であったが黒河川の洪水によって荒地となり、これを櫛林村の逃散田を開いた柴田権右衛門光有が開発し、寛文2年(1662)金山村枝郷となった。柴田権右衛門による開発は万治元年(1658)に田3反を開いたのを初めとして寛文元年に藩の正式な許可を得てから以降年々開発が行われ、同6年には田5町余・畑9反余、天和2年(1682)頃には村高84石余となった。その後も開発は継続して貞享3年(1686)の検地では田8町7反余・畑1町5反余、実高95石余で、この高はすべて柴田権右衛門1人が所持したという。はじめ福井藩領、寛永元年(1624)からは小浜藩領。 貞享5年(1688)の市之野高持百姓家内人数書に家数7(高持1・無高6)・人数26(男11・女15)。「敦賀郷方覚書」では「金山村之内市野々」とあり、家数7(高持1・無高6)・人数22(男12 ・ 女10),馬3。「雲浜鑑」では家数5・人数28。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。「滋賀県物産誌」に戸数10・人口41、産物は莚650束・菜種7石・縄15丸。同22年粟野村の大字となる。 近代の市野々は、明治22年~現在の大字名。はじめ粟野村、昭和30年からは敦賀市の大字。明治24年の幅員は東西3町・南北4町、戸数11、人口は男32 ・ 女25。明治32年敦賀憲兵分隊が置かれる。昭和42年和久野団地建設に伴い、一部が新和町1~2丁目、同52年市野々町1~2丁目となる。 近代の市野々町は、昭和52年~現在の敦賀市の町名。1~2丁目がある。 《市野々の人口・世帯数》 1039・758(市野々町1・2丁目) 《市野々の主な社寺など》  字四ツ目辻に鎮座する。祭神は応神天皇で旧村社。また初代柴田権右衛門は耕雲明神と称し祀られている。明治9年村社となる。 『敦賀郡神社誌』 村社 八幡神社 敦賀郡粟野村市野々字四ッ目辻
位置と概況 本區は若狭街道(丹後)に沿ひ、人家はその沿道両側に併立してゐる。元は金山區の分派で、幕末までは市之野とも書いた様である。當區は何れの頃の洪水にか、多くの田地に土砂流入して、久しく荒蕪地であったが、野坂區の豪農柴田権右衛門、官に乞ひで開拓した地であるが、萬治元年工を起し、寛文二年功を竣つたと云はれてゐる。本區は東方和久野區に隣し、北西方は櫛林區の一部を經で莇生野區に隣してゐる。松原村木崎區へは約二十六町を隔てゝゐる。西南の一部は櫛林區に接續するのみにて、他の三方は田野大に開け車馬の交通亦至便の地である。然して氏神八幡神社は、道路の東側に沿ひ社標及び鳥居を入り、約一町の參道を經て拜殿に至る、平坦の社域は二分し本殿鎮座の地は、高さ三尺の石垣を四圍に築き、前面に四級の石階を設けである。區の中央東端に當り、南面して鎮座し給ふ。參道を除いた社域の周圍は殆ど他地に圍まれ樹木も概して多からず、幹圍七尺位の松數株がある。又タモの常緑樹等あれども何れも樹齢は多くない。されど區民は敬神の念厚く、近年克く神社諸般の設備に、又境内樹林の保護植に努めつゝあれば、年と共に莊嚴を加るべく、丹後街道を往来する人々は、其の施設の努力の蹟を見て自から敬神の念を湧發するであらう。 祭神 應神天皇 由緒 按ずるに、當社の創立年代は詳でないが、氣比宮社記に柴田某が鎮守社として、八幡宮・稲荷社・胸像社(宗像)を勧請し奉ったとあり。又敦賀志稿には稲荷・八幡・辨財天同殿に祀るとある。明治九年十月十七日村社に列せられた。 祭日 例祭 五月二日 祈年祭 三月二日 新嘗祭 十二月二日 特殊行事 辨天祭 七月十五日は辯天祭と称し、當社境内にて近郷の男女老若は、盆踊の如く夕刻から夜を更して踊う興ずるのである。 〔柴田の踊〕 八月十六日柴田の踊と呼んで、當社の境内で踊る。社域には神燈を點じ祭礼気分を漲ぎらすが、舊時は柴田権七氏の屋敷前で、其多数の奉公人が盆休みに踊ったのに、由来すると云はれてゐる。歌詞に「盆の十六日に柴田の踊り、わしも行きませうこしらへて」とあり、或る書に、柴田誦の濫觴は、元祿萬治の昔、村の元祖の権七が、市野々荒地を開拓なして茲に部落を取り立てられた、「盆の十六日紀念の踊り、老も若きも皆打ち寄りて、調子揃えて踊らんせ」云々とあり。歌詞に「踊り見たくは市野々へ来んせ、盆の十六日チヤ柴田の踊り、村の若衆や小娘達が、晒し手拭スキヤの足袋で、風流な浴衣の袖振り挿頭(翳し)手振り足踏み聲張り上げて、踊る姿の扨て面白や、老も若きも皆打ち寄りて、調子揃えて踊らんせ云々」とある。 本殿 内殿… お宮ノ講 三月二日祈年祭當日に、お宮講と稱して氏子各自は辨當を持寄りで會食し、伊勢両宮の代參者二名を決定し、又神事に關する協議をする。代參者が伊勢両宮を代參して歸ると、區民は貰ひ休みと稱して休業する。 神社附近の口碑傳説地 法師塚と稱し柴田事次氏の住宅附近にあり。俗に山法師塚とも呼んでゐる。この塚に手を鵤るれば病むと傳へられ、小さい瓢形塚で一本の太い松が繁つてゐる。… 市野々新田の開発者柴田氏の庭園は野坂岳を借景とした築山回遊式林泉庭園で、 元禄初年狩野探幽の地割設計により築庭されたといわれている。国名勝に指定。庭園(甘棠園)内のヤマモモの木は市天然記念物。柴田氏はまた宝永6年から酒造を行い油屋も営んでいたという。 『敦賀志』(『敦賀市史史料編5』) 市ノ野 以前ハ秋篠と云しとぞ
金山村の支村なり、いつの洪水にや、金山村の田地夥敷砂石入て、年久しく荒野と成たるが、寛文年中櫛林村の農家治部右衛門(柴田氏)の老父権七と云し者、官に乞て開発し、数百頃(ママ)の墾田となす、其中に一町四面の宅地を構へ、門の左右に家隷(地子と称す)二四軒を置、市野村と号し、氏ハ柴田氏にて代々権右衛門と称す、 君侯御参観のをり毎に御休足の所にて盛饌を奉る、園中いと広く、前ハ野坂山を受て筑山造水其勢を得たり、郡中一の林泉といふべし、氏神一社(稲荷・八幡・弁財天同殿に祭る) 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 市野々の主な歴史記録市野々の伝説市野々の小字一覧市野々 水込 上ケ石 元録河原 京野田 東野神越 元録野 深田 中銅 東中堀 石代 階子田 松ノ下 山伏塚 稗田 神田道 野田尻 野畑 秋篠 外鳥居 道ノ上 四ツ目辻 捨高 助高関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『敦賀郡誌』 『敦賀市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2022 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||