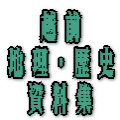 |
新道(しんどう)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新道の概要《新道の概要》  あと1㎞ばかりで滋賀県との境になる。当地は敦賀湾よりも琵琶湖のほうが近い。敦賀へ3里、塩津へ2里という。荷車も通れない路だったそうだが、今はご覧のような立派な道(国道8号)となっている。今は高速もあるが、北陸と近畿・東海とを結ぶ幹線道路である。水が出て道路の雪を溶かすようにはなっているようだが、それでもたまに大雪でトレーラーあたりがスリップして動けなくなると、その処理が終わるまで何百台の車が何時間も動けなくなることがある。国道8号の最高所(標高約400m)辺りを一般に新道野といい、この峠を越す街道を新道野越え(塩津道)と呼ぶ。 地名の由来は、「敦賀志」に「此の村ハ深坂より追分へ出し官道やミて、今の新道野街道やや開け初けん頃、奥麻生より出たる成るへし、いづかたにても、新たに出でて村居せしを、何の新道と云。(中略)されども六、七百年も前の事成へし」とその成立を推定する。新道集落より1キロほど南、国境近くに小字新道野がある。西村家1戸。敦賀より塩津に出る荷物は古くは深坂越を通ったが、険路で運送が困難だったため、享禄~弘治(1528~58)の頃、岩熊(やのくま)村(滋賀県伊香郡西浅井町)の西村某が、国境より南2丁ばかりの地に移り住み、追分茶屋と談合して新道野越で荷物取次を始めたという(西村家文書)。その後新道野越が主となり、天正8年(1580)敦賀代官武藤助十郎が上り荷物の継場を定めた時には、新道野もその一に加えられた(疋田記)。 天正18年(1590)8月18日の日吉神社鳥居棟札に、奧麻生の同社鳥居を建立する際に、新道惣中で米1斗,当地の住人8人が米3~5升を寄進している(奧麻生区有文書)。慶長国絵図では疋田村666石余の一部。 近世の新道村は、江戸期~明治22年の村。はじめ福井藩領、寛永元年(1624)からは小浜藩領。敦賀から塩津に通じる新道野越(塩津道)は慶長国絵図に見えず、慶長年間(1596~1615)よりのちの成立と考えられる。当村は新道野越の要衝にあたる山間の宿駅。新道集落より約1㎞南の国境近くに字新道野がある。新道野には女留番所・高札場が設けられ、問屋兼茶屋が1軒(西村孫兵衛)あった。小浜藩は新道野に米蔵を置き、藩米の継ぎ立て基地とした。寛永19年(1642)には茶屋孫兵衛が藩米の保管料である庭米(扱料)を辞退し、代わりに3人扶持を給された。塩津道は何度も整備が行われていて、元禄2・4年には計132日、延べ人夫1万9,508人を使用して改修工事が実施された。俵物をはじめとする上り荷物は新道野で継ぎ立てた。特に冬季の上り荷である城米の多くは当地を通過し、問屋西村家が小浜藩の米を一手に引き受け塩津へ輸送した。享保12年(1727)の家数23(高持11 ・ 無高11 ・ 寺1)・人数144、馬18。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。「滋賀県物産誌」に、戸数23(全戸農)・人口122、馬1、荷車10、産物は菜種2石・麻20貫・繭250貫・桑2,000貫・炭1万1,000貫。明治11年敦賀陸運会社の寄付金で塩津道は荷車道に改修され、急傾斜の深坂越を避けて同道の貨客の往来が増加した。同22年愛発村の大字となる。 近代の新道は、明治22年~現在の大字名。はじめ愛発村、昭和30年からは敦賀市の大字。明治24年の幅員は東西1町余・南北2町余、戸数25、人口は男61 ・女76。新道野越は,明治11年改修以後塩津道と呼ばれ国道の指定を受け、大正9年国道12号、さらに現在は8号と改称。同道は昭和28年道路幅も改修されて北陸と近畿・東海とを結ぶ幹線道路となった。 《新道の人口・世帯数》 32・13 《新道の主な社寺など》  字釜谷に鎮座する日吉神社、もと山王権現と称し、祭神は大山咋命。旧村社。 『敦賀郡神社誌』 村社 日吉神社 敦賀郡愛發村新道字釜谷
位置と概況 本區は南方十一町餘にて滋賀縣伊香郡と堺してゐる。新道と云へる地名は、深坂より追分へ出た道路が廃れて、新たに麻生口區より分岐したる鹽津街道が開鑿されたので、かくは名付たるものであると、東西南の三面は、山脈圍繞して、北方の一面僅に耕地がある。然して北約二十一町にてあさ生口區がある。鹽津街道は、區の中央を貫通し、人家の多くはこの両側にある。笙ノ川の上流(疋田川)松ノ木峠橋を渡りて、更に進めば本區に到る。氏神日吉神社は、人家より約一町半を隔てたる南方の東端山麓にありて、本殿は西面して鎮座し給ふ。社域は鹽津街道より水田を挟んで、約二十間餘の諸道を進み、石造の小神橋を渡り、数級の石階を上りて、鳥居を入り平坦にして廣き境内を進み、更に十段の石階を上れば拜殿がある。こゝに高さ六尺の石垣を築きて區分し、其の中央正面に設けられた石階十級を階すれば本殿である。背後の山には桂・橅の樹木多く幹圍一丈に及ぶものもある。社前には特記すべき大樹とては無いが、街道を往来するもの誰か其のコンモリしか鬱蒼たる鎭守の森に目を注がざる。 祭神 大山咋命 由緒 按ずるに、當社は山王宮又は山王権現と尊崇し來り、明治十一年三月村社に列せられた。 祭日 例祭 舊八月十五日 祈年祭 舊四月三日 新嘗祭 舊十一月三日 特殊神事と神饌 舊五月五日の節句の當日笹粽十本括を二杷、神前に供へ奉る。毎年その献饌は氏子が順番で、交代に奉仕するので、番に當つた者を當番と稱してゐる。 九月十日當日は俗に宮籠と稱して、夜八時頃より十二時頃まで、區民の老若男女殆ど全部が、神社に参籠して、篝火と神燈の幽暗なる光の下に、青年等は豊年踊をなすのである。因に當區では、當番が神社へ献供することを御供(オゴク)と稱し、その神事に參拜することを宮籠と稱してゐる。 舊十一月三日 新嘗祭當日の祭典前に、宮番は山漆の木を撓めて徑四・五寸の輪を作り、藁を中央に十文字に掛けて結び、之を皿の代りに用ひ、其の籠皿に、小豆り煮たものを握り固めた小豆玉三個を盛りたるもの、大豆の煮たるものを握り固めた大豆玉三個を盛りたるもの及び赤飯の握り三個を盛心たるもの各一臺と、外に御供と稱して赤飯を一升桝大の梯形の型箱につめて、それを三寳に打ち出したる物相(モツサウ)一臺、計四臺の神饌を當番二名が神前に供へ祈念して、撤饌は參拜した區民に配與する。尚當日参拝出来ざる家族には、持ち歸りて普く分與するのである。 本殿 内殿… 境内神社 山神神社 祭神 大山咋命 社殿… 愛宕神社 祭神 火遇突知神 社殿… 神社附近の遺蹟 「太平記十七」に金崎城攻の際に、足利勢の小笠原信濃守は、信濃國の勢五千餘騎を率て新道に向ふとある。果して然りとせば、鹽津街道の開鑿はこれ以前でなくてはならぬが、史料の徴すべきものはない。又新田義貞が、叡山より尊良・恒良兩観王を奉じて敦賀に向ひ、七里半越にて、佐々木・熊谷の賊徒の要撃あれば道を轉じて迷ひ、戦死するものあり、剩へ風雪激しく、弓矢を焚きて暖をとりたるも、宵凍死するもの数多あり、或は敵に捕へられたるもあり、漸くにして新道野に出でたとの記事がある。これには木ノ芽峠の文字見ゆるが故、南條郡鹿蒜村新道の附近なるべく見ゆれども兩者とも確證なければ何れとも断定しがたいが、恐らく寳際地理より考察して、本邦愛發村なるべしと思はるゝので、史蹟参考地として記した次第である。  元禄5年(1692)創建の曹洞宗玉泉寺。 『敦賀郡誌』 新道 麻生口の南に在り。鹽津へ出づ。 氏神、日吉神社、村社、境内神社山神社。 玉泉寺、曹洞宗、奥野宗昌寺末。元祿五年、本山八世融山創立。小字新道野は邑の南國境に在り、西村氏一戸のみなり、藩政時代には問屋を営み、兼て女留番所を勤む。西村は元岩熊の者なりしが、天正の頃此に移りて、新道野を開き、問屋を營みき。
素封家西村弘明(孫兵衛)宅には松尾芭蕉の素竜清書本「おくのほそ道」「細道伝来記」が伝わる。昭和47年奥の細道附細道伝来記(宝暦己卯仲秋三四坊一楽記)が国重文に指定された。 《交通》 新道野越え塩津街道ともいう。敦賀市街から笙ノ川の谷をさかのぼり、同市麻生口から新道を経て新道野の南で県境を越えて滋賀県の塩津に至る街道。名称は新道野を越えることによる。今は国道8号が通過する。西方の深坂越塩津道よりやや遠回りになり、最高点(県境)の標高も405mと約50m高いが、緩傾斜で降雪量も少ないため、16世紀半ばに深坂越に取って代わった。宝永元年(1704)小浜藩は新道野に女留番所・高札場を置いている。明治11年には改修により荷車を通した。 《産業》 《姓氏・人物》 新道の主な歴史記録新道の伝説新道の小字一覧新道 松ノ木峠 入目木 石飛 堀田 中堀田 奥兀ノ谷 兀ノ谷 兀ノ谷口 林之腰 細谷裾 関 ヒモノ谷 萱原 北山腰 余ノ木畑 本トロ原 細谷口 袖田 ジョノケ 山腰 中瀬 庵斬谷 焼原 奥稲葉 稲葉 宮ノ脇 早稲田 脇ノ谷 剣ノ谷 梨ノ木谷 小豆谷 蛇谷 広畑 銚子口 釜谷 坂尻 口梨谷 小亀谷 大亀谷 原 南原 藤三郎作 奥釜谷 扇平 三五坂 芝原 柳原 西山口 西山 松ノ谷 芹原 鞠山 鞠山腰 稗田谷口 稗谷 桂 鳥越口 鳥越 玄道関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『敦賀郡誌』 『敦賀市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2022 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||