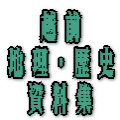 |
旧・敦賀町
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敦賀町の概要《敦賀町の概要》 近世の敦賀町 天正10年(1582)の本能寺の変以後に、武藤氏に代わって敦賀の領主となった蜂屋頼隆が 近世初頭にすでに整然とした都市計画や広域行政、地域分業がなされ、町はその後大きく発展するはずであった。しかし寛文年間は敦賀町にとって大きな分岐点となって、これまでの1世紀にわたる順調な発展にかげりが見え始めた。その大きな要因は、寛文12年(1672)幕府によって西廻り航路が整備されて、中継港敦賀を素通りする船荷が多くなったことである。 寛文期が敦賀町の絶頂期であろうが、貞享~元禄(1684-1704)頃の敦賀港はまだ殷賑を極める状況で、「日本永代蔵」にも 越前の国敦賀の港は、毎日の入船判金一枚ならしの 上米ありと云へり、淀の川舟の運上にかはらず、万 事の問丸繁昌の所なり、殊更秋は立つゞく市の借屋 目前の京の町、男まじりの女尋常に其形気北国の都 ぞかし、旅芝居も爰に心かけ、巾着切も集れば(下略) と記され、また「日本新永代蔵」には「敦賀は北国の長崎にて、春は更衣の末、秋は長月の始まで、諸国美産の万人此湊に入来り、銅・鉛・米・紅花・青苧・練子・いりこ・串貝・にしん・其外さまざまの商売問丸軒を並ぶる」とその繁栄を描写する。 南東に気比神宮が鎮座し、周辺に形成された宮内・社家・執当屋敷の3町は気比神宮の神領で、肝煎も置かれず、町夫役も掛けられなかった。 神宮の浜側には、浜島寺・唐仁橋町・中橋町・三日市町・東町・西町などの中世以来の古い町がある。通り道も矩折になり、辻子町の形態を示すなど、近世に町立された川西や川東、さらに浜手の町々とは異なっている。浜島寺町の寺院、紙屋町の紙漉き、金ケ辻子町・鵜飼辻子町の鍛冶、西町の魚市・青物市、御影堂前町の札場、一向堂町の時の鐘、唐仁橋町の旅籠、小間物町の小間物などの敦賀町の中心部にふさわしく、川中の町々は商業・流通・伝統産業などが盛んであった。 この地域のさらに浜手には、天正年間(1573~92)から慶長年間(1596~1615)にかけて西浜町・東浜町・船町などが新たに町立されて。大船と蔵宿をもつ初期豪商の道川・田中・打它など船頭が屋敷を置いて、また諸藩の蔵屋敷も幾十と並んだ。湊町敦賀の表玄関にあたり、今橋から下小屋橋に至る浜町の通りは表通りと称された。 川中の南部に当たる塔場・射場の両町はその起源は古いが、町場化はやや遅れたらしく馬借の会所が置かれたり牢屋があるなど、在方との接点をなした所である。 川東の浜手は、天正末年、敦賀・河野浦間の荷物回漕や漁業に従事していた川中の唐仁橋町・御所辻子町の舟人が移転させられて、川向御所辻子・川向唐仁橋の2つの漁師町が形成された。寛文7年(1667)には両町で舟数92(うち荷積舟28)・家数309を数え、日本海岸最大の漁師町となっている。同10年には天満宮裏側の芦原近くに遊戯町の新町がつくられ、それ以前からの六軒町などとともに花街四町と呼ばれた。各地から遊女が集められ、芝居小屋も川西から移されて盛り場として繁栄した。また商舟より問屋蔵へ荷物を持運ぶ丁持・平持が津内村から集まり丁持町が成立した。やがて漁師・港湾労務者・遊女の町となり、先の4町と合わせて川向六ケ町と一括して呼ばれた。 川西は敦賀城の跡地にあたり、城の破却後は中央部に奉行所・代官所・蔵などが建てられ、それぞれ以前に建てられた大名の休息・宿泊所としての御茶屋とともに敦賀役所と総称された。町場の中心は寛永12年(1635)浜手に町立された茶町で、敦賀湊最大の移出品であった茶の独占的取引権を与えられた。茶町は大繁盛をきたして、その南側の赤川沿いに飲食街の池子町ができて茶商人の接待に利用されたため、遊女が集まり、芝居小屋もできたという。また寛文2年に、中世以来敦賀湊の重要な移入品である塩魚や干魚を取り扱う四十物町が今橋の西詰に立てられて迪子町の枝町とされた。こうして川西は官庁街・商店街・飲食街となった。 都市計画は敦賀一帯の広域に及び、地域分業の形をとった。酒座・室座・鵜匠座は本来町方にしか認めず、江戸中期以降郷方に許可しても脇座とし、町方の本座の支配を受けた。漁業についても同様であった。海岸沿いの磯付の村々でも、西浦は本浦(漁村)とされ、さらに湾内の名子浦から浦底浦までを網浦および塩浦とし、外海に臨む立石・白木の両浦は釣浦とされた。東浦は塩浦のみとし、漁業への進出を許さず、村方的性格をもたされ、漁場は漁師町の利用するところであった。 町の両隣に位置する泉村と今浜村は舟揚げと網漁・魚の行商権を与えられ、町方と村方の中間的性格をもった。漁師町の両浜(猟浜、川向唐仁橋町と川向御所辻子町)は町内での魚の行商権をもった。漁猟座は大座と小座に分れ、大座は大舟を操り、鰈網・鯖釣など網漁・沖漁を行い、小座は小舟で湾内で磯見をしてアワビ・サザエを捕獲したり、スズキの夜突きや海鼠漁をするもので、大座に従属した。 敦賀役所には町奉行が置かれていたが、南・北両奉行所に分かれ、同心が16名ずつ属した。いずれも足軽で、頭は杖突・小頭などと呼ばれ、その下に物書役・駄別帳付方・破損方・道口番所勤番・市中警邏番などの役があった。杖突は大工仲間・大鋸小挽仲間・鍛冶仲間・左官仲間・桶屋仲間など職人仲間を支配した。 町奉行の町方支配を補助するものに、町人から選出される町年寄・惣代・老輩・肝煎・組頭がいた。町年寄は道川・小宮山・三宅の3氏が江戸中期まで世襲した。町年寄は寄合日には町奉行所に出向いて諸般の行政に参画し、問屋・町医・紙漉師・秤屋・酒屋仲間・質屋仲間・油屋仲間・蝋燭仲間・豆腐屋・丁持・平持・風呂屋・座頭・紺屋・石灰問屋・旅籠屋を支配した。なお三宅氏は魎仲間の支配を独占した。惣代は町年寄を補佐する役で町の名望家が勤めた。町年寄同様に寄合日に参加し、町触など触れ流し、(扌に井)仲間・糯搗・揚屋・芝居を支配した。肝煎は町ごとに1名いて、町内への触伝達や宗門改などの任に当たった。 各町へは小物成が課され、寛文6年の総額は銀約360貫匁であった。うち湊に荷揚げされた米・大豆・四十物などに道口で掛けられる駄別役銀が約253貫匁、米仲役銀約47貫匁・茶仲役銀約31貫匁・町地子銀約16貫匁、その他14品目の額は約12貫匁。駄別銀の多さ、米・茶の取引額の高さなど、敦賀町の諸税がいかに湊・交通に依存していたかがわかる。 人口は、天和元年(1681)1万3,568、宝永6年(1709)1万2,296、享保11年(1726)1万913、天保11年(1840)8,952と次第に減少した。 明治7年、町名の改称や町域の合併が行われた、泉村が月見町、射場町が弓矢町、法泉寺町が末吉町と改称され、同年今屋敷・新田・河原の3か村が合併して稲荷町、筑屋敷・三ノ丸・徳市・田島村が合併して八幡町、同11年鋳物師・松中・今浜の3か村が合併して松島村、同14年弓矢町と末吉町が津内村に合併、稲荷町と八幡町が合併して三島村となり、同年月見町は泉村と改称した。 在方も含めて敦賀町内は、松栄町・川崎町・結城町・蛭子町・大黒町・旭町・神楽町・大金町・鍵屋町・清明町・富貴町・蓬莱町・桜町・大内町・橘町・大島町・御手洗町・曙町・境町・常盤町・大手町・湊町・天満町・入船町・月見町・弓矢町・末吉町・稲荷町・八幡町の29町に編成された。 同10年蛭子町が幸町、鍵屋町が末広町、大手町が浪花町、湊町が大湊町、同13年清明町が晴明町と改称。同17年からは敦賀を冠称。明治14年月見町が泉村と改称、同年弓矢町・末吉町は津内村の一部、稲荷町・八幡町は合併して三島村となる。 同22年市町村制施行により、敦賀24町および泉・津内・三島の3か村が合併して敦賀町となった。 当町の経済をささえる敦賀港は、明治35年日本海対岸のウラジオストックとの間に航路が開かれ、日露戦争後シベリア鉄道が開放されたため、大正元年東京新宿~金ケ崎駅間に国際列車が運転されて活況を取り戻した。 昭和8年敦賀駅の南西に昭和レーヨン敦賀工場ができ、のち次々に近代的工場が立地した。同12年敦賀市の一部となり、当町の27大字は同市に継承された。 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『敦賀郡誌』 『敦賀市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||