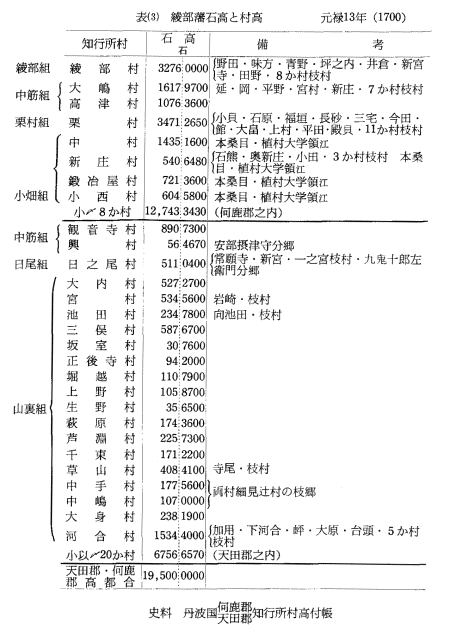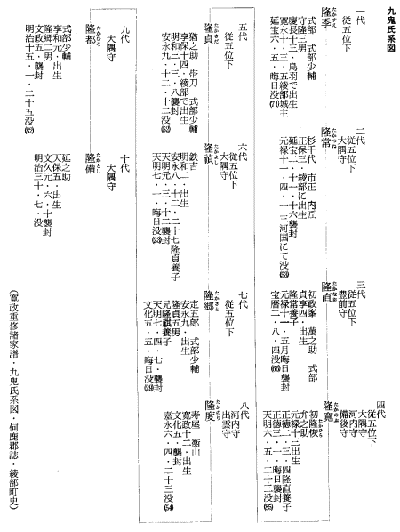京都府綾部市上野町 京都府綾部市上野町
 京都府何鹿郡綾部町本宮村 京都府何鹿郡綾部町本宮村
|
上野町の概要
《上野町の概要》
綾部小学校や大本の長生殿、農研機構の「近畿中国四国農業研究センター野菜部」などがある、本宮山(91m)と藤山(201m)間の台地上に位置する。江戸期には藩邸と武家屋敷があったところ。
上野町は、昭和28年~現在の綾部市の町名。もとは綾部市大字本宮村の一部。
《上野町の人口・世帯数》 845・371
《主な社寺など》
 藤山 藤山
藤山山頂は経塚があった、今は公園となっているようだが、まだ登ったことがない。
 若宮神社 若宮神社

藤山の東麓、藤山登り口の付近に鎮座。正面が若宮神社、向かって左は厄除神社。杵の宮はずっと右側にある。案内板には、
若宮神社由緒
祭神
仁徳天皇(人皇箱十六代)
鎮座地
綾都市上野町藤山壱番地
由緒
一、当若宮神社の創建は、治承年間小松内府三位中将平重盛卿が丹波の国守であった時、山城国石清水八幡宮を此の地に勧請せられたものと伝えられる。
ニ、其の後鎌倉、室町、戦国時代から徳川初期に至るまでの記録が現存しないので同期間の状況は知る由もないが、以後の由緒については綾部九鬼藩の旧記録により稍々明らかである。
即ち寛永十年三月、徳川三代将軍家光の時、九鬼隆季公志摩の国鳥羽から綾部に転封せらなるや、当若宮神社が御屋敷内に奉祀せられていた為、厚く尊崇せられ特に綾部藩の総氏神と定められ、貳萬石の乏しき石高中から見取田並びに金穀を奉献せられ、其れを以て祭典並びに社殿修繕等の費に供せられた。爾後第二代藩主九鬼式部小輔隆常公を経て第十一代隆備公の明治廃藩に至るまで、各代の藩主の家督相続襲封毎に「任先規永代無退転可令執行也」との御朱印書を以て祭礼料、修復料を献納せられた。
三、元禄十四年第三代隆直公は、自筆の「若宮」なる鳥居額を奉献、現在拝殿に掲額されてある。
四、九鬼家の綾部屋形に御出生の御子様は、皆当神社を氏神として初詣、七五三、厄除等に参拝(若しくは代参)せられた。
五、綾部の地形は南部は高台、北部は低平である。隆季公鳥羽より当地に転封の際、屋形は北部低平の地(現時その跡を古屋敷又は焼屋敷と云う)に定められた。又当時、当若宮神社は南北両部を繋ぐ坂口(現在田町、元何鹿郡役所の正面、田町の裏の土地に若宮下なる所がある。之れによって其の所在地が推察出来る)に奉祀せられてあったが、たまたま九鬼初代藩主隆李公の治世慶安四年幕府の許可を得て御屋形を南部高台の地(上野本宮山西麓)に移される時、総氏神たる若宮神社を元の下位の坂口にその侭奉祀するのは誠に畏れ多き事なりとして、御屋形の正面藤山の中腹に奉遷鎮座せしめられた。
例祭日
十月十日
厄除神社
若宮神社六摂社の中、厄除神社の御祭神 猿田彦神は、天孫瓊々杵尊が高久原から日向の高千穂の峰に御降臨の際、道案内にたち種々の厄を払い除き、尊を安全に日向の国に御導き申し上げた古事から「厄除」の神として尊崇厚く、毎年二月十六日の例祭日には遠近よりの参拝者が特に多い。又、猿田彦神は教育教導の神、芸能の神、スポーツ(特に球技)の神、道路の神、船霊神として、全国至る処に祀られてある。
若宮神社 綾部町字本宮村小字藤山に鎮座、郷社にして仁徳天皇を祭神とす。現在氏子四五四戸、田町、新町、上町、東本町、西本町、本町四丁目、月見町、南西町の全部と上野横町、本宮、並松、裏町、北西町の各一部之に属す。徳川時代九鬼侯より左の寄進あり。
見取田 三畝歩(井堰山の下野田村の口) 一代 降季公
奉 納 畑高一石(地所なく引立にて遣はさる)二代 隆常公 奉納
現今例祭は十月十五日。
(『何鹿郡誌』) |
若宮神社(上野)
祭神 仁徳天皇
嘗て大正十三年八月郷社に昇格した。江戸時代家中の氏神として、歴代藩主の崇敬厚く、左の寄進の記縁がある。
見取田 三畝歩 井堰(根)山の下 野田村の口 隆季 奉 納 畑高一石 地所なく引立にも遣はさる 隆常
寛政十三年神社の長床が類焼し、神輿、太鼓其の他の神 具を多く焼失したと云う。
境内社
九鬼霊神社
若宮神社の境内に小祠があって、藩祖隆季を祀つていたが、最近九鬼家の希望によって御神体を他に移したので神殿のみとなった。由緒は元禄六年、二代隆常が始めて江戸北八丁堀の屋敷内に藩祖として祀つたが、四代隆寛の廷享二年二月、これを綾部の本宮山の麓杵の宮の傍に移し、毎年十一月に例祭を行っていたが、六代隆祺の天明三年より例祭を二月廿三日に改め、同四年惣領権現の神号を得、藩主親斎の神社として厚く奉祀されたものである。明治維新後一時隆興寺境内に移し、明治三十七年上野(町役場所在の台地)に移転したが、更に昭和二年若宮神宮境内に移したものであった。因にこの神殿は、桑原直右衛門の作である。
杵ノ宮
若宮神社境内の九鬼霊社と同座で祀つてある。この宮は綾部唯一の伝説とも云ふべき杵の宮由来に詳細に出ているが、昔本宮山と正暦寺の台地の間にあった大池(今日池田と云ふ地名になっている)に住んでいた池の主(鮭)が、里人に危害を加え娘を人身御供に強要して恐れられていたのを、嘗てこの池へ乾鮭を放した商人が杵を以て怪物を退治したので、杵を神として祀ったと伝へられている。
杵の宮は九鬼氏の入部以前既に本宮山の麓池田を見下す辺に祀られていたもので、こゝに陣屋を構へた九鬼氏は土地の神として代々崇敬して来たものである。「寛政八年六月、杵の宮花表(鳥居)建直に付、大工共御酒被下」などの記録が残っている。明治維新後は常に九鬼霊社に合祀され、共に転々と遷された。
(『綾部町誌』) |
西福院の北側、その台地下の今の田町に「若宮下」の小字がある。田町のしょうずは「若宮清水井」と呼ばれる。だから今の西福院のあたりが元々の鎮座地のようである。綾部郷の総鎮守だから、漢氏の祖の阿智使主、都加使主とか、そうした祭神かと思われるが、境内社の中にも漢氏らしき社は見当たらない。
漢氏の渡来は応神天皇の時代とされ、仁徳の一代前になる。
応神二十年紀に、
二十年の秋九月に、倭漢直が祖阿智使主、其の子都加使主、並に己が党類十七県を率て来帰り。
とある。
今の高市郡明日香村の檜前に、於美阿志神社がある、ここ最初のが根拠地とされる。
神社よりも寺院の時代に漢氏は当地へ移動してきたものか、神社が見当たらないかも知れない、あるいは若宮信仰のカゲに早く失われたか、それとも綾中廃寺が信仰の拠点であったものか。
 杵の宮・九鬼霊神社 杵の宮・九鬼霊神社

若宮神社本殿の向かって右の端に祀られている。興味深い伝説を伝えている。
キネだから杵のことと思われているようだが、そうとはかぎらない。
摂津国能勢郡枳根郷(訓注・岐禰、木子)がある。中世は枳根庄といった。今の大阪府豊能郡能勢町に式内社の岐尼(きね)神社がある。
ずいぶん古い言葉かも知れない、なお杵の古語はキであって、キネとは言わない。
『岩波古語辞典』に、「きね【巫覡】 神に仕える人。神楽(かぐら)を奏したり舞ったりする。「山人のたける庭火の起きあかし声声あそぶ神の-かも」(能宜集)。「神垣も霞にこめて見えねども-が鼓の隠れなきかな」(公重集)。「-といふは、かんなぎの名なり」(俊頼髄脳)」
柳田国男は、「神道私見」で、「巫女の最も普通の名称の一つはイチコであります。又イツキとも謂ひますが、是は古い言葉でありまして、今では多くイチ又はイチコと謂って居ります。又キネともカンナギとも申します。カンナギは神を和めると云ふ意と説かれて居りますが、キネはまだ分りませぬ。鹿島其他の大杜では物忌とも申して居ります。」としている。
 綾部藩邸・武家屋敷・綾部陣屋・綾部城 綾部藩邸・武家屋敷・綾部陣屋・綾部城
上野町には綾部藩の後期陣屋が置かれていた。『綾部市史』より↓

綾部塞址
綾部塞址は綾部町字上野にあり。九鬼氏二萬石の治所lこして、式部少輔隆季入部後慶安年中此の地に館を構へしより、明治二年迄続きしなり。其の邸跡は今綾部尋常高等小学校となれり。
附記託 校内の時鐘は徳川時代の遺物なり。始め、綾部城大手門の傍にありて、百姓に時刻を報じ、或は警報に使用せしものなり。明治十年今の地に移せり。和学者大野忍軒を入れし囚屋はこの時鐘の傍にありしなり。
校門に藩の学問所の門をそのよゝ使用せしものにして旧態依然たり。
(『何鹿郡誌』) |

だいたい藩主邸は今の大本長生殿↑のあたり、元は綾部小学校の地だというが、本宮山を背に西向きに陣屋は構えていた。武家屋敷地は北側は高台のヘリまで、大手門は今の「せんだん苑みなみこども園」のあたり。↓

府道中山綾部線(709)号↑が上町台地に登る坂(大手坂・皇后坂)に「みなみこども園」がある、フェンスに小さな↑案内板がある、わかるかな。「綾部城大手門跡」と書かれている。地形は変わっている、左手へ鉤形に曲がった所に門があったようである、ここから上が城地であった。709号のここから北が大手通り、東西は山で、南はたぶんこの台地の南端、若宮神社のあたりと思われる。この石垣は当時のものではなさそう、そのほか堀とか屋敷などは今は残っていない。武家屋敷はたぶんそうかな、それらしい風格を感じる構えの建物もあるが、本当にそうかは不明。

簡単に分けると3万石以下の城郭を持たない小規模な藩主屋敷や藩庁屋敷などが置かれた所は城とは呼ばす陣屋という。園部藩は3万石に200石ばかり足りず園部陣屋である、復元された櫓郭はあるが、園部陣屋と呼ばれている、園部城とも呼ばれるが誤差の範囲内か。福知山藩は最終的には3万2千石だが、8万石とかあった時もあり、お城であった。田辺藩は3万5千石くらいだからお城とするボーターラインか。
水軍の将が築いた綾部の町 ●九鬼氏と綾部藩
九鬼氏は、紀伊国(和歌山県)牟婁九鬼浦の豪族であり、嘉降の時、勢力を伸長した。織田信長・豊臣秀吉に仕えて、水軍の将として戦功をあげ、伊勢・志摩両国(三重県)のうち三万五、〇〇〇石を領して鳥羽城(鳥羽市)に拠った。
関ケ原の戦いで、嘉隆は西軍、子の守隆は東軍に属し父子対立となったが、西軍の敗走により嘉隆は自刃し、守隆が鳥羽城主となり五万五、〇〇〇石を領した。
守隆は四男久隆を後継としたが、三男隆季との間に相続争い(御家騒動)がおき、幕府裁決として寛永一〇年(一六三三)、久隆を摂津三田三万六、〇〇〇石、隆季を丹波綾部二万石に転封した。世に「陸の河童」となったと言われたが、九鬼家綾部藩・三田藩の始まりである。
綾部藩は新規立藩とされ、丹波国何鹿郡八か村・天田郡一九か村を領有した外様の小藩であり、丹波七藩の一つである。
寛永一一年、綾部に入った隆季は下市場に藩邸を置くが、慶安四年(一六五一)上野の台地に居館を移して家中屋敷を設け、崖下の平地に城下町六町を形成して藩政の中心地とした。藩邸は本宮山を背景に、田町よりの大手門、上町よりの新宮門と田ノ口門を定めて、周囲を限った家中の中心部におかれた。
城下町は綾部村・坪内村にあって「町分」と呼ばれた。大手門に通じる田町、京道につづく本町、福知山街道へつづく西町を中核として、上町・新町・西新町をおいている。家数は元禄期(一六八八~一七〇四)に二三八軒、天保期(一八三〇~四四)頃は二七八軒である。町家は本町・西町が奥行二〇間、他は一五間であり、間口は家毎に異なるが一〇間以上が二〇軒あり中心的な商家となっている。道路は丁字型で、本町と西町の交わるところに獄屋をおき、要地に天水桶(防火用の雨水を溜める)を配置している。町端に熊野神社・浄光寺・了円寺を他から移して配置し、二万石の城下町を形成した。
慶安五年八月、隆季は「慶安検地」と呼ばれる内検を実施した。
綾部藩の領域は、かつての福知山藩主有馬豊氏の所領であって、有馬検地高を朱印高としていたが、慶安検地の結果、朱印高に対して増高村と無地高を含む村(土無高村)が生じ、後者は二三か村に及んだ。寛文七年(一六六七)修正の検地を行ない、領政の基礎を確定した。
隆季は寛文九年、弟隆重に五〇〇石を分けて旗本とした。このため所領高は一万九、五〇〇石となり、綾部・中筋・栗・小畑・山裏・川合の六組と飛地日尾の各組にわけて領内を支配した。
六代藩主隆祺は老中・田沼意次の七男である。そのためか天明四年(一七八四)三か村が上り地(天領)となり、新たに物部村、口郡四か村(船井郡)など六か村が綾部領となった。意次失脚後の寛政一二年(一八〇〇)領内富裕村である輿村・観音寺村が天領と再替地をみる。 (木下禮次)
(『図説福知山綾部の歴史』) |
《交通》
《産業》
《姓氏・人物》
九鬼氏
綾部薄の成立
綾部藩は寛永十年(一六三三)に九鬼隆季が二万石の領主として、丹波国何鹿・天田二郡のうち二七か村を与えられ、翌年十一月四日に綾部へ入部したのにはじまる。
九鬼氏は藤原末流と称し、鎌足より十九代目の教真が紀州牟婁郡を領有し新宮に居住した。南北朝のころ隆真は九鬼浦に移って家号を九鬼としたといわれる。文和年中(一三五二~一三五五)隆良の時志摩国英虞郡波切村にうつり、付近の豪族をうって勢いを得、泰隆のとき加茂郷岩倉村に田城を築いて、これにより伊勢の国司北昌氏に従って二見七郷を支配した。水軍九鬼として飛躍するのは嘉隆の時である。織田信長、つづいて豊臣秀吉の部下に入った嘉隆が、志摩七嶋衆を従えて紀州三鬼の一揆討伐を行い、石山本願寺攻略や文禄慶長(朝鮮)の役に水軍として活躍し武名をはせたことは史上に有名なことである。嘉隆は志摩国鳥羽に城を築き、三万六千石を領して従五位下大隅守に任じられ、慶長二年には隠居した。関ケ原の戦では西軍に与し、隣国の稲葉貞通と戦ったが、子守隆は東軍に属して関東におもむいていた。守隆は家康の命により鳥羽城を奪回しようとし、父子相剋の戦となった。西軍が敗れたことにより、嘉隆は家康より切腹を命ぜられたが、守隆は領地を返上して助命を嘆願したために許された。しかし助命の報の到る前に自刃して波乱の生涯を終わったのである。
守隆は慶長二年に家督をついで鳥羽城主となり、関ケ原の戦の後二万石の加増をうけて五万六千石を領した。家康・秀忠の部下として大坂冬・夏の陣に加わり、また、江戸城・駿河城の造営に参加するなど、幕下の水軍(舟手番)としての地位を確保していったのである。
守隆には四男子があり、二子の早世、廃嫡のあと、三男隆季と四男久隆の間ではげしい後継争いを生じた。隆季は西山民部の女を母とするが、父守隆とは不和であり、隆季他出のとき殺害を企てているとの風評がたつほどであった。守隆は隆季を伊勢国飯野郡に一万石を与えて分封したが、長男良隆が病気のため廃嫡し、四男久隆を後継者としたことによりはげしい御家騒動がおこった。久隆ははじめ寿良といい、伊勢国朝熊岳金剛証寺に出家していたが、守隆はこれを還俗させて後継者として遺言し、まもなく亡くなった。
久隆の後継に異議をとなえたのは、隆季およびそれを支持する家臣たちであり、親戚家臣を両分する御家騒動となった。隆季は自分に味方する越賀隼人・九鬼数馬・九鬼豊後ら、いわゆる十三人衆をつれて江戸に下り、姉の婚家先の戸田因幡守忠能を通じて幕府に訴状を提出した。一方久隆は父の遺言をもとに実姉の夫松平出雲守勝隆の後援で応訴し、家督相続を願い出た。幕府においては重臣協議の結果、寛永九年十一月廿七日に家督争いの過怠をせめ、所領中二万石を取りあげて久隆の家督相続を許し、摂津三田三万六千石へ転封し、隆季の敗訴をいいわたした。これにより、隆季および十三人衆をはじめ多くの家臣は流浪することになったが、久隆よりの帰参の勧誘に応じないものも多く、節操をたたえる落首が残されている。
翌寛永十年三月、将軍家光に召し出された隆季は、あらたに綾部二万石に封ぜられたのである。諸書には嘉隆遺領二万石の相続と記しているが、綾部藩では「寛永十年三月五日丹波国何鹿部の内八力村 天田郡の内に二十九力村 両郡にて廿七力村 御知行高二万石 従家光公御拝領 是は守隆公御願を以て被下置候御知行には無之様相心得べく候旨被仰付 時に御歳二十六」とのべているように、新規取り立てであるとしている。隆季は寛永十一年綾部に入部し、綾部二万石の藩政を行うこととなった。
九鬼氏の三田・綾部への転封は海運の要地鳥羽から去ることであり、幕府舟手番よりの脱落であって、水軍としての特色をうしなうことである。これはお家騒動に端を発した改易転封という幕府の政策の意図を明らかにするものであり、これより九鬼氏は近世大名への道を歩むことになった。
九鬼隆季は綾部領主となると、家臣智積寺助左衛門を綾部に遣わして城地を選ばせ、寛永十一年に下市場に城館をきずいた。その後火災にあったため慶安四年(一六五一)に上野の台地にうつり、以後幕末までそこを城地とした。そうしてその北西万の低地に城下町をつくったのである。
綾部藩主 綾部藩主の系図は左の通りである。
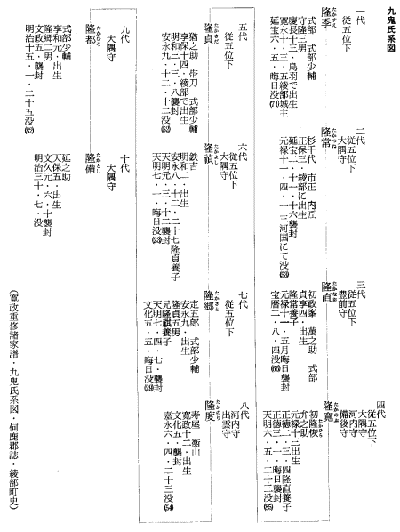
九鬼氏は代々式部少輔、また大隅守であり、従五位下に任ぜられ、柳間詰の大名であった。隆季は寛文三年(一六六三)弟隆重に五百石をわけて旗本とし、所領は一万九千石となった。治世四〇年の間に、大和国高取城番や江戸火消役・朝鮮使節の接待役・宮津城主京極丹後守高国の改易にともなう城受取役などをつとめている。歴代藩主のうち、逸材とされているのは九代隆都で、天保年中、佐藤信淵を招いて藩政改革をこころみたことは有名であり、その治世については第六章綾部藩政改革のところでのべる。他に藩主としては他家からの養子がめだち、幕府の権力者田沼意次の子隆祺が藩主となっていることなど、綾部藩の幕府接近の政策として注目される。八代隆度は病身のため早く引退し、文人としての生活をおくり、歌垣綾麻呂と称して狂歌三大名の一人にかぞえられたことは異色である。
家臣と職制
綾部藩の家臣および職制については史料不足でほとんどわからないが、安政三年の藩士の構成は次の通りである。
幕末の史料であるから初期のようすはわからないが、藩士は鳥羽から従ってきたものや綾部で取り立てたものを含めて、知行取約五〇名と、給米取約一六〇名の計二〇〇余名で、その構成比は大体他領と同じである。井倉八幡宮社前の、元文元年(一七三六)の銘のある石灯寵には、寄進した綾部藩士四三名の名が記されており、藩士の活動を知るための数少ない資料である。
綾部藩の職制は、維新当時の資料から考えると、家老・用人・奉行・御次目付・大目付・御納戸万・郡奉行・代官・御金奉行・札場奉行・武具方・学問所取締などがあったが、職務の内容や組織についてくわしくはわからない。領内政治は郡奉行があたり、その支配下に領内を町方と在方にわけ、在方は領内を七組にわけて大庄屋をおき、村には庄屋・年寄、町方には町年寄をおいている。大庄屋には蔵米二人扶持を与え、庄屋には一反ないし五畝の上田地を支給している。
綾部藩領 綾部藩の所領は何鹿・天田の二部にわたっており、その内容は表(3)の通りである。これを綾部・中筋・栗・小畑・山裏・川合の六組と飛地日尾の各組にわけて支配した。天明四年(一七八四)に物部村の天領が替地として綾部領となり、寛政十二年(一八〇〇)に観音寺村のうちの興村および山裏組の坂室村・堀越村が御上り地となり、日尾・常顧寺村が分家九鬼家の絶家により天領となっていたのを、再び替地として綾部領となった。また中台・新町・質志・三ノ宮の口郡四か村が綾部領となるが、その時期は明らかでない。
(『綾部市史』) |
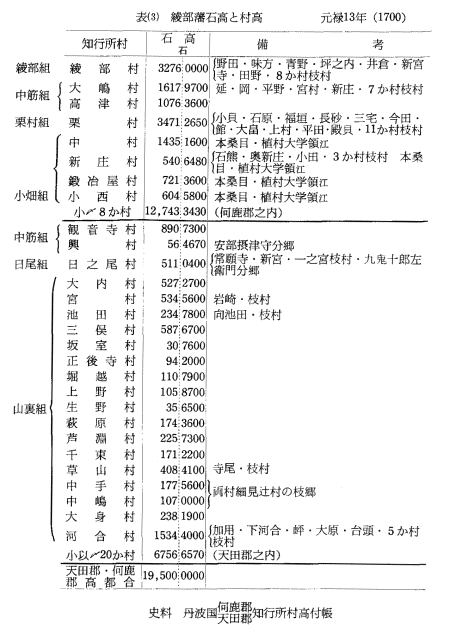
『甲子夜話』巻之二に、「九鬼家節分の事」として面白い話が記載されている。こちらは綾部藩の九鬼氏ではなく三田藩の九鬼氏である。
先年のことなり。都城にて、予、九鬼和泉守〔隆国〕に問には、世に云ふ、貴家にては節分の夜、主人闇室に坐せば、鬼形の賓来りて対坐す。小石を水に入れ、吸物に出すに、鑿々として音あり。人目には見えずと。このことありやと云しに、答に、拙家曽て件のことなし。節分の夜は主人恵方に向ひ坐に就ば、歳男豆を持出、尋常の如くうつなり。但世と異なるは、其唱を、鬼は内、福は内、富は内といふ。是は上の間の主人の坐せし所にて言て、豆を主人に打つくるなり。次の間をうつには、鬼は内、福は内、鬼は内と唱ふ。此余、歳越の門戸に挟すひら木、鰯の頭など、我家には用ひずとなり。これも亦一奇なり。
九鬼のキは鬼ではなかろうが、キは村で、クキは大きな村とかいう意味と思われるが、鬼とも見られていたような節分の様子を伝えている。
水軍といっても、海が荒れる季節は山で鉄を採るので、半分オニと観念されていたのであろうか。埼玉県久喜市があるが、こうした文字を用いず九鬼などとわざわざ鬼の字を用いるのはそう自覚していたのかも知れない。
上野町の主な歴史記録
伝説
杵の宮由来 伝承地 綾部市本宮町
大昔のこと。秋風の吹く頃、丹後から魚売りの行商人がはるばる丹波路を越えて、うんと仕入れた干し魚の荷物を担いで寺村の山道を登ってきた。そして古池のほとりで一服しようとした。
当時この辺りは、うっそうと生い茂った大森林、原生林そのままの大木が、たけなす雑草とともにそびえていた。重い荷物を下ろして休んでいた魚屋は、不意に林の茂みの中からバタバタと異様な物音がしたので、ギョッとした。おそるおそる音のした茂みの中をのぞいてみると、そこには村人の仕掛けた罠に一羽の雉子が足を取られて、バタバタもがいている。「なんだ、びっくりさせるじゃないか」と魚屋は一安心したが、まてよ、魚はいつも食っているが、鳥の肉はなかなかありつけない、ひとつ取りかえっこしてやろうと、雉子を荷物の中にしまい込んだ。そしてそのかわり一尾の塩鮭を罠に掛けて、寺村から須知山(しちやま)峠へと急いでいった。
罠を仕掛けた村人は、なんか獲物はと、日暮どき池のほとりへやって来た。と、見ると罠には思いもよらぬ鮭がかかっているのでびっくりしてしまった。というのは、当時この付近一帯は、大原神社(天田郡川合村大原)の氏子であり、大原の氏子は、うなぎと鮭は絶対に食べなかったのである。鳥の獲物のかわりに、久しぶりに海の魚にありついたが、なんともしょうがないので、「神さんの祟りにあってはつまらない。オイ鮭公、この池の主になれ」と言って、勢いよく鮭を池の真ん中めがけて投げ込んだ。するとどうだろう。鮭はときどき白い腹を見せつつ、こっちを見るようにしていたが、ついに水中に隠れてしまった。村人は思わずゾッとして、まっしぐらに家に逃げ帰ったという。
それから一年あまりたって、この池にはときどき不思議なことが起こるようになった。ある百姓は、池のあたりで何ともいえぬ怪物に出会って逃げ帰ったが、そのまま熱を出して寝込み、あらぬことを口走るようになった。いわく、「毎年秋の末には少女を人身御供に供うべし。言うごとくにせざれば祟りをなさん。我は大池の主なり」と。近隣の者ども、この難題をいかんともしがたく、年毎に少女を供えることに決した。
話変わって数年の後、あの魚商人がいつものように青野の定宿に泊まると、さめざめと泣く声がする。主人に聞けば、大池の主の祟り、人身御供に我が娘を出さねばならぬという。これを聞いた魚商人に思い当たるところがあった。先年この大池の傍らを通り過ぎた折、罠にかかった雉子を盗んで、かわりに乾鮭を置いてきたことがある。その鮭が大池の主になったのやも知れぬと。そこで魚商人は、少し思いついたことがあるので、大池の淵に行って怪物を退治しようと申し出た。
いよいよ当日になったので、魚商人は宿のあるじから渡された屈強の杵を携えて、大池へ出かけていった。池のみぎわに築かれた高壇に娘を残して、草陰に身をひそめて時刻の至るのを待っていた。と、池面にわかに波立ち怪異の姿を現わした。長さ五、六尺、頭は鬼瓦のごとき異形ではあるが、たしかに先年雉子罠に置いた乾鮭に違いない。異形の鮭が娘を引き込まんとしたとき、魚商人は大声で呼ぱわった。「何者だろうと思っていたが、先年雉子罠に置いた鮭に違いない。そのときの値段わずかに三分五厘に過ぎなかったものを。おのれ身の程を忘れたか」と言って杵で頭をしたたかに打ちのめして退治した。
さてこの様子を見聞きした所の者たちは、かの商人を神仏のごとく敬ったが、魚売りは我が手柄を否定して言った。「ひとえにこの杵の威徳によるものなので、むしろこれを神と崇め申すべきだ」と。そこで祠を築いて「杵の宮」と仰ぐようになった。
(『綾部史談』)
【伝承探訪】
杵の宮はいま藩祖九鬼氏を祀る霊社と合祀されて藤山の麓若宮神社の境内にある。井原西鶴が「丹波に一丈二尺の乾鮭(からざけ)の宮あり」(『諸国咄』)と紹介したように、不思議ないわれを有する神社である。興味深いのは伝説が大原神社の鮭の禁忌を語ることだ。大原神社の氏子は鮭を食べない。そして鮭の禁忌を語る伝承も伝わる。この神社は三和町大原に鎮座する。安産・五穀豊穣の神として藩主九鬼氏の崇敬をうけていた。
『丹波志』によれば、天児屋根命が宮地を探してこの地に来たところ、水底より金色の鮭が現われて次のように告げた。「我は水底に住む者ではない。数千年の間この山を守る神である。いま嶺に白と青の幣ありて光を放つ。まことにこの地は大神の鎮まる霊地にふさわしい」と。同書はさらに悪事や不浄のあるときは、水面に鱒や鮭が浮かぶと記す。また鱒や鮭を食べぬとき、お産は安らかになると言い、妊婦はこの禁忌を守ったと伝えられる。大原神社は安産・豊穣の神として、鮭・鱒の禁忌を伝えているのである。
杵の宮伝説は大原神社とかかわって鮭の禁忌を語る。ならばそれは東北地方の「鮭の大助」の伝承と一脈通ずるものとなる。旧暦十一月、鮭の王〈大助〉が一族を従えて川を遡る。そのとき「おおすけこすけ今のぼる」という鮭の声を聞いた者は、三日以内に死ぬという。
なぜ池の主なる〈鮭の王〉を退治した杵が神と祀られるのだろう。若宮神社の四方宮司は、杵の音は邪気を払いますからと答えられるのだ。杵は破邪の呪具である。そしてかつては生命力のシンボルでもあった。宮廷の鎮魂祭(たまふりまつり)(天皇の生命力を増大させる祭り)の呪具のなかに臼と杵が見えるように(『延喜式』〉。
杵の宮伝説は、鮭の禁忌を語る「乾鮭の宮」の物語である。それは遠い昔、杵を神と祀る由来を語る豊穣の神話だったのだろうか。
綾部から須知山峠を越えればそこに大原神社は鎮座する。鮭は末社飛龍峰明神として祀られている。
(『京都の伝説・丹波を歩く』) |
杵の宮由来記
綾部市寺町の谷すそを流れる、田野川の一帯を、「池田」といっていますが、大昔、この谷は、おのづから大きい池であったことは、いまでも古老は、この地方のことを「古池」といい「正歴寺のうらから一ノ瀬まて、船で通った」という、博承さえのこっています。それが後代「池田」と、いわれるようになったのは、いつの世から、開こんされたものか、近くを流れる由良川に切り開いたものか。あるいは風水害のとき、自然に崩れてそうだったものか。ともかくこのあたりが、「寺村」「神宮寺」などと、よばれているように、上代インシンをほこっていた文化の中心地帯てあったろうことは、容易に想像されるようです。また、この地方が須知山峠の麓にくらいし、大昔、京に通じる要路として、たくさんの人々が、往き来し、この美しい池の風光とともに、いくたの物語があったことでしょう。「杵の宮由来記」は、その一つであります。
○
大昔のことである。物語は丹後の魚の行商人からはじまる。
秋風のそよぐ吹くころ、丹後から、魚売りの行商人がはるばる丹波路をこして、うんと仕入た干魚の荷物を、あえぎつつ、中村(綾中)から並松を通り、寺村の山道に登ってきて、この池のほとりで、やっと一ぷくしようとしました。
当時このあたりは、うつそうとおい茂った大森林、原生林そのままの大木が、たけなす雑草とともに、亭々とそびえていました。「やっとこせ」と、重い荷を下して休んでいた魚屋は、そのとき不意に、林の茂みのなかから、バタバタと異様な物音がしたので、ギョッとしました。おそるおそる昔のした、茂みのなかをのぞいてみると、そこには、村人の仕かけた、ワナに一匹の雉子が、あしをとられて、バタバタもがいているのです。
「なアーんだ、びっくりさせるじゃないか」と、魚屋はひと安心しましたが、「まてョ」魚はいつも食っているが、鳥の肉は、なかなかありつけない。一つ取りかえつこしてやろうと、一人がつてんして、雉子を荷のなかに、ぼんとしまい込み、そのかわり一尾の塩鮭をワナにかけて、魚屋はすたすた、寺村から須知山峠えと、急ぎました。
ワナをしかけた村人は.なんか獲物はと、日暮どき、池のほとりにやってきました。と、みると、ワナには思もよらぬ、魚みたいなものがかかっているので、吃驚しました。
「これは何としたこっちや、魚も魚だが、これは鮭じゃないか」
と、二度吃驚しました。というのは、当時この附近一帯は、大原神社(天田郡川合村大原)の氏子であり、大原の氏子は、鰻と鮭は、ぜつたい喰べなかったものです。
鳥の獲物のかわりに、久しぶりに海の魚にありついたが、なんともしようがないので、「チエッ」と、舌打するとともに、
「神さんの祟りにあつてはつまらない、オイ鮭公、この池の主になれ!」
といって、勢よく鮭を池の真中めがけて投げこみました。すると、どうでしょう。鮭はときどき、白い腹をみせつつ、こっちをみるようにしていたが、ついに水中にかくれてしまいました。村人は、恩はずゾッと寒気をおぼえ、まつしぐらに、家の方に逃げ帰りました。
それから、一年あまりたって、この他にはときどき、不思議なことが起るようになりました。ある百姓は、池のあたりで、なんともいえぬ怪物に出合って逃げかえったが、そのまま熱をだしてねこみ、うわ言に池の怪物のことばかりいっている。これが一人だけでなく、誰れさんもみたかれさんもみた。あるときは追かけられた。という話もでて、この美しい池は、いまや淋しい、気味のわるいものになってしまいました。
しかし、この池のはたの道は、丹波、丹後と、そして京街道の要路で、ほかに脇道を通ると、いうわけにはまいりません。それから附近一帯の人々が、大変心配になりました。と、いうことは、ついに毎年人身供養として、少女を一人づつ池の主にださねば、いつ、この地方一帯に恐ろしい祟りがあるかわからんということになりました。そしていけにえになる娘の家には、どっからか白羽の矢がたつというのです。大事な娘を泣きの涙で送った親たちは、もうすでに三人、ことし四人目の人身供養に、ださねばならなくなったのが、青野の宿屋の、かわいい娘でした。
さて、一方鮭と雉子とを、とりかえつこした、丹後の魚屋は、あれから五年目、どっさり魚を仕入れて、都にのぼろうと、やってきましたが、綾部で日が暮れ、いつもとまる青野の宿屋え
「今晩は、丹後の鮭賣りだが、こんばん宿を一つ」
と、勢よくいいましたが、いつも機嫌よく迎える宿の主人が、今日にかぎって、妙にふさぎこんでいます。
「今日はちょっと取込んでいるので、どこかほかの宿え……」
というのです。魚屋は
「冗談いっちゃいけないよ。取り込んでいるつて、誰れも出入があるようすはないじゃないか水臭いこというんじゃないよ。どこだってかまわない」
と、いって元気よく、勝手しった部屋には入ってしまいました。宿屋の主人は、なじみ客のことであるし、しかたなく、「それでわ」と、いって泊めることにしました。
魚屋は、クシャクシャ腹で、夕飯もそこそこ、早寝をしました。フツと眼がさめますと、隣りの部屋から、ススリ泣の声が、するではありませんか。じツと、耳をすましますと、
「ここまで大きくしたのになア」
「いくら池のヌシだといっても、腹がたつ」
「あアあア、もう、今夜かぎりの命か」
すると、娘の声も、まじって、
「おつ父う、おつ母ア、あしや、こわい」
「ああ、いじらしい」
といって。また、夫婦のすすり泣く声がします。魚屋は、やにわにガバと、飛びおきました。
そして、がらりと、ふすまをあけますと、そこには、白裳束の娘を中にはさんで、宿の主人夫婦が泣きくづれています。「あツ」と、驚く夫婦を制した魚屋は、
「なンだって、なンって、驚くのはこっちのこっちや。なにツ、今夜限りの命だツ!驚き、桃の木、山椒の木ってやつだよ。えいツ、黙っていっちゃわからない。なんのこっちや話してみなア」
夫婦の物語は、四年前からの池の怪異と、池の主に献げる人身供養のはなし、今年は、わたくしの娘に、その白羽の矢がたったことを、涙ながらに話しました。
じっと、聞いていた魚屋は、なにか思いあたることがあるとみえ、大きくうなづいていました、決心していいました。
「ようし、おれが一番、その怪物とやらを退治してやろう」
「ええツ、それでも祟りが!」
と、おそれおののく夫婦を制して
「祟りなんてクソくらえだ、そのヌシってやつを、たたき切ってしまえば、こっちのもんじゃ
まア オレにまかしておきな」
といって、魚屋は、帯をしめなおし、はや天秤棒をにぎって、立ちかけましたが、なんと思ったか、土間の隅にかけてある、杵を、みつけ
「やツやツ いい得物があるゾ、これは屈強のものじや」
と、いってその杵をしっかとにぎり、夫婦と娘をうながして、魚屋は、そのあとにつづいて家をでました。綾中から由良川添に、やがて、道を右にとり、池の土手をあがってゆきますと、くらい林にかこまれた、池は、おりからうすぐらい、弓張月にぼんやり照らされて、気味わるく静まり返っています。土手のなかほどには、新らしく作った、青竹の、人身供養の構があります。夫婦は、その中えやつと娘をいれると、かけるように土手をくだりました。魚屋は、それをみ届けると。
一抱えもある大木の影に、そツと、身をかくして、容子いかにと、娘の方をみていました。すると、やがてのこと、池の水がざわめくと思うと、さツと、波もんをあげてあらわれた怪物は、なあ-んと、丈余もある、鮭の怪物ではありませんか。
「やっぱりそうだツ、あいつだ。ここで取りかえつこした、鮭の野郎だ。池の中にはいって、主になりおりやがつたナ。ようし、いまにみておれ!!」
と、腹のなかで叫びました。鮭の怪物は、ばアツと、水をきって、土手にはいあがり、そろそろ、娘の方に近づいてゆきます。いまや、躍りかかろうとするシュン間、魚屋の杵の一撃は、怪物の脳天を打砕きました。
「おのれ! たかが三分五厘の野郎じゃないか。くたばれ!!」(三分五厘とは鮭のねだん、米の代一合たらず)
と、さらに止めの一撃で、怪物は、もう、動かなくなってしまいました。
生きた気持もない、娘をかかえて、魚屋は、夫婦をよび、意気揚々と青野に引きあげました。魚屋は、附近一帯のものから、神様同様の扱いされる騒ぎになりました。
「わしの力じゃない。みんな、この杵の力さ!!」
と、あっさり言葉をのこして、魚屋は、都にのぼって行きました。
村人たちは、不思議な偉力を発揮した、この杵を、寄合の結果、御神体として、池の上のお山げんざいの本宮山のいただきに祭ったのが、この杵の宮であるということです。
○
「杵の宮」のことは、井原西鶴の「諸国はなし」 (一六八五)の開巻一頁の序文の中にもでています。「世間の広き事・国々を見巡りで 談話の種を求めぬ。熊野の奥には、湯の中にひれ振る魚あり、筑前の国には、一つをさし荷の大蕪あり、豊後の大竹は手桶となり、若狭の国に、二百余才の白比丘尼、近江の国堅田に、七尺五寸の大女房もあり、丹波は一丈二尺の塩鮭の宮あり。松前に百間続きのあらめあり。(中暮)是を想ふに、人は妖物世に無いものはなし」
本宮山にあった杵の宮は、そのご綾部藩主九鬼さんの祖霊社とともに、若宮神社の境内にうつしまつられていたことは、綾部の人々には、よくしられていることであります。ところが、昭和のはじめ、兵庫県印南郡西志万村に住んでいられる、九鬼隆治氏が、綾部にこられ、九鬼の祖先が、おろそかにされているとかいって、おこられ、宮居をこわして、持ち帰られるとき杵の宮の御神体まで持ち帰られ、いま、このいわれの「杵」はもう綾部にはなくなっています
杵の宮は、九鬼氏とは何の関係しないもので、この地方一帯につたわる、貴重な文化財てあります。かつて、三都新聞社は、この杵の復帰運動について要望しました。そのご、この要望は、そのままになっていますが、われわれは、何とかして、杵の宮の御神体である、この、杵の復帰を実現ざして、わが郷土の文化を豊かに、したいものと念じています。
なお、本文はかつての「三都新聞」昭和二十六年九月十、十七、二十五日連載のものを、ほとんど、そのまゝ引用ざしていたゞきました。
なお、凸版の地図は、村上佑二氏「平安」(昭和二十九年四月)にのる「綾部の傳説 杵宮由来」から、厚意ある借用ざしていただきました。同誌の由来には、江戸時代、綾部藩士、辻村良衛の「ふるさと」の写本の全部がのっており、まことに、貴重なものであります。三都新聞の記事、したがって、本稿も、この「ふるさと」がもとになっていることは、いうまでもありません。
(『何鹿の伝承』) |

上野町の小字一覧
上野 小倉 五反田 西ケ窪 上池田 下池田 藤山 上野 小倉 藤山
関連情報

|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|