 京都府南丹市美山町原 京都府南丹市美山町原
 京都府北桑田郡美山町原 京都府北桑田郡美山町原
 京都府北桑田郡宮島村原 京都府北桑田郡宮島村原
|
原の概要
《原の概要》

神楽坂トンネル手前の集落。由良川支流原川(宮脇川)の源流域、府道19号(園部平屋線)が走り、沿道に集落が散在する。南の郡境に神楽坂がある。坂名は、江戸期に火災を防ぐため、道祖神社(宮脇)の託宣によって神楽堂が建てられ、神楽が奉納されたことに由来し、現在も神楽は毎年1回奉納され、周辺の地域の安泰が祈られているそうである。
原村は、江戸期~明治22年の村。宮島11ヵ村の1。古代は弓削郷、中世は野々村庄。慶長7年(1602)幕府領、元和5年(1619)より園部藩領。明治4年園部県を経て京都府桑田郡、同12年北桑田郡に所属。同22年宮島村の大字となる。
原は、明治22年~現在の大字名。はじめ宮島村、昭和30年からは美山町の大字。平成18年からは南丹市の大字。
《原の人口・世帯数》 119・43
《原の主な社寺など》
 村内に神社はなく宮脇の道相神社の氏子。 村内に神社はなく宮脇の道相神社の氏子。
 曹洞宗能救山放光寺 曹洞宗能救山放光寺

曹洞宗能救山放光寺は園部徳雲寺末で文政10年(1827)の再建。本尊は地蔵尊で、境内には樹齢250年を超えた老楓があったという。
能救山放光寺 原にあり、船井郡園部曹洞禅宗塩田山徳雲寺末なり。現堂宇は文政十年の再建にか丶る。境内に樹齢二百年を超えたる老楓あり。
地蔵堂 神樂坂の麓にあり。古雅素朴の小堂にして運慶作と傳ふる地蔵尊の木像を安置す。安産及び除災の靈驗著しとて賽者常に絶えず。編者未だ參拜せざれば本尊の彫刻的價値につきては何等云爲する能はず。 (『北桑田郡誌』) |
《交通》
《産業》
マンガン鉱山
《姓氏・人物》
原の主な歴史記録
経の塔、神楽坂縁起、大滝不動明王など、
大字原に「經の塔」と名づくる祈祷講あり。文政十年丁亥正月十七日 放光寺の住職黄梅和尚の村内安全五穀成就悪疫退散を祈祷せるに創まりしものにして、今は毎年二月十七日より三日間、原の男子は禮服を着用して菩提寺に參拜し、十六善神をまつり、大般若理趣品三昧の祈祷會を修行する例なり。現に神楽坂の麓に理趣分經一部の一石一字塔ありてこの事を記念せり。
神楽坂の縁起 本村大字原より船井郡五ヶ莊村大字佐々江に通ずる神楽坂と、その峠に建てる鳥居とにつきては左の傳説ありて、古記に載せらる。
後土御門天皇の文明五年夏より秋にかけて、野々村一庄は火早(ひばや)くしてとかく火災頻に起り人々困難と恐怖に襲はれたるが、恰も九月九日道相神社例祭の御湯の儀に際り、計らずも御託宣あり。曰く。愛宕山をこの野々村庄より拜し得べき地黙あり。この拜所を索め神業を奏し、愛宕明神に祈願せんには爾来必ず火難を兔るゝを得んと。由りて庄内三十三村の人々熟議をこらし、神託の拜所を求めしに、つひに原村南方の峰の峠にこれを發見し、鳥居と神楽堂とを建て、神教の如く神楽を奏し祈願をこめたるに、果して火難鎭まりて庄民皆愁眉を開けり。その後正月五月及び九月の二十四日即ち毎年この三日には神楽を供へ全村より參拜するを例とせしが、かの神楽堂は漸く朽廢に歸し隨つて神業を奉ることも等閑に附せられ、烏居も亦頽破に傾きしに、その頃より庄内にまた火災屡々起るに至りしかば原村より鳥居を建進せり。これ正親町天皇の天正二年にして、この後は原より之を改築し奉る例となり、近くは明治三十九年及び大正九年にも建立したり。神楽は毎年一回之を奏し、以て北部五ヶ村 宮島平屋知井鶴ケ岡及大野 の安泰を祈るなり。かくて神楽坂の名起れりと。
大瀧不動明王 大字原より弓削村に赴く間道奥山筋に大瀧谷と稱する地あり。ここに不動明王の石像をまつる。昔文政二年六月十一日原村より安置し奉る所なりと傳ふ。然るにこの石佛は河中の一岩石の上に在しますも、その後幾回の洪水に遭ひて毫も流されたまふ亊なきは、不思議といふの外なし。殊に明治二十九年九月の洪水は稀有の大水にて、山中数ヶ所崩壊し巨巖轉動して土砂木材の流下夥しく、此の巌には氾濫せる洪水衝突して名状すべからざる状態を呈せしかば、石像も亦土砂に埋められたれど、その位置は聊も変ぜざりき。この靈妙不可思議の實證を目撃せし人々の尊信はこれより一屠の篤きを加へたり。又この谷には燧石と呼ばるゝ岩あり、旱魃打續く時はこの岩より火を吹く。松明を供して祈願すれば必ず雨を降らすと傳ふ。今も毎年七月二十八日にはこの岩に祈祷を行ひ、原の區民皆参拝する例なり。
(『北桑田郡誌』) |
原の伝説
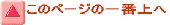
原の小字一覧
原(ハラ)
畑中(ハタナカ) 西垣内(ニシカキウチ) サイミ 尾ノ上(オノウエ) ノテ 竿ノ元(サオノモト) 石原(イシハラ) 坂尻(サカジリ) 和田川原(ワダガワラ) 古ミノ越(フルミノコシ) 屋栗垣内(ヤクリカキウチ) 和田(ワダ) 古田(フルタ) 彦谷(ヒコダニ) 土井垣内(ドイカキウチ)
関連情報

|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|


