 京都府南丹市美山町河内谷 京都府南丹市美山町河内谷
 京都府北桑田郡美山町河内谷 京都府北桑田郡美山町河内谷
 京都府北桑田郡知井村河内谷 京都府北桑田郡知井村河内谷
|
河内谷の概要
《河内谷の概要》
中集落から府道369号(八原田上弓削線)を南ヘ入る由良川支流河内谷川流域の集落。
古代は弓削郷、鎌倉時代以降は知井庄。
河内谷村は、江戸期~明治22年の村。知井12ヵ村の1。慶長7年(1602)幕府領、寛文4年(1664)より篠山藩領、山林は享和2年(1802)より禁裏御料となり京都代官の支配を受けた。元禄13年(1700)丹波国郷帳、天保郷帳に村名の記載なく、中村に含まれていたと考えられる。しかし江戸末期には独立村となったらしいという。明治4年篠山県、豊岡県を経て京都府桑田郡、同12年北桑田郡に所属。同22年知井村の大字となる。
河内谷は、明治22年~現在の大字名。はじめ知井村、昭和30年からは美山町の大字。
《河内谷の人口・世帯数》 31・16
《河内谷の主な社寺など》
 村内に神社はなく北の八幡神社の氏子。 村内に神社はなく北の八幡神社の氏子。
 曹洞宗円通山昌徳寺 曹洞宗円通山昌徳寺

寺伝に、天仁元年(1108)良忍が当地へ巡錫の際開いた寺という。もと天台宗であったが、鎌倉時代に道元の勧化によって曹洞宗に改宗。その後荒廃したらしく元禄15年摂津国尼崎の藩士徳瑞正が同寺の住職となり再興したという。亀山藩より寄進された大般若経600巻のほか、釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来・二十五菩薩絵像・涅槃像・十六善神・千手観音画像などがあるそう。
| 圓通山昌徳寺 字河内谷にあり。鳥羽天皇の天仁元年大原の良忍 融通念仏宗の開祖聖応大師と諡す 本村門防寺へ巡錫の際開基せられ、もと天台宗なりしが、道元禅師 曹洞宗の祖陽大師と諡す の勧化によりり改宗せられたりと傳ふ。東山天皇の元禄十五年攝津國尼ヶ崎の藩士徳瑞正なるもの曹洞宗の僧となりてその布激に力め、四方を巡歴してこの地に来り、つひに當寺の住職となりて本山を中興せり。後龜山藩 丹波 より大般若經六百卷の寄附を受け、今尚襲藏す。寺寶に釋迦如来木像、阿彌陀如来、薬師如来、二十五菩薩繪像、涅槃像、十六善神、千手觀音画像等あり。 (『北桑田郡誌』) |
 門坊寺跡:明智光秀に破壊された古刹 門坊寺跡:明智光秀に破壊された古刹
東隅の門坊寺山中腹の門坊寺遺跡。門坊寺は桓武天皇の勅願寺で、かつては七堂伽藍があったというが、天正年間に廃寺となり、現在は毘沙門堂を残すのみ、堂跡と伝える平坦地があるという。昌徳寺の裏山あたりのようだが、案内がないと行けそうにもない。。。文献だけ紹介すると、
門坊寺址 字河内谷の東隅に峙立せる門坊寺山の中腹にあり。本寺は聖徳太子の頃に創建せられ、桓武天皇の勅願所となり、傳教大師最澄堂宇を修築して丹波道場と定め、寺領五百石 平安朝の初頃領地高を表はすに石の名なし を有し、檀徒今の平屋村に及び、七堂伽藍坊舍門塀悉く備はりしが、明智光秀周山城を築くに當り、寺領を沒收し堂宇を破却して之をその用材に充てたりしを以て、荘厳は一朝に滅失し 麥秀漸々の廢墟となりしぞうたてき。これを福正寺所蔵の縁起には傳へて左の如く記せり。
明智光秀天正八年庚辰より始めて周山に城廓を構へしに、國郡の社寺を破壊し、堂閣をたふし長牀をくづし坊舎を破滅して用材と致せしによりて、梵寶寺(門坊寺)の七堂伽藍も悉く破却して、弓削谷に送り周山に運びたれば、坊址は目前に畑となり双林は空しく猿飛び鹿臥す床と荒れ行き、月夜に霜かと疑はれし堂前の白洲は茅尾花生出でヽ蕈茸を求むる野となり、不斷の霧とあやしまれし香煙はあらはなの烈しき風に跡形もなくぞなりにける。僅に残れるは堪慶の作といふ長七尺餘なる仁王計りぞすごすごとあばらなる軒に立ちたまへる。丈六の釋迦の像は御首のみ見え給ふ。實にあはれなる事どもなり。師弟の因める法師も處々に離散して還俗しけるもありとなり。依て村の中に上坊下坊上ノ坊一ノ坊新シ坊などいふ家の垣名有之となん。その昔は古坊とて河内谷の内東の谷の上にありて。坊舎も六ヶ所有之と申傳へたり。近頃江和村中井の名孫彦兵術といふもの、再建を企て統領して庄内各奉加に進み、三間四方餘の二字の草堂をたてゝ、堂内の両方に二王を安置し、正面に釋迦の坐像を1躯形の如く造立せられたり。今中村蔵王の東にある釋迦堂之なり(下略)
と。明智光秀に対しては住僧も反抗したりしを以て、什器寶物等多くこの時に滅失せしが、坊官の密に隱匿搬出せし佛像のみは幸にして兔れ、今なほ處々に之を散見す。即ち仁王の大像は一且字中の仁王屋敷に移され更に大和國初瀬の長谷寺に、釋迦の木像は周山村慈眼寺に之を見る。その後坊官の遺族は河内谷に住みつ丶も歸農し上坊を冒すといふ。今本寺址に就きて検するに、七堂伽藍屋敷は六十間に四十間、坊官屋蚊は二十間に五十間、仁王門屋敷は二十五間に五間、案内屋敷は四間に六間の奥行間口を存す。寺址に唯一宇の毘沙門堂を存するも、他は悉く荒廃し表門及び裏門に當りし道路も今は樵夫往来の外ゆきかふ人なきはいざゞはかなき心地こそすれ。 (『北桑田郡誌』) |
もう500年も前に破壊された寺院であるにも拘わらず地元では大切にされていて、NHKの大河ドラマを機によみがえらそうと立ち上がられたという。
 「門坊寺を蘇らせる会」 「門坊寺を蘇らせる会」
《交通》
《産業》
《姓氏・人物》
河内谷の主な歴史記録
河内谷の伝説
 御所ヶ谷 御所ヶ谷
南方の山中の御所ケ谷には2間四方の岩窟があり、允恭天皇の皇子木梨軽皇子が罰せられて当地に流された際、この岩窟に住んだと伝えている。
| 御所ヶ谷 河内谷の南方山中 字中の南方約二里 にあり。こ丶に方二間ばかりの岩窟ありて優に数人を容る。内部は漆喰土の如く滑かにして堅く起居するに堪へたり。村民の口碑によれば、人皇第十九代允恭天皇の御字に皇太子木梨輕皇子故ありて東宮の位を失ひ、遁れてこの地に入り、此の岩窟に住みて世を忍びたまへりといふ。宮島村平屋村の傳説にも之を存せること既に記述せる所の如し。 (『北桑田郡誌』) |
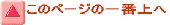
河内谷の小字一覧
河内谷(かわうちだに)
古坊(ふるぼう) 奥ノ田(おくのた) 寺ノ下(てらのした) 蔵ノ本(くらのもと) 下段(しただん) ヲガミ本(をがみもと) 段上(だんじょう) 反保(たんぼ) 小井根(こいね) 西山(にしやま) 梅ノ木(うめのき) 岩滝谷(いわたきだに)
関連情報

|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|

