 |
島(しま)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島の概要《島の概要》  美山町役場、今の南丹市役所美山支所、何かこの一角は閑散として、もうくたばりましたの感がある。合併すると良き点もあるかも知れないが、他方こうした事態になろうことも予測されたところであった。このままではヤバかろう、どう立て直すのであろうか。ガンバレ美山町、上流が荒れると中下流も間もなくそうしたことになる。そうした町の中心施設が集まる所である。由良川本流と支流棚野川の合流点で、昔から重要な場所であった。 古代は弓削郷、中世は野々村庄。 島村は、江戸期~明治22年の村。宮島11ヵ村の1。慶長7年(1602)幕府領、元和5年(1619)より園部藩領。 当村は水利の便が悪く、文政10年に倉内権平が由良川筋大丸に新堰を築くことを藩主に歎願した。これに対し上流知井郷からは筏下げおよび鮎登りに支障をきたすとして異議が申し立てられたが、のち和解し、2年の歳月を費して天保元年大丸堰が完成した。明治4年園部県を経て京都府桑田郡、同12年北桑田郡に所属。同22年宮島村の大字となる。 島は、明治22年~現在の大字名。はじめ宮島村、昭和30年からは美山町の大字、平成18年からは南丹市の大字。 《島の人口・世帯数》 128・70 《島の主な社寺など》 紫雲寺跡に稲荷神社があり、境内に周囲2丈の巨松、参道両側には倉内権平の植樹と伝える松があるという。  応永2年(1395)細川満元の開基、開山は希世と伝える。寺蔵の禁制札によると、文亀年間(1501-04)、由良川・棚野川の落合より上流静原の滝田井までの間は南禅寺(京都市左京区)塔頭聴松院領で、河川流域は殺生禁断であることを布令しているという。 『北桑田郡誌』に、 「龍潭山岩栖寺 島にあり。臨濟禪宗南禪寺の末寺にして、應永二年三月細川滿元の開基。開山希世と傳ふ。寺の過去帳に「岩栖院殿悦道觀公大禪定門開基、應永三十四年十月十六日歿」と見ゆ。この年月日は恰も細川滿元の卒せし日に當り、細川氏の家紋が九曜星にして本寺の紋章が九曜星と五枚笹なる點より、両者を推考して何等かの因縁あるべしと説く者あり。本寺に古制札を存し、之に由って文龜年間に上由良川棚野川の落合より上流靜原の瀧田井までの間は、南禪寺塔頭聽松院の領地にして、而も殺生禁斷を令せしことを知り得。」としている。  創立沿革など不詳、現存の堂宇は天保年間(1830-44)の再建という。 『北桑田郡誌』に、 「坊谷山正願寺 島にあり、眞宗大谷派、起源沿革詳ならず。現堂宇は天保年間の再建にかヽる。」とある。  役場の真正面の標高403mの高地を城山といい、ここに川勝越後守政行または川勝備後守継氏の築城と伝える中世の山城跡や石塁跡がある。地内の朴の木にある豊後の森は川勝豊後守の墓地と伝える。付近に矢竹を多く産し、これを盗伐するとたちまち卒倒するとの言伝えがある。 戦国期に入ると当町の全域は在地の土豪川勝氏の領有地となる。当地に点在する城跡から、有力な土豪の台頭の形跡を看取することができるという。鶴ケ岡法明寺背後の殿城は、天正年間(1573~92)頃川勝丹波守光綱の築城と伝えられ、棚の丘陵上にある乾城には、城主乾清輝の名が見えている。高野今宮の通称津向山と称する台地上には今宮城があり、川勝豊前守光照の築城と伝えられ、大野の丘陵上には松山城がある。島の標高404mの山頂平坦部には島城があり、西側斜面には石垣の一部が残り、内久保山腹には紫磨城の遺構がみられるという。 天文年間(1532~55)に、右京大夫宇津頼重が新たに広大な領地を所有し、禁裏御料への貢租を絶つようになった。当時松永久秀の力をもってしても、宇津氏を制止することができなかったといわれる。しかしその後、明智光秀が宇津氏を制して善政をしき、その功により光秀は織田信長の感状を得ている。一方、川勝氏は光秀とよく提携し、さらに豊臣秀吉からの信頼を受け所領を安堵された。戦国末期と推定される年末詳7月13日の羽柴長秀書出によれば、川勝氏の給人らの軍勢催促として知伊村・弓削村下村・棚野村の各村と野々村荘が見え、当町全域が川勝氏の分国内であったことがわかるという。 『美山町誌下』には、(図も) 「島城(美山町島) 由良川が蛇行して半円形を描く所に、北から棚野川が流入する。この東側に標高四〇三・七㍍の城山がある。主郭(I)の規模は、東西四〇㍍、南北二〇㍍の小判形で、東に小曲輪が二段と西に三段の曲輪かあり、部分的に石積みか見られ、主郭の虎口は南側にある。南尾根には南北三〇㍍・東西一〇㍍の規模の曲輪があり、尾根部に遮断の堀切がないのが疑問である。東尾根は堀切と北斜面に三条の竪堀があり。規模は小規模である。 西は堀切を越えると、六〇㍍の干渉地をおいて、南北四〇㍍、東西六〇㍍の三角形の曲輪(Ⅱ)があり、西尾根三〇㍍下には張出を伴なった土塁囲みの曲輪(企)がある。西斜面には放射状に四条の竪堀が付設してある。登城道が屈曲する部分の上部には、横矢がけが可能となる張り出しがあり、防御の工夫を感じる城郭である。北尾根には、曲輪(Ⅱ)から四〇㍍離れた南北五〇㍍、東西一五㍍の曲輪(Ⅳ)には、中心部に二条の空堀を付設し、先端部分は低土塁を廻している。この曲輪は独自の防御体制をとっており、主郭(I)や曲輪(Ⅱ)に対する求心性がない。他も曲輪間の連続性が欠如し、遺構の状態にもバラツキがみられ、曲輪を後から個別に改修した可能性をもち、各曲輪が独立した遺構である。規模的には美山町随一の城郭である。城主は川勝氏といわれ、棚野川の南部における拠点城郭である。. 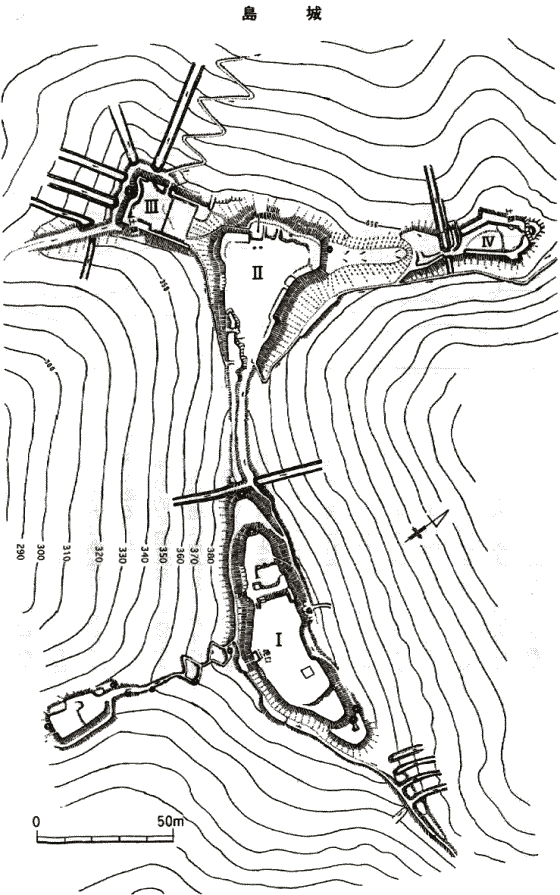 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 川勝氏について、『北桑田郡誌』は、 「川勝氏 聖徳太子の侍臣秦河勝の裔なりと稱す。豊前の守光照に至りて野々村を押領し、本村内今宮に城を構へ、戦国の世一方の雄として此の地方に威を振へり。子孫また代々足利氏に仕へ信任を博せしが。天正年中に至り?を明智光秀に通じ、ついで羽柴秀吉に屬し。いづれも寵愛を受けたり。徳川家康勢を得るに及び川勝氏また之に從ひてよくその領土を全し、つひに一諸侯の身となれり。其の一族下臣旗本の士となりし者多く隨つて江戸に移住し、本村内にその後裔を殘存せざるに至れり。 以上の説は遽に信を措き難しと雖も、本村壁瀬()清吉氏所載の『川勝家系圖寫本』と「寛政重修諸家譜」の川勝系圖とを比較するに符合せる黙多く。殆ど信ずべき値ありと思惟せしを以て、左に之を併せ載することゝせり。 川勝家系圖寫(抄出) 壁瀬清吉氏藏 ○始丹波桑田郡棚野下田殿ト云、川勝美作守、在屋敷砂木村。法號天壑宗珀大禪定門、文眞妙珠大姉室 ○川勝豊前守、在城今宮、大谷佐々江知井野々村棚野若州之内納田終上林之内三分一、以上七ヶ所領知、入道而光照院殿照山道珀大居士、始號二大膳大夫秦朝臣光照一。 ○二男川勝越後守光隆、在屋敷市場、法號樂月常安大禪定門、現照妙權大姉室。 ○三男川勝越前守朝政、法號月光宗心居士、在屋敷今宮、天正五年七月二十六日。 ○川勝九兵衛、石田治部少輔 三成 仕フ ○川勝備後守氏繼、在城今宮、法號前備州大守伯翁榮運居士。 ○川勝兵衛大輔氏隆、在城中村之中山、和田トモ云、法號龍泉院殿上林全譽理安大居士。左京亮、氷上郡黒井江御国替ト云。 ○川勝信濃守、始號二内記一、後丹波守ト云、幼名七九郎。 ○川勝家臣 市原隱岐守勝重、在屋敷砂木村 公文栗栖筑後守 兄弟葉栖豊前守 壁瀬伊豆守 (下略) ------- 寛政重修諸家譜川勝系圖(抄出) 寛永諸家譜に秦始皇より十五代廣隆が後胤なり。廣箙より美作守某まで其の間中絶すとあり。故に美作守某より系圖を記載しあり。 …」 . 『美山町誌』は、 「川勝氏 江戸時代、幕府の旗本であった川勝氏は、『寛政重修諸家譜』によると、秦氏を祖とし北桑田郡に住居したという。当初は住居地の「下田」から下田氏を祢していたが、天文十六年(一五四七)を過ぎて川勝氏と改姓した。現在美山町盛郷の林地区に下田原という地名が見られるが、特定するには至らない。 「鹿王院文書」の、応永五年(一三九八)の「下田将氏田地売券」によると、「たなの」という地名が見られる。当時の弓削庄棚野村のことだろうと思われる。確証はないが下田将氏が川勝氏の祖先であるとすれば、鶴ヶ岡地区の川合から北の地域に住居していた可能性がある。鶴ヶ岡の殿には、川勝氏と関係のある法明寺や殿城がある。また小字名には、荘園領主の耕作田を意味する「佃」があり、棚野村の中心地であったことが考えられる。 大永六年(一五二六)七月、京兆家の細川高国が細川尹賢の讒言を信じて、家臣の香西元盛を謀殺しだのに端を発し、兄の波多野元清(兵庫県篠山市八上)と弟の柳本賢治は、阿波国にいた細川晴元と結んで反乱を起こした。その後、高国方との攻防戦が続き、翌七年二月桂川、川勝寺(京都市)の合戦に敗れた高国は、将軍足利義晴とともに近江国に逃れた。 この時丹波国では、波多野氏に加担していた内藤国貞(船井郡八木町)が高国方となり、片山氏(船井郡和知町)に高国方への加担を促している。「片山家文書」によると、「然間昨日□□□□至野々村令出陣侯」と、内藤氏は、高国方として野々村に出陣しており、片山氏に対し「連々御入魂儀候条、不移時日、御着陣可為本望候」と告げている。「野々村に至り出陣」とあるが、川勝氏がどちらの勢力に加担したか、決定できる史料は見あたらない。 享禄四年(一五三一)六月細川高国の死去後、弟の細川晴国が跡目と称して活動を始める。晴国は、享禄五年若狭国谷田寺(福井県小浜市)から、九月廿五日に丹波奥郡へ入国した。丹波入国については、但馬国守護山名祐豊が丹波国守護代内藤国貞や荻野六郎左衛門尉、夜久彦次郎(天田郡夜久野町)等と相談し実行した。内藤氏が高国方であったため、晴国の丹波入国に助力したことが考えられる。また川勝氏が晴国方として活動したかは不明である。天文三年(一五三四)以降は、細川晴国の史料が少なくなり、同五年八月に摂津国天王寺において、三宅国村(大阪府茨木市)の裏切りにより自害した。 ・川勝氏略系図 ・某-光照-継氏-秀氏―廣綱 『記録御用書本古文書』によると、川勝氏が史料に登場するのは、下田を称していた天文三年(一五三四)で、細川晴元の被官である茨木長隆より、領知宛行状を受けているのが下田彦治郎である。彦治郎は、『寛政重修諸家譜』によると、後に光照と改名した人物で、これ以後、長隆から二回の領知宛行状を受けており、晴国の没落とともに、細川晴元が勢力を拡大し、川勝氏もこれに吸収され、被官となったことが推察できる。 天文七年(一五三八)二月若狭国の粟屋元隆が、武田信孝とともに守護武田氏に叛乱を企て、合戦に破れた元隆は丹波に逃れ、九月丹波の細川氏被官である下田氏に合力をもとめるが、幕府は細川晴元に命じてこれを制止させた。若狭と国境を接する下田氏にとっては、重大な事件であった。 天文十六年(一五四七)宇津備後守元朝が、幕府御料所の桐野河内村(園部町北部)を違乱した。この時の文書と思われるものが残っており、幕府は下田氏に宇津備後守の跡職を宛行っている。 天文十八年六月三好長慶は、摂津国江口の戦いで、父元長の仇である三好政長を討ち、主君である細川晴元が政長に味方したため、主君の晴元とも合戦となり、晴元は敗北して前将軍足利義晴等とともに、近江の坂本へ移った。長慶は、細川氏綱を擁して七月に入京したため、足利将軍とも争うことになった。細川晴元は、天文二十一年(一五五二)三月十二日若狭へ落去し、守護武田氏の元で再起することを目論んだ。その後晴元は、丹波八上城主の波多野元秀との連絡網を確立させたため、三好長慶は四月二十五日八上城を包囲した。しかし、長慶の妹婿である芥川氏や池田氏・小川氏が波多野氏に味方したため、包囲を解いて越水城(兵庫県西宮市)に引き上げた。晴元はその後、若狭から葛川に帰り、八月二十六日丹波の宇津から小野に着いた。 川勝光照は、幕府の奉行人である飯尾元連から領知宛行状を受けており、細川晴元が三好長慶に江口の合戦で敗北し没落したため、光照が将軍側への加担を働きかけたことが推察できる。下田氏は、この時「川勝左京亮」と改姓しており、天文十六年(一五四七)六月の文書では「下田」を称していたため、この文書前に改姓したのである。三好長慶と将軍義輝の仲が悪化した天文末期(一五五〇~五四)、川勝氏は将軍方として活躍し、秀氏が義輝から感状を受け、被官として「仍召加供衆訖」とある。 天文二十二年(一五五三)七月十四日、晴元方の手勢が宇津から洛北に出陣し、長坂口、船岡山に陣取った。この時、晴元軍と行動を共にしていた下田氏が、「出衆之内丹州下田、同名一人馬手に余、河内衆中へかけ入、生討之云々」と『言継卿記』に記述され、下田氏の同名衆が馬の扱いをあやまり、敵の方向に進んで討ち取られたという。 永禄三年(一五六〇)河内国高屋城主畠山高政が、以前三好長慶の力を借りて排斥した安見氏を守護代に任じた。長慶は、この事にっいての相談が無いことに怒り、河内に兵を進めた。これと同時に、内藤宗勝の書状によると、「仍御郡牢大等、若州衆相副、至野々村罷出候」と、六月若狭に潜伏していた丹波の牢人衆が、若狭衆とともに野々村に進入して来た。「一円不甲斐之敷躰候」と内藤宗勝(松永長頼)が嘆いている。また、「彼表衆可引相与之討儀、調略を頼二出候処ニ、川勝を始而、対拙者、無ニ依堅固之覚悟、則取結候条、仰天仕合候」と内藤宗勝に忠誠を誓っていた川勝氏が調略をもって解決すると期待していたが、降伏したため、長頼は仰天した。「彼近辺不残取人質。相固候」と侵入した牢人衆は野々村近辺で人質をとり、戦闘体制をとったため、宗勝は討伐のため若狭の逸見氏と協議をするため、山内へ着陣する旨を、天田郡馬廻衆中へ告げた。 「筑、新陣への事にて候、なたのしやうの打こしもたな村之内に陣とりにて候」と、内藤宗勝は、舞鶴市より若狭に入国し、逸見氏に加勢を要求して、逸見右馬・逸見筑後が出陣し、筑後等は棚村内(美山町)に陣取り、逸見経貴も二班で出陣した。この戦いで「のゝ村口の道ハとまりまいらせ候まゝ」、と洛中へ通る野々村道が封鎖されていた。 若狭では、逸見経貴書状によると、「丹波国内藤連々当国を被頼候ニ付而、去六月八日ニ御人数被相添、丹波野々村之内中の河内と申在所に山取ニケ所、其外つたいの山にて一ケ所被仰付候、其内両度の合戦候へ共何も当国被得勝利候」と、内藤宗勝の出陣依頼に応えて、丹波の野々村の中の河内という在所に二ケ所陣取り、その他尾根続きの山にも一ケ所陣取り、その内両度の合戦に勝利し、「川勝方より拵申子細共候間、如御本意成行可申候間、目出度重而可申上候、」牢人衆に味方した川勝氏の事も色々と子細はあったが、思いのようにかたづき目出度い事であると、逸見氏は川勝氏が牢人衆から離れたことを喜んでいる。 「小林家文書」によると、川勝氏が天文三年に細川晴元から宛行われた日吉町胡麻の領地の一部を、永禄五年に内藤宗勝が、小林氏に支配を任せたことにより、小林氏との争いが発生した。しかし、その後、争いは決着した様である。 三好長慶が死亡した永禄七年七月以降、三好三人衆の一人三好長逸が、川勝継氏に領知の保証を約束した文書である。年未詳であるため詳しいことは不明であるが、永禄八年八月丹波の支配を任されていた内藤宗勝が戦死したため、三好長逸が三好氏の勢力維持をねらって発給したものであろう。 織田信長は、天正元年足利義昭に加担した宇津氏と内藤氏が、同三年の時点においても出仕しないため、これを誅伐するため、明智光秀を派遣するので、協力するように川勝氏に指令した文書が、天正三年の六月に発給されており、川勝継氏は信長入京時の、永禄十一年(一五六八)より協力していたのである。 また同三年十月明智光秀は、丹波国黒井城主赤井直正を包囲したが、翌四年の一月、波多野秀治の裏切りにより敗走する結果となった。二月二十七日信長は、川勝秀氏に対し、敗戦後の態度不変を評し、逆徒討伐の忠節を要求した文書を発給している。 羽柴長秀(秀長)から、川勝氏の知行地域である野々村・弓削上下・佐々江村・大谷村・知伊村(知井)・棚野村・上林三分一・田原村・知見谷村の給人・百姓すべてに、川勝氏の申付けに応じ、罷り出るように指示している。 この文書は、七月十三日発給のため。天正十年の山崎の合戦後が考えられる。同十年九月九日には、川勝右兵衛太夫が何鹿郡内の上林三分二の領知を受け、三五三五石の知行を、秀吉から受けている。その後、徳川幕府の旗本となり、江戸時代末期まで続いた。」 島の主な歴史記録島の伝説『北桑田郡誌』 豊後の森 島地内朴(ほう)の木にあり。傳へて川勝豊後守の墓地なりといふ。この附近多く矢竹を産す。人之を伐採すれば立どころに卒倒すと稱して之を盜むものなし。之を得んと欲するものは、洗米を供へて其の旨を告げたる後これを伐採すれば炎厄なしと聞けり。 島の小字一覧島(シマ) 神田(ジンデン) 狐岩(キツネイワ) 英サ(ハヤブサ) 堤ミ(ツツミ) 名所(ナトコロ) 上島野(カミシマノ) 下島野(シモノシマ) 島台(シマダイ) 往古瀬(オゴセ) 水ノ手(ミズノテ) 山根(ヤマネ) 朴ノ木(ボウノキ) 下小栗栖(シモオグルス) 上小栗栖(カミオグルス) 上栗栖(カミクルス) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『北桑田郡誌』 『美山町誌』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2019 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||