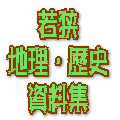 |
口田縄(くちだの)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口田縄の概要《口田縄の概要》 国道162号沿いの「小浜市総合運動場」のあるあたり。対岸へ通じる「口名田橋」がある、南川は深いところを流れている。河岸段丘であろうか。 中世は今富名・富田郷に属し、守護武田氏被官大塩氏の本貫地。中世には奥田縄を合わせて田縄とよび、大永7年(1527)10月21日付の明通寺寄進札に「田縄水船」とみえる。弘治2年(1556)6月の明通寺鐘鋳勧進算用状には「百廿文 たなハ大塩新五郎殿百姓」を載せ、「たなわ」と発音した。 口田繩村は、江戸期~明治22年の村。奥田縄・須縄と合わせて三縄(みなわ)とも呼ばれた。小浜藩領。「雲浜鑑」によれば、家数36・人数165、寺院は禅宗大光寺、神社は春日大明神。元文年間から田繩村で瓦の製造が始まり官家の御用にのみ焼いたと記されている。また江戸末期から石灰の製造が始まり現在もかま跡などを残している。明治4年新滝谷村を合併。同4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。.同22年口名田村の大字となる。 口田繩は、明治22年~現在の大字名。はじめ口名田村、昭和26年からは小浜市の大字。明治24年の幅員は東西5町・南北2町余、戸数44、人口は男121 ・女108、小船25。集落内には大塩氏の館跡をうかがわせる館ノ口・館の小字がある。 《口田縄の人口・世帯数》 150・47 《口田縄の主な社寺など》 古代にも須恵器を焼いており、字大佐近の谷間に窯跡がある。 春日神社は大塩氏(守護武田氏の重臣)の守護神であったという。口名田橋のたもとに鎮座。  春日神社には弓打ち神事(3月8日)が残る。 『遠敷郡誌』 春日神社 村社にして同村口田繩字宮ノ脇にあり、元春日大明神と稱し天兒屋根命・經津主命・武甕槌命・姫大神を祀る。  裏山が大塩城で、大光寺は大塩氏の菩提を弔うために建てられた寺。大塩氏は永禄5年湯岡城主南部久斉との戦いに敗れて滅びた。 『口名田郷土誌』 大光寺建立と梵鐘再建 日輪山大光寺は大塩長門守田縄城主吉信公の開基で、文明元年(一四六九)八月一日に建立された。越前慈眼寺竹翁明三和尚を招じて開山したが、明和年間に諸堂焼失、その後、明治十四年(一八八一)一月五日(旧暦十三年十二月)再度火災に見舞われ山門鐘楼は類焼を免れたが、他の建物は全部焼失した。御本尊並びに諸仏像は辛うじて搬出し無事であった。同年秋、本堂が再建された。住職久我選成師の時である。 以後再度の火災によって梵鐘は火勢の為、音響を失い再鋳の必要ありとなったが、時の住職は大いに心を痛められた。 当時の世話人初代緩詰治作氏が、越前の鋳物師を招き自宅に宿泊させて、寺の境内において再鋳に尽力された。重量三五貫余(一三〇キログラム余)で、作業に際しては檀家の人々が手伝いに従事した。 各檀家からは、銀・錫類の使用された器物などを持ち寄り窯に投げ込んだと言われ、音響・容姿共比類無き名鐘が誕生した。しかし昭和十八年太平洋戦争が最も苛烈を極める時、国の要請によりこの名鐘も供出された。 むかしは、腕時計や懐中時計などは高価で野良仕事には携帯できる時代ではなかった。朝昼夕と決まった時刻に撞かれる鐘の音こそ、時を知る上で唯一の頼みであった。その他集会などの時間を知らせる場合や、火災などの非常を知らせる早鐘などと多様に使川され、梵鐘は信仰の象徴であると共に、一般農家の生活には欠かせない存在であった。 戦争が終結し、再び平和の時代が訪れ人々の心も徐々に落ち着きを取り戻し生活にも少しずつ余裕が持てる様になり、梵鐘再建の願も次第に高まった。住職島本俊学師も自らが先頭に立ち、当時の寺総代緩詰義博氏を中心に、檀家は勿論の事、地区外の縁故者にも協力を仰ぎ再建資金の確保に努められ、昭和三十六年京都市の梵鐘製作会社に悲願の梵鐘を発注、音色・容姿共に要望通りの重量二〇〇キログラム余の梵鐘が鋳造された。再建経費二十数万円であった。 撞初式には、檀家を始め多くの地区外からの来賓を招待して、盛大な入魂式が行われた。以来、再び懐かしい鐘の音を聞く朝夕である。 『遠敷郡誌』 大光寺 曹洞宗慈眼寺末にして本尊は釈迦如来なり、同村口田繩字上殿に在り。口田繩城主大鹽吉信公石見國養谷寺第五世竹翁明三和尚を請じて開創する所と傳ふ。  右手は延命地蔵堂。 中世末期の山城の跡がある。 『口名田郷土誌』 大塩城址 大塩城址は口田縄集落の後背を南北に走る大光寺山にある。海抜一三四・七メートルの小山であるが、南川渓谷の山野を一望に収め得る戦略要地で、山麓には城主大塩氏の菩提所大光寺があり、付近には大塩氏の舘跡をうかがわせる舘、舘ノ口の地名が残る。「口名田村誌」は寛正六年(一四六五)若狭守護武田氏の被官大塩吉信の築城と、文明元年(一四六九)の大光寺開基を記すが、「郡県志」は築城時期に触れず、明応二年(一四九三)大塩吉次の大光寺建立と、卒後の法号「大光寺」及び没年を永正元年(一五〇四)と伝える。 城の大手は大光寺からの経路とみられ、山上には前後二郭を土塁で囲む全長約一〇〇メートル幅約五〇メートルの主郭台地があり、その南後方には大きく東西に落ち込む堀切があって、上橋が五つに堀切を区画する特異な障子堀に類似の様相を示すが、この例は関東に多く、関西では今のところ天理市の福住井之市城以外には類例の無い珍しい遺構で注目される。また主郭北側にも土橋二条で区切る同様の備えがあり、遺構全体としても土塁、張り出し郭、堀切、竪堀などが良く残されており、昭和六十三年(一九八八)には、小浜市指定の史跡となっている。 大塩氏は代々長門守を称し、「口名田村誌」は吉信、吉次、吉忠、助秀の四代、「郡県志」は吉次、新左衛門尉吉忠、八郎左衛門の三代とするが、吉次の法号「大光寺」からみれば、吉信、吉次は同一人かとも思われる。 最後の城主は永禄五年(一五六二)湯岡城主南部久才と合戦、敗退して国吉城(現在の美浜町)の粟屋氏に身を寄せたという。又、春日大明神(現春日神社)は大塩氏の守り神であったと云う。今も主郭跡に愛宕社があるが、併祀する田縄社には祭神大塩吉信の記名札を収め、また城跡北端の「神森(こうもり)」の台地は旧春日社地と伝え、磐境の存在が窺える。 『口名田郷土誌』 口田縄の窯業 元文年間から田縄村で瓦の製造が始まり、官家の御用にのみ焼いたと記されている(稚狭考)。古代にも須恵器を焼いており、大左近の谷間に窯跡がある。また、江戸後期から石灰の製造が始まり、現在も窯跡などを残している。 口田縄大左近地籍の窯からは、八世紀来から九世紀にかけての須恵器が発見されている。「小浜市史通史編」によれば、大左近窯跡について、口田縄区の大光寺東側の山中に須恵器片の出土する所があり、谷の斜面にどうやら窯跡が存在するようである。窯本体は未確認であるが焼き損じの須恵器片がまとまって出土するので、いわゆる灰原の部分が判明していると思う。おそらく群をなしている可能性もあるが、これまでの調査では確認されていない。 出土遺物としては、高台の付いた杯や、深皿、そしてつまみの付いた蓋がありさらに残皿などの小形の製品もある。これらをみる限りここで生産されていた時期は相生区の城ヶ谷窯より古く、八世紀後葉から九世紀の初頭と考えられると記されている。 又、「稚狭考」によると、瓦の生産は甲ヶ崎・西津の間の海辺で城の瓦が焼かれた。その後も補修用として続いたが、元文年間(一七三六~一七四一)に城の瓦は南川沿いの田縄村へ現在の口田縄)で焼かれることとなったと記されている。 明治以降の口田縄における瓦製作業者の創業廃業年代は次の通りである。 業者名 創業 廃業 武藤利兵衛 明治初年 明治三十年頃 武内源助 明治初年 明治三十年頃 的場治良五郎 明治初年 大正一三年頃 水船金平 大正十五年頃 昭和二十年頃 八尾久光 昭和二十二年 昭和五十五年 赤瓦製作会社 昭和二十七、八年頃 昭和三十四年頃 石灰産業 口田縄の石灰の生産は、江戸時代後期より始められたようであるが、明治時代になってからは石灰の需要も増え、口田縄区の窯元も数軒となり従業員も区内の人は勿論、他地区からの出稼ぎ従事者も多く、数十人は働いていたようである。 春から晩秋まで生産された石灰石は、トロッコに積まれ春日神社前の加工場まで運ばれ、ここで消石灰に加工され俵に詰められ倉庫で保管された。休山となった冬期間には、小浜の問屋の倉庫までの運搬には川舟が利用され、その舟乗り人夫は、夏場の鉱夫達が携わった。 口田縄区の石灰生産業者名は、大塩三太夫、辻井助右ヱ門、的場太良助、的場太次郎などがあった。 明治時代の口田縄区は活気に溢れていたが、大正の年代になって石灰業は不況に見舞われ次々と廃業に追い込まれた。大塩三太夫家においても、施設の全てを石川石灰株式会社へ賃貸し、そのまま営業が続けられたが昭和七、八年頃廃業となった。当時使用された石灰窯跡が、現在も数基がそのまま残っている。 大正時代の中頃より、道路の開設によって荷物の運搬の主役である川舟から荷馬車に替わり石灰・木炭などの積みこみ作業で、朝は特に活気を呈したが、昭和七、八年頃の石灰会社の廃業による荷物の著しい減少で、馬の頭数も減り続け、その上昭和二十四、五年以降、三輪トラックの普及で昭和三十年過ぎには口名田から荷馬車の姿は消えた。 《交通》 《産業》 江戸末期から石灰の製造が始まり現在もかま跡などを残す 《姓氏・人物》 大塩氏 口田縄の主な歴史記録『遠敷郡誌』 口田繩 南川の東岸にあり、山上大塩長門守吉次築く所の城址あり、又山下に吉次の子宮忠及孫長門守等代々の宅址あり、大光寺中にそれらの墓ありと云ふ。 口田縄の伝説『口名田郷土誌』 田縄村のはじまリ(口田縄) どれくらい前のことでしょう。孝元天皇という方が大和の国をお治めになっていた頃の話です。 ある日、天皇が丹輪命(たんなわのみこと)を召して、「この国の北へ行くと大きな湖があり、その湖の西側をさらに北へ進むと海がある。海の幸を何とか手にいれたいものじゃ。お前はこれより行って調べるがよい」と言われました。 そこで丹輪命は、さっそくたくさんの兵をつれて北へ北へと進み、今の今津あたりまで来ました。 「さあ、明日はいよいよ山を越えれば海に出られる。今日はゆっくり休むがよい」と、命は兵をねぎらいました。 翌日、けわしい山を越え、熊川の里を過ぎて遠敷の検見坂のあたりまで来たとき、突然山からたくさんの岩や石が落ちてきました。さあ大変です。怪我をする人や死人も出ました。 山の上を見ると、鹿やうさぎの毛皮をまとい、目は怒りにもえた大勢の人たちがこちらを見ています。この人たちは、大和朝廷から異民族とみなされ、土蜘蛛(つちぐも)と呼ばれている集団でした。 丹輪命は安全なところを求めて、南川をさかのぼり、後ろは山、廻りを川に囲まれた、今の口田縄の地に拠点をかまえ、次々と土蜘蛛を平らげてあちこちに平和な村をつくりました。 この丹輪命の名にちなんで「田縄」の地名が生まれたということです。 その後、丹輪命はさらに南川をさかのぼり、平和な村をつくりながら名田庄の山を越え、大飯郡に入って青葉山の近くまできた時、その山麓に住む土蜘蛛とはげしい戦いになったといいますが、その後の消息を知ることはできません。 『越前若狭の伝説』 ひひ退治 (口田縄) むかし大塩長門守(ながとのがみ)吉信の子孫に大塩三太夫(さんだゆう)という人がいた。この三太夫が壮年のころ、大飯郡笹谷(ささだに)村にひひざるが出て人畜に害を加えるので、村内の人はたいへん恐れていた。藩の武士が、たびたび討ち取りにきたが、ひひざるは。たくみに姿をくらまして、どうしても退治することができなかった。 そのうちに、三太夫が鉄砲の名人であることを間いて、村人から藩の役所へ討ち取ってもらうように願い出た。幸いききとどけられ、三太夫は役所へまねかれて、ひひ退治をいいつけられた。三太夫は、すぐ笹谷へ出張して、待ちかまえていると、やがてひひざるかどこからか姿をあらわした。三太夫は、ここぞとねらいを定めて、一発のもとに射とめた。藩主は、その功をほめて、鉄砲一丁と銀を与えた。 三太夫は、享保十七年(一七三二)十月十六日九十五才で死んだ。この鉄砲は、火縄銃で長さ一メール三十センチ、重さ三・五キロあり、いまなお大塩家に伝わっている。 (福井県の伝説) 口田縄の小字一覧口田縄 馬場 石橋 舒野 村下 八幡 五良 道下 水込 川原田 上藤 樋口 此倉 古宮 戸尻 神龕 柿畑 宮腰 和多 森下 上段 上長通 下長通 館 館ノロ 左近田 右近田 久保 瀑方 久保上 的場 辻 大左近 朱谷口 山本 山下 野山 平山 山中 岩神 此倉 大左近 朱谷 念坂 山中 扇谷 馬谷 田繩谷 水口 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2020 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||