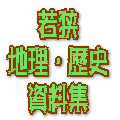 |
下竹原(しもだわら)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下竹原の概要《下竹原の概要》 新竹原とも記される(稚狭考)。また竹原小松原とも呼ばれ、小松原(小尻小松原)・新小松原(出村小松原)とともに江戸期には三小松原と総称された。東を小浜湾に面して位置する。当地はもと竹原村にあったが、慶長6年京極高次による小浜城築城に際して現在地に移転させられたもので、竹原村(上竹原村)から分離したということで下竹原と称されるようになった。その名残は祭礼に引き継がれており、7月17 ・ 18日の祇園祭(広峰神社の祭礼)では上竹原と共同で執り行い、3社が出る神輿は下竹原の西町・中町・乾古町の住人がそれぞれ担ぐことになっている。神輿は江戸末期に西津村長町の豪商古河屋によって寄付されたものとされる。 近世の下竹原村は、江戸期~明治22年の村。小浜藩領。幕府へ届け出た郷帳類では当村名が見えず西津村のうちに含まれているが、藩領内では独立村として扱われていた。明治7年西津村が公式に3町8か村に分村した際に当村も独立村となった。なお当村地籍内には長町(西長町)の一部があった。当村は漁村で、慶長6年竹原村から分離した際には七人衆と呼ばれる船元(船持)がいたという。7年の若狭国浦々漁師船等取調帳(桑村家文書)によれば、船数20。元禄3年の下中郡村控によれば、村高15石余、家数111 、人数625、船数62。「雲浜鑑」によれば、村高15石余ですべて畑方。家数118・人数694。寺院は臨済宗円通寺が当村乾古町にあったが、寛政11年もしくは同12年の大火により類焼し、その後西津村北塩屋の地に再建された。当村の漁業は延縄や一本釣りが中心であり、小松原村・新小松原村のように大網・磯引網の網立は許されていなかった。 「白西(しらにし)は風か、こんぐり魚(いお)か、竹原の人は人間か」という伝承には、一本釣延縄漁業のために沖合いに出ていかざるを得ず、いったん海に出たら風が吹いても容易に帰って来られなかった当村の漁民の悲哀がこめられている。鯖の一本釣りのためかなり沖合いまで出掛けており、時には7~8人乗ハガセ(大船)で丹後半島経ケ崎沖を漁場とした。文政元年7月12日長町から出火し当村と新小松原村で270軒余が焼失。また文政3年7月14日にも当村と小松原村で90軒が類焼する大火があった。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。明治7年西長町が独立して当村内から分離した。同13年板屋町・西長町・北長町を合併。同年の「共武政表」では戸数123 ・ 人数657。同14年旧板屋町・西長町・北長町は当村から分離して明治7年以前のように再び各村内に分属するようになり、板屋町は湊村と堀屋敷村に、西長町は当村と北塩屋村に、北長町は新小松原村と北塩屋村に所属することになった。この結果、当村は再び西長町と通称する地を含むようになる。同22年西津村の大字となる。 下竹原は、明治22年~現在の大字名。はじめ西津村、昭和10年小浜町、同26年からは小浜市の大字。明治初期には全戸数の約95%が漁家であったが、その後沿岸漁業の衰退とともに漸減し若狭塗の箸屋へ転職する者が増え、現在家内工業的な若狭塗箸木地・塗工場が多数ある。 《下竹原の人口・世帯数》 202・87 《下竹原の主な社寺など》 《交通》 《産業》 若狭塗り箸 《姓氏・人物》 下竹原の主な歴史記録下竹原の伝説下竹原の小字一覧下竹原 東竹ノ野 西竹ノ野 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||