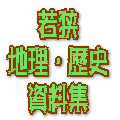 |
旧・内外海村(うちとみ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧・内外海村の概要《旧・内外海村の概要》 明治23年の農事調査事項によれば、農業戸数425うち専業161 ・兼業264。耕地反別225町7反余うち田116町3反余・畑109町4反余。耕地所有者は2町余以上10町余未満9、2町余未満416。主な農産物は米・桐実・甘藷・大麦・櫨実とある。 同24年の水産事項特別調査によれば、漁業・採藻業戸数325うち専業183 ・ 兼業142。主な漁獲物は鯖・鯛・王余魚・鰈・シイラ。大正元年の産業別生産高は、農業8万9,948円・水産業3万6,750円・林業1万533円・工業8,498円。 大正6~8年丹後田井の鰤大敷組合に田烏・志積から年間80~90人が出稼ぎに行った。明治36年内外海村農会設立。大正3年稚蚕共同飼育所を村内3か所に設置。昭和2年内外海村蚕業組合設立。同11年経済更正村に指定された。 昭和26年小浜市の一部となり,当村の14大字は同市の大字に継承された。 《交通》 旧・内外海村の主な歴史記録『遠敷郡誌』 内外海村 本村は全部海岸の部落より成り、東は三方郡西田村及本郡鳥羽村に境し、南は宮川、國富、西津の各村に接し、鳥羽、宮川、國富の各村とは北川流域と日本海の斜面との分水嶺を以て境界とし、山は直ちに海に接し川と名づくる程のもの存在せず、田烏、矢代、志積、犬熊、阿納、西小川、加尾、宇久の各浦は本郡北辺の海岸山脈に黠綴し小湾を控へて直ちに日本海に面し甲ケ崎、古津、阿納尻、若狭浦、佛谷、堅海、泊の諸浦は小濱湾に面す、本村海岸は三方郡との境を突出して黒崎をなし西小川崎、和田戸崎と相對して田烏湾をなし、名古崎の東に田烏浦其西に矢代、志積、犬熊、阿納の諸浦あり、西小川崎は外面の東端シチヤの鼻と相對して宇久湾をなし西小川、加尾、宇久の各浦を擁す。 堅海、泊、佛谷、若狭浦、阿納尻、甲ヶ崎の六區は主として農業を營み、阿納、犬熊、志積、矢代、田烏の如きは農業漁業にして、宇久、加尾、西小川は多少の耕地を有すれ共、主として漁業に從事す。 外面 久須夜岳は松ヶ崎半島をなし、南に小濱灣を擁し、北は一面日本海に面し怒濤岸を洗ひ、花崗岩より成れる一帶の海岸は其浸蝕を受けて絶壁をなし、奇石怪岩を散點し洞窟岩礁多く題目岩、網岩、大門、小門、唐船島、白黒岩、小山、猿落し、二ツグリ、長サキ、ドウジン岩等其著名なるものなり。 小島 二児島は小濱湾内にあり、佛谷に屬す。 甲ケ崎 西津に近く中古漁業、製鹽を業とせしものありしも今は存せず、若狹浦、佛谷浦に渡航する要津なり。 古津は阿納尻と共に小濱湾より更に入り込みたる内を海に臨み古への着船場なりしと傳ふ、昔時は附近の四ケ村の中心をなし、税所代古津三郎時道の居宅ありしと傳ふ。 若狹浦 西は佛谷に接し東は阿納尻の地に接す、往昔は今氏神椎村神社の存在せる西浦にありしが、約千年前今の所に移れりと傳ふ、薬師堂の本尊は廢寺眞言宗ゲンカウ寺の本尊なりと云ふ、附近に古墳あり、発掘の土器猶存す。 佛谷浦 元坂尻と稱し堅海區阿彌陀川の邊に居住せしが、住民の増加に隨ひ坂路を開き今の谷に移り、嘉吉元年八月漁夫脇左衛門海中より今の上ノ山に安置せる如意輪觀世音金銅の像を拾ひ上げてより佛谷と改むと傳ふ。 堅海浦 久須夜ケ岳の北西にあり、古来堅海半島の中心をなし來りし如し、村に領家と名づぐる家あり、恐らく古の領家の遺跡なるべし。 泊 半島の西端にあり、海軍望樓址あり。 宇久 久須夜岳の東麓にして宇久湾に臨み、外面の白黒岩にして泊區海岸地籍と接し、カキバ谷に於て加尾區に境す、往昔矢代の清左衛門一族當浦に来り後刀禰となりしを以て村の始なりと傳ふ、元観音堂ありしと云ふ。 加尾 宇久區との間カキバ谷より加尾坂迄の地籍を有す、薬師堂は神亀五年の草創と傳ふ、元別當興林寺あり、廢寺に禪宗長福寺あり、薬師堂天神社は西小川と共有なり。 西小川 加尾坂より阿納尻ホウジの鼻迄當區當地籍にして観音堂に安置せる十一面観世音は西津松福寺観音と同木同作と傳ふ。 阿納 東阿納崎より外面白黒岩迄の海面は當浦に属す、昔時越前高岡牧原傳五郎開發と傳へ、観音堂は養老元年草創と傳ふ、薬師堂あり廃寺。 犬熊 建久六年犬熊浦者嶮岨山野の地僅三町許也、平地荒畠一町餘濱南北一町餘、東西一丁歟、當所猪鹿の栖によりて居住海人なしとあり、阿彌陀堂あり、永享元年開基と傳ふ、又産小屋あり。 志積 元山王社ありしが小濱町河崎へ合併す、十一面観世音堂あり。 矢代 西名古崎、矢代崎との間を矢代浦と稱す、君が浦とも稱せりと云ふ、昔稻富浦とも稱せりと傳ふ、觀音堂は頼位山福壽寺と號し、現時は安産の所りのため近村より詣づる者多し、手杵祭は有名なり。(民俗篇参照) 田烏 古墳あり、讃岐尼傳領の地ありし事秦氏文書に見ゆ、沖の石の歌は此所にて詠まれしと云ふ傳説あり、此浦の起原に關しては古文書篇に詳し。. 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||