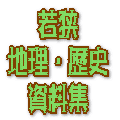 |
山田(やまだ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田の概要《山田の概要》 佐分利川右岸の山麓の農業集落。芝崎の奥に位置する。 山田村は、江戸期~明治22年の村。小浜藩領。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。同22年本郷村の大字となる。 山田は、明治22年~現在の大字名。はじめ本郷村、昭和30年からは大飯町の大字。明治24年の幅員は東西1町余・南北1町、戸数16、人口は男34・女38。 《山田の人口・世帯数》 47・14 《山田の主な社寺など》 『大飯町誌』 古墳 この地域は西の一方が開けているだけで、東南北の三方は山に囲まれ、大方は緩い傾斜面に住居が営まれている。戸数は昔から余り大差がない。谷が狭いのでより多くを入れる余地がないからであろう。古代には山にも依存して生活していたから、あるいは今より大きかったのではなかろうか。この周辺に残存していた古墳の数が、小集落に比べて余りにも多数であったからである。 住居区の山麓から山の神地籍の山地、大飯神社の後背山やその付近、畑地や田の間にも、それが群集あるいは散在して総数五、六十基もあっただろうと古老は語っている。今日ではその過半は破壊されているが、それでも一四基が確認されている(ほとんど後期横穴式)。 古墳にまつわる伝説に、「椀貸し」の話や、古墳の中の灯が遠方から見えたなどという話が伝わって相当な有力者の古墳があったように伝承されている。『大飯郡誌』には「新撰姓氏録」という古典に出ている山田の造、山田の連、山田宿禰などの名を挙げている。これらは右京諸蕃上、河内国諸蕃(和泉にも)中に属していた有力者である。 『大飯郡誌』 山田の古墳〔本縣史蹟勝地調査報告〕 (取意)山田に多数の古墳あり、字二王堂及宮ノ脇のもの顕著なるが、字糀ノ木にも多数群集せり。二王堂のは殆ど破壞せるも其石室の側壁猶殘存し。巨大なる天井石を積重ね、古来椀貸の傳説あり。宮ノ脇のは石室の構造稍完全にして殊に玄室と羨道との區別を認む可し。周圍繁茂封土の形状は認め難し。糀木のは渓谷の傾斜面に、低き圓塚としで築かれしもの數多あるも、多くは石材採集の目的を以で其石室を破壊され、殘存せるもの漸く三ヶ、入口は自然石にて營み奥壁の兩隅は多少彎曲せり。 少なくとも5、60基というからすごい。滝見千軒の伝承が彷彿させられる。 「全国を調べていますが、山田は鉱山と関係する地名でないでしょうか。丹後はどうですか」といったメールを貰ったことがある。丹後山田は穴石神社や苦無神社がありますから、その当時の鉱山でないですか、と返事した記憶がある。いまでもヤマは鉱山を意味するが、山田は野尻銅山の場所だから鉱山所といった意味であったと思われる。  大飯郡・大飯郷の語源となった社(式内社)。今の氏子圏は山田・岡田・芝崎で、文化4年(1807)は氏子85戸であった。祭礼は10月10日という。裏山周囲一帯が「御正作の森」で、後期古墳がゴロゴロ。今の山田集落は向かって左側にある。 谷あいから張出した支峰の先端に鎮座。祭神は大飯鍬立大神。旧郷社。境内摂社として八幡神社・天満神社があり、本殿・拝殿・能舞台が並ぶ。 「延喜式」神名帳の「大飯(オホイヒ)神社」に比定され、享禄5年(1532)の神名帳写に神階正五位の1座として大飯明神とみえる。近世には七社大明神と称されていたようで、延宝3年(1675)の「若州管内社寺由緒記」は「七社大明神者大飯の鍬立の御神也、御宝殿に鋤鍬納り有レ之候、並御正作の森と申脇に御座候時代不レ知、文明三年の比本郷判官殿重而建立の由申伝候」と記す。明治元年(1868)大飯神社となった。「若狭郡県志」には「八幡社 在山田村為産神八月十五日有祭」とだけ記され、大飯神社のことは記していない。  古墳が5、60もありました、私たちの先祖の陵墓です。穢すとタタリありますぞと伝えられていますとか書いておかないとあまり意味ないと思う。檜だろうか植林されていて自然林ではない。  『大飯町誌』 大飯神社(式内元郷社) 別称 大飯鍬立明神、七社大明神 祭神 大飯鍬立大神 所在地 山田字宮の脇(四の一) 境内地その他 三、〇一三・〇平方㍍、山林二、〇四九・四平方㍍、境外山林二ー、九九九・八平方㍍、原野二三一・〇平方㍍ 氏子 岡田、山田、芝崎八〇戸 例祭日 十月十日(十月十八日客祭) 宮司 松田忠夫 主な建造物 本殿、拝殿、舞台、社務所、手水舎 特殊神事 神事能 由緒・系統 『延喜式神名帳』に大飯神社とあり九二七年以前の古社。『若狭国神名帳』に正五位大飯神社とある。祖神信仰 [末社] 天満神社 祭神 菅原道真 系統 北野系 [合祀社] 八幡神社 祭神 応神天皇 由緒・系統 一七一六年以前に創建 八幡系 愛宕神社 祭神 火産霊神 由緒・系統 一七一六年以前に創建 愛宕系 明治四十四年に以上二社を合祀 八幡神社 祭神 応神天皇 元地 芝崎字墓前 由緒・系統 一七六七年以前に創建 八幡系 大正九年合祀 大飯神社 字宮の脇所在、式内元郷社である。祭神大飯鍬立大神(合祀社八幡二、愛宕一社)、古来諸説あり、猿田彦神であろうともいわれていたが確証がない。『延喜式神名帳』には大飯神社と明記、『若狭国神名帳』(九四四)には正五位大飯神社又は大飯鍬立明神とある。まぎれのない古社である。しかし中古は民間で専ら七社大明神という通称を用いたため、元の大飯神社という社が不明になってしまった。 明治維新の際に神社改めということがあって、村々の神社の確認が行われたのであるが、その際、大飯神社の所在が問題となった。関係村から証拠書類を提出してこれを明らかにしたため、明治元年(一八六八)三月に小浜藩において式内大飯神社と確定され、同十四年四月二十七日には郷社に列せられたのである。 文明三年(一四七一)本郷の地頭本郷判官源政泰が社殿を再建、寛文十一年(一六七一)秋氏子中で社殿を造営(大工・市場村吉兵衛小堀村忠左衛門)、その後安永七年(一七七八)九月二十八日社殿を再築した(大工・下薗村市左衛門)。これが現在まで続いているのである。 本殿二間四尺五寸×二間四尺二寸五分の流れ造り三扉である。明治四十四年十月九日八幡神社と愛宕神社を合祀し、大正九年(一九二〇)五月芝崎字墓前にあった八幡神社を合祀した。そして今日に及んでいるのであるが、この神社は元々大飯郷といった時代からの氏神であった。大飯郷は後分かれ分かれになって八力村になった。上下、市場、下薗、小堀、下車持、岡田、芝崎、山田である。村は分かれても氏神としての祭りは皆合同で奉仕してきた。藩政時代終始共同奉仕してきた証拠は、その村々に残っている庄屋文書などで明らかである。 ところが明治時代になって戸籍簿に氏神を記入することがしばらく続いたので、二重氏子という変則な関係を生じる者が増えてきて、ついに大飯神社から離れる村ができた。現在は岡田、芝崎、山田の三集落だけの神社ということになってしまった。 しかし、右八力村の本当の氏神は、大飯神社すなわち大飯郷を開き始めた鍬立の御祖であることは動かないのである。末社は天満神社(祭神菅原道真、創建不詳)。なお、次に『若州管内社寺由緒記』の関係記録を挙げておく。 「一七社大明神は大飯の鍬立の御神なり、御宝殿に鋤鍬納りこれ有り候。並に御正作の森と申す森脇に御坐候、時代知れず。文明三年の頃本郷判官殿重て建立の由申伝え候。延宝三年、庄屋善兵衛」 『大飯郡誌』 大飯神社 〔若狭國神名帳〕正五位大飯明神 〔若狭郡縣志〕〔若狭國志〕在處不詳 〔稚狭考〕大飯は本郷なるべし。 〔神社私考〕本郷の中山田村と云ふに大飯鍬立明神と稱すが坐て本郷八村の本居(ウブスナ)神とすこれ決く大飯神社なるべし〔祭神を猿田彦神なりと云へと慥なる傳記はあらずとぞ〕此社里人つねには上宮と申すまた七社大明神とも申すは合殿の神なるを總ていへるなり此社の本神往古此わたりの田を開發給へる神継て鋤鍬を霊寶として祭来れり(〔神祇志料〔地名辞書〕の記事原之) (附記本郷村の章山田に關する〔新撰姓氏録〕の文参照を要す) 郷社 大飯神社 祭神不詳外二神(合祀) 山田字宮ノ脇に在り境内七百十五坪 氏子九十八戸 境外風致林二町 六畝六歩(実測)社殿〔〕拝殿〔〕能舞臺〔〕神饌所〔〕廊下〔明細帳〕不詳明治元年二月舊小濱藩に於て式内 に確定 同十四年四月二十七日郷社に列す 〔全群誌神社章参照〕 〔寛永四年國中高附〕七社大明神三月四日九月十日十八日に能仕候但下薗芝崎岡田小堀下車持市場上下村八ヶ村立合祭〔神社私考〕大飯鍬立明神と稱す…蓋し大飯神社なるべし(之れ小浜藩にて式内と定めし本拠) 〔若狭郡縣志〕 八幡社在山田村爲産神八月十五日有祭。 境内社天滿社 祭神菅原道真公社殿一宇 大正九年五月二十四日次の社を合併せり無格社八幡神社祭神応神天皇柴崎字墓前。 〔若狭郡縣志〕 七社明神社在芝崎爲産神三月四日九月十日祭日也九月十六日有神事能。 「御正作の森と申す森脇に御坐候」とあるが、オショウサクでなく、ミササギ(陵)の森のこと。当社に祀られている祖先の陵墓の地なのであろう、当社がてきる以前の祭祀の場所であったのだろう。ニソの杜のようなものか。 『大飯町誌』 溝作森(みそさこ) 明治のころにはまだ若宮付近に溝作の森、また源太夫森というのがあった。この森で不浄の行いをすると必ず地主にたたると言われていた。 これはいずれ若宮に関係のある遺跡の一つだろうと思われる。伴信友の著書『神社私考』大飯神社の項に、「又この社の傍に、御正作(おしょうさく)の森といふ古木の立る森あり正作とはいかなる由の言にか、作田(たつくる)ことを俚言に、ただに作(さく)ともいへば、もしくは作田の事に霊験のありし古事に依れる由を、さとび言もて名づけたるにはあらざるか」と見え、また、一説にみそさこはみささきのなまりで高貴な人の古墳であっただろうとの説をも伝えている。昭和六十一年(一九八六)十二月氏子の有志等によってここに「御正作の森」記念碑が建てられ、参道を挟んで石木を左右対称に配した不思議な森であるといい、また、芝山や岡を開墾した神の霊験を高くたたえている。 『大飯郡誌』 溝作(マササコ)の森 溝作の森とは俗に元太夫森のことなり。此森を汚がすときは必ず祟ありといひ傳ふ。溝作とは山陵の傳訛にて往昔貴人の墓所なりしならんとの説もあれども今は其の證左なし。  大飯郡大飯郷の郡名郷名の由来となった社であろう。本郷8か村の総氏神だという。本来は多氏(青氏)の拠点であったと思われる。 大飯の社名はあるいは大飯豊の豊が省略されたものかも、飯豊青皇女の青飯豊の意味の書き替えでオホオホと呼ぶのか、それとも飯豊は「飯」は、飫富、飫豊の「飫」の書き違えか書き替えで大飯は本当は「大飫」かも知れない、それならオホオ神社ということか。多氏の神社ということでなかろうか… 『古事記』に、 神八井耳命は、意富臣、小子部連、坂合部連、火君、大分君、阿蘇君、筑紫の三家連、雀部臣、雀部造、小長谷造、都祁直、伊余国造、科野国造、道奥の石城国造、常道の仲国造、長狭国造、伊勢の船木直、尾張の丹羽臣、島田臣等の祖 とある。神八井耳は神武の長男で本来なら天皇(大和大王)家の継承者であろうが、皇位はなぜか次兄に引き継がれている。 神八井耳の神も耳も美称、尊称で八井という名であった。昔からヤイと読んでいるが、八は数が多いの意もあり、八岐大蛇は頭が八つあったという意味でなく、頭がたくさんあったの意であろう。そうしたことで八井はオオイとも読めなくもない。多氏の祖・当地鍬立の祖・神大飯耳命を祀る社であったかも… 神武の長男ということは媛蹈鞴五十鈴媛命の長男であり、まさにタタラと深い関係があるものと思われる。 神とは天から降ってきたものでなく、額に汗して土地を拓いた自らの祖先であった。当地あたりから大飯郡は拓かれ、当時の日本も新たに拓かれていったのかも…  このごろは汗して働くなど尊くない、工夫ない愚か者とするヤシ経済学の幼児にも劣る考えで、神社も廃れ、労働も頽廃し、国も傾くことになる。  『大飯町誌』 杉森山玉正寺 宗派 臨済宗(南禅寺派、高成寺末) 本尊 薬師如来 所在地 山田字村中(一〇の四一の一一) 主な建物 本堂、庫裡、観音堂、本堂は大正七年(一九一八)再建 境内地その他 境内六九四平方㍍、宅地六八四平方㍍、山林一〇、九〇九平方㍍ 住職(兼務)中西禅活 檀徒数 一二戸 創建年代 寛正年間再興(一四六〇~一四六六) 開山 陽洲素紋禅師 寺宝 涅槃像、十六善神 玉正寺 字村中所在、臨済宗南禅寺派小本山小浜市高成寺、 本尊薬師如来、創建不詳。寛正年間(一四六〇~六六)温洲素紋和尚再建、明応年間(一四九二~一五〇一)梅崖恵白和尚またまた改築、延宝三年(一六七五)の住持は宗秀、元禄二年(一六八九)に周元首座の名が出ている。 『大飯郡誌』 玉正寺 臨濟宗南禪寺派高成寺末山田字村中に在り 寺地八十三坪 境外所有地五反三畝八歩 檀徒六十四人 本尊藥師如来 庫裡〔〕由緒〔明細帳〕寛正年間湯洲素紋和尚再建明應年間梅崖惠日和尚三建之 〔若狭郡縣志〕 三十三所観音十八番如意輪観音本郷松森玉正寺准山城國六角堂。 『大飯町誌』 海音堂 『本郷中古伝説記』によると、「山田村には海音堂とて大いなる観音堂あり、並に仁王門(仁王像は現在江州石山寺へ移してあるという真偽不明)毘沙門堂、阿弥陀堂あり、同じく天台宗六ヶ寺あり永禄中に焼失す」と伝え、口伝でも延暦中(七八二~八〇六)の創建で七堂伽藍の備おった立派な寺院があった。 その跡地だという所に、仁王堂、上坊、下坊、ほうせん坊、毘沙門、灯明田、本寺等の地名がある。東寺の百合文書には、「文安六年(一四四九)五月大飯郡本郷正扇院」という記事がある。その所在等は一切不明であるが、『大飯郡誌』は玉正寺の前身であろうという推測を述べている。 さらに『本郷中古伝説記』は、「山田村の南の入口に岡本坊と申す山伏あり、其のいわれを尋ぬるに若宮千軒時代、皆岡本坊祈祷檀那にて、殊の外繁昌しけり」とある。ここに密教式修験道の一拠点が存在したのではなかろうか。これは、若宮、滝水などの大集落を控えていたからであるが、また、中古の山田そのものの規模も宗教の力が加わって衰えていなかったように思われる。 しかし、南北朝の抗争のためか、戦国争乱のためか、又は天災のためか、あるいは耕作の便否によるものか、滝水、若宮の両千軒集落が漸次離散していってからは、この山田も宗教的な繁栄の基礎を失って、ただ農産物だけが生活の糧となるほかはなかった。江戸時代に下るともう昔の面影はなく、玉正寺が観音堂を守って、若狭国三十三所の第十八番札所としてわずかに昔の名残をとどめていたようである。 『若狭郡県志』第五巻寺院付録の部に、「三十三所観音……十八番如意論観音本郷松森玉正寺同国(山城国)六角堂に准ず……」と記してあるから、江戸中期にはまだ現在ほど衰えていなかったようである。 今日は兼務寺院になって、境外の観音堂も荒廃にまかされている。由緒だけは、「観音堂本尊千手観世音菩薩、(七八二~八〇六)延暦年間創建、初七堂伽藍本尊は柏原院の御守本尊であった」と伝えている。 「永禄年中(一五五八~七〇)義昭将軍の時代に天災のために焼失し、天正八年(一五八〇)に宗源和尚が改築、文久年中(一八六一~四)実山宗育が又改築した」(『本郷村誌』及び口伝)という。また、海音堂の本尊の脇に祀ってあった聖観音については次のような口碑が残っている。「昔諸国漫遊の遍路がこれを背負って来て、この堂に宿っているうちに死亡したので本尊の脇に祀ったものである……」と。 海音堂の御詠歌は、「春は花夏は山田の稲の波秋は緑の月の本堂」である。現在祀ってある仏像の丈量は本尊千手観世音菩薩長一尺五寸四分、台座高四寸、聖観世音菩薩長一尺七寸五分、台座高五寸である。なお、この聖観世音は海音堂にあったものをここに移したのであるという。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 山田の主な歴史記録山田の伝説『舞鶴の民話4』 古墳のなぞ (大飯町山田) 佐分利川にかかる大飯橋を南へいくと山田という集落がある。小さい集落であるが古墳の多い地域である。しかし田畑を作ったり、遺品をとったりなどして破壊されている。古墳にまつわる伝説が語りつがれている。 人身御供を供えないと、田の水が流され、農作物が荒され、そこを通る村人に危害を加える古墳があった。村の人たちはくじをしてその年の人身御供を決めていた。くじに当った家の両親はもちろん、娘の悲しみは言葉で表わせなかった。その当った家に、みすぼらしいが、学のありそうな廻国の僧がやってきた。僧はその話を聞き、たんとかしてその難をのがれるようにはからうから任せなさいと言った。僧はさっそくその古墳に行きお祈りをした。古墳が左右に大きくゆれ、何ともいえぬ臭がただよってきた。僧はなおも祈った。 数日すぎて、娘が人身御供になる日、僧はとこからともかく一匹のたくましい犬をつれてきた。そして腹一杯御馳走をたべさせて、人身御供を入れる唐びつの中へ、娘の代りにその犬をいれて古墳に供えさせた。娘も両親も村人も不安な一夜を明かした。朝になると、犬が口のまわり、体いっぱい血だらけになって戻ってきた。村人は古墳の前へ行ってみると、唐ひつはこなごなにくだけ散り、辺りははげしく争った跡があって、血が点々とおち、その血の落ちているところをたどっていくと、草むらの中に年を経た大きな狸が死んでいた。その後、農作物は荒されることもなく、人身御供も出さなくてもよいことになったが、たたりをおそれた村人は、木片に人の顔をがいたものを作って古墳に供えるという。僧は何時のまにか犬と共に姿をけしていた。 『郷土誌大飯』 山田の人身御供 山田の山の神の祭には、しめ飾りや白御供などの神饌の外に、人形(板切れで形作る)をその年の月数だけ作って、これを人身御供の代りだといって、神前(山神の森)に供える例になっている。 この仕来りの原因として次のような伝説が語られている。むかし山田の岡右エ門に唐犬という犬がいた。気性の荒い犬であった。ある年一人のたくましそうな遍路が来合した。その時はちょうど「山の口」の祭日で、岡右エ門がお供番に当っていて、ただひとり残った大事な娘を、神前に供えねばならなかった。家内親類をはじめ村中のものが娘を取囲んで別れを惜んでいる最中であった。遍路はたんだんその訳をきいて、大そう気の毒がり、何とか一工夫して見るから自分に任してくれといい、その家にとまり込んで床の中で考えつづけていた。その時どこからともなく「とうけい犬に知らすな」という、声らしいものが聞えるように思った。不思議だ何かわけがありそうだと気付いて、一同のものに「とうけい犬というものがいるか」ときくと、それがこの家の飼犬だと分った。「よし、それで分かった、その犬をからひつに入れて参れ」といいつけ、皆一しょうに山の神へ参り、供物と共にそのからひつも供えて、遍路はものかげにかくれて残り、一同は家へ帰った。丑満つ時になると案の如く怪物があらわれて、やにまに、からひつの蓋を取った。とるが早いか、かの唐犬は猛然として怪物にとびかかって、烈しい闘争の後ついに怪物を喰い殺してしまった。遍路は一同を呼んであった次第を告げた。一同は感動して大いに喜んだ。数日後に山神の上の方に古狸の死体が見つかり。唐犬も幾日かの後に死んでしまった。 この事があってから、毎年人形を作って供える例になったという。なお岡右エ門の前に平たい大石があって、これが唐犬のすわっていた石だといっていた。今は取除いた。 『越前若狭の伝説』 人身供養 (山田) 山田にひとつの古墳がある。古墳の台石の上には、木片に人の顔を描いたものが、たくさんのせてあり、台石のまわりのタモの木にはしめなわが張ってある。ここで毎年供養が行なわれている。 むかし山田の村が開発された当時、なに者かが出てきて、作物を荒した。あとには村の娘を毎年ひとりずつ出さねばならなくなった。娘を出さねば、ますます村人に危害をくわえるので、村人はしかたなく、それに応じていた。 ある年のこと、人身供養の白羽の矢が、岡右衛門の家に立った。岡右衛門の家では、ひとり娘のことであり、大そう悲しんでいた。しかし、それを断わると、どんな災難がおこるかわからないので、泣きながら、その日の準備をしていた。 この時、廻国の僧が、この村へやってきて。村人からこのことを聞き、「いっさいわたしにまかせてください。」といったが、村人は村のならわしであるといって、この僧の申し入れをことわった。それでこの僧は村を立ち去ってしまった。 人身供養の日の朝、先日の僧が一匹の犬をつれて、またこの村へやってきて。「ぜひおれにまかせてくれ。」と自信をもっていうので、村人はその僧にまかせることにした。 この僧は、村人に命じて、ごちそうを作らせ、つれてきた犬にそのごちそうを思いきり食べさせて、娘のかわりにこの犬をからびつに入れ、村人に山奥のお供え場に運ばせた。犬はたらふく食べて、からびつの中でぐっすりねこんでいた。 その日村人は一睡もせず、なりゆきを心配して、岡右衛門の家に集っていた。真夜中になって、犬が囗のまわりを血だらけにしてもどってきた。 夜が明けるのを待ちかねて、村人は山奥へ出かけた。からびつは無残にこわされて、あたりは血でそまっていた。その血のしたゝりをたどって行くと。草木の茂みのなかに、大きなたぬきが倒れていた。 村ではこのあと、人身供養もなくなり、農作物を荒されることもなく、平和がやってきた。しかしそのたぬきのたたりをおそれて、人身のかわりに、木片に人の顔を描いたものを供えて、毎年供養をすることになった。 (福井県の伝説) わん貸し (山田) 山田にたくさんの古墳があり、昔は五十基もあった。今はほとんど破壊されて。二十基ばかり残っているが、これも盗堀されて、完全なものは七、八基である。 大飯神社の近くの宮の脇(わき)にある古墳は、その中でももっとも大きく、わん貸しといういい伝えがある。この古墳の入口で、「いついっかに、おぜんとおわんをなん人分お貸しください。」と頼むと、その日には必らず古墳の入口に数をそろえて出してあったという。 また暗夜になると、この古墳から十五キロほど離れた岡田の村から、古墳の中に明り火が見えたと伝えている。 (山口久三) 山田の小字一覧山田 山鼻 角田 宮ノ脇 宮ノ腰 下畠 宮鼻 谷ノ下 延ケ下 林谷 村中 二王堂 叶谷 山ケ屋敷 本寺 奥本寺 上ノ坊 法選坊 山ノ神 古加谷 宮本 金井谷 取ノ奥 狸口 毘沙門 林 古谷 方円 大狩 乳母谷 出口 中ノ谷 山田奥 奧古谷 瓜垣 六蔵 糀ノ木 向六蔵 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『大飯郡誌』 『大飯町誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2020 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||