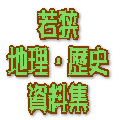 |
遠敷郡(おにゅうぐん)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠敷郡の概要《遠敷郡の概要》 「延喜式」民部省国郡表に見える若狭国三郡の1つ。訓は「乎爾不」(「和名抄」刊本郡部)。九条家本に「ヲニフ」の訓を付す。文武天皇元年と推定される藤原宮出土木簡に、「丁酉年若狭国小丹生評岡田里三家人三成」「御調塩二斗」と墨書したものがある。大宝令の郡制施行に伴い「小丹生郡」が成立する。「小丹生」の表記は和銅5年(712)10月の年紀を有する平城京出土木簡まで見え、同6年以後は「遠敷」に変化する。これは和銅6年5月の諸国郡郷名に対する好字改変に対応するものであろうという。郡名は以後正式には遠敷であるが、戦国期には「中郡」の私称もあった。上中町とか下中とか今も使われている。 古墳は上中町に多い。脇袋には西塚古墳・上の塚古墳・中塚古墳があり、5世紀代に若狭地方の首長であった膳臣一族のものと考えられている。大鳥羽に城山古墳、日笠に上船塚古墳・下船塚古墳。天徳寺の十善の森古墳、平野の白髭神社古墳、これらは前方後円墳。天徳寺の丸山塚古墳は若狭地方最大の円墳である。6世紀後半のものには下タ中の大谷古墳群がある。一方、名田庄村では下の坪の内古墳群のみである。上中町末野に奈良時代ー平安時代中頃の須恵器窯跡があり(末野窯跡群)、若狭の古代窯業の中心地であったと考えられている。 木簡からは郡内に居住した氏族として、三家人・秦人・若倭部・三家首・中臣部・五百木部・三次君・土師・三宅・壬生・无?津君・膳臣・私臣・丸部・矢田部・大湯坐連・道公などが知られる。表記形式としては調塩付札木簡が多く、多比鮓・貽貝・伊和志腊などの海産物も見える。 「和名抄」高山寺本は遠敷郡に遠敷・丹生・玉置・安賀・野里・志麻の6郷を載せ、東急本は余戸・神戸・佐文・木津・阿桑・丹生の6郷を加える。このうち遠敷・丹生は現小浜市、玉置・安賀は現上中町、志麻は現大飯郡大飯町に比定され、余戸・神戸は不詳、佐文・木津・阿桑は大飯郡に入れるべきものの重出、野里は現上中町に比定する説がある。名田庄村に所在した郷はないが、平安時代には仁安3年(1167)11月29日付沙弥盛信私領相博状案に名田郷がみえる。なお天平19年(747)2月の大安寺伽藍縁起并流記資財帳には「乎入郡」とある。「続日本紀」宝亀元年(770)7月20日条に若狭遠敷朝臣長売、同2年5月19日条に若狭遠敷朝臣長女の名がみえる。「延喜式」神名帳は遠敷郡に16座(大2座・小14座)を載せるが、うち「石桉比売神社」「石桉比古神社」「波古神社」が上中町に、「苅田比売神社」「苅田比古神社」が名田庄村に比定される。 鎌倉末期~室町期にかけては若狭姫神社門前の遠敷市が定期市としてにぎわった。同じく鎌倉末期より三方郡気山津の衰退に伴って小浜津が発展し、南北朝期以降は守護所や税所の政所が小浜や西津に置かれて都市の様相を強め、室町期の小浜には北からの津軽船、南からの南蛮船が着く港となっている。また小浜と近江今津を結ぶ九里半街道も物資運送が盛んであった。南北朝期の若狭は守護が短期間で交替したが、遠敷郡の鳥羽・宮河などの国人たちは絶えず守護に抵抗した。まず観応2年(1351)10月、守護大高重成の代官大崎八郎左衛門入道が若狭へ下向すると、若狭国人は一揆を結び、大崎氏を若狭から追い出した。国人一揆の主力は遠敷郡の国人で鳥羽一族であった。次いで応安4年(1371)5月の守護一色氏と遠敷郡を中心とする国人一揆との合戦には、国人方が敗れたことによって安定した。 室町期には安賀荘・宮川保・鳥羽荘・富田郷の全部もしくは一部が幕府料所とされている。永享12年(1440)一色氏に代わって守護となった武田氏もまた小浜に守護所を置き、大永2年(1522)には小浜の西の後瀬山に築城したと伝える。また16世紀後半には宮川新保を拠点とする武田氏一族の信高・信方父子が「宮川殿」と称されて支配権を振るった。なお戦国期には京都の陰陽道家の土御門有脩が名田荘上村納田終に下向し居住したことも注目される。戦国期には遠敷郡を中郡とも称すようになり、明応9年(1450)9月に「中郡」と見え(明通寺文書・小浜市史社寺文書編)、「羽賀寺年中行事」によれば、大永6年(1526)に丹後の海賊の襲来に備えて来た越前からの援軍がかえって三方郡で乱暴を働いたのでその攻撃に備えて中郡の人々は木戸を結び溝を掘って防備を固めたとある(羽賀寺文書・同前)。 文永2年(1265)の若狭国惣田数帳写によると、遠敷郡域に苽生庄・鳥羽庄・鳥羽上保・鳥羽下保・安賀庄・三宅庄・吉田庄・玉置郷・津々見保、名田庄が記載される。 戦国時代遠敷郡の各地には数多くの山城が築かれたが、熊川城・膳部山城・安賀里城・山内城・箱ヶ岳城・霧ヶ嶺城・持田城、三重城・坂本城などがあった。 浅野長政は九里半街道の重要性にかんがみ、天正17年(1589)熊川を宿駅と定め、判物を出して諸役免除し、熊川陣屋を設けて町奉行を置き宿場町の基盤を築いた。以降木下勝俊、小浜藩主京極氏・酒井氏も保護奨励策をとり、小浜湊に荷揚げされた北国米や海産物が当宿を経て近江今津へと運ばれた。 慶長5年(1600)京極氏、寛永11年(1634)酒井氏が入封して以来の小浜藩領。浅野時代には「京升ニして」高4万2,351石余、物成2万7,305石余と伝える。領知目録や郷帳では遠敷郡とするが、小浜藩ではこれを上中郡と下中郡に二分して支配し、藩内ではこの郡名が多く使用された。 「正保郷帳」では119村4万2, 461石余(田3万6,850石余・畑5,610石余)とし、竹原村に雲浜天神領10石、遠敷村に上下宮大明神領11石余、青井村に高成寺領14石余、門前村に明通寺領3石余、金屋村に万徳寺領10石、太良庄村に山王領5石が見える。寛文4年(1664)の領知目録は111村とするが石高は変わらない。貞享元年(1684)領知目録で111村4万3,030石とし、「元禄郷帳」では112村とするが石高は同じ。村数は享保12年の領知目録から122村となるが、「天保郷帳」では112村4万4,219石余、「旧高旧領」1町109村12浦4万4,510石余。「雲浜鑑」は2郡に分けて載せるが、上中郡が2万1,158石余(田1万8,796石余・畑2,361石余)のほかに、外高338石余、一ツ高144石余、下中郡を2万1,338石余(田1万7,995石余・畑3,342石余)、外高1万2石余、一ツ高1,038石余とする。明治2年122村4万3,030石余、ほかに改出新田663石余(公文録)。郡内の村を組別に示すと、上中郡には野木組が下野木・中野木・上野木・玉置・武生・兼田・加福六・堤・杉山の9村(以上上中町)、加茂組が加茂・新保・大谷・本保・竹長の5村(以上小浜市)、三宅組が日笠・神谷・天徳寺・井口・市場・三宅・刈屋の7村、有田組が有田・持田・長江・大鳥羽・黒田・麻生野・海士坂の7村、山内組が三生野・無悪・三田・小原・山内・末野・安賀里・脇袋・下吉田・上古田・瓜生・関・新道・熊川(大杉とも)・河内の15村(以上上中町)、下中郡では府中組に上竹原・府中・和久里・和久里村之内木崎分・多田・青井・伏原・湯岡・生守・野代・尾崎・須縄・奥田縄。口田縄の14村、遠敷谷組が遠敷・国分・金屋・竜前・神宮寺・忠野・下根来・上根来・上根来村之内中畑村の9村、松永谷組が東市場・上野・池河内・門前・三分市・四分市・大興寺・平野の8村、国留組が羽賀・奈胡・熊野・次吉・栗田・高塚・遠敷高之内高塚村分・太良庄の8村、浦方組が西津村之内大湊方・西津村之内北塩屋・西津村之内福谷分・西津村之内塩屋敷分・西津村之内下竹原分・西津村之内北松原分・甲ケ崎・阿納尻・阿納尻村之内古津分・阿納・犬熊・志積・矢代・田島・加尾・西小川・宇久・若狭・仏谷・堅海・泊の21村(浦)、名田庄谷組には谷田部・滝谷・新滝谷・飛川・五十谷・窪谷・桂木・深谷・和多田・田・小屋(以上小浜市)・三重・小倉畑・虫鹿野・木谷・出合・挙原・永谷・虫谷・挙野・久坂・堂本・染ケ谷・槙谷・小倉・下・中・西谷・井上・坂本・納田終村(以上名田庄村)の31村があった(雲浜鑑)。村高を「正保郷帳」でみると, 1,000石以上5村, 500石以上26村, 100石以上62村, 100石未満28村うち16村が50石未満。寛文6年(1666)寺社分を除いて6,853軒・3万8,065人(若狭郡県志)、延宝7年(1679)3万3,211人、寛保元年(1741)4万378人(拾椎雑記)、文化4年(1807)上中郡分が家数2,314軒・寺49・社223, 1万820人、下中郡分が家数5,279軒・寺180・社174, 2万6,843人(雲浜鑑)。明治2年には,武士が屋敷199軒・長屋86棟(265竈)、人数4,237人(男2,426 ・ 女1,811)、小浜の町人が2,412軒・9,023人(男4,346 ・ 女4,677)、出家など166人、郡村は7,444軒・3万5,400人(男1万7,520 ・女1万7,880),出家など256、馬191 ・ 牛645 (公文録)。 明治22年の市制町村制施行により、小浜町と西津・鳥羽・熊川・松永・雲浜・内外海・瓜生・三宅・野木・宮川・遠敷・口名田・南名田・国富・今富・中名田・奥名田の1町17村となり、このときの戸数9,754。その後明治41年9,182戸・4万8,262人、大正9年1万121世帯・4万5,811人。小浜町は昭和10年西津村・雲浜村を合併、同26年小浜町と7村を合わせて小浜市成立、同30年には宮川村と大飯郡加斗村の一部を編入。鳥羽・瓜生・熊川・三宅・野木の5村が昭和29年合併して上中町、南名田村は明治24年知三村と改称したが、昭和30年奥名田村と合併して名田庄村となった。 遠敷郡の主な歴史記録関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 『上中町郷土誌』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||