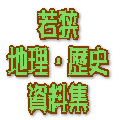 |
白屋(しろや)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白屋の概要《白屋の概要》 旧三方町の南部、倉見村の西、鰣川上流の支流・白屋川西方に位置する。 中世の白屋は、鎌倉期に見える地名。倉見荘のうち。永仁3年(1295)12月2日の倉見荘実検田目録案および翌4年2月の倉見荘実検田目録のうちに「白屋国守」1町302歩、「白屋若王子」1反が見え、江戸期の白屋村の小字である脇山は「脇山円仏并国重」、同じく泉谷は「千石十禅師」として見える(大音文書)。このうち脇山は室町期の応永20年には「脇山名」とあり、京都の真言宗寺院安禅寺の所領となっていた。 近世の白屋村は、江戸期~明治22年の村。「元禄郷帳」には「古ハ白屋村」と注記され西路村、「天保郷帳」も西路村と見える。小浜藩領。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。同22年十村の大字となる。 近代の白屋は、明治22年~現在の大字名。はじめ十村、昭和29年からは三方町の、平成17年からは若狭町の大字。明治24年の幅員は東西2町余・南北15町余、戸数79、人口は男194 ・ 女194。 《白屋の人口・世帯数》 234・73 《白屋の主な社寺など》 『三方郡誌』 加茂神社 熊野神社 山神社 共に白屋に鎮座。  ちょっと高台にあってどこからでもよくわかる所にある。「若州管内社寺由緒記」に「一向宗三百年以前より有レ之、二百年以前迄久保の道場と申候得共、五代以前の住持の時実如上人浄泉寺と法(木)仏の御裏に寺号被レ下候」とあるそう。 『三方町史』 浄泉寺 所在白屋二九-一。山号竜華山。真宗大谷派。本尊阿弥陀如来。天長二年(八二五)に、弘法大師が初めて設けたものであるといわれている。元は真言宗であったが、延文年間(一三五六-六〇)に、当時の住職が本願寺第四世法主善如の弟子となって、松川正真坊義空と名を改め、真宗に改宗したという。その後久保道場と言われていたが、第六代の住職正源のとき、本願寺第九代法主実如から浄泉寺の寺号を授かった。現在の本堂は、大正七年に建て直したものであるが、鐘つき堂は元禄(一六八八-一七〇三)初期のもので昔のままである。 ところで、「浄泉寺久保系図」によると、寺は正応元年(一二八八)四月下旬に、越前金崎城の落武者によって焼き払われたという。それまでの寺は、棟数四十余りの大きな寺で、寺地は上白屋村と、倉見村の中間(倉見狐塚の西南約百メートル付近)にあった。このことは昔からこの付近の石垣に、宝篋印塔(供養塔)の笠が積まれていたことや、この地がちょうど、白屋川が東の方へ曲がっていて水利がよかったこと、さらには、昭和四十九年の土地改良の際、大きな礎石が沢山出てきたこと、炉で火をたいたようなたき火の跡があって炭も残っていたこと、また、つぼのようなものや、小さな鉄の玉が出てきたことなどによって、ほぼ明らかである。 なお、釣り鐘は、太平洋戦争中、昭和十七年に供出したが、この釣り鐘は、銘文(拓木保管)によると、寛文十一年(一六七一)七月に、敦賀の鋳物師である助右衛門が作ったことが分かる。また、この釣り鐘を鋳造するとき、特に信仰心のあつい中村弥伝治が、純金のかんざし、小判などを鋳入したので、音色が非常にすぐれた名鐘であったと伝えられている。現在の釣り鐘は、昭和三十年に再鋳造されたものである。 『三方郡誌』 淨泉寺。眞宗大谷派、白屋に在り。天長二年、弘法の創建にして、眞言宗なりしが、延文年間眞宗に改宗したり。 『三方郡誌』 薬師堂。白屋に在り、淨泉寺の真宗に改宗の際、此に一宇を建立して、薬師の本尊を安置すと傳ふ。 『三方郡誌』 梅谷堡址。白屋に在り、口碑に云、信濃守の築く所と信濃守、姓名と事蹟と共に詳ならず。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 白屋の主な歴史記録『三方町史』 白屋 永仁三年(一二九五)十二月二日付けの倉見庄実験旧目録案に「白屋、国守一丁三百二歩」(大音文書)と記されているところから、この時代に、すでに白屋の集落のあったことが分かる。 また『三方郡誌』には「白屋は旧西路と称したり」とある。白屋中村徳治郎の「参考日記」(明治三十二年)によると、昔は白屋村と西路村の二か村に分かれており。制札場(立て札を立てておく場所)も二ヵ所あって、白屋村は藤の森川緑に、西路村は広畑川縁にあったという。しかし、合村以後は、制札場は西路村一ヵ所に定められた。ところで、南から北へ流れる白屋川に沿って道路が西に通じていることから西路村と呼ばれたといわれている。 この集落は、昔は製油業を営む者が多く、キリの実油を中心に多くの油を生産し、また、石灰の製造も盛んに行われた(第四編第五章参照)。 毎年八月一日には大刈り干しと言って、水田の肥料にするため区民総出の草刈り作業が行われた。刈り終ると、刈った草は牛に負わせ、牛落としというところまで運び、そこがらがけ下の平場へ落とし、ふたたび牛に負わせて持ち帰って積み上げ、翌年の肥料にした。また、三十三間山の奥地にスゲの群生があり、夏にこれを刈り取り陰干しにし、冬期にこれを材料にみのをつくり、農家や漁民に販売し、白屋の特産として好評であった。 明治期には浄るりや謡曲が盛んで、明治三十年ごろ、南西郷村金山から浄るり師を招き、また、旧北西郷村早瀬から来た三味線弾きを師匠としてけい古に励み、仲間の家で公演した。これにともなって、田上・井崎で組織されていた人形芝居の来演もあり、当時流行した野芝居も盛大に上演された。謡曲は、明治の中ごろ倉座の謡曲師について学んだ。また、金紙、銀紙、色紙を使ってハス・ボタン・菊・ツバキなどの花を作り、葬儀の献花にする仏前供花の流儀を、田烏の釣姫の一郎から習った。大正初期には、小原六右衛門から「専慶流」を習い、現在も浄泉寺の報恩講や、壇家の仏事には献花されている。 集落から旧国道へ出るには、鰣川・白屋川を通らねばならない。ところが、昭和の中ごろまでは、台風時などに豪雨があれば、堤防が壊れ、田畑や家屋は水浸しとなり、水害が繰り返された。昭和三十七年に、上白屋の入口から鰣川合流点までの河川が改修され、同年十月一日に完成して水害をうけることが無くなった。 大倉見城主熊谷大膳の出城であったと言われている梅谷城は下白屋北側山頂にあったと伝えられており、水は西側の滝谷から峰づたいに運んだといわれている(白屋「郷土誌」)。 白屋の伝説白屋の小字一覧『三方町史』 白屋 山王前(さんおうまえ) 山王(さんおう) 脇山(わきやま) 岩畑(いわばたけ) 広畑(ひろばたけ) 立畑(たてばたけ) 堂田(どうでん) 田矢(たや) 梅谷口(うめだにぐち) 水無口(みなぐち) 荒神(こうじん) 鎗田(やりだ) 泉谷(せんごく) 子守(こもり) 東馬場(ひがしばんば) 長塚(ながつか) 西馬場(にしばんば) 六町田(むまちだ) 五反田(ごたんだ) 検業(けんぎょ) 大谷口(おおたにぐち) 中条(なかじょう) 小谷(こだに) 西路(にしみち) 針の木(はりのき) 原内谷(げんないだに) 桐の木谷(きりのきだに) 鳥羽坂(とばさか) 坊の上(ぼうのうえ) 前の下(まえのした) 養老田(ようろうでん) 長町(ながまち) 柳原(やなぎわら) 山崎(やまさき) 保城谷(ほしろだに) 神服(かんぶく) 神明(しんめい) 上の山(うえのやま) 村中(むらなか) 久保の下(くぼのした) 桂(かつら) 風呂の上(ふろのうえ) 満処(まんどころ) 支那山(しなやま) 茶園(ちゃえん) 藤の森(ふじのもり) むしろじ谷(むくろじだに) 赤松(あかまつ) 庄司谷(しょじだに) 中田(なかだ) 坪の内(つぼのうち) 墓の前(はかのまえ) 狼谷(おかめだに) あじち畑(あじちばた) 河原田(かわらだ) 竹ヶ端(たけがはな) 池下(いけのした) 堤(つつみ) 北谷(きただに) 中の谷(なかのたに) 南谷(みなみだに) 峠(とうげ) 間谷(またに) 大石口(おいしぐち) 引廻し(ひきまわし) 槇の本(まきのもと) 安閑谷口(やすまだにくち) 由里の下(ゆりのした) 小豆谷(あずぎたに) 名谷(なこく) 冬山(ふゆやま) 杭座谷(くいざだに) 大石谷(おいしだに) 峠谷(とうげだに) 狼谷筋(おかめだにすじ) 竹山筋(たけやますじ) 小松原(こまつはら) 西路奥(にしじおく) 奥谷奥(おうたんおく) 北山(きたやま) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『三方郡誌』 『三方町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||