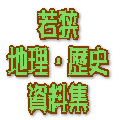 |
田上(たがみ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田上の概要《田上の概要》 井崎から梅街道を西ヘE27(舞鶴若狭自動車道)の高架の下をくぐった先の谷間にある。 中世の田上保。康安2年(1362)3月20日、幕府は大草十郎跡の田上保地頭職を去る文和3年(1354)5月25日の御下文の旨に任せて左京権大夫の代官に打渡すよう幕府使節国富長俊・吉岡禅棟に命じている(大音文書)。この左京権大夫とは観応3年(135)頃の守護斯波家兼とみられる。「康正二年造内裏段銭并国役引付」に飯河兵庫助が「若州三方郡四上 恒枝」の段銭1貫642文を納入しているが「四上」は「田上」の誤写と考えられる。弘治2年(1556)6月の明通寺鐘鋳勧進に「北方田かミ村」が300文を奉加している。 近世の田上村は、江戸期~明治22年の村。小浜藩領。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。同22年十村の大字となる。 近代の田上は、明治22年~現在の大字名。はじめ十村、昭和29年からは三方町、平成17年からは若狭町の大字。明治24年の幅員は東西3町余・南北5町余、戸数41、人口は男105 ・ 女92。 《田上の人口・世帯数》 143・41 《田上の主な社寺など》  『三方町史』 八幡神社 田上字中街道に鎮座。祭神誉田別尊・住吉大神・天照皇大神・豊受大神・春日大神・天児屋根命・比売神(六座)。国帳の、正五位梶生(かじふ)明神というのは、この社のことである。昔は字「かじふの」に鎮座し、梶生明神と呼んでいた。ところで、その地のたんぼの中に「大神森」という森があって、今から数十年前までは、年の古いクスノキが一本残っていた。たんぼの中に鎮座していたので別名を「田の神」と言い、村の名も「田神」と言ったが、いつの時代からか「田上」と改められた。この社が勧じょうされた年代については明らかでないが、神礼所蔵の箱の蓋に「貞和」(一三四五-五九)の年号があることから、創立年代の古いことが分かる。 本殿の再建については、承応三年(一六五四)と、寛文二年(一六六二)、宝永元年(一七〇四)、安永七年(一七七八)の棟札が残っている。拝殿は、明治四十五年一月に新築されたものである。 この社には、先に述べた貞和二年卯月七日と書いた箱の蓋・古面・文書をつけたしし頭と王の舞面、永禄十二年(一五六九)二月二十八日と書いてあるししとこまいぬ(高さ約八寸、台座約六寸)、「月山」銘入り の太刀、宝永元年(一七〇四)八月吉日と書いてある御前立神鏡(小島宗左ヱ門奉納の銘あり)が所蔵されている。しし頭と王の舞面につけられている文書には次のように記されており、その由来や社領のことなどが分かる。 この王ノ面・しし頭は、昔両村寄合祭の節に用い候品なり。社領もつぶれ、神輿は乱国故向笠へぬすみ祭もたえぬ。古き祭の神器なれば、未代まで大切に心得うべし。若き者等心得違い致し是を取扱ふ事なかれ、右は古き人の言い伝えを筆記するものなり。当時の主は天正年中(一五七二-七九)に滅び給ふ。 文化十二年(一八一五) 前田 義斎 社領有之候は武田家領主の頃なり。足利将軍義勝公の御代領主武田大膳太夫信公より八代孫八郎元明、この時に断絶す。 明治二十二年九月に、木造の鳥居が建立されたが、昭和四十六年には石造りの鳥居に建て替えられた。本殿は、こけらぶき、ひわだぶきと何回か屋根のふきかえが行われてしたが、昭和三十七年に銅板にふき替えられた。石垣は明治十四年に積まれたが、昭和十五年には、本殿前の階段がみかげ石の階段に改造された。 『三方郡誌』 八幡神社 田上に鎮座す、村民云國帳に正五位梶生野明神とあるは此れならんと  若狭梅街道沿いの立派な寺院。天授元年に創建され享保15年伽藍が焼失したが、のちに再建された。明治維新まで累世大本山総持寺に住し輪番職を勤め、末寺が15ある。 『三方町史』 常在院 所在田上二九-六。山号正法山。曹洞宗。本尊薬師如来。本尊は弘法大師の作である千体地蔵中尊・伽羅陀仏地蔵尊であった(共に絵像)といわれている(『若州管内社寺由緒記』)が、現在は寺宝として保存されている。この寺は、天授元年(一三七五)六月十日に、当時、若狭の一豪族であった飯郷山城守江戸左馬助(後市左衛門)が、大本山総持寺(現横浜市鶴見)の第四代目の住職寂霊の弟子であった道泉の徳を慕って、小浜の常在小路に一堂を建てて、道泉を迎えて開山としたのが初めであり、その後、山城守が城を田上に移すと、第四代の住職祐慶もこれに従って、寺を現在地に移したという。 享保十五年(一七三〇)には火災のため伽藍全部が焼けてしまったが.第十五世覺英が寺を再建した。また、明治三十年十月一日(住職は第二十二世月海)にも火災に遭って寺は全焼したが、第三十五世実応のとき再建された。明治維新までは檀家六百戸をもち、曹洞宗中本山として栄えていた。 また、この寺は、大本山総持寺五派中の妙高庵に属し、総持寺の輪番寺として活躍し、明治維新までに、歴代住職中、八人もり住職が輪番住職を勤めた。寺格は常恒会(格地)の位をもっており。これは曹洞宗での最高の寺格である。この寺の末寺は十五力寺であり、本山は、武生市土山の願成寺である。 寛文十二年(一六七二)八月に鋳造されたこの寺の釣り鐘は、太平洋戦争のとき、昭和十七年に供出された。現在の釣り鐘は、昭和二十三年四月に再鋳造されたものである。 『三方郡誌』 常在院。曹洞宗。田上にあり、招寶山と號す本尊は地蔵尊なり。傳云、草創は天授元年六月十日なりと。當時豪族飯郷山城守、僧龍室道泉の徳を慕ひ、小濱常在小路に一宇を創し、龍室を仰きて開山となす、其後山城守、城を田上に移し一時、當院四世一峯祐慶、從ひて寺を今の地に移すと、若狭舊跡傳来記に云、本寺は長門の國にあり、開基は飯江山城守と云ヘり天文年中、長門國より當國に引移されしとなり云々。孰れか是なるか詳ならず、されど開基の年代は伝来記の説是ならん。享保十五年、伽藍焼失して、十五世冑山堂宇を再建す。??三十年十月一日、再ひ災火に羅り、全院十三棟、烏有となる時に満舟代たり次代篤禅之を再建す。即現時の伽藍これなり。當院は開山の法系により、明治維新に至るまで、累世大本山總持寺に住し、輪番職を勤めたり。現今末寺十五寺、即ち圓成寺〔岩屋〕永正院〔倉見〕弘誓寺〔黒田〕良心寺〔西田村世久見〕久永寺〔以下遠敷郡三宅村三宅〕常源寺〔同村井ノ口〕神通寺〔遠敷村遠敷〕洞源寺〔今富村生守〕松福寺〔西津村西津〕清月寺〔野木村杉山〕長江庵〔鳥羽村長江〕安樂寺〔同村無悪〕吉祥院〔同村三生野〕香等院〔同村三田〕明渓院〔同村大鳥羽〕等なり。 『三方郡誌』 飯郷山城守首塚。田上常在院の庭前にあり、傳云ふ、飯郷山城守、田上山上に居城を構へたる頃、趙前朝倉氏来襲して、山城守敵する能はず、その一門江戸左馬助と共に自殺したり。因て兩氏の首を此處に、大石の下に埋めしなりと。 『三方郡誌』 川上堡批 田上の山上字庵の上にあり、飯郷山城守が築きて據りし所なりと傳ふ。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 田上の主な歴史記録『三方町史』 田上 田上の地名は第五編第三章で述べたように、田の神が田神となり、田上となったものである。永仁四年(一二九六)二月の倉見庄実検田目録に田上の地名が出現する(大音文書)ことや、常在院は天授元年(一三七五)に田上村の豪族飯郷山城守江戸左馬助によって開基された(第五編第二章参照)といわれているように、田上の歴史の古いことが分かる。 江戸左馬助のもとの姓は横田であり、五男を田上村の大屋家(現在の屋号大屋の先祖と思われる)へ養子にやっており、これが江戸家のはじまりである(木下貞一「横田家の人々」)という。江戸左馬助の居城は、北山の頂上にあったといわれている。朝倉勢の攻撃を受け、左馬助は一門と共に自刃した。その首塚であるといい伝えられている塚が常在院の庭園の片隅にある。また、左馬助の自刃については、無用の戦禍から逃れるための単なる見せかけではなかったかとの説もある(同前「横田家の人々」)。 この集落では、昔、百姓分と小百姓分に分かれていた。田三十アール以上所有する者が百姓分、それ以下の者は小百姓分であった。祭礼には百姓分は大神事、小百姓分は小神事といい、当屋もそれぞれ違っていて別々に祭りを行っていた。また、区費の割り当てなどにも差があった。この身分上の差別も、太平洋戦争後は廃止された。 明治末期から大正期にかけて養蚕がさかんで、中庄、上庄の畑地は全部桑畑であった。田上には北方製糸工場があった(第四編第五章参照)が、大正十四年ごろから、桑畑の跡は富有ガキの栽培が始められた。富有カキの産地である岐阜県本巣郡を視察して苗木を購入し、カキ組合を結成して計画的に運営し、年産一八・五トン余の収穫をあげた。昭和八年に、越前平野を中心に行われた陸軍大演習に行幸の天皇に、田上産のカキを献上した。 昭和二十八年九月の台風十三号により、田上川(俗称くろのうち)が壊れ、水田約二十アールが土砂に埋もれた。この川の復旧は昭和三十七年に完了したが、昭和四十六年には俗称芝原に砂防えん堤を建設した。 さらに、昭和六十一年度には、幅七・五メートル、高さ十一メートルの「滝のえん堤」と、幅八・八メートル、高さ十三メートルの「サンマイ奥えん堤」を完成した。 昭和二十九年に、わら屋根であった集会場を、階下が集荷場、階上を集会場とした公会堂に改築した。 昭和四十八年に上庄の畑地百四十アールをブドウ畑に造成し、十戸余りで組合を結成して生産に励み。一時は観光ブドウ園も開いた(第四編第七章参照)。平成元年に生産に従事しているのは四戸余である。 田上と上中町無悪を結ぶ田上坂道路や、佐古と結ぶ佐古坂道路は、昔は大事な路であったが、今ではほとんど利用されていない。現在、三方町と上中町を結ぶ広域農道のトンネルエ事が田上で進められているが、これが完成すると交通上非常に便利になる。 田上の伝説田上の小字一覧『三方町史』 田上 芝原(しばはら) 薬師谷(やくしだに) 古坂(ふるさか) 蓑毛畑(みのげばた) 隠谷(かくれだに) 牧口(まきぐち) 堀の内(ほりのうち) 落尻(おとしじり) 若宮(わかみや) 武久呂谷(むくろだに) 中の街道(なかのかいどう) 宮の前(みやのまえ) 藤の木(ふじのき) 馬場の上(ばばのうえ) 庵の上(あんのうえ) 高畑(たかはた) 堂端(どうばた) 鍛冶屋川(かじやがわ) 北畠(きたばたけ) 観音山(かんのんやま) 小竹(こだけ) 志跡喜谷(しろきだに) 大畑(おおはた) 中島(なかじま) 田中畑(たなかばた) 鴫の尾(しぎのお) 無悪条(さかなしじょう) 坂の尻(さかのじり) 寺ヶ谷(てらがだに) 片山(かたやま) 前田(まえだ) 黒の内(くろのうち) 馬場の下(ばばのした) 御代田(ごだいだ) 三角田(みすみだ) 上町田(かみちょうだ) 下町田(しもちょうだ) 大坪(おおつぼ) 門田(かどた) 柿木畑(かきのきばた) 稲葉尻(いなばじり) 稲葉山(いなばやま) 堂屋敷(どうやしき) 恵寿母(えすぼ) 森畑(もりばたけ) 杉山(すぎやま) 小笹(こささ) 上大坪(かみおおつぼ) 小東谷(こひがしだに) 東山(ひがしやま) 立山(たてやま) 山た(やまだ) 水梨(みずなし) 陸老喜(むくろぎ) 神納山(じんむさん) 北山(きたやま) 口落(くちおとし) 西山(にしやま) 秋葉山(あきばやま) 千代子口(ちょうしぐち) 細畑(ほそばた) 大東谷(おおひがしだに) 口東谷(くちひがしだに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『三方郡誌』 『三方町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||