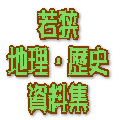 |
田井(たい)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田井の概要《田井の概要》 上ノ湖(三方湖)西岸から西南岸を占める広域の村。西田村にはほかにはこんな広い土地はない。 中世の田井保。鎌倉期~戦国期に見える保。文永2年(1265)11月の若狭国惣田数帳案の「便補保」のうちに田井保23町3反72歩とあるのが初見で、この田地は田井の地に18町3反72歩、三方郷に5町あった。元亨年間頃に書き加えられた朱注に、もとの地頭は金子又太郎であったが、今は多伊良小太郎隆能が地頭であるとし、当保は「大炊寮領」であると記す。平安末期から大炊頭を局務家中原氏が世襲したので、中原氏が領家の地位を占めた。年未詳11月20日の綸旨には「大炊寮若狭国田井保内小面浦刀禰友吉以下事」とあり(大音文書)、常神半島の小面(小河)浦も当保に含まれていたことがあった。南北朝期の中原師守の日記「師守記」には当保の記事が多い。同書によると、領家中原氏のもとで預所が置かれ、公文が任命されて年貢収納にあたっていた。また,鎌倉期と同じく地頭がいたが(康永4年9月26日条)その名を知ることができない。当保から年貢・夫役・兵士用途銭・上葉銭のほか月菜・和布・鮒鮨・鯛・鰹・貝蚫・海松・鰺・アマサギ・大豆・小角豆・唐梨などの産物が納入、進上されている。南北朝期にはまた公文職をめぐる争いもあった。康永4(1345)年5月1日に公文であった石崎(井崎)大夫房良成は補任料を納めて公文職と楽一名を領家から安堵されているが、貞和3年(1347)正月にはもと公文であったと推定される道尊の子石崎大進房円慶が公文職補任を望んで訴訟となり、結局貞和3年3月10日円慶が公文に任じられた。貞治元年(1362)11月29日守護石橋和義は丹後出兵の兵粮料として当保の半済を行い、貞治2年閠正月6日には丹後出兵中は半済に加えて当保4分1を石橋氏被官(給人)に与えるという命令を発している。同3年から守護となった斯波義種のもとでも守護の支配は強まり公文も斯波氏に従わざるを得ない状況となって、そのことが貞治5年8月の斯波氏の幕府に対する離反ののち、守護一色範光によって当保公文職は敵方与同人として闕所と見なされる理由になったものとされる。領家は守護方奉行小江房を通じて交渉し、先公文井崎円憲の舎弟である道成に安堵することができた。この井崎円憲・同道成は三方部倉見荘井崎を本拠とする人ではないかと思われる。公文職については、さらに公文名楽一名の本年貢を収納する「田井保法花島(田井島)大乗寺」の寺僧たちが名の本年貢の一円寄付を求める申文を領家に提出している(同年8月19日条紙背文書)。また守護方よりも公文職を管領するとして貞治6年7月10日市河入道が入部したため領家は再び守護一色氏と交渉し、7月26日当保は内裏供御料所であるので公文職違乱を止めよという一色氏の下知状を得て一段落した。その後大炊寮領としては文安6年(1449)5月9日に権大外記中原安富が大炊寮領の回復を幕府に願ったうちの1つとして見え、醍醐寺三宝院の仲介によって安禅寺に照会することになったとある(康富記)。この安禅寺とは京都の真言宗寺院で、この頃倉見荘内3名を領しており、あるいは当保にも支配権を有していたのかも知れない。文安6年の東寺修造料足奉加人数注進状には田井保内の田井島の大乗寺と保内の竜泉寺が見える。竜泉寺は寛正4年(1463)の常神神社棟札にも、常神社造立の勧進上人長門国住人能満寺智俊は今は真言宗「田井保竜泉寺住」とある。三方湖内の田井島にあった大乗寺には天文6年(1537)5月21日醍醐寺理性院主厳助が逗留したことがあり、天文15年には田井の領主入江実次が本堂を再建したという。当保の名は弘治2年(1556)6月の明通寺鐘鋳勧進に「田井保ヨリ」400文を納めたとあるように戦国期にも用いられている。 近世の田井村は、江戸期~明治22年の村。小浜藩領。田井野・田立・河内・別所・世久津・伊良積の小村からなる。江戸期を通じて新田開発が盛んで、そのほとんどが島新田の開発である。同新田は世久津の武長宗兵衛から3代にわたって開発されたもので、最終的に3万坪に及んだといわれる。江戸後期から明治期にかけては郡内有数の養蚕地でもあった。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。同22年田井村の大字となる。 近代の田井村は、明治22~40年の三方郡の自治体。田井・海山・成出の3か村と世久見浦が合併して成立。旧浦村名を継承した4大字を編成。役場を田井に設置。明治36年田井尋常高等小学校設立。同40年西田村の一部となり、4大字は同村の大字に継承された。 近代の田井は、明治22年~現在の大字名。はじめ田井村、明治40年西田村、昭和28年から三方町、平成17年からは若狭町の大字。明治24年の幅員は東西25町・南北20町、戸数159、人口は男489・女487、学校1、小船38。同42年頃はほとんどが農業に従事していた。大正期頃から梅の栽培が行われ西田梅として知られている。 《田井の人口・世帯数》 591・169(田井野、梅ヶ原、田立、別庄、世久津、伊良積、北庄の合計) 《田井の主な社寺など》  村の真ん中あたりに鎮座。隣に慈眼寺がある。田井というのは当社の多由比(田結)が訛ったものか。田井という所はあちこちにあるが、ずいぶんと古い地名でなかろうか、互いに関係があるものかも知れない。 『三方町史』 多由比神社 田井字尾上に鎮座。祭神誉田別尊・菅原道真。 式内社・指定社・旧村社。明治四十一-四年、次の神社の祭神が、この社に合祀された。 大髭神社祭神大髭大神(元、この社の境内社) 白髭神社祭神白髭大神(同) 若宮神社祭神若宮大神(同) 稲荷神社祭神稲倉魂神(同) 山神神社大山祗命(元、田立・世久津・伊良積に鎮座、四社) 天満宮祭神菅原道真 (元、田井野に鎮座) 稲荷神社祭神稲倉魂神(元、田井野天満宮の境内社) 神明社祭神天照大神 (元、田立・河内に鎮座、二社) 杵築神社祭神素戔鳴尊(元、成出に鎮座) 岬神社祭神蛭子尊 (元、杵築神社の境内社) 多由比神社の名は、「延喜式神名帳」に記されており、国帳には「正五位手結明神」と記されている。この社は天満宮とも言われているが、伴信友の「神社私考」に「今田井ノ八幡と称す社あり、これ田結ノ神社にやあらむ、然らば当国の田結ノ神社は、国も郡を隣りたる越前敦賀ノ郡の田結ノ神を祭来れるにて、地名にもおよびたるが、ともに訛りて田井と呼ぶ事となれるべし、かくて越前なる田結ノ神社を、八幡と袮ふ事となりたるに例ひで、此方なるも八幡を合セ祀りたるか、又然らでもおのづから同じきにてもあるべし、いづれにもその合セ祀れる方の御名のみ、もはら申ならひて、旧の御名はかへりて隠れ給ひ、つひに田井ノ八幡とのみ称す事となりたるなるべし」とあって社名の由来を知ることができる。 この神社の別当寺は慈眼寺で、この寺の住職が明治になるまで、多由比神社の祭礼、そのほかを管理していた。 神殿の背後には、一反一畝(約十一アール)余の風致林指定を受けた社有林があり、また、河内地籍にも、昭和三十六年十二月に、田井大総(田井地区の長)から寄進を受けた山林七反がある。 昔は祭りの当屋は、どの集落でも特に家柄のよいごく限られた家だけで行われていたが、現在は氏子区域六集落が翰番で受け持ち、費用は四反歩の神田からの収入のほかは、当番区の負担となっている。例祭は四月十八日で、この地域の最も大きな行事である。神役は、昔は田立五人・世久津四人・田井野一人・伊良積二人の十二人であったが、明治十年ごろ、京都古田神社の祭事をまねて、大御幣の人(メンナシ)を増やしたので、現在では田立五人・世久津九人・田井野一人・河内一人・成出一人・伊良積二人の計十九人となっている。 例祭は四月十八日であるが、神事は二目前の十六日から始まる。その日は一週間前から酒・肉を断って心身を清めた十九人の神役が当屋に集まり、神主による祝詞の奏上や玉串奉奠など古式に従った諸行事が行われ、夜は宴会となる。十七日は宵祭り、十八日は例祭で、早朝からのぼり立てをはじめ、いろいろな神事が行われる。女児による人身御供・青年のはやし・社頭への行列・神役の御幣にべんざらさ大鼓を従えての出迎え・「ヨイヨイボー」「サイヨー サイヨー」の村人の掛け声・神主の幣ふり・青年のみこし担ぎ・松の浜への行列・王の舞・獅子舞・べんざらさ太鼓・面なし・みこしの巡行などの行事が、昔のままに行われている。十九日に、神事の清算・直会・当屋渡しなどがあって祭礼は終る。 現在の社務所は昭和四十二年に改築されたものである。 『三方郡誌』 多由比神社 村社。式内。田井田井野に鎮座す、もと八幡宮と稱す、後に合祀したる所を以て稱したるなるべし、又邑名の田井も多由比の約なるべし、もとの祭神詳ならす國帳には正五位手結明神とあり。  『三方町史』 慈眼寺 所在田井九三-五(別庄)。山号普品山・高野山真言宗。本尊聖観世音菩薩・慶長元年(一五九六)に、天神・八幡両宮(多由比神社)の境内にあって、本地仏阿弥陀如来と、観音菩薩をまつっている講坊(教えを説く小さい講堂)を普品山慈眼寺と名付け、従来の大乗寺の仏法に関する一切の事務を受け継いだのがこの寺の始まりである。それから約五十年後の慶安二年(一六四九)に、紀伊国那賀郡大野村の僧宥将が住職となり、本堂を建て寺としての体裁を整えた。 明治期には、特に学僧風の住職が続き、人々を仏道に導く教化活動を中心に、一般社会事業にも貢献した。現在この寺に所蔵されている貴重な文化財(三方町指定、六点を含む〔本編第四章参照〕)も、ほとんどがこの時期に入手されている。明治六年の学制発布に当っては、この寺の本堂が、温知小学校(第二小学校の前身)の教室に充てられた。 現在なお、祈願所としての、古くからの伝統的な宗教的行事が、田井地区の各集落や、海山・塩坂越区などで行われている。 『三方郡誌』 慈眼寺。眞言宗。田井田立に在り。もと法華山大乗寺の末寺なり。田井村の惣鎮守天神・八幡両宮の別當は大乗寺之を勤めたり。両宮の社域に講坊あり、普品山慈眼寺と號す、別當田井島に在りては、勤行自由なりかたかりければ、慶長元年、住僧此講坊に移り住む、是今の慈眼寺の創始なり。寺に大乗寺の開山道嚴〔開山は道嚴に非るべし〕及ひ同寺の大旦那入江越前守入道實次夫婦の位牌を安するは、亦之か爲なり。  『三方町史』 観音寺 所在田立一-七。山号瑠璃山。曹洞宗。本尊薬師如来。正保二年(一六四五)に、臥竜院十世長天が初めて開いたもので、宝寿庵といった。本尊は、竜泉寺廃寺の時、竜泉寺の本尊を田井八十一号字南河原三番畑地に下山安置したといわれており、この畑地は三畝十五歩(三・五アール)あって医王庵畑(養庵畑またはよあん畑ともいう)と呼び、宝寿庵の所有地であったが、大正四年に、区の協議により個人所有としたものである(石崎寛治「田立区語り草」昭二七・三)。現在の本堂は安政二年(一八五五)九月に改築したものである。 宝寿庵は臥竜院の末寺であったが、昭和十七年に、小浜市太良庄の長英寺の末寺となり、昭和十九年四月に、長英寺の末寺であった観音寺(格式は平僧地〔曹洞宗寺院最下位の格付〕)の名儀移転を長英寺に交渉し、昭和二十年七月一日、曹洞宗宗務庁からその許可を得、昭和二十一年八月には、法地に昇格して一寺院として認められた。 昭和二十二年四月四日に、法地開山勤宗の晋山峨結制大法要が実施された。昭和三十二年四月には、庫裏の建設が、また、昭和三十六年八月には本堂・開山堂・そのほか諸堂の増改築が、昭和四十三年七月には、本堂屋根の改修がそれぞれ行われた。 イッパツでは行けそうにもヤヤこしい所、ナビにもない、カンで行くより手もないが、田立の一番奥になる。このあたりの人々はまことに親切で、道を問うと「さて、あのジイさん行けるかいな」と心配してか、農作業中であろうに、軽トラであとを追い掛けてくれる。おかげでめでたくたどりつきました、感謝。  『三方町史』 養命院 所在田井一〇六-二〇(世久津)。山号紫雲山。曹洞宗。本尊延命地蔵菩薩。釈迦堂の前身である法華山大乗寺が太閤検地による収奪(財産などを強制的に取り上げること)によって、次第に荒れ果てたため、明暦三年(一六五七)に、本尊そのほかの仏像を世久津の養命庵に移した。その後、臥竜院第十二世貝江が庵主となり(約二八〇年前)、真言宗から曹洞宗に改宗した。 太平洋戦争後の宗教法の改正によって、昭和二十八年臥竜院末寺から独立して法地となり、山号を紫雲山、寺号を養命院と名付けた。この時の開山は、臥竜院第三十二世良仙であった。 この寺の釣り鐘は、太平洋戦争のとき、昭和十七年に供出されたが、戦後昭和二十八年三月に再鋳造された。 『三方町史』 徳林寺 所在田井野八-三五。山号金光山。曹洞宗。本尊延命地蔵菩薩。田上の常在院の末寺で、徳林庵といった。創建年代などについては記録がないが、過去帳に書いてある一番古い年号に、寛文(一六六一-七二)の年号があるので、この寺は二百年余り昔に、はじめてつくられたと考えられる。 明治三十年火災に遭って全焼したが、過去帳、秘蔵の宝物や寺の備品は災難をのがれ、数年後に現在の堂が再建された。開山堂は昭和二十六年に建立されたものである。 昭和三十九年三月十八日、法地に昇格が認められ、寺号を徳林寺と名付けられた。法地昇格による法地開山は常在院住職照雄で、二代目は円成寺住職源亮であり、現在の住職良童は三代目である。この寺の釣り鐘は太平洋戦争中、昭和十七年に供出されたが、昭和三十九年法地昇格を記念して再鋳造した。 『三方町史』 愛宕神社 田井字田立に鎮座。祭神迦具土神。七月二十四日には、区内は休業して総講を行う。前日二十三日の宵宮には、笛太鼓で灯明をお社に奉納し、お火たきを囲んでお神酒をいただく。昔、神仏混淆時代には、宝寿庵の住職が読経し、参詣者は焼香した。 明治四十四年に、神明社・山神社が多由比神社に合祀されるまでは神明社が田立の代表神で、毎年一月六日に初講・旧三月三日に小祭りを行った。 『三方町史』 愛宕神社 田井字世久津に鎮座。祭神迦具土神。山の神神社を多由比神社に合祀するまでは、村はずれの「辻の端」の山の中腹にあったが、その後、山の神神社の跡地(養命院の裏山)に移した。祭日は七月二十三日で、青壮年による献灯(はやし)がある。建物は約六平方メートル程度である。 『三方町史』 秋葉神社 世久見峠の中腹に鎮座。祭神迦具土神。祭神は火の守護神としてまつっている。建物は約四平方メートルである。祭日は九月一日であるが、八月三十一日の宵宮に、青壮年による献灯(はやし)が奉納されている。 『三方町史』 廣嶺神社 田井字北庄に鎮庫。祭神素盞嗚男命。北庄では昔から、廣嶺神社を氏神としてまつっていたため、相当大きなほこらがあった。しかし、明治四十一年に宇波西神社の境内社である八幡神社に合祀されたため、その後は小さなほこらに分神をまっり、区民信仰の対象として崇拝してきた。ところが、昭和四十年には、立派な神殿が新築され、宇波西神社の宮司を招いておごそかに遷宮式(神霊を移すときの儀式)が行われた。 例祭日は四月十八日である。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 田井の主な歴史記録田井の伝説田井の小字一覧『三方町史』 田井 東赤尾(ひがしあかお) 赤尾(あかお) 南赤尾(みなみあかお) 畑山口(はたけやまぐち) 西赤尾(にしあかお) 天神下(てんじんした) 本田(ほんだ) 東本田(ひがしほんだ) 西谷壱(にしのたにいち) 西谷口(にしのたにぐち) 西本田(にしほんだ) 池の下(いけのした) 岡(おか) 岡の下(おかのした) 浦池(うらじ) 東清水(ひがししょうず) 中清水(なかしょうず) 二通南(にどうりみなみ) 岡西(おかにし) 二通(にどうり) 高柳(たかやなぎ) 桑原(くわばら) 二通北(にどうりきた) 三通北(さんとおりきた) 三通中(さんどうりなか) 四通北(よんどうりきた) 四通中(よんどうりなか) 四通南(よんどうりみなみ) 清水(しょうず) 川東(かわひがし) 五通南(ごどうりみなみ) 五通中(ごどうりなか) 五通北(ごどうりきた) 六通北(ろくどうりきた) 六通中(ろくどうりなか) 六通南(ろくどうりみなみ) 破風東(はぶひがし) 破風西(はぶにし) 奥の谷(おくのたに) 七通南(ななどうりみなみ) 七通北(しちどうりきた) 八通(はちどりり) 入屋(におや) 館(たち) 大橋(おおはし) 佐生(さそう) 西佐生(にしさそう) 下田中(しもたなか) 田中(たなか) 河原(かわら) 神明(しんめい) 上行司(かみぎょうじ) 行司(ぎょうじ) 西見口(にしみぐち) 西見(にしみ) 鳥羽道(とばみち) 下摺畑(しもずりばた) 摺畑(ずりばた) 南山寺(きなみやまでら) 山寺(やまでら) 橡谷(とったん) 荒坂(あらさか) 羽谷(ばたん) 市の庄(いちのしょう) 清水道(しょうずみち) 本通(ほんどうり) 新兵衛(しんべえ) 桃木谷(ももきだに) 無庄(むしょう) 中村(なかむら) 上片山(かみかたやま) 片山(かたやま) 下片山(しもかたやま) 新道(しんどう) 広田(ひろた) 北の下(きたのした) 南山田(みなみやまだ) 山田(やまだ) 茶の前(ちゃのまえ) 西の上(にしのうえ) 南河原(みなみかわら) 中河原(なかがわら) 上坪の木(かみつぼのき) 坪の木(つぼのき) 繩手(のて) 防ヶ丘(ぼうがおか) 防ヶ市(ぼうがいち) 池の尻(いけのしり) 宮の上(みやのうえ) 奥(おく) 北奥(きたおく) 東奥(ひがしおく) 尾上(おのうえ) 別所(べっしょ) 南谷(みなみだに) 五郎ヶ浦(ごろうがうら) 上五郎ヶ浦(かみごろうがうら) 堂の下(どうのした) 大浜(おおはま) 上大浜(かみおおはま) 瀬松口(せまつぐち) 瀬松(せまつ) 長畑(ながばたけ) 村沢(むらさわ) 上の山(うえのやま) 平尾(ひらお) 小崎(こさき) 北脇(きたわき) 世の下(せのした) 陀妻(だつま) 上陀妻(かみだつま) 千年寺(せんねんじ) 柿の浜(かきのはま) 田井越(たいごし) 南畑(みなみばたけ) 上南畑(かみみなみばたけ) 弐反畑(にたんばた) 青井下(あおいした) 北畑(きたばたけ) 上北畑(かみきたばたけ) 西新田(にししんでん) 西島(にしじま) 新田(しんた) 西島田(にししまだ) 百八切(にしやきり) 東八切(ひがしやきり) 南島田(みなみしまだ) 東島田(ひがししまだ) 東島(ひがししま) 島堂(しまどう) 西行司(にしぎょうじ) 柿ヶ内(かきなうち) 西広田(にしひろた) 上河原(かみかわら) 下河原(しもかわら) 鍋割(なべわり) 北千年寺(きたせんねんじ) 松尾下(まつおした) 上青井下(かみあおいした) 出川谷(しつかわだに) 成出村上(なるでむらかみ) 柳谷(やなぎだん) 畑山(はたけやま) 滝の坪(たきのつぼ) 鳥越(とりごえ) 股谷(またに) 西谷(にしのたん) 清水奥(しょずおく) 桂谷(かつらだん) 天原日(あまらび) 中の谷(なかのたん) 滝の谷(たきのたん) 上奥の谷(かみおくのたん) 入屋奥(におやおく) 佐生奥(さそうおく) 田中谷(たなかだん) 行司谷(ぎょうじだに) 西見奥(にしみおく) 蔵谷(くらたに) 上小柿谷(かみこがきだん) 下小柿谷(しもこがきたん) 奥摺畑(おくずりばた) 雛窪(ひなくぼ) 蛙股(かえるまた) 柿ヵ内奥(なきなうちおく) 山寺口(やまでらぐち) 山寺奥(やまでらおく) 橡谷口(とったんぐち) 橡谷奥(とったんおく) 青木原(あおきはら) 荒坂谷(あらさかだに) 上本道(かみほんどうり) 新兵衛谷(しんべえだに) 無庄谷(むしょうだに) 竜泉寺(りゅうせんじ) 無庄北(むしょうおく) 片山奥(かたやまおく) 新道谷(しんどうだに) 上山田(かみやまだ) 栗木出(くりきだし) 権現谷(ごんげんだに) 池の堀(いけのほり) 出ヶ窪(でがくぼ) 高畑(たかはた) 大平(おおひら) 庄坊谷(しょうぼうだに) 漆谷(うるしだに) 北滝谷(きたたきだに) 細谷(ほそだに) 奥落(おくおち) 上勝(かみかつ) 坊ヶ奥(ぼうがおく) 奥の前(おくのまえ) 別所谷(ベっしょだに) 奥坂(おくざか) 世松谷(せまつだに) 長谷(ながたに) 赤畑(あかばたけ) 小谷(こたに) 永振谷(えぶりだに) 坂谷(さかたに) 滝世谷(たきせだに) 唐木谷(からきだに) 堀木谷(ほりきだに) 平尾谷(ひらおだに) 比の谷(ひのたに) 立間(だつま) 猿橋(さるはし) 此の上(このうえ) 岡の上(おかのうえ) 立屋(たちや) 上栖(じょりさらし) 松尾(まつお) 後谷(うしろだに) 青井谷(あおいだに) 橡木谷(とちきだに) 島(しま) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『三方郡誌』 『三方町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||