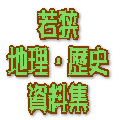 |
上野(うえの)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上野の概要《上野の概要》 国道27号沿いの成願寺と能登野の間、鰣川支流八幡川流域に位置する。 近世の上野村は、江戸期~明治22年の村。小浜藩領。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。同22年十村の大字となる。 近代の上野は、明治22年~現在の大字名。はじめ十村、昭和29年からは三方町、平成17年からは若狭町の大字。明治24年の幅員は東西4町余・南北4町余、戸数34、人口は男86 ・女82。 《上野の人口・世帯数》 169・52 《上野の主な社寺など》  このあたりが村の元々の中心なのであろうか。 『三方町史』 専照寺 所在上野二二-四。山号日照山。浄土真宗大谷派。本尊阿弥陀如来。創立当初の年代は明らかでないが、僧現導が植野村に開いたのが、この寺である。初めは天台宗であったが、その後現導が、天正二年(一五七四)に、現在の浄土真宗大谷派に改宗し。山号を日照山、寺号を専照寺と名づけたと伝えられている。 本堂は、文化四年(一八〇七)九月二日、九代目住職慶遠のとき建てた。そして、成願寺村の岡本坊(真言宗)の信徒である井上喜右衛門一族を除いて、区内の大半がこの専照寺に帰依し、信徒になった。 釣り鐘堂は、明治二十七年に再建された。この時、今までの釣り鐘は音色が悪いので再鋳造された。ところが、太平洋戦争中、昭和十七年に供出され、昭和二十九年四月、滋賀県八日市で鋳造されたものが、現在の釣り鐘である。この寺に駕籠が残っているが、僧侶が医業に使ったらしい。 現在の住職浩は第十五世である。 『三方郡誌』 専照寺 真宗大谷派。上野にあり。現道と云へる者の開基なり、元、天台宗なりしが、天正二年、今の宗旨に改宗す 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 上野の主な歴史記録『三方町史』 上野 この集落に初めて人が住みついた時代は確認できないが、今から約六千年前(縄文時代)、大洪水や大地震などが起こったとき、上野の東山が大きな山崩れを起こし、その土砂が流れ出して、現在の上野の耕地や住宅地の原型ができたものといわれている(上野「郷土誌」)。嵯峨天皇の時代(八一〇-八二三)に、氏神として信濃(長野県)の諏訪神社の神霊を勧じょうしたという。諏訪神社(旧村社、明治四十二年に闇見神礼に合祀)をまつっていたことから、このことが事実とすれば約千二百年前には既に集落ができていたと考えることができる。「明治六年物産表」(白屋大之六兵衛文書)には、植野村とあり、「明治二十三年三方郡茶業組合十村実業者人名」(同前文書)には上野とある。このようにこの集落名は、明治十七年五月に、区町村会法が改正されたとき、植野村から上野に改められたものと思われる。 集落ができた最初は、民家は三十三間山の山すそに在ったものと思われるが、人口が増えてきたので東西に道路を造り、川を造って北へ拡がっていった。その後、南北に国道が造られると、人馬の通行がはげしくなり、さらに人口も増え、平らで交通の便利な街道沿いに移り住む者が多くなり、他村からの移住者も住みつくようになった。 三十三開山には石灰岩があり、薪炭用材も豊富で、石灰や薪炭の生産がさかんに行われた。また、シナの本の皮をはいで、その繊維をござのたて糸や、わら工品の製作に利用し、さらに、白屋と同じようにスゲを採集して、みのを作ったり、多くの山菜を採集して、主食や副食にするなど、三十三間山の資源は、住民の生活を大いに潤していた。 明治三十八年には、旧十村地域にあった四小学校が統合されて、十村尋常高等小学校となり、当区北端の山道地籍に新築された。昭和四年には能登野地籍に増改築されたが、昭和四十四年には上野第五号六番地に鉄筋校舎が新築された、昭和二十九年三月に旧十村が三方町に合併するまでは、上野は、旧十村の政治・教育の中心地として、村のすべての行事が学校、役場を中心に行われ、非常に恵まれた環境であった。 明治四十二年から大正三年までの五ヵ年間に、耕地整理組合を中心に狭い田や段々畑を十三ヘクタール以上の水田に整理した。現在の水田は、第四編農業で述べたように、昭和五十九年に、地区再編農業構造改善事業として、土地改良が完了したもので、その面積は八・八ヘクタールである。 明治初期から昭和二十年ごろまでは、水車が沢山あって、米つき・麦つき・製粉・わら打ちなど水力を利用していた。明治十五年一月十八日の記録によると、田中長右衛門宅に営業用の水車が二基あり、一基について五銭の税金を納めていた。 上野川上流の山のふもとに山ノ神社があり、昔は、三月三日に、この神社の祭りをにぎやかに行っていたが、今は、「山の口講」として行事が行われているにすぎない。山ノ神社には財産として「山の口田」があって、この用からの収入を山ノ神社祭りの費用にあて、残りは区の会計に繰り入れたといわれているが、現在は植林にょる収入によって賄っていく計画であるという。 上野の伝説上野の小字一覧『三方町史』 上野 岸下(きしのした) 山王前(さんのおまえ) 丁畑(ちょばたけ) 長尾端(ながおばな) 瀨戸分(せとぶん) 高岸(たかぎし) 杉の木(すぎのき) 畑上(はたがみ) 三反田(さんだんだ) 志津計(しつけ) 松原田(まつわらだ) 奥下(おくのした) 山道(やまみち) 白木ヶ市(しらきがいち) 梨の木(なしのき) 市姫(いちひめ) 諏訪森(すわのもり) 観王寺(かんのじ) 茶の木(ちゃのき) 五反田(ごたんだ) 平柳(ひらやなぎ) 御仏供田(おぶくでん) 天王守(てんのまぶり) 岩田(いわだ) 北山田(きたやまだ) 山の口(やまのくち) 南山田(みなみやまだ) 下谷(しもだん) 細越(ほそごえ) 東の谷(ひがしのたに) 河内谷(こうちだに) 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『三方郡誌』 『三方町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||