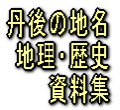 |
堂奥(どうのおく)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堂奥の地誌《堂奥の概要》 堂奥は舞鶴市の東部。祖母谷川の流域。東舞鶴インターの周辺である。 《人口》282《世帯数》89 《主な社寺など》 『加佐郡誌』 〈 『丹哥府志』 〈 『丹後国加佐郡寺社町在旧起』 〈 『倉梯村史』 〈 〈 《交通》 舞鶴若狭道の「東舞鶴インター」がある。 《産業》 堂奥の主な歴史記録《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 樹徳庵雲門寺末寺なり。昔矢野備後守橘の朝臣達政ミチマサ嫡子弥三郎政秀天文十五丙午のころ城山にあり元亀年号の頃は矢野藤市共云う。 「解説」天文十五丙午(1546後奈良天皇将軍足利義勝丹後守護一色八代義幸) 元亀年号(1570-1573)正親町天皇将軍足利義勝丹後守護一色九代義道 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 堂奥村 高四百四十九石二升八合 内十八石七斗一升五合九勺 万定引 五十三石御用捨高 樹徳院 雲門寺末 山之口社 八月朔日祭角力有 堂奥村多門院村ノ氏神 元文二年春宮津白カシ町加右衛門と云者の野田去 年の水にて山崩れたり 此度地を平均申候処土中 より鰐口を掘出す 銘有り田辺山口大明神と在之ニ 付其後嘉右衛門田辺引土町六兵衛と云者に右之段語 り双方上江無沙汰ニ而遺申度由 六兵衛堂奥江知ら せ掛合ニ而貰申候由 鰐口ノ銘 丹後加佐郡倉橋郷祖保谷村 山口大明神 曽此ノ字違シカ此脇ニ彫付有 文安二十一月廿一日 勧進聖道仙敬白 年数元文二年迄二百九十三年及 天神社 荒神社 薬師堂 八幡社 《丹哥府志》 〈 【山口大明神】 山口大明神の禁口元文二年の春宮津白柏町の人の田より掘り出す。其銘に云。丹後国加佐郡倉梯郷祖保谷村山口大明神文安二年十一月廿一日勧進聖道仙敬白とあり、後に其人より其村へ遣す今に在り。 【瑠璃山樹徳庵】 【矢野備後城墟 《加佐郡誌》 〈 堂奥は後花園天皇の康正年間に祖母谷村と称したといふことであるが、(参考三に記せる山口神社の鰐口の銘には曾保谷とある。)文安二年は丁度康正元年から十年前に当っているから、此処は少し研究の余地があるやうである。北方の中城山に矢野備後守の居った城址がある。正親町天皇の元亀年間に天野藤平と云ふ者が居り、後には橘朝臣幸政息彌三郎秀政といふ者が依っていたさうであるが年代が詳かでない。 《倉梯村史》 〈 昔堂奥字谷口に大神宮を奉祀せる社ありて広き参道あり手洗の池も備はり、一層勝れし神木もありしか、切りて牧野侯の城閣の櫓太鼓を作り残木を以て矢野山法起菩薩の神庫を作れりとなん。 三條橋 堂奥に小字三條橋あり、徳川の初期基督教の信者三十八士此の地に潜みしが遂に露れて討首に遇ひたり此の三十八士を三條橋と訛伝せしなりと。 此説は思ふに細川忠興の夫人は有名なる基督教の信者なれば其の従者當地方に残りて信仰のために相果てしか、先頃此事件を委しく記せし文書ありしも古本屋の手に渡り行方不明となりしは誠に惜しき極なり。 青路の銭塚 堂奥字青路に銭塚あり、普軍用金を埋めし所なりと傳ふも 今膳塚と言へり。と 堂奥の小字堂奥 妙ケ迫 生水ケ迫 岡 一ノ谷 二ノ谷 安ノ堂 荒堀 大井ノ木 旭 中通 鎌谷 由リ道 中河原 家中 奥ノ堂 上路 湯舟 吉田々 水戸口 小迫口 西ケ谷 大平奥 大平 林下 松ノ下 石ケ迫 柳ケ谷 千丈谷 青ジ ナシノキ 原ケ谷 大谷 大谷口 土別 野家 垣ケ坪 中ケ坪 土垣 後ケ迫 堺 大迫 大迫口 オクボ口 北ケ迫 三条橋 西ケ森 小谷 馬場 五丁木 谷口 沢 迫田 天神 竹中 サイカセ 稲谷 稲谷口 稲田 鍋森 小和田 笠神 稲山 上河原 宮ケ谷 八幡 宇呂谷 八王子 姥ケ谷 イタドリガ谷 桧ケ迫 谷ノ奥 東青路 西青路 スケヒ山 堤ケ谷 三条 細迫 上ノ山 札ケ迫 安ノ奥 関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||