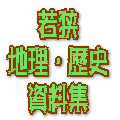 |
犬熊(いのくま)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犬熊の概要《犬熊の概要》 田烏湾に面して位置する。今は国道がよく整備されているが、近年まで当浦の人々は山越をして熊野村へ下り、小浜市街へと出ており、この道が阿納・阿納尻を回るより一里も近く、熊野越といわれていた。産小屋の風習が昭和期まで残っていたことで知られる。 犬熊は、鎌倉期から見える地名。犬熊野・犬熊野浦とも見える。建久6年(1195)12月4日の太政官符に「令吉原安富子孫相伝領掌国富保・同領犬熊野荒浦壱処事」「浦壱処〈字犬熊野〉」などと見える。同書には永万元年国富保の成立後平経盛が国司(仁安元年~嘉応2年)の時「無主荒浦、無人寄住」であったため、開発を目的として国富保内に組み込まれ四至を定めたとある。その開発に当たっては国富保保司「吉原安富」(左大史小槻隆職)の活動があったものと思われる。建久6年国富保の立券荘号に伴い、再び四至を定めた際は「平地荒畠壱町余、浜南北壱町余、東西壱町歟、随則当時依為猪鹿之栖、無居住海人」という状況で、いったん開かれた浦が海民の移動によって再び荒浦となったことがうかがえる。その後国富荘を支配した小槻氏の努力によってか鎌倉期半ば過ぎには再び海民が定住し浦の再開発を進めていたようで、文永2年(1265)11月の若狭国惣田数帳案によれば、建久6年に定めた四至を越えて阿納浦側内へ3反分の水田開発が行われていたことが確認できる。当時の刀禰かと思われる「犬熊野源大夫」の父が阿納浦刀禰重延の父の養子となっていることから、おそらく阿納浦から移り住んだ人々によって再開発が行われたのであろうという。永正12年(1515)6月19日の地頭政所瑞泉田地寄進状には「国富地頭分犬熊野浦」と見え、戦国期半ば頃まで国富荘に組み込まれていたと考えられる。弘治2年(1556)6月22日の明通寺鐘鋳勧進算用状には「百文 井のくま」と見える。 近世の犬熊浦は、江戸期~明治22年の浦名。小浜藩領。「雲浜鑑」によれば、家数14・人数86。 慶長7年(1612)の若狭国浦々漁師船等取調帳によれば、船数は惣船1(1人乗)、個人有6(2人乗3、1人乗3)、惣中で鯖網1張。明治4年小浜県、以降敦賀県、滋賀県を経て、同14年福井県に所属。同22年内外海村の大字となる。 近代の犬熊は、明治22年~現在の大字名。はじめ内外海村、昭和26年からは小浜市の大字。明治24年の幅員は東西1町余・南北1町余、戸数13、人口は男61 ・女50、小船24。 《犬熊の人口・世帯数》 41・13 《犬熊の主な社寺など》  浦の山裾に鎮座。宝治元年の勧請と伝え、鳥居は20年ごとに上棟祭を行うがこの儀式には熊野村の人々も参加していたという。今は石造り。 『内外海誌』 得良神社 所在 小浜市犬熊5号8番地 祭神 得良大神 尚山神社(祭神大山祇命)、合祀。例祭 10月23日 本殿 流レ造6.3坪向拝1.2坪計7.5坪。拝殿 12.3坪。手水舎 0.4坪。鳥居石造一基 境内地 602.73坪(被譲与国有地) 氏子数 13世帯 宝治元年五月の勧請。越前阿蘇村式内利椋明神、と伝える。中頃戸倉御前社と尊称した。犬熊の氏神。 「戸倉御前社 犬熊浦にあり、産神にして五月五日祭礼を行ふ」若狭郡県志。 「右同(註犬熊浦)得良御前神宮 往昔不レ知無跡 永正十二乙亥年当浦之守護神と泰二崇敬一之山其時地頭瑞泉殿倍被二寄附一神と申伝候 開基の袮宜不レ知 今至百六十一年と申候 得良御前袮宜 与右衛門」若州管内社寺由緒記。 附記、鳥居石造一基は元木造のしきたりの為二十年毎(最近昭和32年10月23日)に式年上棟祭を行い、この儀式には国富地区「熊野」の区民が参加して行われる。 『遠敷郡誌』 得良神社 村社にして戸倉御前社とも稱し祭神不詳なれ共同村犬熊浦にあり、産神にして寶治元年五月越前國阿蘇村式内利椋明神を勧請すと傳ふ。 敦賀市の阿曾に式内社・阿蘇村利椋神社(利椋八幡神社)があるが、彼の地と由縁の地と思われる。むこうから移動してきたものか。 『内外海誌』 薬師堂 (名称ハ通称ニシタガウ) 所在 小浜市犬熊13号2番地 本尊 阿弥陀仏 当寺薬師堂ハ永亨元年ノ建立ニシテ 行基菩薩ノ作ト伝ヘル阿弥陀仏ヲ安置ス 往昔ハ無量山海福寺ト称シタル事有ルモ現在の小堂一宇有リ、薬師堂卜通称ス。 管理者 小浜市阿納11号1番地蓮性寺。 「犬熊浦 阿弥陀堂 往昔永亨元巳酉年開基之由申伝候 其時ノ住持不レ知 至二只今一 致二退転一 住持職無二御座一候 今年迄二百四十七年と申候 九月廿三日 犬熊浦 与右ヱ門」若州管内社寺由緒記。 当地には産小屋の風習が昭和期まで残っていた。海岸に近い小川のほとりには産小屋が残されていた。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 犬熊の主な歴史記録犬熊の伝説・民俗別に特に珍しいわけではない、日本各地に最近まで残っていた習俗である。 『西丹波秘境の旅』 立石半島の西浦七郷とよばれる縄間・常宮・沓・手浦・色ケ浜・浦底・立石の七郷と、それに隣接する白木・また常神半島の常神・神子・小川の三村落や内外海半島の外浦の犬熊にも、産屋があった。 『新わかさ探訪』(写真も) *犬熊の産小屋 若狭のふれあい第30号掲載(昭和60年5月21日発行) *若狭の漁村に見られたかつてのお産の風習 犬熊は、内外海半島のつけ根にある小さな漁村です。後ろに山が迫り、昭和40年10月に小浜市街に通じる阿納坂トンネル(旧道)が開通するまで、ここは自動車が走る道の通じていない“陸の孤島”でした。  それまで犬熊の女性たちは、男たちが海でとってきた魚などを天秤棒で担ぎ、阿納坂や熊野坂の細い峠道を越えて売りに行きました。それぞれにお得意さんがあって、その家々を回るわけですが、小浜市街のほか、遠敷や根来、ときには上中(若狭町)の安賀里あたりまで足を伸ばしたそうです。往復20~40㎞にもなる距離を荷を担いで歩いたわけで、「ここらへんの女の人は、みんなそれをしてきた。今から思うと、ようあんな遠いところまで歩いたなあと、我ながら感心する」と植本高子さん(57歳)。「お産が軽くなるからと言われて、大きなおなかで山を越えたこともある」というのは、佐藤きくさん(68歳)。それが「つらかった」という声は聞かれず、「今でも歩くことじゃ、若いもんには負けん」と誇らしげに話されます。とはいっても大変な重労働であったことには違いなく、その顔には、苦労を苦労とも感じないバイタリティーがあふれています。 そうした犬熊の女性の暮らしは、トンネルの開通と自動車の普及で大きく変わりました。今は、ほとんどの家が民宿を営み、お客さんの世話が主婦の仕事になっています。 犬熊のおばあさんたちは、魚売りのほかに二つのことを、みなさん経験しています。一つは、娘時代に京阪神へ女中奉公に出たこと。もう一つは、産小屋で子供を産んだことです。 産小屋(産屋とも)というのは地区共有の建物で、女性は自宅ではなく、そこで子供を庶みました。赤ん坊を取り上げるのは、年配のおばあさんの役目。男児が生まれたときは出産から17日間、女児は18日間、産婦は乳児とともに産小屋で過ごしますが、この期間は家に帰ることを許されず、父親も産小屋に入ることができながったそうです。 「産気づくまで普段通り仕事をして、陣痛が始まると産小屋に行った。赤ん坊の世話をするだけで、何もせずに養生できたし、姑の目もない。みんなが代わる代わる食べ物を持って見舞いにきてくれたから楽しかった」という上亟しずゑさん(62歳)の話に、みなさんうなずきました。産小屋は、お産を不浄なものと見る考え方から長く続いた風習ですが、おかみさんたちは、それをつらいとは感じていなくて、お産の苦しみもなんのその、むしろ、日ごろの重労働からの解放感のほうが強かったようです。 犬熊の産小屋は、使う人がいなくなってからは消防ポンプ小屋として利用され、それも近年建て替えられて、昔の面影はありません。当時は、囲炉裏のある部屋とかまどのついた台所があり、小屋のすぐ下を流れる小川で食器洗いや洗濯をしたそうです。この産小屋は、犬熊だけでなく、かつては若狭の漁村に多く見られましたが、今はそのほとんどが姿を消しています。 (年齢は取材時点) 犬熊の小字一覧犬熊 波洗 阿納脇 阿納谷 田ノ淵 宮ノ谷 宮ノ奥 中山 下駒ケ谷 上駒谷 田ノ頭 高木 高木口 宮ノ前 船場 竹腰 大野 疎路里 森ノ下 坂尻 船原 高平 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||