 京都府福知山市談 京都府福知山市談
 京都府天田郡上豊富村談 京都府天田郡上豊富村談
|
談の概要
《談の概要》
和久川の最上流、豊住谷の最奥に位置する。地内を東西に走る国道429号線(佐治街道)と北へ分岐する府道526号段夜久野線の分岐点附近に集落がある。佐治街道をさらに西へ進めば枝村法用の集落がある。
談村は、江戸期~明治22年の村。「正保郷帳」では豊留村2、357石余のうちに含まれて当村名は見えない。「寛文印知集」は当村名を記す。「元禄郷帳」で豊留、「天保郷帳」では豊富を冠称する。福知山藩領。
明治4年福知山県、豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年上豊富村の大字となる。
談は、明治22年~現在の大字。はじめ上豊富村、昭和24年からは福知山市の大字。
《談の人口・世帯数》 117・58
《主な社寺など》
 氏神は畑中の島田神社 氏神は畑中の島田神社
 臨済宗南禅寺派長安寺末法用山松林寺 臨済宗南禅寺派長安寺末法用山松林寺

法用山松林寺 禅臨済 談村
奥野部村長安寺末寺開基善首座
境内一反一畝廿五歩村除方丈五間ニ三間四尺
庫裡五間三間半 鎮守
十一面観音堂有郡巡礼札十三番札所
(『丹波志』) |
法用山 松林寺 (臨済宗) 同村談
本尊 釈迦如来 脇立 文殊菩薩 普賢菩薩
開山 壽山和尚(長安寺三世)
創建 寛永七年 善公首座禅寺とす(元真言の道場と云)
郡四国十三番、郡新四国第十六番の札所なり。
(『天田郡志資料』) |

『平家物語』の、
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。
当寺はその「沙羅の花」が咲くのだそう、六月末という。
《交通》
 榎峠 榎峠
地内法用の裏から「七曲りの榎峠」を越えると青垣町中佐治・山垣に達する。また一つ北方の梨木峠(車両通行不可、今はクマかタヌキ専用道だそう)を越えれば山垣・遠坂に至る。
以前は不道9号(福知山青垣)線だったが、今は酷道429号線となって倉敷から福知山までの200キロ超の一部である。峠道には、「幅員狭小のため大型車両通行不可」「これより先、幅員狭小3メートル、急カーブ半径6メートル、大型車両通行不可」の大きな立て看板があちこちに立てられている。普通車なら通れる、通行量はまずない。
今は寂しい峠道だが、古来、太平洋側と日本海側を、加古川と由良川を結んだ重要な街道峠で、海路を行くのでなければ、これら本州島中央分水嶺を越えて多くの人物が往来したという。今の道のようなジクザグ道ではなく、古くは屏風の急斜面をまっすぐに登り降りしただろうから、牛馬も往生するようなものであったと思われる。榎峠や穴の裏峠ばかりでなく、古来この分水嶺を越える峠はたくさんあったが今はほとんどが廃道の状態。
《産業》
《姓氏》
足立姓
法用は峠の向こうの古来佐治・遠坂方面と関係が深い。佐治・遠坂は、鎌倉時代にその地方へ派遣されたという足立遠政の子孫を名乗る者が多く、一帯に足立姓が多いが、法用も全戸足立姓である。江戸期以降、佐治・遠坂方面との間に婚姻が多く、言葉も非常に類似しているという。
この足立は今の東京都足立区、武蔵国足立郡の足立である。
『氷上郡志』
山垣 一一六戸 一三○戸
中佐治の北、但馬街道に沿ふ村落にして、更に向山垣、上へ地、下垣内、市山、平地に小分せらる。
此の地は足立氏の発祥地にして、鎌倉の中期より地方に勢力を張れり、足立氏は遠兼の時より武蔵国足立郡領たりしが、曾孫遠政に至りて、佐治郷を恩賞に得て来郡し、爾後、山垣村寓歳山に築城して居る、俗に山垣城と称す、足利尊氏、丹波篠村に義旗を挙ぐるや、郡内の豪族荻野、小島、和田、江田、本庄等と共に其の下風に立つを屑とせず、若狭より別に京都に侵入せんと企てたる者にして、常に南朝に属し、延元元年十二月、後醍醐天皇、吉野御潜行後の諸国宮方蜂起の際にも、本庄等と共に高山寺城に拠り、武家方と奮闘したりしが、足利時代に至りても佐治郷に於ては非常なる勢力を有し、常に南方葦田氏と相拮抗せしが、天正年中、赤井氏の勢力に圧せられ、更に羽柴秀長の侵入によりて勢力を失ふに至れり、遠政の墓は寓歳山の西麓にあり、報恩寺殿仁勇義隆大居士と諡す、今に五輪塔あり、大正十三年、郡内足立の同族相謀り大改修を行へり、其の正統子孫等多く存せるが、庶流として聞ゆる足立堀政利は堀ノ内に住し、足立修理大夫、足立趣後は垣ノ内に住し各、子孫あり、藩政時代に至り織田上野介の領有となり、後に柏原藩と永見氏に分領せらる、村役場、小学校あり。産土神は中佐治と同じく遠阪の熊野神社なるが、明治以前は左記の神社なり。 |
『福知山市史』
承久以前、丹波の国に関東から入部して来た武士に次のような者がいた。武蔵の国足立郡から頼朝に仕えていた足立遠元の孫遠政が、氷上郡佐治荘を承元三年(一二○九)に拝領している『氷上郡志』。氷上郡葛野荘には荻野氏があり、多紀郡の酒井氏が相模の国酒井郷から、何鹿郡物部荘の上原氏が建久四年(一一九三)、信濃の国諏訪郡上原から丹波の国に入部したとされている。天田郡では河口荘に駿河の国牧から牧左衛門が、頼朝の命令で平家方の河口平内左衛門を打つために来たという「牧六人衆」の伝承を伝えている。承久の乱以前から天田郡内に実在した地頭で、史料的に明らかなのは雀部荘の梶原景時の本司跡に補任された飯田清重だけである。).107(足立氏
足立氏も『太平記』に登場し、南北朝時代には丹波の国人として活躍した。その出自をたどれば、『丹波志』には、「足立左衛門尉遠政流一(子)孫上(山)垣村 天正年中迄此所ノ城主也」とし、系図上では、藤原鎌足をその始祖に置き、それより十五代の遠兼以後、武蔵の国足立郡に住し、鎌倉時代に遠元というものが足立郡の地頭職を得て、のち承元三年(一二○九)遠政の時に佐治郷を賜り来住したと伝えている。
話はかわるが、紅葉の名所として知られている桧倉(兵庫県氷上郡青垣町)の高源寺を開創した僧は、遠谿祖雄という。『名僧行録』に「丹波州氷上郡佐治庄瑞岩山高源寺開山遠渓祖雄禅師之行実(中略)師者、丹州氷上郡佐治庄之産也、俗姓藤氏○高源寺略縁起ニハ当郡山垣ノ城主足立光基ノ子也トアリ」といっている。遠谿和尚は足立遠政の子の足立光基の子として弘安九年(一二八六)に生まれ、十三歳で出家、徳治元年(一三○六)に中国に渡り、天目山中峰明本禅師(普応国師)に謁し、仏道修行に勤め、後、帰朝して中峰派の本山高源寺を開き、同派弘通の中心とした。おそらくその初期、高源寺は足立一族の心のよりどころとして大きな存在であったろうと想像できる。福知山にも足立姓は多いが、この足立氏に発するところのものが多くあろうと思われる。 |
談の主な歴史記録
『丹波志』
談村(古豊富村) 法用 上下ノ間三十丁 右同
高五百六石壹斗壹舛三合
此村ヨリ氷上郡佐治村ノ内有河内村ニ越嶺ヲ榎ノ木峠ト云牛馬道同遠坂村ニ越嶺ヲ梨木峠ト云 |
伝説
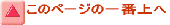
談の小字一覧
談(ダン)
芦ケ谷 赤岶 合田 今井腰 石橋 岩上 大杉 大田 大スヘ 奥法用 カツラ谷 黒石 小法用 境川 下川 関上 談アソ 椿井 寺井 寺谷 峠 長尾 ヒツ巡 古川 細岶 松尾 ムクロジ 湯舟 ユリノ下 杉釜 大杉 奥法用 大スヘ 木ノ丸 黒石 談アソ 寺谷 長野 畑方 深山 太西 松尾 松葉谷 杉釜
関連情報


|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|


