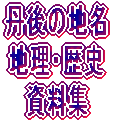 |
友重(ともしげ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友重の概要《友重の概要》 川上谷川の西の山麓に位置する集落。国道312号から分岐する府道町分久美浜線(706号線)を入ったところ。 中世の友重保で、室町期の「丹後国田数帳」に「一 友重保 十町五段九十三歩 氏家遠江守」と見える。「丹後御檀家帳」には「一 ともしげ 家八拾軒斗」と見える。当地には氏家伊勢守・小国若狭守友重の居城であったという氏家伊勢守城址があり、観音寺という寺院跡の観音堂には友重の位牌があったという。地名は彼の名によるもののよう。 友重村は、江戸期~明治22年の村名。はじめ宮津藩領、寛文6年幕府領、同9年宮津藩領、延宝8年幕府領、天和元年宮津藩領、享保2年からは幕府領。明治元年久美浜県、同4年豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年海部村の大字となる。 友重は、明治22年~現在の大字名。はじめ海部村、昭和30年からは久美浜町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 《友重の人口・世帯数》 122・48 《主な社寺など》 式の谷という大きな谷にあり、府道から当社の鳥居が見える。  「室尾山観音寺神名帳」「熊野郡八十四前」 〈 『丹後旧事記』 〈 神伝止裳志気の文字に篭れり神代菊部の里といふ故に神号とす川上麻須郎勧請なり。 『京都府熊野郡誌』 〈 由緒=式内社にして、延喜式には聞部とあり、今聴部神社といふ。明細帳には祭神不詳とあれど、神名帳考証には菊理媛命水分神と記せり。按ずるに社名の起りは祭神菊理媛の約音より起れるものにて、クリのキとなり媛のヘとなりキキベと称するに至れるなり。されば祭神の菊理媛命たるは当然の帰結論にして、蓋し誤なきが如し。而して当社の創立は最も古く、人皇第十代崇神天皇の代の創建にして、丹後一覧記等に言へる如く、川上摩須の勧請に係れる処なりといへり。明治四十五年幣帛神饌料供進神社として指定せられ、益々尊崇の厚きを致せり。 氏子=七十七戸。 境内神社。稲荷神社。祭神=豊宇気毘売神。 城末神社。祭神=不詳。元小字高西谷に鎮座ありしが、明治四十年十二月三日付を以て境内移転の義を認可せられ、現地に奉安す。祭神は城主小国若狭守友重の霊を祀れりと伝ふ。天正十年九月二十六日戦死す。今東岳寺に位牌を存す観音寺殿前若州大守月桂宗視大居士之なり。 『丹後史料叢書』「丹後国式内神社取調書」 〈 【覈】友重村【明細】同上祭神忍穂耳命祭日九月九日【道】所庇同上聞部大明神ト云旧事ニ筑紫聞物部アリ此氏ノ祖ヲ祭レルナラム【豊】同祭日九月九日)(志は丹波志・豊は豊岡県式内神社取調書・考案記は豊岡県式社未定考案記・道は丹後但馬神社道志留倍・式考は丹後国式内神社考・田志は丹後田辺志) 当地の友重は中世以降の地名で古名を菊部の里というそうだが、当地の古代史を秘めた興味引かれる社が残されていた、加悦谷の奥にも菊部神社がある、これらの由緒は「丹後但馬神社道志留倍」の、旧事ニ筑紫聞物部アリ此氏ノ祖ヲ祭レルナラムが正解ではなかろうか。豊前国の企救(きく)郡にいた天日槍一族が当地へやってきたものと思われる。企救郡は今は消滅してないがだいたい福岡県北九州市門司区のあたりになる。関門海峡に突き出した半島を企救半島というし、洞海湾を企救浦とか呼んでいる。 雄略十八年紀に筑紫の聞物部大斧手という人が見える、伊勢の朝日郎が反乱を起こしたのを鎮圧に赴いたのだが、朝日郎の射る矢は超強力で大斧手の楯と二重の鎧を射通して一寸ばかりも肉に食い込んだという。この時代になると聞部の銅製武器は旧式になっていて鉄製鏃にはかなわなかったのかと思われる。同郡内に採銅所という所がある、香春町立採銅所小学校が今もあるが、古来有名な「香春の採銅所」で宇佐八幡の発祥の地とされ、全国の何万とある八幡神社の故地であるが、また現人(あらひと)神社というのもあって都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)を祀っている。だから当社の祭神も敦賀市の角鹿神社と同じで都怒我阿羅斯等(天日槍と同じといわれる)と思われ、当地で銅を作っていたのかも知れない。川上摩須もこの一族なのかも知れないことになる。 境内社の城末(きのすえ)神社は祭神を意布伎城主で天正10年(1582)戦死した小国若狭守友重と伝える。 友重が帰依した観音寺があり、その寺跡である観音堂に彼の位牌を安置してきたが、現在は堂とともに東岳寺に移されているという。観音寺については、永留村延命寺所蔵の大般若経奥書に「応永二十七年子仲秋日修覆建生妙仁尼」とあり、修覆の裏紙に「大般若経勧進友重観音寺」と所々に記しているところから応永年間(1394~1428)に存在したことがわかる。位牌には「天正十年九月二十六日」とあって、意布伎城が落城した年月日がわかる。意布使城跡の山腹に「城主切腹の岩」があったが、大正年間に城末神社の裏手に移したという。  どれがそれなのかわからない。歴史の闇に消えようとしている。 どこかのいかれたムラなら適当にそこらに転がっている石をその石にしてしまうだろうが、そういうムチャクチャはしないでもらいたい。 『京都府熊野郡誌』 〈 本尊=薬師如来。恵心僧都作。 由緒=当山創立の来歴を按するに、字友重には往古観音寺西岳寺の二寺あり応永廿七年修復の大般若教の観音寺勧進たりし事は、延命寺の所蔵経巻奥書により明なる処にして、且つ観音寺は城主小国若狭守の帰依せし処なり。而して元和元年観音寺西岳寺の二宇を合併し、東岳寺を建立して両寺の遺仏を安置せりといふ。爾来大破に及び天宝四年仲秋再建落成せし事は当山棟札により明にして、現精舎は即ち是なり。 境内堂宇。観音堂。本尊=正観音。由緒=本尊は元観音寺の本尊にして、城主小国若狭守の深く尊崇帰依せられし尊像なり。堂宇は享保元年の建立に係る。 庚申堂。本尊=帝釈天釈。 『京都府熊野郡誌』 〈 友重城は大字友重に在り、田数帳に友重保氏家遠江とあり、御品田の部にも氏家遠江とあり、檀家帳には氏家殿一宮殿御一家一城主也とあれば、足利時代に於て氏家の居城たりし事明にして其の後氏家伊勢守此の城に主たりしが、伊勢守は氏家遠江の子孫にして、類代家禄を襲へるものの如し。後小国若狭守の居城となり、天正十年に落城せり。城跡中最も完備せる処にして、そぞろに在城当時の偉観を想像せしむ。友重には元観音寺といへる精舎あり、小国若狭守友重帰依の寺にして、其の寺跡観音堂内に友重の位牌を安置し来りしが、現今堂宇と共に東岳寺に移転せり。戒名あり観音寺殿前若州大守月桂宗視大居士といふ。片書に天正十年九月二十六日とありて落城の年月を詳にするを得、而して城址の山腹に城主切腹の岩ありしが、保存せんが為近年城末神社の裏手に移転せり。 友重座という人形座があったという。 《交通》 《産業》 友重の主な歴史記録『注進丹後国諸荘郷保惣田数帳目録』 熊野郡 〈 『丹後国御檀家帳』 〈 一宮殿御一家一城の主也 是も一城の主也 氏 家 殿 外村三郎左衛門殿 外村殿御内の人 立 野 殿 くるさき与三左衛門殿 御ちうげん 左 衛 門 殿 〆 『丹哥府志』 〈 【瑞雲山東岳寺】(臨済宗) 本尊薬師如来(恵心僧都作) 【聞部神社】(延喜式) 聞部神社今聴部大明神と称す。(祭九月九日) 【氏家伊勢守城墟】 氏家伊勢守又小国若狭守友重の居城なり、前後慥に記したるものあらねど、観音寺といふ寺跡に観音堂あり、其内に友重の位牌あり観音寺殿月桂宗視大居志天正十年九月廿六日卒、天正十年は一色氏断絶して細川氏一国平均の年なり、其より以下此国に如斯ものある事なし、されば氏家伊勢守は其前なるべし、蓋一分村城主氏家大和守の一族ならん。抑小国若狭守友重は足利の臣なり、足利家滅びて後一色氏を手よりて丹後に来る、今木末大明神と祭りて小さき社あり。 友重の小字一覧友重(ともしげ) 才ノ神 林谷 ヒジロ岡 大久保谷 カン音谷 大久保 高居谷 牛谷 堀 六反田 鯨谷 山崎 岡ケ後 若桑高西 曲 梨木 梨ノ木 梨ノ木谷 小清水 宝 大清水谷 大清水 北谷口 北谷 フトウ 笠ノ谷 崩山 小谷 タカラ 中地 上ノ谷 家ノ谷 ドフノ岡 月ノ前 砂原 下絹田 上絹田 平 立総 広総 姫田 森 中コウジ 小姓前 所境 出島 下中地 中ノ谷 蓮池 登リ田 木戸谷 宮ノ谷 敷谷口 高西谷 式ノ谷 横総 カン音寺 公事四維谷 若葉 敷ノ谷 ハヤシ ヒジロヲカ 観音寺 ウシ谷 坂井堺 曲リ 梨木谷 フトウ 桜谷 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『京都府熊野郡誌』 『久美浜町史』 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||