

| 誰が敵だかわからない
福知山20連隊と南京事件 -5- |
昭和12年11月5日上海南方の杭州湾に第10軍が上陸すると、上海防衛の中国軍・約70個師・約40万は南京方向へ総退却をはじめた。これを独断で追撃する中支那方面軍(上海派遣軍と第10軍)の「南京を落とせば敵はまいる」の強い意見に引きずられて中央では12月1日に南京を海軍と協力して攻略するよう下命した。またマスコミも煽りに煽り、全国民はそれを待ち望んだ。これで戦争は終わる、-はずであった。 中支那方面軍のうち6個師団(推定約20万)は南京を直接防御した中国軍約10万を四方から包囲、中国軍は12月12日退却に移り、13日南京は陥落した。バンザイバンザイと全国民は提燈行列で祝った。 南京大虐殺事件や英米の艦船に攻撃を加えたパネー号・レディバード号事件等が起こり列国の非難をうけ、また10月以来進めてきた駐中国ドイツ大使トラウトマンの和平工作も打ち切り、早期決着のもくろみは達することができず、いよいよ日本を先の見えない泥沼の大戦争へと引きずり込んでいくことになった。4億の中国はそうはまいらなかった。不気味な強固な抵抗が続いた。蒋介石をもう相手にしないなどと言い始めた。 暴走し火を付けて廻る現地軍ばかりがワルとは言えない、中央もブレーキをかけずアクセルを踏むこととなった。戦局収拾の可能性を自ら絶ってしまった様子をみて、石射猪太郎は「アキレ果てたる大臣どもである…もう行きつくところまで行って目が覚めるよりほか致し方なし。日本は本当に国難にぶっからねば救われないのであろう」(一二月八日日記)と書く。 こうした日記を読めば政府では外務省の一部の外交官くらいだけが正気だったかも知れない。少し後になるが、杉原千畝の6000人ユダヤ人に対して日本通過のビザを徹夜で発給、おかげで彼はすぐ外務省をクビになったが、後に我国の人道的名誉を高めることになった。 (8)は、 〈 申す迄も無く、首都南京の表玄関たる中山門の占領は、単なる一ケ中隊の占領でも、勿論一将校斥候のものでも無く、其の占領を決定的ならしめた第一、第三大隊の言語に絶する血みどろの死闘と、青木聯隊長代理の御配慮に感激せし、第二大隊の捨身の突進が麗はしくも凝結して成し遂げし偉業であり、其の武運長久を祈り績けら将軍(当時大佐)の率いられし第三十三聯隊は、紫金山の戦斗で感状を受け、又光華門占領の脇坂部隊も感状に浴されしと聞く。例へ聯隊長不在(大野部隊長病中)とは雖も、斯くも赫々たる戦功を樹てつゝ数多く空しく骨を埋めし聯隊格兵の悲運!果たして後世の史家は如何に其の健筆を揮うだろうか! 元来軍の功罪は天の裁ばくもの、人の与へし栄辱は単なる幻想の夢に似て、泡沫の如し。 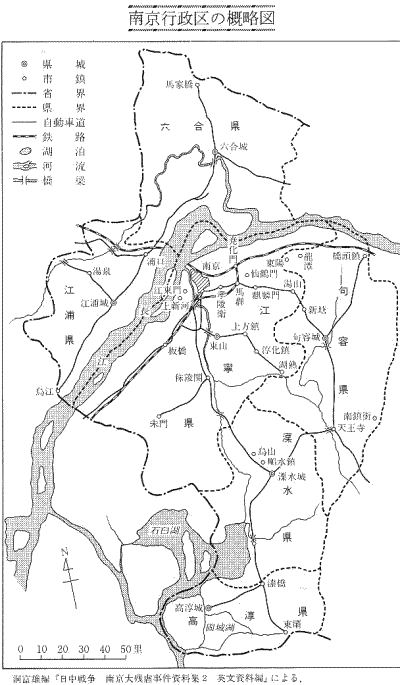 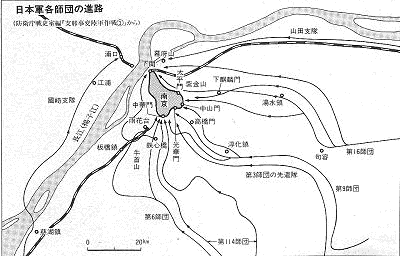 ↑(7)より (1)によれば、 〈 郊外の民衆で、末だ他所へ避難できず、難民区にも入れない者は、昼間は一か所に集まって助け合って身を守っているが、不幸にして日本侵略者にみつかると多くが被害に遭う。背後から撃たれて倒れている者がいたが、逃げる途中で難にあったものである。横臥した形で、刀で突かれて血を流している者は、生きているうちにやられたものである。口や鼻から血を出し、顔面が青くなり、脚が折れているのは、大勢の者から殴られたり、蹴られたりしたものである。婦人で髪が顔にかかり、乳房が割れて胸を刺され、ズボンをつけていない者、これは生前辱めを受けた者である。また、頭をもたげ、目をむき、口を開けて歯をくいしはり、手足を突っ張り、ズボンの破れている者は、乱暴されるのを拒んだものである。惨たるかな、惨たるかな。 毎日夜になると、集団をなして遠方に逃げる。声が聞こえると草叢に隠れたり、田の畦に隠れる。一番危険なのは、夜が明けてから、敵が高所から遠くを見渡すときで、逃げるところを見つかると、すぐ弾丸が飛んでくる。中に婦人がいると、手で止まれと合図して、追ってきて野獣の仕業をなす。言うことを聴かないと殺されるし、言うことを聴いても輪姦されて殺される。立ち止まらずに行こうとする者には、銃声がいっそう激しく浴びせられ、死者がますます増える。それゆえ、農村部の遭難者は都市部より多い。(「南京市崇善堂埋葬隊活動一覧表・付属文書」『中国関係資料編』所収) 「陸軍刑法」(一九〇八年制定)には、「第九章掠奪の罪」に「〔第八六条〕戦地又は帝国軍の占領地において住民の財物を掠奪したる者は一年以上の有期懲役に処す。前項の罪を犯すに当たり婦女を強姦したるときは、無期または七年以上の懲役に処す」とあるそうだが、そうした自分の規律さえ崩壊に至ったアキレ果てたる皇軍の聖戦となっていたが、何もかもが現地軍まかせであった。 同法には掠奪罪はあるが、強姦罪がない、掠奪を伴わない単純強姦ならやり放題という欠陥刑法である、のではなかろうか。 全体の統制がとれてないのだから、比較的規律が生きていて住民は殺さない部隊も少数あれば、そんなものはまるっきりない部隊もあった。中国住民はどれが本当の日本軍の姿か見極められなかった、よい評判を真に受けて対応を誤れば、とんでもない部隊に皆殺しにされることになった。 (2)、16師団9連隊のことのようである。 〈 句容が攻略されて高島部隊[師団]が砲兵学校に司令部をおいたときには、部隊[師団]長の馬でさえも敵の死体を跨いで行かなければならなかった。 こういう追撃戦ではどの部隊でも捕虜の始末に困るのであった。自分たちがこれから必死な戦闘にかかるというのに警備をしながら捕虜を連れて歩くわけには行かない。最も簡単に処置をつける方法は殺すことである。しかし一旦つれて来ると殺すのにも気骨が折れてならない。「捕虜は捕らえたらその場で殺せ」それは特に命令というわけではなかったが、大体そういう方針が上部から示された。 笠原伍長はこういう場合にあって、やはり勇敢にそれを実行した。彼は珠数つなぎにした十三人を片ぱしから順々に斬って行った。 彼等は正規兵の服装をつけていたが跣足であった。焼米を入れた細長い袋を背負い、青い木綿で造った綿入れの長い外套を着ていた。下士官らしく服装もやや整い靴をはいたのが二人あった。 飛行場のはずれにある小川の岸にこの十三人は連れて行かれ並ばれられた。そして笠原は刃こぼれのして斬れなくなった刀を引き抜くや否や第一の男の肩先きを深く斬り下げた。するとあとの十二人は忽ち土に跪いて一斉にわめき涎を垂らして拝みはじめた。殊に下士官らしい二人が一番みじめに慄えあがっていた。しかも笠原は時間をおかずに第二第三番目の兵を斬ってすてた。 そのとき彼は不思議な現象を見た。泣きわめく声が急に止んだのである。残った者はぴたりと平たく土の上に坐り両手を膝にのせ、絶望に蒼ざめた顔をして眼を閉じ顎を垂れて黙然としてしまったのである。それはむしろ立派な態度であった。 こうなると笠原はかえって手の力が鈍る気がした。彼はさらに意地を張って今一人を斬ったが、すぐふり向いて戦友たちに言った。 「あと、誰か斬れ」 さすがに斬る者はなかった。彼等は二十歩ばかり後へさがって銃をかまえ、漸くこの難物を処分した。 〈 句容は、南京外囲防御陣地線の主要な県城であり、東部はトーチカで防備をかため、城内には砲兵学校があった。国民党軍が倪塘村の西の句容に通ずる橋を爆破したため、進行を阻まれた第一六師団所属の歩兵第二〇連隊の部隊はその日、倪塘村に宿営することになった。そこで、村民虐殺事件が発生した。 それまでに成年男子は付近に避難していた。いっぱんに村民の避難の順序は、それまでの中国国内の戦争の経験から、殺害されるか連行される危険のある成年男子がまっさきに遠くへ避難し、つぎに女性と子どもが付近に避難し、殺害されるおそれの少ない老人が家と家畜・作物を守るために残るというパターンをとった。日本軍が倪塘村にきたとき、婦女や老人、子どもはまだ村に残っていたが、侵入してきた日本軍の銃声が聞こえたために、婦女や子どもも夕闇にまざれて逃亡、付近に身を隠した。日本軍は逃げおくれた村民と他所から避難してきていた人など四〇余人を捕まえて、倪安仁という村民の家に押しこめて火をつけ、焼き殺してしまった。翌朝の八時か九時ごろ、日本軍の一部隊が、国民党軍の捕虜もふくめた他村の村民約八〇名を捕縛して句容公路(丹陽-句容道路)沿いに連行し、機関銃で全員殺害した。このとき、溜め池の土手で一人の若い女性が八名の日本兵に輪姦され、その後精神に異常をきたし、まもなくして死亡した。日本軍は村を去る前に村落を放火していったため、村の公共の建物(祠、油絞り場、製粉所)以外、全村八〇余戸は全部焼失した。倪塘村虐殺事件では一二〇余人が殺害されたが、多くが他村の農民で、倪塘村民は七人が犠牲になり、そのうち二人は女性だった(『句容県誌』、「日軍侵占句容期間暴行録」。なお、本多『南京への道』には、目撃者からの聞き取りにもとづいて事件が詳述されている)。 (3)に、 〈 空が白んでくると、部落が見えた。 背のうといわず持物すべてに霜が降りていた。霜は剣のように地面一杯に生えている。 私たちはただちに部落を掃蕩した。五名の男と一人の女がくくられた。五人の男はまず木にしばられ、女は女なるがゆえに解除放免した。この女は、二十六、七歳の色白の男にしがみついてはなれなかった。女は二十二、三歳だと思えた。 彼女は彼の愛人であったのか、愛妻であったのか、男に対して、見るに耐えないほど--いやそれが当然かも知れない、激しい愛着をしめした。だれかが彼女を男から引き離し、彼女だけ逃げ去るようにと指示したが彼女は頑としてきかなかった。彼らの家には、敵の無線機が二台あったのだった。 彼らがスパイ行為をしていたものか、敵兵が彼らの家にいて行為していたものかである。 とにかくかかる物件の存在は、死をもってむくいられるのだ。この男は、ただ一語の日本語を知っていた。 「アリガトウ」この一語である。 彼は「アリガトウ」という言葉が、さながら「許して下さい」という意味であると思っているのか、殺すぞといっても、この女は貴様の妻かといっても、この部落の敵はいつ逃げたのか、貴様はスパイしていたのかといっても、ただ「アリガトウ」と日本語で答えた。 我々は、ついには、彼がそのような意志でいってるのではないけれど、小馬鹿にされているような感じを抱いて、腹立たしく思えた。 木にしばられた男は、突き刺されたり、斬られたり、射殺されたりした。我々は、この青年と女に興味を持ったので殺すのを最後にした。 「女を男から引き離せ」と中隊長がいった。 一人の兵士が、彼女の腕をもぎとるようにひっぱって、ようやく引き離すと、他の一人が「エイ」と男の胸を突いた。 「アゝゝ」と女は叫ぶと、狂気のように走り寄って男をかき抱いて泣いた。彼女の声は血を吐くように号泣した。劇的なシーンである。やがて男の胸のうちへふかぶかとうずめていた涙の顔を振り向けた彼女は、決然として我々を見張った。あらんかぎりの憎悪をたたえて。 彼女は己が指で、彼女の下で刻々に血を流し呼吸をかすらせ、命を失いつつある男に対する絶対の愛と、我々に対する極度な憎悪のうず巻く己が胸を指示した。 彼女は「刺せ」といっている。いやもっと激しく……命じている。一人の女は、今や将軍のように大きな威厳をもって我々に命令している。 「刺せ!」と。 「エイ!」彼女は「ウゝゝ」と唸って愛人の胸の上へ愛人をかばうように重なった。殉死だ。愛の殉死だ。 彼女のふくよかな胸から流れる赤い愛と憎悪の血は、死んでも彼をかばうように、彼の体の上をはって流れた。 この悲劇はたしかに我々の胸を打った。 「支那にもえらい女がいる」と我々はささやいたのである。 愛は死よりも強しかー。 それからただちに部落に火を放ってつぎの部落へ出発した。 放火するーということは、このごろの我々には何でもないことであって、子供が火遊びするよりも、面白がってやるのである。 「オイ、今日は寒いね」 「じゃ、一軒炎やしてあたろうか」 これが今日の私たちなのだ。私たちは殺人鬼であり放火魔である。 (20)に、 〈 (4月)六日--国際救済委員会は救済事業を推進している。二〇〇人の男性が紅卍字会の死体埋葬作業に雇われている。とくに農村地域においてはまだ死体が埋葬されないままになっている。 (4月)一五日--紅卍字会の本部を訪ねると、彼らは以下のデータを私にくれた--彼らが死体を棺に入れて埋葬できるようになったときから、すなわち一月の中旬ごろから四月一四日まで、紅卍字会は城内において一七九三体の死体を埋葬した。そのうち約八〇パーセントは民間人であった。城外ではこの時期に三万九五八九体の男性、女性、子どもの死体を埋葬した。そのうち約二五パーセントは民間人であった。これらの死体埋葬数には私たちがきわめてむごい殺害があったことを知っている下関、三叉河の地域は含まれていない。 (4月)二二日--金陵大学の馬文煥〔音訳〕博士が訪ねてきた。彼と彼の家族は、およそ五カ月にわたって農村地域で避難生活を送ったが、強姦、殺害、放火、掠奪が同地ですべておこなわれた。くわえて地方の警官が逃げたあとでは匪賊に苦しめられるという辛い、悲痛な体験をした。〔中略〕彼は、長江河岸にそって膨大な数の死体が埋葬されない恐ろしい状態で現在も放置されたままであり、いまでも多くの死体が長江を漂って流れていると、確証にもとづく話をした。 南京城内外で死体の埋葬をした団体はほかにもあるようだが、紅卍字会とは、同書によれば、 〈 我が軍のこととはいえ、あまりにむごく、我が軍に対する憎悪の念で一杯になられるのではなかろうか。これらがもし本当なら日本人であることが嫌なる、などと思われるかも知れない。罪もない者を殺して何のための戦争なんだ、正義は我が軍にあるのか、どこかの国々の「対テロ戦争」と同性格のものではないか、自分の国を侵略されれば誰だった抵抗するだろう、オマエラはそんなことはないから理解できないのだろうが…。莫大な国費を使い莫大な人命を犠牲にしてそれに釣り合うだけの戦争なのか、庶民の生活は苦しくなるばかりではないか。 やっていることの実態が知られることを我国は極度に恐れた、こうしたことは隠し続けてきたのであった。今もあるどこかの国々と同じであった。 懸命に隠してもそんなことはそのうちに知れ渡る、ムダな努力であるが、国民には隠して隠して来たが隠していても全世界にはすでに知れ渡っていることであった。先のパナイ号やレディー・バード号事件だけでなく、「誤爆」「誤射」事件をわざと起こして外国人の目を追っ払おうとした。これはさすがどこかの「対テロ戦争」中の国でもしないが、あの連中ではしないこともなかったかも知れないが、それがかえって世界の目を南京に集めた。 生き残った中国人の証言は信用ならないとし、日本兵の証言はセンノーといって消そうとする。これもさすがどこかの「対テロ戦争」中の国でもしないようだ。隠せば隠すほど立場は悪くなろう、「優秀民族の大和民族」が「劣等民族の支那人」に対して行った誠に不名誉な戦争であったことがかえって顕れてくる。 世界が、中国が、言うような大虐殺事件はなかったというなら、その自称の優秀ぶりを、この機会によく知って貰えばいいではないか。何を隠すのか。中国にはシベリアなどと大違いでこんな立派な捕虜収容所があり、自軍の兵隊のメシすらも持たなかったのですが、十万を越えたの中国人捕虜には温かい食事で厚遇しました、貧弱な食事しかくれなかったロスケとは大違いです。捕虜は殺してないと言うならば、もしや一つでも捕虜収容所があったのならばそれを示してぜひ国民を納得させて貰いたいと願う。 日本は祖国を守るために、こんなに立派な戦争をしました、日本人の誇りです。そうしてから、ロマンチックだなぁ、ノスタルジックだなぁ、アートだなぁ、カルチャーだなぁ、ふるさとの大きな誇りです。貴重な文化財です。と、ノーテンキで歴史知らずで世界知らずのどこかの町のように大宣伝でもすればよろしかろう… 被害ばかりを言って加害は忘れる手前勝手な信用できない国民、周囲の国々からそう思われたくはないので、ぜひやってくれないだろうか。 根拠が示せないのに、ええかげんな話をしてはならないだろう。  ↑(1)より、キャプションに「日本兵の荷物を運ぶ中国人。当時、日本兵に協力する民衆などと伝えられたが、実は徴用されたものであった。毎日新聞提供」とある。 兵站のない部隊の進軍。中国人は何も喜んで「協力」しているのではない。協力を拒めば射殺だから、こんなことをしているだけ。スキを見て逃げても射殺された。 プレスのこうした作られた写真も多い、特派員などはハイ笑って、などと注文を付けて写真を写している(20)。うっかり笑わないと銃殺かも知れず、ムリに笑顔を作っているものもある。 (24)に、 〈 〈 本当はAP特派員らしいが、これを清野作戦と呼んでいた。注釈に、 〈 反攻したりすれば反逆者で、たちまち銃殺であった。真冬だから彼等周辺住民は住むところが焼かれれば、城内に逃げるより道はなかった。 またこのため、厳冬期に食糧すら持たない攻略軍も南京城外に留まることができず城内に入る、17日の段階では7万の攻略軍が入った。憲兵は17人しかいなかった、7万人の食糧、防寒、露営のための掠奪放火を防ぎ、攻略軍はすべて餓死せよと言えただろうか。  ↑(7)より 〈 日本兵とあるのも、小林部隊とあるのも、福知山20連隊のことである。 南京城はもうそこであった。 (3)より 〈 … 外は小春日和。いたるところに敵兵の死体が転がっている。 敵は、よほど狼狽して逃げたらしく、幾千という弾薬が封も切らずに放置されていた。 中山門へ面した方向には、幾重にも張りめぐらされた鉄条網が朝日に光っている。足元に、まだ息のある敵兵を見つけた。銃を持ち直し、とどめを刺そうと構えた。 すると、彼はかすかに目を開き、ぜいぜい鳴る息の下で何かつぶやき、重たげに手をあげた。 私は殺すのを待った。 彼は懐中から小さな手帳を出し、震える手で万年筆をにぎった。懸命に何かを書きつけている。それを私にさし出した。 そこには五文字の漢字が書いてあるのだが、判読できなかった。 彼は最後の渾身の力をふりしぼって、五文字を書くのがやっとであった。書き終えたとき、かすかな笑みが表情に浮かんだ。 これは何だろう。本当は何と書いてあるのか。手紙か、それとも遺言だろうか。 彼の顔には、すでに死相が出ていた。しかし、夢見るような微笑を浮かべていた。 私は急に、この男をいとおしく感じていた。 刺殺をためらっている様子を見て大嶋一等兵が「東さん、殺そうか」と聞いた。 「さあ……」--私はあいまいに答えた。 「どうせ死ぬんだから殺そう」と大嶋は剣をかまえた。 「待て。突かずに射ってやれ」 銃声が響き、男はもう動かなかった。 後方の塹壕のなかには、白粉のビンや紅いハンカチ、女物の靴などが散乱していた。娘子軍がいた壕だったのだろう。全員逃げ出せたのか、死体はなかった。 朝日のなかを我々は身も心も軽く、四方城通りの舗装路を歩いていた。 高い城壁と堀が現われた。橋は破壊され、人一人がやっと渡れる。中央に三つの大きな門があった。 夢にまで見た、あこがれの門だ。突撃する何人もの戦友が傷つき、死んだ門でもある。 「大野部隊、十三日午前三時十分占領」 おゝ、大野部隊の一番乗りだったのか。 新聞記者が、しきりと写真をとっていた。 どの部隊の兵士の顔も明るく、髭づらが笑っている。 南京市街は、ほとんど破壊されていなかった。どの家も表戸を堅く閉ざし、住民はほとんど歩いていない。 私たちは口笛を吹きながら歩いた。  ↑(8)より。「戦友に抱かれて遺骨の南京入城(第八中隊)」とある。 日本軍は昼頃に城内に入ったようだが、トラブル防止のため選抜された精鋭だけを入れる予定が全軍が入ってしまったという。そしてまずはこれら投降兵全員の「殺処分」に当たったのであった。ようやく命からがら南京に到着できた兵たちはメシもヤドも後回しで「捕虜の処置」あたらねばならなかった。 それは師団長や旅団長日記などいままで引いてきた通りである。凄まじい限りの今では信じられないような大規模で残忍な「南京大虐殺」とは普通はこれらを呼んでいる、虐殺はもっともっと長い広い範囲で行われたのだが、一応狭い意味の南京大虐殺としておくが、これらについては日本側だけでもたくさんの証言があるので信じられない方々はじっくりと目を通していただきたい。実際の被害者・南京人や外国人の目から見たものはさらにさらに多く、隠すことなどはユメできない事件である。 福知山20連隊の場合は、(3)に、 〈 〈 夕碁が足元に広がり、やがて夜の幕が下がり、すっかり暗くなって星がまたたいても歩いていた。 三、四里も歩いたと思われる頃、無数の煙草の火が明滅し、蛙のような喧噪をきいた。約七千人の捕虜が畑の中に武装を解除されて坐っている。 彼らの将校は、彼ら部下を捨て、とっくに逃亡してしまい、わずかに軍医大尉が一人残っているだけである。彼らが坐っている畑は道路より低かったので、一望に見渡すことができた。 枯枝に結びつけた二本の、夜風にはためく白旗をとり巻いた七千の捕虜は壮観な眺めである。 あり合せの白布をあり合せの木枝に結びつけて、降参するために堂々と前進して来たのであろう様を想像すると、おかしくもあり哀れでもある。 よくもまあ、二個聯隊以上もの兵力を有しながら何らの抵抗もなさず捕虜になったものだとも思い、これだけの兵力には相当な数の将校がいたに違いないが、一名も残らずうまうまと逃げたものだと感心させられる。我々には二個中隊いたが、もし七千の彼らが素手であるとはいえ、決死一番反乱したら二個中隊位の兵力は完全に全滅させられたであろう。 我々は白旗を先頭に四列縦隊に彼らを並べ、ところどころに私たちが並行して前進を開始した。 綿入れの水色の軍服に綿入れ水色の外套を着、水色の帽子をかぶった者、フトンを背負っている者、頭からすっぽり毛布をかぶっている者、アンペラを持っている者、軍服をぬぎ捨て普通人に着がえしている者、帽子をかぶっている者、かぶらない者、十二、三の少年兵から四十歳前後の老兵、中折帽子をかぶって軍服を着ている者、煙草を分けてのむ者もあれば、一人で誰にもやらないでのむ者もあ り、ぞろぞろと蟻のはうように歩き、浮浪者の群のような無知そのものの表情の彼ら。 規律もなく秩序もなく無知な緬羊の群は間から闇へこそこそとささやきつつ、歩いていく。 この一群の獣が、昨日まで我々に発砲し我々を悩ませていた敵とは思えない。これが敵兵だと信ずることはどうしてもできないようだ。 この無知な奴隷たちを相手に死を期して奮戦したかと思うと全く馬鹿らしくなってくる。しかも彼らの中には十二、三歳の少年さえ交っているではないか。 彼らはしきりにかわきを訴えたので、仕方なく私は水筒の水をあたえた。これは一面彼らが哀れにも思えたからである。休憩になると、彼らは再三こうたずねた。 「ウォデー、スラスラマ(私は殺されるのか)」 彼らにとってもっとも重大なことは、今後いかに処置されるかである。彼らはそれが不安でならないといった顔付きである。私は、顔を横に振って、この哀れな綿羊に安心を与えた。 夜が深まるにつれて冷えびえとした寒気が増した。 下キリン村のとある大きな家屋に到着し、彼らを全部この中へ入れた。彼らはこの家の中が殺りく場ででもあるかのように入ることをためらっていたが仕方なくぞろぞろと入っていった。戦友のある者は、門を入っていく彼らから、毛布やフトンをむしりとろうとし、とられまいと頑張る捕虜と争っていた。 捕虜の収容を終わった私たちは、コンクリートの柱と床だけ焼け残った家に、宿営することになった。 翌朝私たちは郡馬鎮の警備を命ぜられた。私たちが郡馬鎮の警備についている間に捕虜たちは各中隊へ二、三百人ずつあて、割りあてられて殺されたという。 彼らの中にいた唯一の将校軍医は、支那軍の糧秣隠匿所を知っているからそれで養ってくれと言ったとか。 なぜこの多数の捕虜が殺されたのか、私たちにはわからない。しかし何となく非人道的であり、悲惨なことに思えてならない。私には何となく割り切れない不当なことのように思える。七千の生命が一度に消えさせられたということは信じられないような事実である。 戦場では、命なんていうものは、全く一握りの飯よりも価値がないようだ。 私たちの生命は、戦争という巨大なほうきにはき捨てられていく何でもないものなのだ-と思うと、戦争にはげしい憎悪を感じる。 20連隊の匿名少尉の日記。(4)に 〈 将校斥候として中山門附近の敵情偵察に赴く帰途地雷にかかる。貴重なる生命を犠牲にせしこと申訳なし 五時二十分なり 何の悪日ぞ、而し此の日南京へナダレを打って入城せし日なり、恨みは探し南京。十三日の日又なく、自分は微傷だにせぬが尚恨めし (以下地雷爆発による戦死者四名、戦傷者三名火葬残置兵五名の氏名が記されているが、省略)。 四遺骨と共に夜を共にす(このあと、現場見取図とメモあり、省略)。 十二月十四日 野戦銃(重)砲の掩護にゆく 投降者二百余名死刑に処す 一匹 余自ら一刀両断、 手ごたえ小気味よし血を吸うた業物の切れ味格別なり白旗を翻えすもの次第に多く続々投降す、其の数二千以上、一万」。 20連隊と伏見9連隊は中山門側から南京に近づくが、38連隊と33連隊は佐々木支隊と呼ばれて南京城外を北回りして長江に開いた南京の港・ 16師団38連隊(奈良)は、(24)に、 〈 連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して、彼我入り乱れて混戦していた頃、師団副官の声で、師団命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」と電話で伝えられた。私は、これはとんでもないことだと、大きなショックをうけた。……参謀長以下参謀にも幾度か意見具申しましたが、採用するところとならず、その責任は私にもあると存じます。部隊としては実に驚き、困却しましたが命令やむを得ず、各大隊に下達しましたが、各大隊からは、その後何ひとつ報告はありませんでした。激戦の最中ですからご想像いただけるでしょう(畝本正巳「証言による『南京戦史』(5)」)。 16師団33連隊(津)は、(24)に、 〈 20連隊は13日は城内に宿営して、城内の「残敵掃討」に入るのは14日からのようである。福知山20連隊第4大隊上等兵。 (4)に、 〈 「それが……南京の残虐事件のことは……わしも……思い出すまいとしとっても……忘れられん。おっそろしゅうて……人様の前では……とても話なんか……でけんことや」。 早口で一語を口にしては、短い沈黙が断続する。増田六助氏の南京大虐殺の回想は、重い石うすをごろりと回しては手を休めるように、つかえ、つかえしながらはじまった。 「いかに……上官の命とはいえ……むごいことをしたもんだと……わしの罪を中国の人たちに……ざんげ((懺悔)する気持ちでいます」。 「これが……当時わしの付けとった陣中日誌です」。 「十二月十四日掃討 外国租界ニ入リ避難民中ニ混リテ居ル敗残兵ノ掃討ス第四中隊ノミニテモ五百人ヲ下ラス 玄武門側ニテ銃殺セリ各隊ニテモ又同シト云ウ」。 「銃殺……というか、あれは罪もない人間を引っくくって皆殺しに……中にはまだ生きとったものもいたと思うが……とにかく重機二挺、軽機六挺、計八挺でもって、じゅずつなぎにして押し集めた五百人あまりに……号令一下、いっせい射撃をして……百メートルやったか、いや…‥五十メートルも近かったやろうか……至近距離から射ったら……脳ミソがとび散るんです。中国人の頭半分ぐらいが、パッと吹っとんでしまう……わしは五十メートルぐらい離れたところで、処刑現場の警備にあたっとった……脳ミソや肉片が、飛び散るのが……見えた」。 「射たれたあと……まだ体の動いているのもいた……そんなものに構っとられんので、死体の山に土を掛けて、次の行動に移ったが……あとはどうなったか」。 「殺されたのは、中国兵の捕虜ばかりでしたか」私はたずねた。 「いや……半分以上は一般の市民やった」。 (1)『南京事件』(笠原十九司・岩波新書・1997) (2)『生きている兵隊』(石川達三・中公文庫・1999) (3)『わが南京プラトーン』(東史郎・青木書店・1987) (4)『隠された連隊史』(下里正樹・青木書店・1987) (5)『続・隠された連隊史』(下里正樹・青木書店・1988) (6)『中国の旅』(本多勝一・朝日文庫・1981) (7)『南京への道』(本多勝一・朝日文庫・1989) (8)『福知山連隊史』(編纂委員会・昭和50) (9)『舞鶴地方引揚援護局史』(厚生省・昭和36) (10)『京都の戦争遺跡をめぐる』(戦争展実行委・1991) (11)『なぜ加害を語るのか』(熊谷伸一郎・岩波ブックレット) (12)『新版南京大虐殺』(藤原彰・岩波ブックレット) (13)『完全版 三光』(中帰連・晩聲社・1984) (14)『蘆溝橋事件』(江口圭一・岩波ブックレット) (15)『語りつぐ京都の戦争と平和』(戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会・つむぎ出版・2010) (16)『言葉の力』(ヴァィツゼッカー・岩波書店・2009) (17)『土と兵隊・麦と兵隊』(火野葦平・新潮文庫) (18)『満州事変から日中戦争へ』(加藤陽子・岩波新書) (19)『国防婦人会』(藤井忠俊・岩波新書・1985) (20)『南京事件の日々』(ミニー・ヴォーリトン・大月書店・1999) (21)『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』(小野賢二他・大月書店・1996) (22)『銃後の社会史』(一ノ瀬俊也・吉川弘文館・2005) (23)『草の根のファシズム』(吉見義明・東大出版部・1987) (24)『天皇の軍隊と南京事件』(吉田裕・青木書店・1986) |
(2) (3) (4) (5)このページ (6) (7) 資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2011 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||