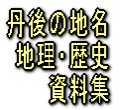 |
浜(はま)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜の地誌《浜の概要》 浜は舞鶴市の中央部。東舞鶴の市街地である。 東舞鶴駅から海までの全域がほぼこれにあたる。舞鶴市役所・京都府地方振興局など官庁がある。 《人口》10404《世帯数》4293(これは新舞鶴地域の合計) 《主な社寺など》 『加佐郡誌』 〈 『丹哥府志』 〈 『丹後国加佐郡寺社町在旧起』 〈 〈 《交通》 東舞鶴駅 国道27号線 汐路通り 《産業》 浜の主な歴史記録《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 得月庵余部雲門寺末寺なり。昔三島外記この村山城に住せり一説には桜井佐吉とも云う 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 浜村 高五百七拾六石二斗二升八合 内二拾二石三斗六升九合六勺 万定引 三拾石御用捨高 古城 三島外記 桜井左京 稲荷社 恵比須堂 水無月明神 六月晦日祭 得月庵 雲門寺末 愛宕 戊亥の方にあり 昔西村何某の男古城の跡に遊ヒ俄に物狂ひ飛廻り口はしり云事無舌不通 折節松尾大門坊大峯の出掛当村を通る 是を頼みて祈るに童子の舌和き明かに詞も聞へ語りていわく我ハ此杉山の神なり祭る人の為に可為守護となり 仍而草社を営み祭此童後に山伏となり延寿院被移る 杉山祭 七月廿三日日尽シ 八月廿四日護摩供 香花勧行 延寿院ヨリ執行 《丹哥府志》 〈 【水無月明神】(祭六月晦日) 【波照山得月庵】(臨済宗) 【三島内記城墟】 【猩々の頭】 浜村は元森村の浜村なり。よつて産土は森村の大森大明神なり、其祭礼の道具一切龍宮より納ると語り伝へて浜村に伝はる。浜村の磯に島あり、祭の前夜其島に往きて例年の通り祭の道具借用せんと請ふ翌朝迄に其用ゆる所の道具一切備りぬ、これを用ひて又元の如く揃へて其島に返す事を年々如此仕来るなり、一年雨にぬるるよつて是を干す。以是一日遅延に及ぶ、是歳より取りに来らず遂に此村に伝はるといふ。深く秘蔵して祭礼には新たに道具を造り其品は用ひずといふ。斯様の事は怪しき事なれども吾山陰にては往々此類の事多し、近年も谷の中より膳椀の類を取り出す事あり、皆狐狸の所為なりと聞く。其道具の中に猩々の頭といふものあり、頭の所に皮を剥ぎて毛の長サ二尺余り其色紅の如し、又其家に八百比丘尼の縫ひたる幕あり。 【付録】(稲荷大明神、愛宕権現、桜井佐吉城墟) ○矢之助村(浜村の枝郷、若狭街道) 《加佐郡誌》 〈 浜の小字浜 波崎 半田 長溝 鍵田 シメン山 フケ 口波崎 塚穴 奥波崎 浜 片山 石ケ坪 五久 干場 穴田 敷田 観音堂 田井中 橋詰 中川原 壱本松 下深田 諸畔 古屋敷 六島 森尻 白糸 東江 関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
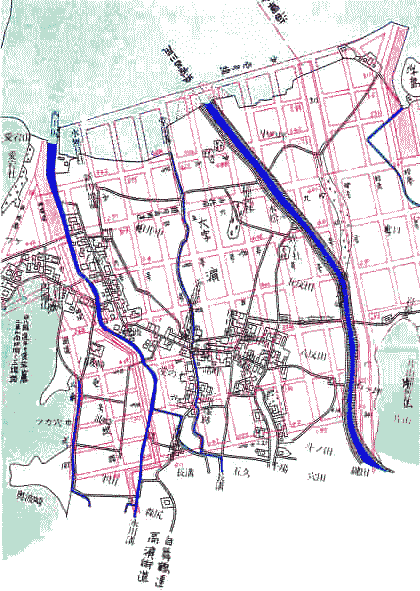 市街地が作られるまでの浜村 『得月寺と浜村』より |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||