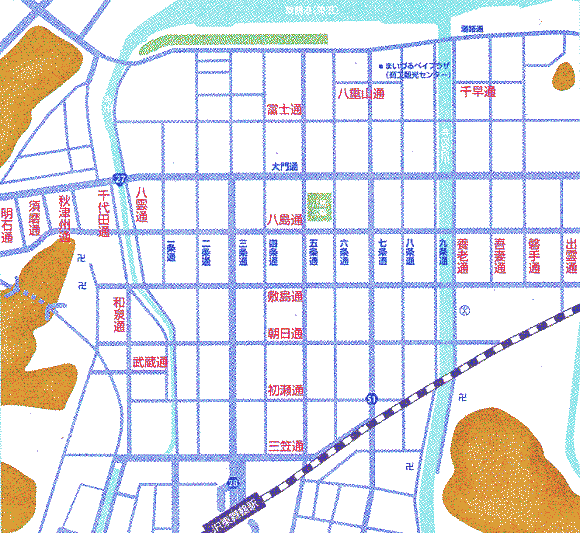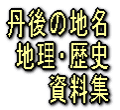 |
�C�R�鉺����
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![���ߒ���{(�]����)](../../maitin2.gif) �����ߒ���{(���ߎs�E��������)�@����34�N(1901)10���ɊJ���B���{��4�Ԗڂ̌R�`�Ƃ��Ē���{�E�C�R�H���Ȃǂ̌R�W�̒����{�݂��u����A�R�`�s�s���߂Ƃ��Ă̊�b��z�����B(�w�ڂŌ��镑�߁E�{�ÁE�O���100�N�x���B�L���v�V������) 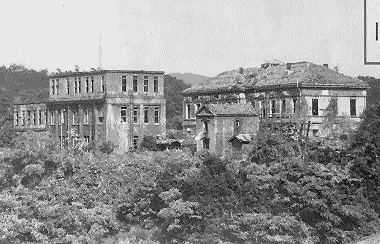 �������ߒ���{�i�ߕ��̌����@�����R�S�N�P�O���P�����ߒ���{���J�����A���{�ő�S�Ԗڂ̌R�`�����������B�������{�i�ߒ����͓��������Y�����ł������B�i�ߕ��̌����́A���݂̒����ߗX�ǖk���̎R�̏�ɂ���A�R�`��C�R�̏��{�݂����n�����Ƃ��ł����B����E����́A���a�Q�V�N�U���܂ŘA���R�ɐڎ�����Ă����B���̌�A�����������ߏo�����̊Ǘ����Ɉڂ������A�������V�������Ċ댯�ɂȂ����̂œ��R�X�N�P�P���ɉ�̂��ꂽ�B(�w�ӂ邳�ƍ��̎ʐ^�W�x���B�L���v�V������) �ꏊ�͒����ߗX�ǂ̔w��̉��̏�ł������B �����݂̗l�q�B  ��Ղ̖�����{�̂��G���A���̒����߂͂��Ƃ��A���̓����ɘA�Ȃ铌���߂̎s�X�n����������Ă������B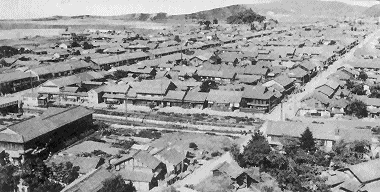 ���V���ߑS�i(���ߎs�E���a����)�@���ߒ���{�J�݈Ȍ�A�R�`�s�s�Ƃ��Ĕ��W���݂镑�߁B�s�X�n���L���铌���߂̑S�i�B(�w�ڂŌ��镑�߁E�{�ÁE�O���100�N�x���B�L���v�V������) ����S�i�ł͂Ȃ��A�������ʂ��ĂȂ����A�l�ʎR���瓌�����ʂ������̂Ǝv����B �����Ñ�̃~���R��f�i������ꂽ��͂��܂��H �����ʒu���炱���̌��݂̎p���ʂ������ƍl���Ă��邪���ɂȂ邱�Ƃ��c ���Ԃ�F����̒��̕��������ł��傤���A�������ł͂���܂����A���J�Ɉ��ɖ����t�����Ă���A���j�ɋ����̂�����ɂ́A����ȂЂ����肪���������B ���邢�͋��̓s�̃}�l�����A�c�Ɏ҂̋��̓s�R���v���b�N�X�����B���������̓s�͏��Ə��̊Ԃ������Ԃ�ƍL���āA�P�O�{�ȏ������A���̊Ԃɂ͉��{���ʂ肪����B�����͂T�O���[�g���u���Ď��̏��ɂȂ�B�c�Ɏ҂͍��������قǂɃ��x���̊i���ɂ��ǂ낫�J���`���[�E�V���b�N����B�䂪���݂͂��߂������B���܂Œm��Ȃ������B�����p��������������Ȃ������݂��߁B ����ȃJ���`���[�E�V���b�N���邱�Ƃ��ڂ��o�߂邱�Ƃ��Ȃ������h�K���Ȃǂ����傤���Ȃ��h�c�Ɏ҂��u�k�s�̗Y�v�ȂǂƑ�����ꂻ���Ȃ��ƂC�Ō����̂��낤���B �@�@�@ 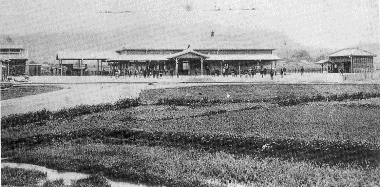 ���V���߉w(���ߎs�E�������N)�@���ߌR�`�ւ̓S���~�݂̂��߁A����37�N(1904)�ɕ��m�R�`�V���ߊԂ����ԕ��ߐ����J�݂��ꂽ�B���݂̓����߉w�B  ���O��ʂ�(���ߎs�E�吳12�N)�@�O��ʂ蔪������C�ݕ����Ɍ������ĎB��ꂽ�ʐ^�B�V���߉w�̊J�݂ƂƂ��ɏ��X�X�ɔ��W���Ă����B  ���V���߉w�O(���ߎs�E�吳���N)�@�w�O�čs�i���镗�i�B  �����a�����̎O��ʂ�(���s�{���ߎs�l�����ʂ�(���ߎs�E���a����)�@�ʂ����������l�тƁA�ʂ�̗����ɕ��ԏ��X�����킢������������B �������(�w�ڂŌ��镑�߁E�{�ÁE�O���100�N�x���B�L���v�V������) ���N�ɂ��S���͐�������Ă����A�얞�F�̓��V�A�����݂��Ă������L�O�������B �����푈�̂���́A�S�����Ȃ��A�����͕����������ł���B�[�����W�̕����掵�����́A����։�܂�160�L���𗤍s����Ƃ̗��c���߂���́A�k�������𑖂��Ă��C���ɂȂ�قǂ̋����ł��邪�A��������4�`5�������ĕ������A�w�X��5�іځA����ɓS�C��e�ۂ����Ăł���A�������������ŁA���˕a����1259���A����6���B�S�����Ȃ���ΐ푈�͂ł��Ȃ��B�������h����̃A�W�A�����͓S���Ȃǂ͂Ȃ��A�����Ƃ������炢������A�L��ȃA�W�A�̒n������ĕ����ĕ����s�������B���̈��g����ǂ��瓌���߉w�܂ŕ�������ł����A��ς������ł��傤�ˁA�ȂǂƂ������������������A���ꂭ�炢�̋����͖��łȂ��B 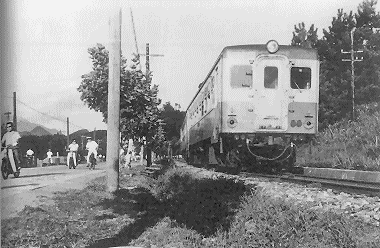 ���S���������@���ߐ����J�ʂ����̂́A�����O�\���N�ł���B�����ɁA�u�V���߂Ɨ]���v�u���߂ƊC���߁v�����Ԉ��������J�ʁB�܂��A�吳�\�O�N�ɂ́A�V���߂Ɠ��`�̊C�݂����Ԉ��������J�ʂ����B �C�R��p�̒����ߐ��@�V���߂Ɨ]���Ԃ̈������i�����ߐ��j�́A�����A�V���߉w�i���E�����߉w�j�ƊC�R�{�݂����Ԑ�p�H���Ƃ��ĕ~�݂��ꂽ���̂ŁA�R�`�������Ƃ���ꂽ�B�������A�吳�S�N�ɌR�`����̈�ʒʍs���A�������𗘗p���邱�ƂɌ��肳�ꂽ���Ƃ���A�l���̗A���ɂ�����B�吳�W�N�ɓS���ȂɈڊǂ���A����w�ƒ����߉w���ݒu���ꂽ�B���́A�o�X�⎩�Ɨp�Ԃ̕��y�ŁA���p�҂͌����B���a�S�V�N�ɔp�~����A���]�Ԃƕ��s�҂̐�p���ɐ��܂�ς�����B(�w�ӂ邳�ƍ��̎ʐ^�W�x���A�L���v�V������) ���V�A�́A 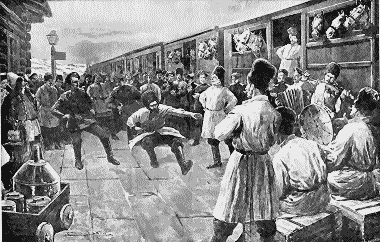 ���V�x���A�S���A���r���̈ꕗ�i�u�O���t�B�b�N�v���ځ@��Ԏ��Ԓ��v���b�g�t�H�[����ł̃��N���G�[�V����(�w���ߑ�S�N�j3�x���A�L���v�V������) �є�̖X�q�̓��V�A���E�t�@�[�n�b�g�Ƃ������A���̘V�t�͍�渂̃t�@�[�����Ă���ꂽ�B��渃t�@�[�̓��V�A�ł��c���������Ȃ��������́A�����т��͂������Ēn���o�Ă��܂��A������O�̂��̂Ȃ炩�����Ȃ����F�̍�渃t�@�[���������A�̂��T���ƊԈ���āA����ȕ����v���[���g���ꂽ�Ƃ����b�ł������B-40���̐��E�ł͂���i�V�ł͉߂����Ȃ��B�A�~�_�ɔ�����炠���܂���A��������Ƃ��f�R�܂Ŕ���Ă��Ȃ��ƁA�O���t����u�ɓ�����Ă��܂��܂��A�����͐l�Ԃ̗����̍��ł�����A��������x����Ƃ������ւ͖߂��܂���A�g�����ɂȂ�Ȃ��A�z�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ������Ƃł������B����Ȃ��ƂŎ��̓t�@�[��ڐ[�ɔ��N�Z�����Ă��܂����̂�����ǂ��A�������Ă�Ɖ��ƂȂ��A�o���`���[���ȕ��͋C�ɂȂ�̂��A�����ɂ͂ǂ��炭���Ă�B ����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł���낵�����A�X�������o�C�J���Ώ�ɐ��H��~���A�P���̃V�x���A�S���ł͉ł��Ȃ��Ȃ����ԗ��͏Ă������Ȃ���A�P���X��Ԃ��������A�㑱���������X�����B�A���ɖ��S�������Ă����B ���V�A�͉��ƂȂ��A�W�A�I�ȂƂ��낪������B���V�A�͔����A�W�A���Ǝv����̂�������N�\�A���������̏�w���ɂ͑��������A�A�^�V��̓��[���b�p�Ȃ��A�Ǝv��ꂽ���悤�ł������A���������A�z�����R���v���b�N�X���犴��I�ɓ��m���������Ȃ��o�J�ɂ��ē��{���O�l�Ƀ��V�A����l�ł悢�Ƃ܂ŐM���Ă����B�c��͓��{�����ƌĂ�ł����B �����⒩�N�Ɠ������Ǝv����̂��������ē��{�l�͐��m�l�̈�킾�Ǝv��ꂽ���ǂ����̍��̃^�R�A���Ɠ����ŁA���̎�̔n���������������Ă����悤�ł���B���܂������l�⒩�N�l��l�Ƃ��v�킸���{�͐_���A���`�̐푈�������Ȃǂƌ��������̂͂��̃R���v���b�N�X���낤�B���Ă�肳�炷���V�A�c��Ǝ������x�̃A�^�}���B ���̒��x�̎O���ȉ��̐l������Ό��͂������A���̊�F���������݂Ă��Ȃ�����ʎ�芪���ǂ��ƌR�Ɣ閧�x�@�ŋ������Ƃ����B����Ȃ����_�Ȃ����������̔ᔻ�͋����Ȃ��B�鐭���V�A�̘b�ŁA�~�~�ፑ�̘b�ł͂Ȃ��B���ꂪ�ǂ�قǍ����ɂƂ�A�N�����ꂽ���ӂ̍��X�ɂƂ��Ă����낵���قǂɍ��������̂��͒ፑ�b���Ȃ炾�������z���ł��悤�B ���E�̂ǂ��ɂ��N��l�Ƃ��Ē鐭���V�A�ɖ���������̂͂Ȃ������B�S���E�����{�ɓ���������Ă���Ă����B�S���E���鐭���V�A�̓G�ł���A�鐭���V�A�͓���������O��������G�ɕ�������͂���Ă����A���[�j���Ɍ��킹��A�n������ߏグ�鐢�E�鍑��`���͂́u�S�̍��̍ł��ア�ցv�ɂȂ��Ă����B�R�T�b�N�R�������ĐN�����ꂽ���Ӓn��(�E�N���C�i�Ƃ��h���͗���)���珢�W���ꂽ�҂����A�ނ�Ƃċ��������������Ȃ���̎Q��ł������B���{����l����Ă����̂ł͂Ȃ������B�K���o���j�b�|���A�ǂ��������Ă���j�b�|���ł������B ���������łɂ��̓��{���u�S�̍��v�̈ꕔ�ł����Ȃ��Ȃ��Ă���A���E�͓��{�̑叟���]��ł��Ȃ������A�������叟���Ă��܂����悤�ȁA�����āc����͕����Ă��������Ƃ��āc�A ���łȂ���x�g�i���푈�̍��̔���́u�Ԃ͂ǂ��֍s�����v�͂��Ƃ��Ƃ͂����������������푈�Ɋ������܂�Ă������R�T�b�N�n���̎q��S���q���g�ɍ��ꂽ�Ƃ����B�։�ς������ċ������܂��J��Ԃ��A�����������m�I���E�ς����邪�A�S���E�̑����̃V���K�[��X�|�[�c�I��܂ł����̋Ȃ����グ�ĕ��a��i���Ă����B�R���u�`�J(�s���l)���ނ�̋Ȃł���B ���Ĉ���A���E�̗��ꂩ��͂������c����A���̂Ƃ�ł��Ȃ�����`���v���J���Ƃ���ɂ��C�Â��Ȃ����_�o�ȓ��������ƍc���͐��E��M������`���������A���̓��{�́A  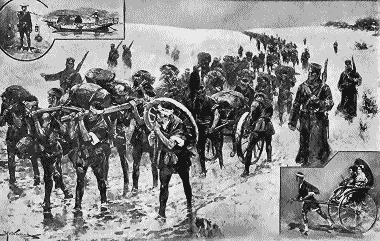 �����n�d�A���������Ȃ�Γd�M���ɉԂ��炭���@�����푈�͂����ς�R�v�̎�ɗ��������A���I�푈�����n�d�������n�߂��B�����������͕����Ƃ��đ��d���ꂸ��i�Ⴂ���̂Ƃ��ꂽ�B�u�G�������h���V���v����(�w���ߑ�S�N�j3�x���A�L���v�V������)�B ���āu�k�s�̗Y�I�v���₢��u�a�@�Ԃ��̗Y�I�v�̂��Ȃ��Ȃ珟�Ă邾�낤���A���₢��ܕ��ܕ��܂ł����Ă����邾�낤���B�m�\�̌�����i���čl���ĉ������B���₢��܂��������B 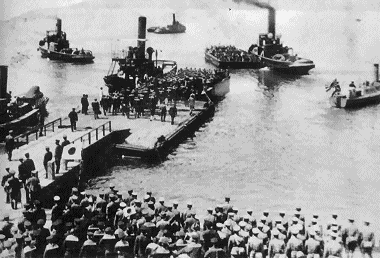 �����V��(���ߎs�E���a9�N)�@���Nj��y�������n������ۂ̌��i�B (�w�ڂŌ��镑�߁E�{�ÁE�O���100�N�x���B�L���v�V������) 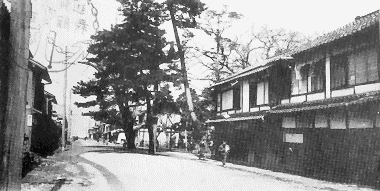 ������ʂ�(���ߎs�E���a10�N��)�@�b����_�АՒn�t�߂̒ʂ�̗l�q�B (�w�ڂŌ��镑�߁E�{�ÁE�O���100�N�x���B�L���v�V������) ���ʂ͗^�ۘC�썶�݂̒ʂ�œ�����̈���ʍs�ɂȂ��Ă��鋷���ʂ�B���㋴������́u���s�v���J����A������ƗL���Ƃ��B���Ă�SL�������Ă��� 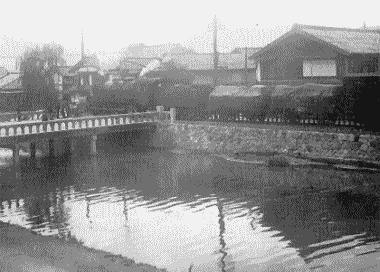 �����㋴�t�߂𑖂�ݕ����(���a10�N��)�@�V���߉w�Ɠ��`�C�݂����ԓS���́A�^�ۘC��̍��݉����ɊC�݂܂ŕ~����Ă����B���̓S���́A���Ƃ͐V���ߎV���q�Ɋ�����Ђ��ݒu�������̂ł��邪�A���a�O�N���Ђ��o�c�s�U�ʼn��U�������߁A���ܔN�S���Ȃɕғ��B�����ɐV���ߍ`�w���ݒu���ꂽ�B(�w�ӂ邳�ƍ��̎ʐ^�W�x���A�L���v�V������) �@�@�@ �Ȃ�ڂ������d���₢���Ă��A���������Ƃ炵���d��������B����Ȃ���͌��������ɂȂ�킢��B�������������܂ŃA�z�����肻������B�[�[�L����ǁA����������ɂ�����B ���������A����Ȃ���ɃJ�l�ق����ȁB���߂̎s���̓{�P�Ƃ�Ȃ��B�����ƘV�l�z�[�������Ă���A���Ƃ��낪�A������̂�����c�ȂǂƃI�o�`����(����)�����܂ł��W�܂�u�݂�Ȃ��������Ƃ��Ă��v�Ə�Ȃ���B �����{�P�Ƃ�͓̂��Ɏs�������ł͂Ȃ��A�N�\�~�~�N�\�����N�\�����c����ȘA���S�������̗l�q�B �s�����ꂵ�߂�Љ���Ȃǂ͌��X�������S���Ȃ�����������ł��Ȃ�����Ȍ��z�ɐ������܂���Ă̂��V����܂ǂ������炻������R�ȘA�������m��Ȃ��A�Ԏ����ƕa�@��ׂ��Ă���Ɏs���a�@�\�Z�͒ʂ��Ȃ��A�s���Ƃ͉����W�̂Ȃ��Ԏ����ƌ��܂�����ԃ����K�P�O���͑�^���A�ǂ����̃x�b�s���d�����l�Ƃ͋t�ŁA�Ђǂ��^�R�A�������A�Ƃɂ����ǂ��ł���ςɐl�C�������A�N�ɕ����Ă��ُ�Ȑ����ɉ������Ă���̂����A�s���͌����čs�������Ȃ��B���悢��{�C�ʼn��Ƃ����Ȃ��ƕ��߂��ׂ��B ���p�l�A�V�ѐl���̔��z�����Ȃ��悤�ȁA������ƌ������Ƃ���Ȃ��A�Ƃ������̂��Ȃ��B�V��ł��肢���̂��A��J���ĕ��������ƂȂǂȂ��悤�ȁA�������肹����A�Ƃ����Ă�����ł���[�̍��m���ǂ�ŁA�s�������Ȃǂ͓��ɂȂ����X�Ȃǂ͐c����o�J�ƌ��ĕ����������Ȃ��̂ʼn��܂�킯�͂Ȃ��B �s���Ƃ��Ă̓u�[�u�[�������������͂Ȃ��B����ɐ���傫�����ău�[�X�J�ƌ��������邱�ƁA����ł������Ȃ��Ǝv���邪���̎��͂�������Ǝ��̑I���ł͑������Ɨ��Ƃ��Ă��܂��܂���B�悢�������ɂ̓n�R���厖�����m��Ȃ����A�����ȃ{�����e�B�A�������K�v�A�������I������ςɑ厖�Ȃ��́A�_���͗��Ƃ����ƁA�ǂ��҂�I�Ԃ��Ƃ͎s���Ƃ��Ă̍Œ���̐ӔC�ł���B���������������Ȃ��ƕ��߂͂悭�͂Ȃ�܂���B �S�N��܂Ŏc��A�Z���ɂ������͊��ӂ���邩���A�J���R�[�����ɂȂ邩���́A���d���Ƃ͂���Ȃ��̂����A�̖����̂��d�������Ă݂悤�B �@�����̃��[���ʂ����ʂ�(����27����)�����ʂ������́u�����ʂ�v�ƌĂ�ł����B���͒P�Ɂu �����߂̒ʂ薼���E���Γ��I�J����̊C�R�̐w�e��ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃ��ł��邩���m��Ȃ��S���ǂ��ɂ��Ȃ��ł��낤�n���Q�A���߂ł����������߂����ł���B �ߍ��ł͖Y���ꂩ���Ă��Ă��邵�A�ǂ�ȌR�͂������̂��A�ǂ�Ȑ푈�������̂��͎s���̒N�����͂�V�J�Ƃ͒m��Ȃ��B�s���s���ς���Ȃ܂��߂Ȏd���͂����ɕ����̐ԃ����K�Ł`���A����ɕ����Ă���B ���̑O�̔s����Y��A���g���X�R�[���ƖY��邭�炢�ɖڏo�x������A��������I�Ȃlj����ߋ��Ȃǂ͏��߂���m��Ȃ��A�m��Ȃ��Ƃ������Ƃ���m��Ȃ��Ȃ��Ă���B�m���Ă���肾���L���̉�H�����߂��Ȃ��B�Ȃ����ΐԃ����K�Ł`���B�����A�z�炵���A�R�̃T����������B����ł͌��݂̎����̗��ʒu�ł���X�R�[���ł͂Ȃ��낤���B ���Ȃ��̕��������ɗ��j������B�����E���I�������ɂ���B���߂͂����̂��Â��C�R�n������̗��j�������ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ����ł���B�ߋ��̘b�łȂ��A����͍�����������ƕ��߂ɐ����Ă���B�L���ȏ������ł��������łɎ��グ�Ă݂悤���Ǝv���B 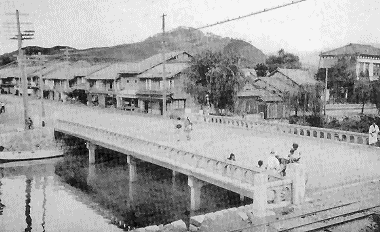 �����㋴(���ߎs�E���a10�N��)�@�^�ۘC��ɉ˂��閜�㋴�B��O�Ɍ����郌�[���́A�V���߉w�Ɠ��`������ł����S���B 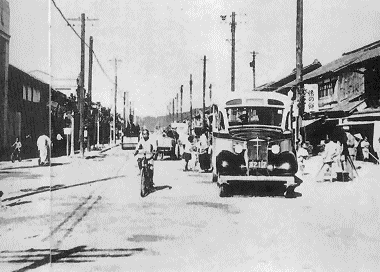 �����ʂ�(���ߎs�E���a����)�@���݂̑��O�������_�t�߂��瓌����]�ށB���c��s�̌��������Ɍ�����B (��������w�ڂŌ��镑�߁E�{�ÁE�O���100�N�x���B�L���v�V������) ��͖����������ʂ�  ����́u�O�}�v(�܂��Â�q�b�U) �O�}�ʂ� ��͎O�}�ɂ��Ďs�j�́A ��͎O�}�ɂ��Ďs�j�́A�@�q �@��͂́u�ł���z����U���͂Ɩh���͂Ƃ�L���A���S����Ȃ�C�㕐�͂̍����v�i�ߐ��鍑�C�R�j�v�j�ł���A�C�R�̉Ԍ`�ł������B���I�푈�J�n���ɂ͐�͘Z�ǂ����{�C�R�̒��S���͂ƂȂ��Ă����B���ł����̎O�}�͓͂��I�C��ɔ����đ����C�R�g���v��̂����Ō�Ɋ���������͂ł������B �@�����O�\�l�N�A���ߒ���{�������ɂ́A�܂��p���Ō������ł������ɂ�������炸�A�O�}�͕��߂��`�Ƃ��邱�ƂɌ��肳��A���̏�����͎O�����ɒ�߂��Ă����B����͍����m�����܂߂Ĕ��O���l�̑����ɋy��ł����B�ꓙ��́A�r���ʈꖜ�܁A�������g���A�@�֏o�͈ꖜ�܁A�������n�́A���͈ꔪ�m�b�g�A���C���`�C�l��A���ˊǎl��ق�������铖�����E�ł̍ŐV�s�͂ł������B���O�\�ܔN�O�������H���A���N�܌����{��R�`�ɉ�q�A�����ɂ͂��̗Y�p�ߘp���Ɍ��킵���B�R�͂Ɋ���n�߂��n�������A���̐V�s�͂ɐڂ��ĉ��߂Ėڂ����������B������\����n���𒆐S�Ƃ����Z����ʂɌ��J���ꂽ���A���̖͗l��V���͎��̒ʂ���Ă���B �@�����\�������ʂɔq�ς������ꂽ��O�}�͐��E�L���̋��͂Ɖ]�ЁA��ɕ��ߒ���{�̏����͂Ƃ��āA�V�c�j���̕ʂȂ��A�������ƑD��������l�́A�����̗t�̗���@���A���鑽���̔q�ϐl�ɂāA���Ԏm���ȉ��͈��͂���������ɐ����̘J�����A�傢�ɊC�R�v�z�̗{���ɓw�ߋ�����̂̔@���B�����͍͂��b���ؕd�̗\��Ȃ�ƁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i��㒩���V���u���s���ꕍ�^�v�j �@�O�}�͓��I�푈���A�A���͑��i�ߒ������������̊��͂Ƃ��đS�͑����w�������B��ɓ��{�C�C��ɂ�����P��������ʂɂ��A�u�����v�̖��𐢊E�ɂƂǂ납���A���{�C�R�̑�\�͂ƂȂ����i�ʐ^31�j�B�@ �����������Ƃ��炩�����ߕl�n��̒ʂ薼���R�̖͂�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ͎q���̍����玄�͒m���Ă������A�ւ��[�����Ȃ�A�Ƃ���Ȃ��Ƃ͂܂������m��Ȃ��Ƃ������ߐ��܂�̕��ߐl���������������B���y����ɗ͂𒍂��ł���ꂽ�s����ψ���l�̓w�͂̑傫�Ȑ��ʂ����m��Ȃ��B ����́u�O�}�v(�����N���j�N���w�Q�O���I�x���) 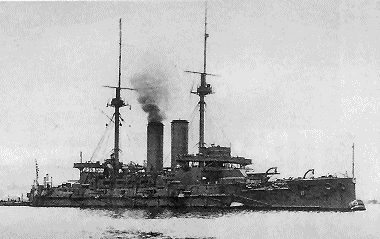 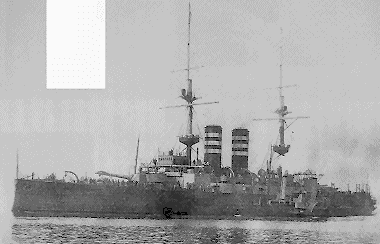 ����͎O�}�v�H�@�p���C�b�J�[�X�ЂŌ�������Ă����ꓙ��͎O�}���P���قڏv�H���A���^�]�̂��߃^�O�{�[�g�ʼn��o�����ꂽ�B���{���C�M���X�ɒ������Ă����U�ǂ̈ꓙ��͂̍Ō�B�r���ʂP���T�R�U�Q�g���A�S���P�R�P�D�V���[�g���A�R�O�Z���`�C�S��A���͂P�W�m�b�g�œ����̐��E�����ł��ŐV�s�͂������B���I�푈�J�n�O�ɘA���͑��̊��͂ƂȂ�A�i�ߒ������������Y�叫�����悷��(�����N���j�N���w�Q�O���I�x���B�L���v�V������) ���O�}�ʂ�(���s�{���ߎs�l) �����ʂ��@  ����́u�����v�v�H�@�����푈��A���{�͊C�R�ߑ㉻���}���A�U�ǂ̈ꓙ��͂��C�M���X�ɔ�������B�����͂��̂S�Ԋ͂Ƃ���1��18��(1901�EM34)�A�[���X�g�����O�Ђ�������n���ꂽ�B�r���ʂP���T�O�O�O�g���A��C��30�Z���`�C�S��A����18�m�b�g�̋ߑ�I��́B�������A���I�푈�J�n���X��1904(����37)�N�T���A�����`�O�ŋ@���ɐG�꒾�v�B(�����N���j�N���w�Q�O���I�x���A�L���v�V������) 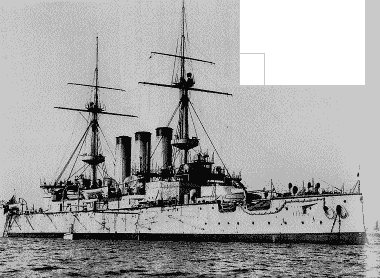 �@�@�@ �@���̎��u�����v�̂��Ƃɓ�Ԋ́u�~���v���������A����͍K�^�͂ł������A�@���Ȃ̂������͂Ȃ̂����킩��ʒ��A�@���Ȃ�Γ������ɂQ�͂Ȃ��Ɓu�����v�̍q�H�킾���̐Ղ�q�݂Ȃ���S���ő��蔲���Ė����ł������B�Ƃ��낪�O�Ԋ͂̐�́u�����v���헋����œ�x�G����6���߂��ɒ��v���Ă��܂����B���̓��̂킸���ȊԂɂU�ǂ̐�͂̂����̂Q�ǂ��ꋓ�Ɏ����Ă��܂����B����5�E15�ƌ�����B���̂Ƃ����V�A�ɂ͂P�P�ǂ���͂��������B�S�P�P�ƂȂ��Ă��܂����B �ʂ薼�𖽖��������ɂ́u�����v�͂������A���C�C�����{�C�C�펞�ɂ͂��łɂ��Ȃ������B �������ʂ� �����ʂ��@��͒����̖��B  �����ʂ�͂��ɂ����̒O��X��(�ዷ�X��)�Ǝv����B���̍���27�����̋����ł͂Ȃ��낤���B �������ʂ� �����[�́u�a��ʂ�v����ʂ��Ă���A���̒ʂ�͎��͎O�}���w�Z�ʊw�ɖ����ʂ����ʂ�ł���B�������͎O�����m�́u�a��v(2987�g��)�Ǝv����B �@�@�@ �C���t���u�M�Z�ہv�̓o���`�b�N�͑��̂ǐ^�ɂ����A�G�͑�����������m�F���ė��E���ߑO4��45���A�Í��d����ł����B �u�G�m�͑��A��Z�O�n�_�j�����v ���X�ɐH���������Ă���ɑœd�A �u�G�j�H�A���k���B�Δn�������j���J�E���m�m�@�V�B�v ����� �u�G�j�H�A�s���B�Δn���������w�X�B�v �悢�d��������D�����A�u�M�Z�ہv�͖���33�N�v�H�̉q�D6388�g���A���̌�������Ԃ�ƒ����ԏA�q�������D�ŁA�剪�������́w�ؗ��L�x��l�����t�B���s���}���ɗ���̂����̑D�Ƃ��ŁA���g�D�ɂ��Ȃ����悤�B ���a22�N2���ɑ�A���畑�߂ֈ��g�҂��悹�ē��`���Ă���A���̌�i�z�g�J����20�����̈��g�D�ƂȂ��Ă���悤�ŁA���g�D���X�g�Ɂu�M�Z�v�������邪�A���̑D���낤�Ǝv����B  ���u���I���g�L�O�فv�̈��g�D�E�M�Z�ۂ̖͌^�B�ē��v���[�g�Ɂu���g�����F6.155�g���B���́F15.4�m�b�g�B�o�^���@�F133.5�~15.2���[�g���B�����N�F����33�N�B�D�̎�ށF�q�D�B��Ȉ��g�n�F�i�z�g�J�E��A�B�A�q�F19��B���g��D�Ґ��F38.621���v�Ƃ���B �ߌ�6��0���A�����͑�{�c���ɁA �u�G�͑������g�m�x��j�ڃV�A�A���͑��n���`�j�o���A�V�����ŃZ���g�X�B�{���V�C���N�i���h���g���V�B�v �N�����m�钴�L���ȓd���B�R���̕��炵���Ȃ������A�u�H�R���w�v�Ƃ��Ă��B 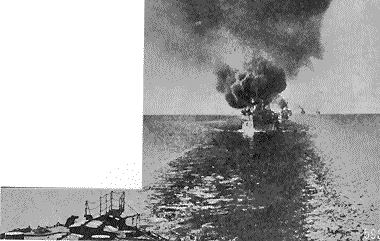 ����͊͑����C�p���o�����Ē��N�C���Ɍ�����5��27�����B(�w���ߑ�S�N�j3�x���) �u�M�Z�ہv�Ə�������サ���̂���{���˂ɓ�{�}�X�g�̏��m�́u�a��v�ł������B�u�a��ʂ�v�̘a��ł���B ��_�Ƀo���`�b�N�͑��ɐڋ߂��A���������댯��`���Ă܂Ƃ����悤�ɊĎ��𑱂����B �u�G�͑������B��͔��ǁA���m�͋�ǁA�C�h�͎O�Njy�r���z���m�́A�H��͓���A���r�j�쒀�͐��ǁB�v �o���`�b�N�͑��݂͂Ȑ^�����ȑD�̂ɉ��F�̉��˂����Ă����B������œd�����B�A���͑��͔Z�D�F�ł���������A�G�����̎��ʂ��y�ɂȂ����B����ɂȂ��Ă��A�Ƃɂ������F�̉��˂Ȃ�u�b�������悭�Ȃ����B �o���`�b�N�͑��͖����̒���ɂ������s��Ȑw�e�A�m����������R�Ɩk��𑱂��Ă����B�e�͂���f�����S�{�ɂ��Ȃ鍕���A���̎p�������҂݂͂Ȑk�������Ƃł��낤�B �����[���B��������͑��v���낤���B ���{�C�C��͉��m��(�@���s)�̖k���P�`�Q�L���̊C�ʂŐ���A�s���Ō����҂͎s�n���P�����J��@����Љ��Ë{�̎G�p���N(���l���̓�)������l�ł����������ł͂��邪�c ���܂�ɋߊC���Е����X�ƍs���̂ŗ��R�̕������ڂ̗A���D�u�������ہv�͓��{�͑��Ɗ��Ⴂ���đ����b�ɏo�āu�o���U�C�I�o���U�C�I�v�Ƒ吺�����ċ��тȂ���o���`�b�N�͑��ɑ��т��Č���ɋ߂Â��Ă������Ƃ����B�u����ȑ�͑������{�ɂ������̂��A����Ȃ烍�V�A�ɏ��Ă�o���U�C�I�o���U�`�C�I���ނ������Ă����v���x�~�߂悤�Ƃ��Ă����ꂪ�G�̑�͑����ƋC�t���Ȃ��A���悢��G�̎˒����ɓ����Ă��܂��A�u�a��v�̂���Ă����Ƃ́A���b�̂悤�ȁc ����Ȃǂ������I�Ȏp���c���Ă������A�l�Ԃ��q�̓I�Ƃ����̂��A���w�I���}���I�p�Y���I�Ƃ����̂��A���I�푈����͂܂����݂��ɌÕ��m�̂悤�Ȗʉe�������͂������悤�ł���B�x��ɂȂ���ɂЂ��݂Ȃ�������݂��̎�r�𓊂������Č���������A�����J��̓��͓��I�̕��m�B�����݂��ɚ͍����o���č���̓G���m������g��ŗ����̎���J��o�����Ƃ��B�����l�E���̂��߂����̐푈�ł͂Ȃ��ʂ��c���Ă����B �悫���オ���݂��ɂ܂��c���Ă����B�����̍����͖����ߑ㍑�ƂɊÂ������̏W�c���z������������邪���߂̏@���I�M�̑ΏۂƂȂ��Ă����B  �����V�A���̃q���[�}�j�e�B�@�����U����̂��Ȃ��A�����������{�R���Z�������������ĉ^��ŗ������V�A�R���m�̃q���[�}���ɍs�ׂɁA�G����������������������߂Ėڂ��݂͂����B�u�G�������h���V���v1904.11.1���� 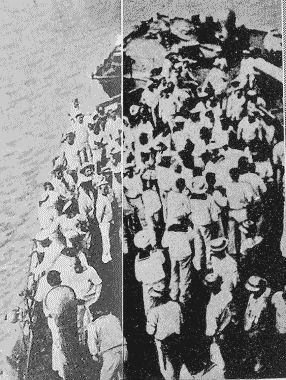 ��1904�N8��14���U�R���C��ɂ����Č������ꂽ�����[���b�N���̐���600�]�����㑺�͑��͏헤�ۂ̉����z���ċ~�������B(��������w���ߑ�S�N�j3�x���B�L���v�V������) �M���������B �l�͏�A�l�͐Ί_�A�l�͌@�B��͖����A�w�͓G�B �s�����v������Ȃ���A���ǂ͕挊������Ō@�邱�ƂƂȂ�B���j��������B �ق��ɂ͉������������\�͂͂Ȃ����A���̂����ɖ���R�̕a�@�D�߂�̂Ȃ畑�߂̃N�\�c����N�\�������͐��E��̒B�l�ŃE���W�I�͑����}�b�̘r�O�Ȃ̂����A���̂��ߍ����A�s���̔��̓S�E�S�E�A���{�̏d���͑�������Œǂ��������p�ɂ����Ìy�ɂ����ƃE���T����ь�������ŕߑ��ł��Ȃ��ł����B �����͑��������Ƃ��E���W�I�͑����A�����ē����ɈႢ�Ȃ��A�����͑����}���ɕK���o�����Ă��邾�낤�Ɨ\�z�����ĂāA�����ő҂��Ă����B ���̂Ƃ��͊��́u���V�A�v��擪�Ɂu�O�����{�C�v�u�����[���b�N�v���쉺���Ă����B���{���͊��́u�o�_�v��擪�Ɂu��ȁv�u��ցv�u�֎�v�B �����[���b�N�̓��V�A���̗D�G�́A�q�������͒������x�͑����A�U���͂������A��̏��m��͂̂���{�B�R���オ�郊���[���b�N�A���ꂪ���̂ĂĂ�����傤���A�Ɖ��x�����x����F�̗��͂������Ԃ����Y���A�Ƃ��Ƃ��C�e���Ȃ��Ȃ�A���̂Q�͂͒��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�N�����Ȃ�ǂ�����A����������Ɠ�����B���₢�□�����m�ł����Ă������ē����邩�ȁB���肪���̂���d���͑��ł���B ���U�R���̊C���@���Z�l�N�i�����O���N�j������l���A�헤�ی����̂̕��߂ɃE���W�I�͑������߂Ă������͑��͂��ɉU�R���œG�����A�����[���b�N�������������B�ʐ^�͐������̂��Ȃ��ɃE���W�I�͑�������u�ԁB 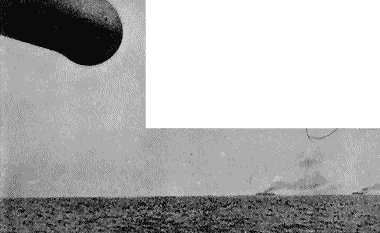 �����v���O�̃����[���b�N���@�b�ɔj��C�e�A�o�^�o�^������镺�m�A���݂Ȃ��C�e�͂Ȃ�ʗE�m�B�u�G�������h���V���v���ځB(��������w���ߑ�S�N�j3�x���B�L���v�V������) 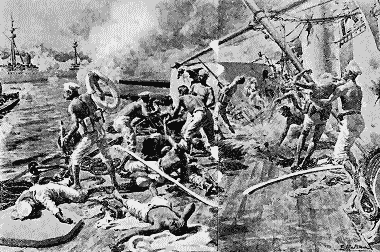 ���̍��͖]���Ə��͂Ȃ��A���V�A�C�R�ɂ͂��������������A���{�C�R�ɂ͂܂��Ȃ������B����Ō����Ă���B�e�b�|�E�����̍˔\�͐��܂���̂��̂炵���āA���̍˔\���Ȃ��҂͂�����P�����Ă������������̂ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�C�R�ꋉ�̍˔\�͂��ׂĐ�͂̎�C�����ɏW�߂��A�������̏d���͑��ɏW�߂��Ă����B �~���ʂ� �����݂̕~���ʂ� 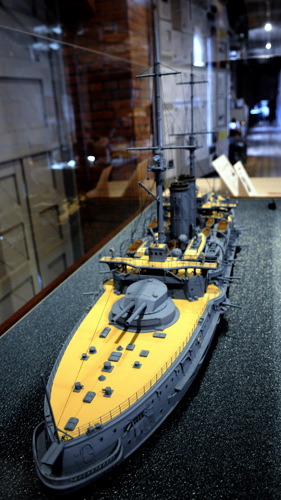 �����C�M���X���ł��邪�A���ꂽ���D�����Ⴂ�r���ʼn��P�����ꂽ�̂��ו��Ńr�~���[�ɈقȂ邪��C�A���C�A���̑���v�����͓����ł���B ��͎O�}���ƁA �r���ʁF15.140�g�� �ő呬�x�F18�m�b�g �S���F131.7m �q�������F7000�C�� �S�ЁF23.2m �@�ցF15.000�n��(�ΒY���ĂQ�����B�C�M���X����C���|�[�g���������Y���ŗǂł�����) ����F860�� �����́A ��C�F40���a30.5�Z���`�A���C2��F4�� ���C�F40���a15.2�Z���`�P���C�F14�� �ΐ������C�F40���a7.6�Z���`�P���C�F20�� 47�~���P���C�F16�� �������ˊǁF45�Z���`���ˊǁF4��(���ʉ��ɑ���) �Պp�F(�C�ł͌��������Ȃ��Ɗ͂��w���G�͂̃g�e�b�p���ɂԂ���A���̂��߂̊p�����Ă����B���ʉ��̂��̂ł��̖͌^�ł͌����Ȃ��B) 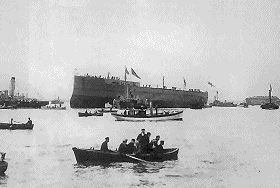 ���W����͐i���@�C�M���X���ւ鐢�E�ő�̐�́u�h���b�h�m�[�g�v��2��10���A�|�[�c�}�X�R�`�Ői�������B�S��161���[�g���A�ő呬��21�E28�m�b�g�B30�Z���`�C10�������A�h��b�������A���ĕ��Ȃǂ̊C�R���ꋓ�ɋ����������Ă��܂����B���E�͂���Ȍ�A��͋��C����ɓ˓��B�u���W�i�ǁj���v�Ƃ������t�͂��̊͂ɗR������(�����N���j�N���w�Q�O���I�x���B�L���v�V������) ���W����͐i���@�C�M���X���ւ鐢�E�ő�̐�́u�h���b�h�m�[�g�v��2��10���A�|�[�c�}�X�R�`�Ői�������B�S��161���[�g���A�ő呬��21�E28�m�b�g�B30�Z���`�C10�������A�h��b�������A���ĕ��Ȃǂ̊C�R���ꋓ�ɋ����������Ă��܂����B���E�͂���Ȍ�A��͋��C����ɓ˓��B�u���W�i�ǁj���v�Ƃ������t�͂��̊͂ɗR������(�����N���j�N���w�Q�O���I�x���B�L���v�V������)�ă|�[�c�}�X�C�R�H���͓��I�u�a��c�̉��ƂȂ����Ƃ���Œm���邪(1905�N8���`)�A���߂̎o���s�s�͉p�|�[�c�}�X�ł�����ł͐��E�����Q�����h���b�h�m�[�g���閧���Ɍ��͓ˊэH���̍Œ��A���邢�͐v���ł������̂ł��낤���B ���݂Ō����f�V�_���d�q�@��̂悤�Ȕ��B���x�ŌR�͂͐i�����Ă����B��̓h���b�h�m�[�g(30.5�Z���`��C10��A21�m�b�g)�̐i����1906(����39)�N�A���{�C�C��̌o������v���ꂽ�Ƃ������A�Ќ����Ȃ炱��܂ł̂Q�{�A�͎�����Ȃ�S�{�A�͔������Ȃ�R�{�̖C�́B�������̂P�͂ł��ꂾ���̗p���ʂ����B�O�}�Ȃǂ͂��̒��O�^�A�� �Ȃ���͎O�}�͎��������{��s���O�}�L�O���Ƃ��ĕۑ�����Ă���B �@�@�@ �ŐV�s�̓��^�͂��Œ�Q�͂̃y�A�łق����A�l�ԂƓ����łP�݂͂̂ł͊��S�̂ɂȂ�Ȃ��A���M�͕K���M�Q�z���g��g�ށA����̏M���u�₤���M�v�ƌĂсA�ǂ�Ȋ댯�ł��������Č��̂ĂȂ����m�ł������A�v�[���֓���q������l�őg��g�ށA���ƌ��������킷�ꂽ���A���������댯���ꍇ�݂͂ȓ����ŁA�͑��s������b�P�ʂ͂Q�B���������Ă��̔{���̂S�́A�ł���W�́A�P�U�͂Ɨ~�����B ���ł����A�ŐV�̂P�O���g�����q�͋��(�Q���~�ȏ�����邻���ł���)�������̃Z�b�g�Ŕ������Ƃ���悤�Șb�ł���A�n���͂ƂĂ��ƂĂ������Ȃ��̂ʼn��Ƃ��S�͂������Ƀ������Ă���Ƀ������đ������킯�ł���B ���q�͋��̓A�����J�ɂ͂P�P�ǂ����邻���ŁA�����ۂ≡�{��ȂǕ�`�ɂ��Ă�����̂��������ƋL�����邪�A�I�o�}�哝�̊t���A���ЌR�`���߂ɂ��P�ǂ����ł��z���肦�Ȃ��ł��傤���A���łɌ������ڂ̌��������߂Ȃ��ł��傤���A���������������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��������ȏ�ɍ������̂ł͂Ȃ��낤���A���������Ԃ��̌�����������������̃A�����J�����ǂ��������đ��ъ��ӊ��ӂŒs��ł����邱�Ƃ͊m���A�����c �j�͂Ȃ����܂��傤�A�̓m�[�x�����a�܂��́B���q���ȂnjR�����Ȃ����܂��傤�A�͎��̉ۑ肩�B����Ȉ������k���镨���Ȃ��̂��Ȃ���Έ��S�ɐ������Ȃ��̂��A�l�Ԃ��܂Ƃ����낤�����͂��̐������ɂ͂��̒��x�̒m�\�����Ȃ���Ȃ����̂��A����ł͓��m�����ŖS�Ԃ��B�������͂�����������ɐ����Ă���̂ł����āA�����͉����ߋ��̂��b�������Ă��邾���A���オ�Ⴂ�A�l�ނ̂�������ۑ肪�Ⴄ���Ƃ��ԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B�{���͖��Ɗ�]�������Đ����͍s�����́A���ꂪ�����ƁB�����Ȃ���`�{�[���Ȃ��u���������v�Ȃǂ͖{���͐����ł͂Ȃ��r�W�l�X�̘b�A���l�Ƃ��������ƌĂԁA����ł͖����͗��Ȃ��B  ���C��ネ�V�A��̓A�����[����b�|�����Ζ�̈З͂ɂ��(�w���ߑ�S�N�j3�x���) �����Ƃ̂��̑�O�Ζ̍H�������E��ƌւ鉺���Ζ�ƈɏW�@�M�ǂ����ʂ��傫�������B �S������ł��܂������A�����P�ǁu�I�����[���v�́u�A�����[���v(�h)�Ƃ�������邪�A�I�̌��^�ŃA�Ɣ�������̂ł���Ȃ��ƂɂȂ�A�{�J�X�J�Ɍ�����Ē��v���O�ɍ~�����ߊl���ꂽ�A�����������ۂ܂ł̉g�q������A�ߋ����̕��߂։�q���ꂽ�B�s�j�́A �@�q �@�܂��A�������߂̊C�R�a�@�ɂ́A���{�����폝�ғ��l�A�a�C�×{�ҘZ��l�A�v����l�����@���Â��Ă������A���V�A���ߗ��̂����O��l�����킹���Â����邱�ƂɂȂ����B�@ �w�����ߍZ�S�N���x�́A�@ �@�q �@�d�����邪����������J�C�i�O�n�����ĕ��o�������j�ҏW�̋L�����ؗp���ē������Â�ł݂悤�B �@����38�N�T���Q�V���A���{�C�ŁA���I���͑��̌����������́A�o���肠����ŕ������Ƃ����B �@����38�N�T���R�O���ߌ�ꎞ���A�X�Ƀ��b�p���苿���āA�ߊl���ꂽ�����A�̌R�͂������ė����B�q���̎��A�l�X�̂��Ƃɂ��Ă����āA����������L���̂���ØV�̘b�ł́A�A�����[���ƁA������t�A�o�[�����ł������Ƃ̂��Ƃł���B �@�R�̓A�����[���͔r���ӈ�O�A�܈�Z�ӁA�\��D�C�l��A�Z�D�C�\���A���̑������a�C�l�\�Z��A���͏\���m�b�g�Ƃ����D�G�͂ŁA����͑��X�E�I�[���t�A�A���N�T���h���V�A�{���W�m�ɑ����l�Ԋ͂ł������B �@�����A�A�����[���́A�R�͒����Ɍ�q����āA���߂ɓ��`���ė����B�q���≌�˂ɂ́A�傫�Ȍ����������A�S�͂߂���A��b�͂߂���߂���Ő퓬�̌������ƁA�s��݂̂��߂������炵�Ă����B�������ĕߗ����㗤���A�C���c�Ɏ��e���ꂽ�B�܂��A���a���́A�C�R�a�@�ɓ��@�����B�����̏�i���A�����́A�g�̂Ђ����܂�C���Ō�������B �@�����Ē��������R�̉ԑ����āA���a�̃��V�A�������Ԃ߂��B �@�A�����[���́A������C�����A���{�͐Ђɓ����āu�Ό��v�Ɩ������߂��B �@���łɂӂ邳�Ƃ̒n������������́w�O��x���ߊl�͂ł��蕑�߂ŏC�����ꂽ������m��Ȃ��l�X���������ƂƎv���V���̒��������͈͂��Љ�Ă����B �@����Õv���u�C�R�͒��j�v�Ɂw�O��x�͓��I�푈�ŗ����`���ɒ��ꂵ�Ă����w�|���^���x���R�W�N�W���Q�X�����߂ɉg�q���C�����������w�O��x�Ɩ������R�͐Ђɕғ�����Ă������A�吳�R�`�T�N�̑�ꎟ���ɍۂ��A���������ɎQ���A�吳�T�N�S���ɂ̓��V�A�ɗL�����n���ꂽ�Əq�ׂ��Ă���Ƃ�����݂�Ƌ��m�Ƃ̓���͒Z���������̂ł��낤�B�i�ʐ^416�j�@ ���� �֘A��� |
���̃y�[�W �|��͒ʂ�| �����҂̍���
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Q�l�����z �w�p����{�n���厫�T�x �w���s�{�̒n���x�i���}�Ёj �w���ߎs�j�x�e�� �w�O�㎑���p���x�e�� �w��C�R��z���x�w�C�̎j���x�w��̏�̉_�x ���̑��������� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2010-2011 Kiichi Saito �ikiitisaito@gmail.com�j All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
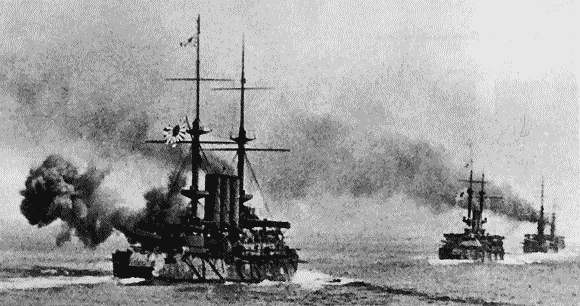
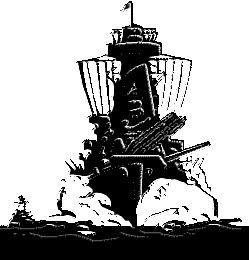


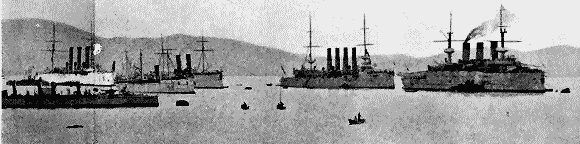

![�u�]������{�t�ߐV�s�X�n���}�ʁv](hamamap02.gif)