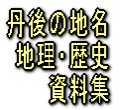 |
旧・池内村(いけうち)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サイト内検索
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧・池内村の地誌《旧・池内村の概要》 池内は舞鶴市の南部。伊佐津川支流・池内川流域に位置する。往古、五老山(302M)の山崩れで池内川が堰止められ、池となったことによりこの名があると伝わる。 中世は池内保。『角川日本地名大辞典』には、「南北朝期〜室町期に見える保名。丹後国加佐郡のうち。明徳3年4月25日、「丹後国衙領内池内保正税」を毎年10月中に京済すべく請文に任せて沙汰せよとの幕府御教書が□(屋か)部氏宛てに出されている(八坂神社文書。大日料7-1)。「丹後国田数帳」には「一 池内保 十九町二段内」と見え、そのうち8町3反余は吉原殿、8町4反余は成吉越中、残余は庶子分下宮四良左衛門の知行とされている。成吉・吉原両氏はともに丹波郡に根拠を置く有力国人」 池内村は明治22年〜昭和11年の加佐郡の自治体名。今田・堀・池内下・布敷・別所・上根・寺田・白滝・岸谷の9か村が合併して成立した。布敷に役場を設置、今は農協が使っている建物。明治43年池内尋常高等小学校が開校した。 村内には銀・銅・硫化鉄の鉱山があった、昭和初期に廃坑となったという。昭和11年舞鶴町に合併。村制時の9大字は舞鶴町の大字に継承された。 《人口》1847《世帯数》590 《交通》 府道舞鶴綾部福知山線 《産業》 池内の主な歴史記録《注進丹後国諸荘郷保惣田数帳目録》 〈 八町三段百八十歩 吉原殿 八町四段百九十七歩 成吉越中 □□五段 庶子分 下宮四良左衛門 《加佐郡誌》 〈 池内村 (一)戸数 四七三戸 (二)住民 男一二五五名 女一一三二名 計二三八七名 (三)生業の状況 本村は純然たる農村部落で、地勢の然らしめる所、山地多く平地に乏しく、耕地は僅かに山地の十汁の一にも足りない位である。土質は概して、砂質壌土で、殆んど何れの作物栽培にも堪え得るが、耕地は面積の狭小なのと、生産能率の除り大ならざるために、耕地産物は自給自足の程度以上多くを期待することは難い。たゞ山地にあっては、面積の割合に広い上に概して地味植林に適してゐるから、前途に対して十分望を嘱することが出来る。 かゝる状態にある本村生業の首脳は、勿論全く農業であって、傍ら山林に関する木材、薪炭の製造が行はれてゐる。他に僅少の商店、(材木、雑穀類、雑貨、文房具類、菓子、茶、酒、醤油類、太物、荒物、飲食等の)及び工業者(大工職、瓦師)があるが、中には農業を兼営してゐる者もある。然し近来農村経済の不況につれて、村内住民にも衣食を給料に需めんとして、工作部、会社、商店及び官公衙に通勤する者が漸く多くなって来た。 耕作田面は(今田、堀、布敷別所の一部)、村先覚者の努力によって、既に明治四十二年以来約七十町歩の耕地整理が遂行され、今は生産能率の増加を図って米麦作の改良に励み、着々其の実績を挙げつゝある事は他村に餘り見られない所であらう。作物は 平地には主として米、麦、豆類が作付けられ、傾斜地には甘藷、馬鈴薯等が栽培せられて居り、特に岸谷、寺田、白瀧の如き山畑には蕎麦、粟、黍等が耕作せられてゐる。 副業としては、近年大いに養蚕を奨励して、之に熱心しつゝある結果、飼育戸数も漸次増加し来つて、今は年額五萬圓を収めてゐる。村中、今田、堀、池ノ内下、布敷、別所は米、麦、田の耕作を主としてゐるが.白瀧、岸谷、寺田、上根の如き平地の少い部落は、養蚕に励む外薪炭を製造して市に売出し。山林よりは木材を伐採搬出してゐる、畜牛飼養家は他村に比して稍多いけれども、養鶏飼戸の少いのが甚だ遺憾である。 普通作物の栽培は熱心で成績も概して他に遜色ないが、たゞ果樹疏菜の如き園芸は近隣に比して大いに劣ってゐるやうである。之は現今村当事者によって大いに改善案が考慮せられつゝある所である。 山林は公有私有に亘って禿赭地の復舊工事及び植林の奨励実施をなし、殊に大正十年四月全村部落有林野の統一協議を調へて、林地二百十二町歩の造林経営に着手してゐる。之は確かに本村自治の基礎を鞏固ならしめるものと言ふべきである。 村内には銀、銅、硫化鍬、鑛山があるので、加賀の横山氏によって採掘事業が経営せられてゐる。其の普通採掘年額は百萬貫といはれてゐる。之れが為に坑夫、鑛石の搬出車夫等の他縣から入って来た者が約百名を算してゐる。 (四) 主要物産 (今大正十二年度調査のものを示す) (五) 人情一般 村民の大部分は、古来農業を主としてゐるので、動もすると進取的の気象に乏しいが、人情は一般に温良で親切味を有し、風俗も亦質実醇朴で、謂ゆる『醇厚俗ヲ成シ』でゐる。然し時代の趨勢に件ひ又環境に支配せられて、人情風俗自ら変化しつゝあって、中には時代の弊風たる浮華軽佻の悪風に感染して、矯激の言行を敢えてするものも少くない様になって来た。之に封して村当局も大いに鑑みる所あり、池内村自治会(村内十五才以上の男女全部加入)を組織して、青年男女は勿論村民一般に向って精神的方面、勧業方面、体育衛生方面の修養を要望し、『本村をして住み心地よき所たらしむべし』といふ信條の下に活動しつゝあるのは、誠に好ましい現象であるといはねばならぬ。 (六) 各種団体名 池内村自治倉男子部(青年部、中年部.老年部) 同 女子部(處女部、中年部、老年部) 帝国在郷軍人会池内村在郷軍人分会 池内村青年団 池内村處女会 池内村婦人会 池内村農会 有限責任池内村信用購買組合 池内小学校少年赤十字団) 《舞鶴市史》 〈 加佐郡内の鉱山は、中世、南山村に銀銅山が存在したことが「田辺藩土目録」によってわかる。す なわち、 定免四ツ四分 一 高八石六斗九升 同村銀掘跡 とあり、江戸時代は畠になっている。 江戸時代は「瀧洞歴世誌」に次のように記している。 延享元年(一七四四) 四月ヨリ池の内銀山はしまる 同むろ谷ニ而掘ル同せんげじ村ニ而ほる昔こわぎ長助と云者の掘し古まぶのよしとあって、延享元年四月、藩内に三か所の採鉱が始められたのであるが、鉱石は池内の銀と室尾谷・泉源寺も同様と思われる。 藩は同二年二月晦日、銀の採鉱との関係は不明であるが銅山札の発行を認めて、すでに発行の下さつ(銅山当分札か)とともに毎月引換日を設けて、札所にて落札と引き換えるよう次のように触れている。 銅山札出来仕候付下さつ共町方へ罷出候而 取替申候ハゝ無滞受取候而 当札所ニ而毎 月三日九日十三日十九日廿九日の月五日ツ (「竹屋区有文書」) 当分札、銅山札は銀壱分札がいずれも白色、銀壱匁札は当分札が鼠色、銅山札は赤色の各々二種類であった。藩が同年五月三日、月行司平野屋町孫右衛門に渡した銅山当分札と銅山札の判鑑は写真213の通りである。 銅山は何時休山したのか不明である。… 《まいづる田辺 道しるべ》 〈 池ノ内の地名の由来について前述「池ノ内下村」において若干触れたが、池内の五郎山の山崩れにより池内谷が堰き止められ池が出現したことから「池内」の地名が付けられしと伝えられ、旧語集の中にも地名について、次の様なことが上根村に記されている。 「老民の云う上根村に船繋と言石有、昔五呂の嶽(五郎山)大雨に而抜崩る。其の時、谷中湖となる。舟を浮ベリ仍而(ヨッテ)名有、此所に船繋弁財天を崇め、惣名池ノ内という」。 「惣名池ノ内」とは、今田、堀、下村、布敷、別所、上根、寺田、白滝、岸谷の九ケ村を指したる地名であり、江戸時代には、田辺藩の代官支配の一管轄区画であり、「池之内」と呼ばれていた。 池内の地名が史料に初見されるのは、元暦元年(一一八四)六月日付。 □後国池内保百姓等 言上 丹波国淤与岐別宮庄民等 訴申無実二箇条陳状 百姓等 平 国元 丹波武安 竹野宗遠 当時「池内保」は丹後国領の地領にして、その場所は現在の池ノ内下辺りであったという。 この言上書は、鎌倉時代の池内の百姓の生活の一端を知る上で大変興味があり、その内容について少々触れて見る。 「淤与岐別宮(源氏の氏神石清水八幡宮を勧請して祀る)の明厳権寺主が池内保領の山野を買いとったといい、その証文があるというが、それはねつ造された文書である。 そもそも他国の保領と知りながら買い取ることは「押領」となすことになっているのに、当保領を今押領しようとすることは不当なことである」 この事件の本質は、丹波の蓮実法師が武士と共謀し明厳権寺王を敵人として淤与岐荘を押領しようとしており、これといった証文も所持しないのに淤与岐荘と池内保の境を越えて所領の証文を出していることによる。 この最中に池内保の牛一頭が丹波の武士によって押し取られたが、これ等は蓮実法師の謀計である。ご裁許がなければ池内保の百姓等は安心して生活できないと言上しているものである。 今一件は、淤与岐別宮に入り倉の中に納めてあった御供料の稲二○○束と釜、鍋が盗まれた事件について反論している。この事件が発生した時代は丁度源平の戦の最中で、元暦元年(一一八四)二月、平家は一ノ谷の戦で敗れ屋島へ逃れ、壇の浦に追いつめられた平家は翌年の文治元年(一一八五)三月遂に滅亡した時代に当たり、当時池内側の平家と淤与岐側の源氏とは、丹後峠を境にして絶えずいざこざを起こしていた時代であったのではないかと推察され、興味がある。 この外に、古い史料に出てくる池内の地名には、明徳三年(一三九二)四月二十五日付 室町幕府御教書 丹後国衙領地池内保正税 (八坂神社文書) 長禄二年(一四五八)五月三日 丹後国諸庄園郷保惣田数帳 池内保 一九町二段 (成相寺文書) これ等の資料から判ることは、鎌倉時代既に「池内」の地名が使われていたことである。 池内の字岸谷、白滝、寺田、上根、別所、布敷、池ノ内下、堀、今田関連項目 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||