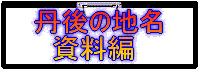 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河辺由里
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
《河辺由里の概要》 単に由里とも呼ぶ。河辺が冠称されるのは江戸後期から。 舞鶴市の東北。河辺谷のなかほど。観音寺の登り口に位置する。東は河辺原、北は観音寺、西は西屋、南は室牛。府道561号線が通る。 『角川日本地名大辞典』は、「地名の由来は、河辺谷の口の意か、もしくは河辺谷の主邑の意か。口碑に当地は源頼政の所領で、野上と称されていたという(丹哥府志)。」としている。 『京都府の地名』は、「古代は志楽郷(和名抄)、中世には志楽庄河辺村の地と推測される。」としている。 現在も河辺由里と河辺原の境には、伝説の矢竹に適するような節の間隔の長いシノビ竹があるそうである。 《人口》62。《世帯数》21。 《主な社寺》 若宮社。下森神社。 氏神は河辺中の八幡神社。 《交通》 府道561号線。 《産業》 農業。
《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 観音寺麓なり。昔源三位頼政知行所之由申伝るなり。頼政鵺を討たる時 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 《丹哥府志》 〈 【源三位頼政の古跡】 丹後旧記云。加佐郡志楽の庄は源三位頼政の所領なり、其庄由里といふ村に頼政矢竹の薮といふ處あり、今に矢竹封して節を同ふすといふ。源三位頼政は摂津守頼光五世の孫兵庫頭仲正の長子なり、射を善し和歌を工にす、素より武勇の誉人の知る處なり、嘗て□(空に鳥)を射る、久寿二年兵庫頭に任ぜらる、治承三年従三位に叙す、翌四年剃髪して名を真蓮と改む世の人源三位入道と称す、後に義兵を挙て宇治平等院に戦死す時に七十七。太田系譜云。其子孫丹後に居る初て太田氏を冒すといふ。諸書に考ふるに其所領丹後にあることを記せず、今国史及口碑に伝はる處を以てしるす。 【付録】(若宮、荒神) 《加佐郡誌》
河辺由里 千本 竹西 若宮 サンマ 村ノ内 川向 東谷 下ノ坪 堂田 姫ケ谷 カイダ オクボ ミノ谷 広木山 八坂 西ケ谷 細迫 大長野 中尾谷 大ヘラ 蛇ケ谷 赤坂 長野 ヒノクチ 坪口 内ノ山 細道 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺の梵鐘 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||